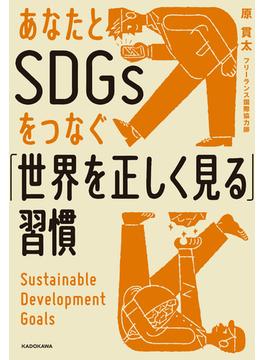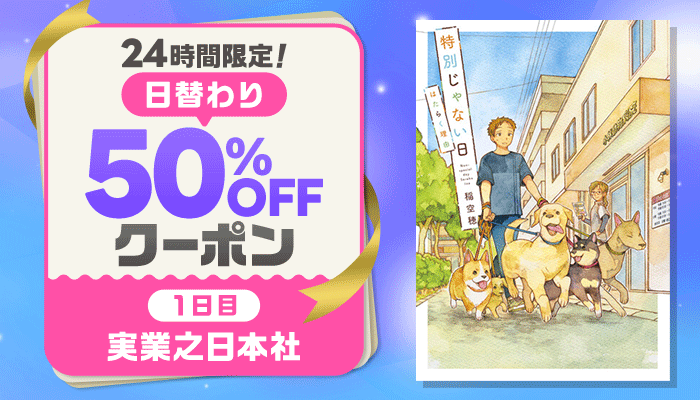0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:michaq - この投稿者のレビュー一覧を見る
捨てるよりは人の役に立つかな?とチャリティーや寄付に古着を出すことが実はアフリカの服飾業界を破壊して、あのカラフルで伝統的な服を作る機会を奪っているという現実はショックです。服に限らず、環境に良いと思っているプラスチックのリサイクルなども日本以外の国に問題を押し付けている、そう考えると衣食住全てにおいて余分なものを買わずに足るを知ることがSDGsへの1番の近道な気がします。
自分では知り得ないアフリカの現状が知れる
2022/01/10 09:25
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:魚大好き - この投稿者のレビュー一覧を見る
世界や日本で起きている社会問題を取り上げている本。
.
どれだけの人が地球環境や途上国のことを考えながら生活しているのかな。(アメリカ在住なのでアメリカからの視点で)アメリカは日本のような過剰包装はないけれど、大量浪費国であることは間違いない。周りを見回すと過剰な消費が目について、自分1人ができることは微力の微力過ぎて本当に意味があるのかと思ってしまう。
投稿元:
レビューを見る
書評を書きました。https://twitter.com/nobushiromasaki/status/1473218650924789767?s=21
投稿元:
レビューを見る
私たちが普段からこよなく愛するスマホ、肉、衣服など私たちにとってはそういったごく普通のモノが実は誰かの生活を脅かし、後に社会問題となって浮き彫りになっている。そうした社会問題に対して1分1秒でも良いから関心を持つことが全人類の使命でもある。
そのことを教えてくれる良書。
投稿元:
レビューを見る
SDGsについて学ぶ機会があり、たまたま目についたこの本を手に取りました。より多くの人、特に若い世代に伝わるように分かりやすく書かれていると思います。地球規模、世界規模の社会問題について考えるきっかけはなかなか無いけれど、まずは知ることが大事であると痛感しました。無知、無関心な人間にはなりたくないと思うので、この本をきっかけにまずは知ることから始めたいです。
投稿元:
レビューを見る
sdgs関連の本では珍しく、その根本を身近なテーマに惹きつけて考えさせてくれる秀逸な一冊。魚の釣り方を教えるのではなく「引き出す」という表現は、非常に教育的なテーマである。
投稿元:
レビューを見る
YouTubeで寄付の実態に衝撃を受けて本書を読んだ。私達が享受している当たり前の便利な暮らしは、誰かの犠牲の下に成り立っているという事実を理解した上で過ごしたい。関心を持ち続けることを大事にしたいと強く思った。
投稿元:
レビューを見る
とても勉強になりました。
アフリカの問題等知らなかった事が多々ありました。
色々な視点で物事に関心を寄せる事の重要さ!
関心を持ち続ける事、大切ですね!
親ガチャについても書かれていたがなるほどと思うところがありましたw
投稿元:
レビューを見る
原貫太さんのYouTubeチャンネルから。
YouTube以上のことを知れるのかと思って購入したが、ほとんどYouTubeと同じ内容だった。
良いとされてることが地球の裏側ではマイナスに働いてる。自分が持てていなかった視点を学べた。虫の目、鳥の目、魚の目は意識して生活したい。
ただ、結局世界を良くするためにはどうしたらいいんだろう?って感想に辿り着くのが、読み終えた後ももやもやが残って残念。本書の目的として、読者に考えさせたいんだろうが、せめて「僕はこう考えますが皆様はどうですか?」ぐらいはあってほしかった。
日本の貧困については、あまり共感できんかった。25年かけて植え付けられた自己責任論はなかなか消えないな。
投稿元:
レビューを見る
☆先進国で集められた大量の古着は、その多くが、国外に輸出されている。
2016年、アメリカ:75万トン. ドイツ:50万トン、イギリス35万トン、日本:24万トン。
☆東アフリカ共同帯(ケニア、ウガンダ、タンザニア)古着屋や靴の輸入額は1億5100万ドル以上(2015年)
☆売れなかった古着は最終的にアフリカにて埋め立てへ流れる。このことを受けてアフリカの国々では自国の繊維産業を盛り上げるために輸入をSTOPしようとし、2016年に、国外から輸入される古着に高い関税を段階的に引き上げ2019年を目安禁止しようした。しかし、自由貿易協定に反するとアメリカが反発。それはなぜか。アメリカで古着に従事している人たちが大量に失業する恐れがあったため。アフリカの経済成長「アフリカ成長機会法」がちらつかせ、アフリカの輸入を引き続き継続させた。(貿易制裁のプレッシャー0
☆1975年~2000年にかけて繊維・衣料品関連の雇用が80%減少している。ウガンダでは衣料品の81%が古着
☆アフリカによるアフリカのための包括的な開発計画【ラゴス行動計画】
=資源と原料を搾取され続け、先進国に依存している経済体制から脱却することを目指すための指針。アフリカ内の貿易・交流をもっと密に行い、相互ともに経済成長を狙う動き。
BUT、【構造調整プログラム】によって上記政策は頓挫する(世界銀行&国際通貨基金などの主導で)
→貧困問題がなくならないのは国内政策に問題があるから。だから、先進国が加入して援助をしてあげる代わりに、経済政策を指導しよう
☆魚を与えるのではなく、魚の釣り方を”引き出す”べき!!!
日本では年間10億着以上の新品の衣服が捨てられている。
【感想】
つくづく世界平和、みなが平等な生活は皆無に等しいと考えさせられる。得するものと損するものがここに成立しているし、貧困があるからこそ、国際機関やNGOなどの需要が得られ、みな収入が得られる。極端な話、途上国にとって一生貧困であるべきだ!と先進国がいってようなもの。それが、ラゴス行動計画を頓挫させた国際機関の考え。
善意で寄付する人たちも、何も考えないで100%良心で手を差し伸べる行動もただの偽善でありありがた迷惑である。この一章のみで世界の縮図が反映されている。
今後国際開発に携わりたいと考えているが、いかに活動をするべきか、頭を悩ましてします。
☆淡水(生活・農業・工業で必要な水)は、地球上において全体の2.5%。内1.7%が氷河や南極の氷として存在している。地下水や沼などの形で存在する淡水の量は0.8%に過ぎず、大部分が地下水。人類が取水しやすい状態の淡水は地球全体の0.01%(約10万立法キロメートル).
今後石油より水を取り巻く戦争・奪い合いも懸念されている。
【感想】
チベットには周辺国の貴重な水資源がある場所。その水に恩恵を受けている人口は30億人。これを統治しているのが中国。各ポイントにて水力ダムを建築している。これは30億人の生命線を握っているということ。こんな理不尽なことがあるもものか。日本では蛇口を捻れば、あたりまえのように水が流れるが、他国では本元の水源は多くの国を経由し、生活に根付いている。まさに地球のどこに属しているかで、奪う側に立つか、奪われる側に立つかが決まってくる。。。。
☆3TG(すず、タンタル、タングステン).電気自動車を製造するのに必要なものはレアメタル(コバルト)
リチウム電池をを製造するために必要になってくる。ノートパソコンやスマホにも使われており、昨今需要が急増している。このコバルト産出量のうち約68%がコンゴに集中している。採取するのに”クルーザー”と呼ばれる手堀に従事する人が11万人~15万人いる。労働者の中には、18最未満の子たちが多数おり、児童労働に虐げられる。
【感想】
今後IT化が進みパソコンやスマホの需要が増すことは大いに予想される実態である。より便利な生活を送るために日々各企業は知恵と研究を絞って開発に挑んでいいるが、その裏で、虐げられる人たちもいるのが現状。皆が平等な生活は無いものか考えさせられる。
☆バングラディッシュ:1971年にパキスタンから独立。当時の平均寿命は41.5歳。5歳の誕生日を迎える前になくなる子供の割合は1000人中221人。一人あたりの子供の数は6.9人2019年の平均寿命は72,5歳・子供1000人中30人。JICAの報告によると2019年に下痢による死亡者数は91%減少し、栄養失調による死亡は79%減少した。公衆衛生の改善・啓発活動が大きく貢献している。
【感想】
世界規模の枠組みで考えるとどこから対策すればいいのかわからないが、個々で見た場合しっかりと人々の生活が改善され、人々の命が救われたことにはとても感銘深い物を感じる。
投稿元:
レビューを見る
原貫太さんのYouTube動画の内容をまとめた本。国内外の問題点・課題を公平な視点を持って学ぶことができます。
本書の学び
1.関心を持つこと以上に、関心を持ち続けることが大切。そうすることで、いつか、自然と次の行動に移すことができる。同じ興味、関心を持っている仲間を見つけるとなお良い。
2.鳥の目、虫の目、魚の目で、物事を正しく見よう。無意識の偏見や自身の願望が入っていないか?メディアに踊らされていないか?良い意味で疑ってかかることが大切。
3.ベジタリアンの種類は様々。ヴィーガン、ラクト・ベジタリアン、オボ・ベジタリアン、ペスカタリアン、フレキシタリアン。
投稿元:
レビューを見る
YouTubeで原さんの存在を知って色々なことに興味を持つようになりました。
本の内容は、ほぼほぼYouTubeで話されていることです。
自発的な意思が欠けたSDGsを会社でやっていこうと思っていた自分が恥ずかしい
投稿元:
レビューを見る
データを元にしながらも、非常にわかりやすくアフリカ・日本の社会問題が解説されており、非常に多くの気づきがあった。
アフリカの問題は、直感的に正しいと思うことがことが、回り回って相手の不幸につながるという、表層的な問題には本質的な問題が存在しているという二重構造である、という非常に深い気づきになった。
ということは、相手のためを思ってやっているということは、実は相手を苦しめているかもしれない、ということであり、本質的な構造に目を向けない、無知、無関心が、どれだけ無意識の悪意に繋がるのか、ということが理解できた。
つまり、無知・無関心による善意の押し付けはほぼ悪意であるということ。
これは社会問題だけでなく、構造が複雑化している現代においては、人間関係など全てのことに言える問題だと思った。
ここを避けるためには、どれだけ知ろうとするか、表面的なことだけ一方だけの意見だけで理解した気にならず、構造的に知ること、両者の意見を知ることが必要だということ。
というか、ほぼ必須リテラシーだと思うが、これ(クリティカルシンキング)を初頭教育で行うべきだと思う。
投稿元:
レビューを見る
SDGs
牛肉1kg穀物12kg
豚肉1kg穀物6kg
鶏肉1kg穀物4kg
穀物消費は8割弱が飼料、かたや7億弱の人口が飢餓。
穀物1kgに水1800l
Tシャツ一枚に水2700l
輸入する品物の製造で予め消費された水はバーチャルな水の輸入。
資源があると、狙われ搾取される。資源の生む富は寡占され、資源に甘えて産業発展せず、貧困がほうちされる。
善意の寄附は産業発展の妨げだが、寄付されることで生まれる仕事もある。
いまや生活必需品となりつつあるスマートデバイスに必要なレアメタルのために、児童労働と現地コミュニティ破壊のための性暴力が現在進行形で行われている。
多産なのは労働力と死ぬことを暫定にしているからで、貧しいのに子供を作るわけではない。
日本の貧困は、本人の自己責任論になりがちだが、云々。
※リベラルな社会では努力すれば成功するという信仰がある
自分が触るもの、消費するものと地球の見たことない場所との関わりを感じて考えてしまう読後感の悪い本。正解の見えない問いが頭に残る一冊。
投稿元:
レビューを見る
企業の取り組みがメディアで取り上げられたり、学校の宿題でも関係することについての作文の宿題が出たりと、身近な課題となっているSDGs。
これからの世界を生きていくためには考えなくてはならない重要な課題なのだけれど、この本に痛いほど、いかに自分が本質を知らないかを知らされました。
経済発展だけでなく、環境や社会が抱える問題にもバランスよく取り組み、その根本的な解決によって世界を持続させようという17個の目標が設定されましたが、解決すべき問題の本質がわからないと具体的に何をするべきかわからず、おそらく多くの人にとってどこか他人事感があるのではないかと思います。
この本を読むと、見えないところで、思いもよらないところで日本と他の国がつながっていることがわかります。本当は何を考えなくてはならないのかが見えてきます。
とてもとても深いのですが、子どもたちにはこのレベルで問題意識を持ってほしいなと思います。