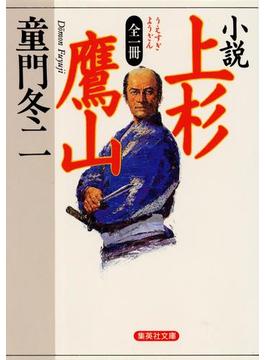すべてのリーダーに送る
2004/08/06 22:48
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なかちん - この投稿者のレビュー一覧を見る
故J.F.ケネディ大統領が「ウエスギ・ヨーザンは、私の最も
尊敬する日本人」という逸話は有名な話。
彼が成し遂げた偉業を綴った一冊である。
上杉鷹山公は当時どん底にあった、米沢藩政立て直しの立役者である。
わずか17歳にして藩主となり、あえて藩内の嫌われ者を
集めてプロジェクトチームを作り、藩の財政悪化に
歯止めをかけ、今でもさかんな地場産業の開発を行った。
リーダーとして評価すべき点は、次の事につきる。
・リーダーとして自ら進んで矢面に立つ
・部下を信じ、常に気配りを忘れない
・不要な古いしきたりを徹底的に排除する
・部下のモチベーションを上げ、持続させる
・下(藩士・藩民)の意見を聞く
・常に「愛」を持って接する
様々な職種の中でリーダーという存在は欠かせないが、
上からの一方的な指示では、部下は動かない。
いかに部下の心を動かし、やる気を出させるかが
リーダーとしての腕の見せ所だ。
ぐいぐい引っ張るリーダーシップも否定はしないが、
やはり日本人らしさも持ち合わせた、彼のリーダーとしての
存在は圧巻させられる。
現在の日本にもこんな政治家がいたら…と思わせる
著書である。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さっさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本人なら知っておくべき人物の1人である上杉鷹山の生涯を描いた長編小説。上杉鷹山の行政改革に対する情熱に何度涙が出そうになったかわからない。また、行政改革を成功させるのは容易ではない。その苦労もひしひしと伝わってくる。
個人的にはラストのシーンの上杉鷹山とその小姓たちとの会話がとても印象深い。
生きているあいだに一度は読んでもらいたい名作だ。
投稿元:
レビューを見る
〇幕府に返上しなければもたないところまで極貧になった米沢藩。そこに養子に入って上杉家を継いだ治憲。改革をすすめるがそこに立ちはだかる保守派重臣や冷ややかな物見達にどうするか? 芯が強く慎重で本物の政治見識を持つ凄い人だ。
4087485463 684p 1998・5・25 8刷
投稿元:
レビューを見る
理想の指導者とは?
理想の組織とは?
普遍の定義が載ってます。
童門冬二の著作の中で、一番作品と論理のバランスがいいと思う。
投稿元:
レビューを見る
九州の小藩からわずか十七歳で名門・上杉家の養子に入り、出羽・米沢の藩主となった治憲(後の鷹山)は、破滅の危機にあった藩政を建て直すべく、直ちに改革に乗り出す。―高邁な理想に燃え、すぐれた実践能力と人を思いやる心で、家臣や領民の信頼を集めていった経世家・上杉鷹山の感動の生涯を描いた長篇。
投稿元:
レビューを見る
上杉鷹山は、九州から上杉家の養子として出羽・米沢にやってきて、後に藩主となった。破滅の危機にあった藩政を建て直すために、改革に乗り出し、倹約を軸にして大成功したと言われる。ときどき政治家が彼の業績を引用するシーンもある。江戸時代に登場した有能な治世家の生涯を童門冬二 さんが描いている………と聞けば、読まずにはおれない。
投稿元:
レビューを見る
なぜか注目してしまった、江戸時代の政治家(!?)、上杉鷹山。
「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も
成らぬは人の 為さぬなりけり」
で有名な方ですね。
困窮していた米沢藩を養子の身で引き受けた藩主として、
当時の武家では思いつかないような行財政改革を行って、
立て直した方ですね。
どこから手をつけてよいかわからなかったので、簡単どころで、
童門冬二の小説から入ってみる。
思ったより情感深く書かれていて、すんなり頭の中に入ってくるし、
660ページあるのに、一気に読み進む。
いつの時代でも、抵抗する力が内にも外にも存在するのね。
相手を変えるのは生半可なことではないのに、少しずつでも
取組んで、大きな成果を残す。
その成果があっても、まだ動かない人もいるというのがよく
わかった。ちょっとドラマチックに書かれているけど。
いくら正論でも、そのときでは考えられないことを着実に
進めていく熱意。なかなかできるもんじゃない。
ケネディがインタビューで日本の尊敬できる政治家として
名前が挙がるというのもわからんでもない。
だれがレクチャーしたのかは知らんけど。
もう少し、鷹山を勉強してみよう。
投稿元:
レビューを見る
開始:20070717、完了:20070717
ジョン・F・ケネディ元大統領が日本人記者と会見した際に、記者に
「あなたがもっとも尊敬する日本人は誰ですか?」と質問され、
「ウセスギヨウザン」と答えたが、その場にいる記者
は誰も「ウエスギヨウザン」を知らなかったという逸
話がある人物だ。江戸時代に米沢藩を改革した人物な
のだが、まさにこの本は組織変革のための教科書とい
える。現在の企業に置き換えてみても十分通用する。
変革に反対する旧来の家臣たち、変革しようとす
る、はみ出し者。そして人間の価値観は変わらないと
いう現実...。しかし、そうした中で上杉鷹山の何が
すごいという点は、我慢強く「決して怒らない」と
いう点を貫き通したことと、結果ではなくプロセスを
重んじたことだろう。またそれと同時に自分自身が改
革の具体案を出し、それを実行もした。でも何よりも
世の中、そして周りがまったく違う価値観を持ってい
る中で自分の価値感を信じ続けたことだろう。そして
それが無私だったとうことだ。それにしても改革のプ
ロセスがJ・P・コッター氏とほぼ一致している点がす
ごい。また、普通に小説としても面白いので、大変読
みやすい。
以下メモ。
農民は国の宝。新しい収入源の発見もない。
形式主義、事大主義。
まず改革にあたる者が自分を変えること。
逆に藩内でなかまはずれにされている人間に目をつけよう。
そしてなぜなかまはずれにされているか?
人間をよくみている。
怒りや悲しみが決して私欲に基づくものではない。
世の中は何をいっているかを大切にすべきであって誰がいってい
るかは問題ではない。自分を変えてほしい。
藩内の身体障害者・病人・老人・妊婦・子供など社会的に弱い立場に
ある者たちをいたわる政治を実現したい。
大切な人々とは年貢を納める人。
気付いた方から自分を改めるよりほかない。
自分にやさしくしてくれる者は、無批判・無制限に信じた。
総論賛成、各論反対。
自分の生き方をもたず形式の中で生きてきた。虚礼廃止。
虚礼で社会が成り立っていた。
「徳」を政治の基本におき、「愛と信頼」で展開する。
藩政改革は藩民のために行うもの。
三つの壁、?制度の壁、?物理的な壁、?意識(心)の壁。
心の壁を壊すために、?情報は全て共有する、?職場での討論
を活発にする、?その合意を尊重する、?現場を重視する、?
藩庁に愛と信頼の念を回復する。
人間は、「何をやるのか」ということにはあまり意に介さない。
「誰がやるのか」をひじょうに気にする。
改革とは藩政を変えることではなく自分たちを変えること。
民を愛せ。心が死んでいる。人間たちの表情に希望がない。
上杉神社。どこまでできるかを素直に話す。
(1) 私は大藩の生まれではなく九州の小藩の生まれ
(2) 若年dえある
(3) 経験が非常に不足している
(4) 米沢藩を継いだものの、米沢本国には初めて入ってきて米沢の実態を全然知らない
(5) 今日���広間に集まってもらったおまえたちとは初対面であり、江戸藩邸でいっしょに暮らしたものの他は誰をも知らない
(6) 同時におまえたちの方も私をまったく知らない
富民。情報経路を太く短くする。人口減を許さない。
仕事に興味はなくても人事にだけは異常な関心を寄せる。
怒るのはただ一度だけ。怒ったら全てが終わる。
眼が美しい。
先入観、虚像。弱いものをいたわれ。
「その改革は、なぜ成功したのか」
「その改革は、なぜ失敗したのか」
→(1)改革の目的がよくわからないこと、(2)しかもその推進者が一部の人間に限られていたこと、
(3)改革をおこなう政庁員全員にも改革の趣旨が徹底されていなかったこと、(4)当然、改革の目的
や方法が親切に領民に知らされに一方的に押し付けられたこと、(5)改革が進んで、
幕府や藩が身軽になれば、当然領民の負担が軽くならなければならないのに、逆に幕府や藩は
増税したこと。
私の改革は愛といたわりが必要。
農民たちがかたくななのは、何のために働き、何のために生きているか、目標がまったくないから。
領民の全てが働くことを楽しみ、生きることを喜ぶようにする。
原料に極限まで付加価値をつける。ただ経費を切り詰めればよくない。
逆に思い切って使うことも必要。それが生きた金の使い方。
老人子供は鯉のえさやり。これで家の中の地位も昔のようにもどる。
発想の転換。武士の権威とは何か。民の年貢で養われる徒食の人間にすぎない。
他人にやってもらうには、まず、頼む人間が自分でやってみせなければ駄目。
不運というのは、自分が自分の年齢に応じた生き方ができない。
籍田の礼。老成。学問はないが直感でいい人か悪い人かを感じ取る勘のようなものがある。
米沢を傍目八目で見られる。
人間の笑いの中で失笑ほど気分の悪いものはない。
灰の国にも人はいたのだ。毎日惰性で城を出てくるだけ。竹俣はいつでも死ぬ覚悟をもっている。
田沼意次、賄賂。金は大切なもの、その大切なものを他人に送るのだから、それは誠心。
役人の子はニギニギをまず覚え。
力で押さえつけるのは得策ではない。納得してくれなければ意味がない。
人は一朝一夕で変わるものであhない。
人間のかなしい習性は、自分をたかめる、という方法ではなく、ひとをひきずりおろせば
自分と同じ位置にきた、という錯覚の中に生きること。
自分が上昇したことにはならないのだが、出世欲にかられた亡者たちは、性懲りもなく
その方法をとる。
ほかの人間からみれば正義であることが不正義になり、誠意も不誠意になる。
人の心の不気味さ。
休まず・遅れず・仕事せず。
改革はなんといっても現場が軸となる。
身分の低い層ほど支持している。
藩士世論の支持のない改革は進みっこない。
本当にそれが藩士世論であるならば言い訳をせずにだまって去ろうと
心に決めていた。上に立つ者が下の者のきもちを代弁していると称して、
まったくの嘘をついて自分たちに都合のよいようないい方をしたことが
怒らせたのである。
ただ人間がいるだけでは何の役にも立たない。忍びざ���心を持つことが大切。
改革というのは、制度や政治のやりかたを変えるだけではない。
何よりも大切なのは、人間が自分を変えることだ。そして自分を変える
ときにいちばんさしさわりになるのは、古い考えへのこだわりだ。
そしてそれは自分がこのことは絶対に変えられないのだ、と思いこんでいる
ことだ。傍からみれば瓦のようなものを本人だけが宝石のように思い込んで
いることがよくある。
考えが自分の血肉にならなければダメ。
頼んでいる、決して命令はしない、強制もしない。民こそ国の宝である。
きあぴたれ餅。やさしい眼をしている。
人間は貧しいとき、そして前途に希望がないとき、必ず自分のまわりを
見渡す。それも下ばかりみる。自分より下位にある者がいると安心する。
そして、「あいつよりは、まだ自分のほうがましだ」と思う。
この優越感はやがてその下位者に対する侮蔑に変わっていく。
何の警戒心も持たずに、ズバリと本当のことを話せる。
心の問題はそう単純ではない。
出世のためにはなりふりかまわないのが、多くの人間の本心です。
人を知るにはまず接触しなくてはならない。
どんなに優れた人間にも、好事魔多しというたとえがある。
まして権力は魔ものである。権力に永く馴れていると、
知らないうちに人間は堕落する。
水商売の女の子供。小さい頃は母親の苦労をみている。でも大きくなると...。
改革の美しい面ばかりみて、改革は成功していると思ったらそれは間違いだ。
それに人間はそれほどきれいなものだとみるのも考えが浅い。
若いけれど人を見る眼、洞察力に優れたいた。
探るというのは、もうその人間を信頼していないということになる。
不信の念が沸いたからこそ探るのだろう。
汚れ役が根回しをすればだしかに仕事の進みは速かろう。
が、私はそういう姑息な道はとらぬ。私の改革派、どれほど道が
遠かろうと、清い方法で歩く。それは、領民のためである。改革派
領民のためにおこなっているのだ。領民の眼にいささかの汚れも
見せてはならぬ。
トップの信頼を一身に集めて、自分ではそのつもりでなくても、権力が
集中していると見られれば、まわりの人間が放っておかず寄って集って
堕落させてしまう典型的な例。
民には責任はない。
いちど得たこの座はわたさない、と人はなってしまう。
おまえたちの中に私をだます者がいても、私は決しておまえたちをだまさない。
竹俣は結果だけを急いでいる。私が大切にしたいのは過程だ。
周りが自分をえらい人間だと思いすぎる。生きた仏のように扱われてしまう。
人君の心得、一、国家は先祖から子孫に伝えられるもので、決して私すべきものではないこと、
一、人民は国家に属するもので、決して私してはならないこと、一、国家人民のために立ち
たる君(藩主)であって、君のために人民があるのではないこと、伝国の辞。
政治家は潔癖でなくてはならない。
鷹山の改革案は、一、民を富ませること、一、改革が楽しいものであること、一、士農工商
が身分を忘れて一体となること、一、若き人材を育てること。
生きていながら実は死んでいる。
「トップ層はわれわれの意見をちっとも聞かない」というが、「それでは意見を聞くから
存分に言ってみろ」というえばこれがなかなか出てこない。自分が意見だと思っている
ことが、実はただの不平や不満の場合もあるからだ。
節約一辺倒で、景気浮揚策がないと必ず国民はソッポを向く。
鷹山は柔軟な思考と果敢な行動力をもっていた。そして本物の誠実な人間であった。
投稿元:
レビューを見る
、誰かがお勧めしていた本を読みました。
上杉鷹山って有名な方だったんですね。
それって、もしかしたら話していた子が
山形出身だからだったのでしょうか。
上杉鷹山という方は財政危機にあった
藩を倹約や新規事業投資を行い、立て直した方です。
その経緯で、抵抗勢力との戦い、裏切り、飢饉など
多くの困難を乗り越えていく経緯が書かれています。
ポイントをいくつか。
・自ら例となって、実際に行動に移していた。
ただ、上から命令するのではなく、命令した内容を
自分で示すことをされていた方のようです。
・教育の大切さを認識していた。
武家のものはもちろん、そうでない人に対しても
教育は大切だという事を認識しており
学校を予算を出して作っていました。
当時から、教育の大切さに気が付いているっていうのは
素晴らしいですね。
・就任当時17歳。
小説だから良く書かれているのかもしれないですが
彼は就任当時17歳だったようです。
17歳って自分が何をしていたかっていうと。。。
大した事はしていなかったですね。
今は24歳同じ事ができるだろうか。
読んでいて、感動できた一冊です。
ちなみに、
なせば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり
は上杉鷹山の言葉だそうです。
昔読んだ本にライバルは歴史上の人物にも
一人設定した方が良いと書いてありましたが
上杉鷹山を勝手にライバルにしようと思います。
もう少し、毒舌を減らそう。
投稿元:
レビューを見る
集英社文庫 と−12−6
2010/02/05 読了
最初イマイチでなかなか読み進められなかったけれど、途中から乗ってきてかなりの勢いで読めました。
正直、上杉鷹山という人を知らなかったので、勉強になりました。
投稿元:
レビューを見る
ちょうど10年前に読んで、感銘を受けた上杉鷹山の小説を再読。
前回は単行本を図書館で借りて読んで、今回は文庫化されていたので買ってみました。
投稿元:
レビューを見る
これは、1番のオススメ!!!
歴史の本だけど、読み終わって、
ちょっと自分の人生考えちゃった。
すごいゎ。上杉鷹山。
そして、
童門さんの本は、読みやすい。
グッと作品に引き寄せられてしまうんです。
読み始めたら、とまりません。。
ケネディが、最も尊敬する日本人、というのも、納得!!
投稿元:
レビューを見る
確かに凄い人のようだけど、なぜか暗い・・・
全体的に重々しいというか、暗さが拭えないのは何故だろう
投稿元:
レビューを見る
最高におもしろい本でした!!
改革と一言に言っても、そこには多くの意味での『魔』が存在する。
それに真っ向から立ち向かう洗練された清らかな姿は、時に涙を、感動を与えてくれました
投稿元:
レビューを見る
「なせば為る 成さねば為らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」
【人が何かを為し遂げようという意思を持って行動すれば、何事も達成に向かうのである。ただ待っていて、何も行動を起こさなければ良い結果には結びつかない。結果が得られないのは、人が為し遂げる意思を持って行動しないからだ。】
今回はこの言葉で有名な上杉鷹山について書かれた本です。
簡単に感想をつらつらと。
童門氏の作品は初めて読むのですが、経営指南書として書かれているのかな?と思う箇所がありました。
私としては上杉鷹山という登場人物にどっぷりと入り込んで、小説として読んだ方がよいと思います。
全体として政(まつりごと)の理想を追い求めています。「世の中はこうであるべきだ!」という強い気持ちが伝わってきました。綺麗な話が多く、現実との乖離を覚える方もいるかもしれませんが、物事の本質的は基準を確かめたい時、心の掃除をしたい時などはお勧めです。
藤沢周平の「漆の実のみのる国」という上杉鷹山について書かれた本があるそうなので、今度読んでみます。
いずれにせよ、生きてるうちに読むべき一冊に入る名著です。ぜひ読んでみてください。