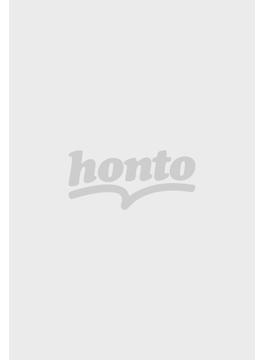「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
本書は梅棹忠夫によるモンゴル関係のメモワールやメモをまとめたものである。書名ともなっている「回想のモンゴル」は本書の半分くらいを占めるにすぎず、残りは梅棹が張家口に駐在し西北研究所を拠点に展開した研究活動の成果をまとめたもの、36年ぶりに梅棹が内モンゴル自治区を再訪したセンチメンタルジャーニーの旅行記である。
2010/11/15 10:01
7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:塩津計 - この投稿者のレビュー一覧を見る
梅棹の文章の最大の特徴は、その分かりやすさにある。日本では長らく「岩波文化」の悪影響もあって、難解な文章を書かなければ知識人でないみたいな風潮が旧制第一高等学校を中心に日本中に蔓延するという不幸な時代が長く続いた。九鬼周造の『いきの構造』が、その悪い見本だが、丸山真男の『日本の思想』だって、すらすら読める人はそうはいないだろう。これらの本は、山本夏彦曰く「まるで外国語」であって、日本語ではないそうだ。こうした旧制高校の悪しき伝統とは無縁なのが梅棹の文章である。梅棹の文章は福澤諭吉ではないが「サルでもわかる文章」である。その記述は正確無比で、まるで映像を見ているような臨場感たっぷりの描写力には全く舌を巻く。以前、梅棹の『東南アジア紀行』を読んだことがあるが、その中にあるラオスの古都ルアンプラバーンの描写が素晴らしかった。ラオスの首都ビエンチャンから真北にあるこの古都は、東南アジア全体の中でかなり北部に位置する街であるにもかかわらず、梅棹が指摘する通り、ヤシの木が生い茂る風景は熱帯そのものだったので、梅棹の文章を読み進むにつれ、ルアンプラバーンを訪れた際の記憶が次々と蘇ってくるのを感じた。梅棹の文章には、こうしたパワーが確かにある。本書を読んでいても、内モンゴルの大草原に展開するモンゴル族の生活、そこに放牧される牛、羊、馬、ラクダが、まるで目の前にいて手に触れることが出来るような錯覚を覚えるくらいの臨場感で迫ってくる。
本書を読んで感じるのは「わが大日本帝国は確かに朝鮮半島と北京を含む中国の北半分を支配していたのだなあ」というものである。梅棹は張家口にある西北研究所に勤務するため移動するのだが、下関から関釜フェリーで釜山に渡るのだが、当時の朝鮮半島は日本の一部だった。満州も日本の一部みたいなものだった。山海関を越えてはじめて外国に入るわけだが北京でも要所要所に銃剣付き三八式歩兵銃を持った日本兵が警戒にあたっている。当時の北京は現在のイラクのバグダッドやアフガニスタンのカブールみたいなものだったんだろう。あと、梅棹は「中国人」という言葉を一切使わず「漢人」という言葉を使っている。中国という名称は1902年に梁啓超が発明した呼称だったんだそうだが、1944年になっても日本人には中国という名称は一般的ではなかったんだと推察される。同じく梅棹による対談集『語る』には、当時の張家口の凄まじい風景が出てくる。張家口の長城にある大門・大境門のそとに住居を構えていたが、毎朝自宅から研究所に通勤する際、その通勤ルートの道の両側に大量のシナ人が座ってウンチをしていたんだそうだ。沿道に男がズラーッと並んで毎朝ウンチしている。そんな風習はアジアでいち早く文明開化を成し遂げた日本にはなかったし、江戸時代、いやそれ以前の日本でもなかったであろう。この風景を見ただけで、梅棹は「中国と日本が同じ文化、文明であるわけがない」と断じる。さすが、理科系の学者ならではの、見事な断定である。現実を見ずに書物から入る文系の学者は、往々にしてシナを理想化し、脳内に形成した理想のシナのみを見て、現実のシナを見ないという愚を犯しがちだが、梅棹は自分の目で観察したものからシナ像を形成していく。このくだりを見て、パリにある東洋語学校で学んでいたエドウィン・O・ライシャワーに対し、フランス人の指導教授が放った台詞を思い出した。「ライシャワー君、君はシナが大変好きなようだが、もしシナを好きで居続けたいのであれば、シナを訪れてはいけない」。このフランス人の教授は、当時のシナの凄まじい現実を知っていたのであろう。路上で毎朝大量のシナ人が並んで脱糞し、周囲に異臭が立ち込めている現実を。河には死体が浮き、その死体を拾い集めることを商売にしているシナ人が大勢いたという現実を。確かにシナは日本とは異質な文明の国であることがこれだけでも理解することが出来る。鳩山由紀夫が放った軽薄な「東アジア共同体」なるものは、いずれ形成されるのであろうが、その道は遥かであることを、既に多くの日本人は理解している。