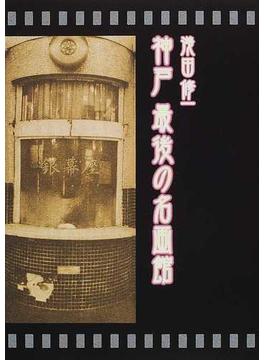「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
神戸の映画館、松竹新劇・新公園劇場・六甲東映のことや、そこで見た映画、一緒に映画を見た人たちについて綴る。「神戸わたしの映画館」の増補改訂。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
浅田 修一
- 略歴
- 〈浅田修一〉1938〜2001年。著書に「教師が街に出てゆく時」「現代高校生気質」「映画のあとで」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
映画館に足を運ぶのって、こういうことだったんだな
2001/08/18 22:43
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読ん太 - この投稿者のレビュー一覧を見る
神戸の新開地には、かつてすごい数の映画館、芝居小屋があった。今では、一般的に神戸と言えば、三宮から元町のあたりを指すのが普通かと思うが、当時(大正から昭和30年代のあたりだろうか)は、神戸と言えば新開地である。
私は神戸人ではありながら、新開地についてはほとんど知らない。私よりやや世代が上の友達は「聚楽館に行けるおもたら朝からうれしぃてたまらんかった。」と語りながら、聚楽館のテーマソングみたいなものを口ずさんでくれたものだ。この聚楽館の閉鎖によって、新開地は完全に印籠を東に渡してしまったようにも感じられる。
この地で生まれ育った有名人に淀川長治さんがいる。映画をこよなく愛する淀川さんを育てたのが、新開地であったのだ。そしてまた、新開地は、本書の著者 浅田修二さんという、これまた映画をこよなく愛する人を育ててもいたのだ。
浅田さんは、兵庫県の龍野という田舎町から、大学受験のために神戸に移り住んだ。もともと映画が好きだったので、この引越しによって「筋金入り」の映画人になるのは、自然の成り行きであった。
本書は、そんな浅田さんが、1985年1月から4月という、映画がやや下火になり且つ新開地の賑わいも下火になっている状況下で、あちこちの映画館を巡って、そこで観た映画評とともに劇場での出来事や思い出を綴ったものである。
ページのところどころには、浅田さんがスケッチした劇場内の絵があり、また、モノクロの全景写真や、おまけのように、酢昆布やサンリツパンの懐かしい写真が貼り付けられていたりと、たまらない一冊に仕上がっている。
表紙をあけると、まず油紙のようなものが差し込まれており、次のページには浅田さんの顔写真があるので、油紙を透かして見ると写真がセピア色になる。まったく心憎い装丁だ。
単なる映画評だけがずらずら並んでいるだけなら、私のように「そこそこ映画を観る」タイプの人間にとってはあまり心に響くものがなかったと思う。しかし、浅田さんがかつて安保闘争で体も心も疲れ果てた時に、救いを求めるように通った映画館の話、三本立ての映画を観ながら、サッカーボールのようなお握りを食べた話などなど、様々なエピソードが語られていて、すっかり浅田さんに魅入られてしまった。
キリコさんという素敵な女性が時々に登場するのだが、これによって物語が生まれて、この本一冊が一本の映画のようにも感じられる。
浅田さんは、晩年、体があまりよくなくて、映画館に通うのもままならくなるが、それでも家のビデオで映画を見続ける。座っているのがつらいので、枕をふたつ重ねて見るのだが、これを浅田さんは「何だか申し訳ない」と表現する。浅田さんの思いが胸にジンときた。
元町の烏書房というところでこの本を購入し、その近くでお茶を飲みながらパラパラとページをめくると、無性に映画が見たくなった。その足で新開地まで赴き、新劇会館に入った。館内が闇に包まれて、映画が始まるまでの一瞬間、なぜか今日のことが結構記憶に残るような気がして、「おまえは、今、どんな心持で毎日を過ごしてるか?」と、駄目押しのように自分で自分に問いかけてみた。