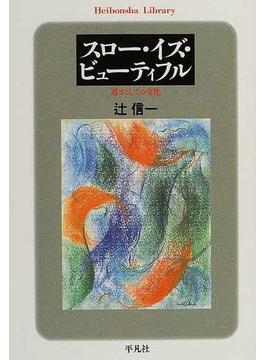「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
紙の本
スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化 (平凡社ライブラリー)
著者 辻 信一 (著)
「スロー」をキーワードに、スピードに象徴され、環境を破壊しつづける現代社会に抗するライフ・スタイルを求めて、さまざまな場所で模索し、考える人々の言葉に耳を澄ます。2001...
スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化 (平凡社ライブラリー)
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
「スロー」をキーワードに、スピードに象徴され、環境を破壊しつづける現代社会に抗するライフ・スタイルを求めて、さまざまな場所で模索し、考える人々の言葉に耳を澄ます。2001年刊の再刊。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
辻 信一
- 略歴
- 〈辻信一〉1952年生まれ。文化人類学者、環境運動家。明治学院大学国際学部教員。NPOやNGOにも参加している。著書に「スローライフ100のキーワード」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
名著である
2005/12/02 20:23
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:喜八 - この投稿者のレビュー一覧を見る
『スロー・イズ・ビューティフル』は名著である。
ただし、ごく表面的になでるだけなら、「スローライフ」「スローフード」「反グローバリゼーション」などの言葉をちりばめた今風の「お洒落な」本という読み方さえできるかもしれない。
多くの企業が自社イメージを高めるため「環境に優しい」ことをむやみに謳う昨今では、スローライフやスローフードという言葉もだいぶありがたみの薄いものになってきたからだ。
辻信一。1952年東京生まれ。15年以上にわたる北米での生活を経て、現在は明治学院大学国際学部教員(文化人類学専攻)としてカナダ先住民の調査をしている。また南米エクアドルのミツユビナマケモノを保護するNGO「ナマケモノ倶楽部」の世話人を務める。
なぜカナダ先住民なのか?
なぜミツユビナマケモノなのか?
という疑問を抱いた。どこか「お洒落」なものを感じて、警戒心を抱いてしまうのである。
けれども辻信一の文章には心ひかれる。『ハーレム・スピークス』新宿書房(1995)、『日系カナダ人』晶文社(1990)、『常世の船を漕ぎて−水俣病私史−』世織書房(1996)、著作をこの順番で読んでみた。
『常世の船を漕ぎて』まできて、ようやく分かってきた。これらの著作は「忘れられた庶民」の人生を掘り起こす一連の叙事詩なのである。辻信一は自らの旅の途中で出会った庶民の姿を記録し続けてきた。
辻信一の旅はスローに歩きながら道草をくうことに喩えられるかもしれない。道草をくって遊ぶこと。寄り道。逸脱。
カナダ先住民やミツユビナマケモノは辻信一にとって、寄り道(逸脱)の途中で知り合った仲間なのだろう。北米大陸で15年の寄り道をした。その途中で先住民たちと遭遇した。南米ではナマケモノと出会った。仲間となった彼ら彼女らに肩入れする。
仲間を助けるための行ないを「お洒落」と批評することはできない。私(喜八)の第一印象はピントが外れたものだった。
「進化主義」という宗教的狂信にとりつかれ驀進する世界、「頑張ること=善」と信じて疑わない社会、これらへの対抗概念としての「スロー・イズ・ビューティフル」と「頑張らない」。「自己否定や自己憎悪という呪詛」から自らを解き放ち生きてゆくこと。
再び言う。『スロー・イズ・ビューティフル』は名著である。
文章のうまい人だと思う。つぎのような一節にはやはり感動させられてしまう。関係ないけれど、女性にも好かれる人なのだろうな。
紙の本
節度のメカニズムとしての文化
2004/12/29 21:35
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る
季刊誌『住む。』(誌名に出てくる句点はほんとうは右半分が半分欠けている)に長田弘さんの詩が連載されている。「世界を、過剰な色彩で覆ってはいけないのだ。/沈黙を、過剰な言葉で覆ってはいけないように。」(「2004年冬の、或る午後」)とか、「自由とは、新しい生活様式をつくりだすことだ。」(「シェーカー・ロッキング・チェア」)とか、切りとってこころのなかにしっかり刻んでおきたい言葉がちりばめられている。
和歌に屏風歌といわれるものがある。丸谷才一さんの『新々百人一首』によると、「屏風絵とは、大和絵屏風の色紙形の部分に書かれた画讃としての歌で、いつそ「調度的装飾歌」(橋本不美男)と見るほうがわかりやすい文学形式であつた」。長田弘さんの詩文は、出来合のものではない思想や生き方や住まい方を目に見えるかたちで表現しようとする雑誌の余白に添えられる讃に、いかにもふさわしい。
辻信一さんがやがて世におくることになる『スロー・イズ・ビューティフル』という本の種が蒔かれたのは、一九八○年、モントリオールのマッギル大学に在学中の著者が、客員教授をしていた鶴見俊輔さんから「ふろふきの食べかた」という詩のコピーを贈られた時のことだった。この作品は、長田弘さんが当時『婦人の友』に連載していたものの一つだった。「こころさむい時代だからなあ。/自分の手で、自分の/一日をふろふきにして/熱く香ばしくして食べたいんだ。/熱い器でゆず味噌でふうふういって。」
この詩を読んで、辻信一さんは、「いつのまにか失っていて、それと気づかずにいた、ある感情」を思い出した。その感情とは、子どもの時の著者をつつんでいたはずの「今はまだない未来の自分ではなく、今の自分の、今この時を抱きしめることの歓び」で、それは書名の「ビューティフル」につながっている。「このビューティフルということばを、ぼくは次のような態度だと定義したいのです。そのもの本来のあり方を、遠慮がちにではなく、といってことさら誇るのでもなく、他を否定するのでもなく、他との優劣を競うこともなく、ありのままに認め、受け入れ、抱擁すること。」
この書物は、ゆっくりと読まなければならない。気温の変化に合わせて森は一年間に五百メートルまで移動できるが、温暖化で三十年間に気温が摂氏一度から二度上昇すると、樹木たちは一年に五キロもの移動を要求されるという。「前に進むしかないという「進化主義」はひとつの宗教的狂信といっていい。このせいで、毎年少なくとも二万五千もの種が絶滅している。絶滅種が生態系に開けた穴を埋めるためにかかる生物進化の時間は少なくとも五百万年だそうだ。この気の遠くなるような遅さこそが進化の本質だともいえる。ぼくたちは人間の歴史を語るのに「進化」などということばを使うことを慎むべきだ。」
そのような生物時間、生物進化の時間、地質学的時間に寄り添いながら、寄り添うことは無理でも、思いをはせながら、ゆっくりと読まなければならない。スローネス、つまり遅さ、慎み、節度をもって、そして過去への畏れと未来へのノスタルジーをもって、ゆっくりと読まなければならない。「ここで重要なことは、多くの伝統社会がかつて、その大きさや速さや力の限度をわきまえていて、それはまるでそこに自然界と同様の均衡、調節、浄化の力が働いているかのようだった、ということ。ぼくは思うのだが、本来、文化とは社会の中にそうした「節度」を組み込むメカニズムなのではないか。」