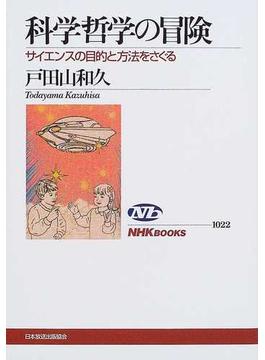「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
紙の本
科学哲学の冒険 サイエンスの目的と方法をさぐる (NHKブックス)
著者 戸田山 和久 (著)
「法則」や「理論」の本当の意味って知ってる?「科学」という複雑な営みはそもそも何のためにある? 素朴な疑問を哲学的に考察し科学の意義とさらなる可能性を対話形式で軽やかに説...
科学哲学の冒険 サイエンスの目的と方法をさぐる (NHKブックス)
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
「法則」や「理論」の本当の意味って知ってる?「科学」という複雑な営みはそもそも何のためにある? 素朴な疑問を哲学的に考察し科学の意義とさらなる可能性を対話形式で軽やかに説く。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
戸田山 和久
- 略歴
- 〈戸田山和久〉1958年生まれ。東京大学大学院修了。名古屋大学情報科学研究科教授。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
「実在」という概念はそんなに魅力的なのか。
2005/05/08 12:35
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キューティス - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、各パートごとに導入とまとめが付いているという大変親切な本であり、今更ありふれた要約も不要と思うので、単刀直入で魅力と問題点を述べたい。
本書の最重要キーワードは、「説明」である。
本書の最初の部分で、著者は次のように書いている。
「科学も哲学も、世界を理解しようという試みである。」
「科学哲学の第一目標は科学を理解することである。」
ここで「理解」とは何か。(主観的な「理解したつもり」との違いは?)
「世界を丸ごと理解する」なんてのは置いといて、例えば地震や遺伝を理解するという場合、その意味は比較的明瞭である。つまりそれは、科学的説明が与えられ、それを受け入れるということであるから。
「科学的説明とは何か」をめぐる議論は本書の最大の読みどころである。
本書は科学方法論ということで、まずオーソドックスに「演繹」と「帰納」の検討から始める。ここで帰納概念は「最良の説明への推論」といったものも含め広く捉えられる。著者は、個別事例の単なる一般化ではまともな帰納にならず、法則も支えられないことを示す。科学理論は個別現象に対して、予測や制御も可能にするような「良い説明」を提供できないといけない。
本書で著者がイチオシと言う「科学理論の意味論的捉え方」は、科学で使われる多様な表象(法則文・数式・図など)による多様な「説明」のありかたを統一的に理解できる点で優れたものであり、これについては私も本書の主張に非常に説得された。
一方、本書の問題点は、科学的説明が説明としての力を持つ根拠の追求の仕方にある。
本書の中ほどで著者は「科学の権威のかなりの部分は、科学の持つ説明能力にある」と言っているが、これはむしろ逆だろう。科学的説明がなぜ自然現象の説明として受け入れられ、人を納得させるかというと、説明に使われる道具立て(質量やエネルギーなどの物理学の基礎概念、元素や物性の知識、数学的技法など)が今までに汎用的に自然現象の説明に使われてきたという歴史的実績の重みがあるからだ。「権威」はその実感が支えている。自然現象の予測・制御が成功し、説明が破綻もしないのは、科学者の長年の絶えざる試行錯誤と努力の成果であるし、膨大な応用とフィードバックの結果である。
確かに、努力が報われる保証はないし、試行錯誤も空回りすることは多い。しかし、科学者の努力が成果を上げ、科学が成功している事実を、さらになんとか説明すべきなのだろうか。
著者はそのために「科学的実在論」にこだわり、擁護しているようである。
著者によると、実在論と反実在論の対立は、現在も科学哲学の最もホットな話題らしい。しかしそれが本当に科学に対する理解や態度を左右するような対立かは疑問だ。
著者の整理では、電子のような観察不可能な理論的対象の実在性が争点らしい。
しかし「実在」という概念は見かけほどしっかりした概念ではない。「認識活動とは独立の世界の側にある事実」などと言い換えてもより明確になるわけではない。むしろ言語的指示の共有や操作という行為に現れる「何かを対象扱いする」という我々の態度が原初的なものであり、科学における電子などはそういう対象である。
哲学の素人は(一見)いい加減に「ある」という言葉を使うが、これは単に習慣や実用性に屈服しているわけではない。哲学者が「本当の意味で」「文字通り」などの強調句で「実在」という語の一用法に特別待遇を与えても、そちらの方が二次的なのだ。
著者は、「帰納は信頼できるはずだ」とか「電子はエーテルの二の舞にならない」という確信(希望?自然な直観?)を守るため「実在」という概念にすがっているように見える。我々人類は、他に生き方を知らない以上、帰納と心中する覚悟は決めている、ということで別にいいじゃないと私個人としては思います。
紙の本
「帰納を使い続ける本当の理由」とは?
2005/11/14 20:04
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:半久 - この投稿者のレビュー一覧を見る
良い入門書である。
一人称の説明文もあるが、叙述の中心はリカとテツオ男女2名の学生とセンセイと呼ばれる人物との鼎談形式で、なかなか親しみやすく分かりやすい。
以前似たスタイルのものを読んだことがあり、出来映えとしてはあまり感心しなかった。本書の方が良いと思っていたが、あとがきで著者はその本に習いしかもそれを傑作と激賞していた。「あら、そうだったのね〜」と頭を掻いた次第(苦笑)。
本書のターゲットは、ちょっと背伸びした高校生から大学一、二年生ぐらいとのこと。高校時代の知識すら朧になった私でも何とかついて行けたので、親切な作りであると思う。
それだけに工夫されている。各部の始めに目標が示され、章の始めにもガイダンスがある。迷子にならないための、良くできた見取り図だ。
さらに、キーワードは黒字強調され、適切なタイミングで図表とイラストがはさまり、要所要所には簡潔にしてつぼを突いた「まとめ」が置かれる。本文中に重要概念が再登場すると、該当ページを指し示すだけではなく復習もしてくれる。とにかく、読者を挫折させず途中で置き去りにしないように、工夫が凝らされている。
最近よく見かけるのだが、著者も近頃の学生の学習意欲(中でも知的動機づけ)の減退を嘆いている教師の一人であるようだ。だからこそ読者の関心を持続させるために、ここまで親切な作りにしたのかと想像する。なんにしろ、こういう入門書が増えることは学生でなくとも歓迎したい。
ただ、それにしても「科学は世界を正確に理解できるか」という議題に対して、わりあい、常識的な結論に帰着するために、どうしてこうも小難しい用語を振り回すのかなあ〜〜、と思わないでもない。
哲学とは厳密にものごとを考えようとする行為だし、そのための用語であるから、こういった優しい入門書であっても避けて通れないのは分かっているつもりではあるが。
常識的な結論については、著者は以下のように弁護している。
《あのね、結論はたしかに、言われてみれば当たり前のことかもしれない。だけど、当たり前のことを無反省に受け入れていることと、いろいろ対立する考え方を批判したり議論したりした末に、やっぱり当たり前のことが正しかったんだ、というのではずいぶん違う。何が違うかと言えば、議論の末に「当たり前」にたどり着いた場合にはさ、これまでその当たり前のことを見えにくくしていた思考の枠組みの偏りがはっきりと分かるからだよ。》
ところで、読者というのはわがままで贅沢なものである。タイトルに「冒険」とあるが、一緒に冒険をしているという感覚が乏しいことがやや不満だったりする。冒険者が各種武器(哲学的述語)を使って、これまた様々な技を繰り出す論敵達を、(著者の言葉を借りると)「やっつけて」行く訳なのだけれども、知的スリリングさにいささか欠ける。
先に触れたように、見取り図を渡されて手取り足取りナビゲートされるのだから、親切すぎるのが仇になっている。読者に挫折させない冒険ってのもねえ・・・どちらかと言えば「ぶらり科学哲学の旅、夢気分」という感じなのである。
無い物ねだりをしてしまったが、最初の一歩としては好適な入門書だと思う。参考書として、「次にぜひ読もう」と推挙されている『疑似科学と科学の哲学』は途中でストップしていたが、再読したら理解が深まった。本書のおかげだ。
著者の支持する科学的実在論の修正バージョンについては、読者はそれを最終解答として受け入れる必要もない。
人類が生存し続ける限り、知的探求の荒野はほぼ無限大に広がっている。
本書を糧にして、さらなる科学哲学の(本当の?)冒険に旅立とう。