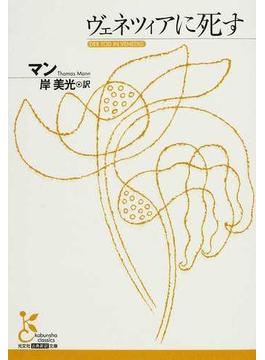「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
ヴェネツィアに死す (光文社古典新訳文庫)
高名な老作家グスタフ・アッシェンバッハは、ミュンヘンからヴェネツィアへと旅立つ。美しくも豪壮なリド島のホテルに滞在するうち、ポーランド人の家族に出会ったアッシェンバッハは...
ヴェネツィアに死す (光文社古典新訳文庫)
ヴェネツィアに死す
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
高名な老作家グスタフ・アッシェンバッハは、ミュンヘンからヴェネツィアへと旅立つ。美しくも豪壮なリド島のホテルに滞在するうち、ポーランド人の家族に出会ったアッシェンバッハは、一家の美しい少年タッジオにつよく惹かれていく。おりしも当地にはコレラの嵐が吹き荒れて…。【「BOOK」データベースの商品解説】
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
老いていくことも、人に惹かれ勝手に思いを募らせることも、うっかりとした不注意も、すべて現実は酷いものなのだという厳しさに貫かれた名作。酷さゆえのめまいに襲われそうな……。
2007/05/05 21:55
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
四半世紀も前に観たヴィスコンティ映画「ベニスに死す」でかすかに記憶に残るのは、タッジオ役ビョルン・アンドレセンの波打つ金髪に濡れたようなくちびる、そして有名なラストシーン、タッジオへの思いを抱いた老作曲家アッシェンバッハの顔にしたたる墨色の液だれの酷さ。酷いけれども、ヴィスコンティはこの映画をやはり彼独特の美学のなかで描き切っていた。不世出の映画監督にとって、愛読小説の映像化は夢だったという。
監督がなぜこの小説を映像にしたのか——その理由は以下のようなものだと思っていた。老いた芸術家への共感、同性愛と少年愛への志向、水の都に集う上流世界の人びとの社交という、視覚効果高い舞台設定への期待、そして人の滅びを美しく表現することへの欲。映画を観た後、私はトーマス・マンの原作を読まずに、そういったものだとずっと思い込んでいた。
しかし、こうしていざ原作に当たってみると、トーマス・マンとヴィスコンティの微妙な差異に気づかされ、ふたりの芸術家の表現の違いに面白味を感じる。ヴィスコンティは美しい世界を描くことによって「酷さ」を際立たせた。一方、マンは決して酷さを「美」によって描こうとはしていないと思えるのだ。あるいは、美に流してしまうような対象の描き方をしていないと言ってもよい。
マンは、酷いものは酷いのだと、現実は厳しく、老いることも片恋もごまかしようのない残酷な成り行きであり、恍惚や陶酔のような「美」に通ずる官能のしばらくを過ぎれば、そのあとの無念は覆い隠しようのないものなのだという姿勢で書いているように取れる。そういう非情な現実の受け止め方とは、どこかゲルマン的ではないだろうか。もっとも、マンの出自にはラテンの血も少し入ってはいるようなのだが……。
では、ヴィスコンティがこの小説のどこに強烈な魅力を感じたのであろうか。もしかすると、こういう部分なのではないかという箇所に出くわした。
——孤独と沈黙の人が行う観察や、その人が出会う出来事は、仲間の多い人の観察や出来事よりも曖昧であり、同時に切実でもある。そういう人の考えはより深刻で、変わっていて、どこかに悲哀の影がさしている。ただ一度の視線、一度の笑い、一度の意見交換で簡単に片付けられるような映像や発見が、異常にその人を刺激し、沈黙の中で深められ、意味を持ち、体験となり、冒険となり、感情となる。孤独は独特なものを生み出す。(48P)
引用したい文章はまだこの先もつづくのだが、自重する。この先の文章で明らかになるが、ここには芸術に向かう人の傾向が書かれている。このような部分を始めとする思念のいくつかが、芸術家の創作意欲をかき立てたことは想像に難くない。
この思念というものが小説では重要で、それは作家である主人公(映画では作曲家)がヴェネツィアに旅するまでに全体の3分の1が費やされていることから分かる。次の3分の1が年端のいかない美しい少年に魅せられていく過程であり、そして残る3分の1が、ストーカーばりに彼の跡を追い身の破滅を自覚していくという内容となっている。映画では、なぜ旅するかという事情は、ここまで表されていなかったのではないだろうか。マンにとっては、「なぜ旅に出るか」「それもなぜヴェネツィアに向かうことになったのか」という結末に至るための経過が、少年への恋同様に大切な内面だった。
そして、深い思念を離れ、無意識に老芸術家が起こした行動が、彼の運命を一気に暗転させてしまう酷さ。マンの姿勢は一貫している。
紙の本
北杜夫氏が
2017/05/21 20:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:igashy - この投稿者のレビュー一覧を見る
その構成の見事さを賞賛していたが、前半と後半で対となるエピソードが現れる。出会いのレストランと、別れの砂浜での振り向く少年。少年にキスした若者を内心脅しながら雄々しく口にする苺と、死への感染源となる市場の苺。不気味な若作りの老人と、彼自身がそれと化してしまうラスト。 ラストにかなり露骨に性行為の暗喩が出てくる(気がする)。パイドロスと対話しているってことはこの作家はソクラテスなの?等々、マンは博学すぎて、こっちは単語をググるだけでも打ちのめされる。