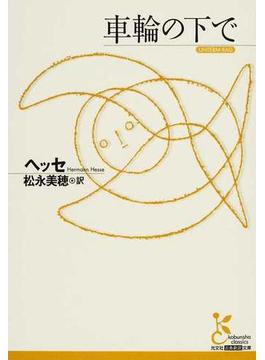電子書籍
運命はまわる
2016/05/07 18:47
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:猫目太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者のヘッセが、一時期送った神学校での出来事。優秀であったはずの主人公が、悩み苦しむ。車輪の回転にように、運命がまわる。最後に悲劇がある。
誰もが経験するだろう、思春期ゆえの悩みか。真面目に勤勉な人間が、陥る苦しみ。当時の教育制度の不備を批判した作品。
投稿元:
レビューを見る
ほんとうによい作品だった。
「中途半端な進学校に行き、入学当初は期待とやる気に胸をときめかしていた体をとっていたのに、根っからの反骨精神やできる人間からの重圧感と不安感、周囲の他人事な期待から来るプレッシャーと勉強に対しての嫌悪、子供時代を思い出して後悔をし、大人になることをためらう上、昔は勉強できたけれども今じゃあとてもついていけてないくせに、昔培った他人を見下す精神はいまだ健在で、口ばっかりの無能になりつつある人間」に是非読んでほしい本の一つ。
勉強と子供であること、趣味に生きることを丁度50:50で生きていたい。自分にとって、その思いがとても強くなる本だった。
投稿元:
レビューを見る
主人公の少年ハンス・ギーベンラートは小さな田舎町の秀才。痩せていて小さくても、他の子より圧倒的に勉強ができるハンスは、親・先生・牧師さん・町中の期待を受けて神学校を受験する。受験のため大好きな魚釣りや川遊びを禁じられ、猛勉強により毎日頭痛を抱えながらも受験には成功し、神学校へ入学する。そこではハイルナーという親友ができるが、彼は問題を起こし退学、ハンス自身も成績が落ち、初めは彼に一目置いていた教師たちからも見放され、退学になる。その後彼は故郷に戻り機械工として新たな人生を始めるが・・・
可愛そうな少年ハンスを抱きしめてあげたいと思ったり、思春期特有の苦しい思いは自分のことのように感じたり、2人の自分がハンスを見ていた。私はちょうど今、思春期と大人の中間にいるのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
2009.12.12 三洋堂書店購入
ヘッセの自伝的小説。
思春期の苦悩を描き出している。結論がちょっと納得できない・・・。
投稿元:
レビューを見る
ヘッセの幼少時代を重ね、学校教育・期待に踊らされる少年を描いた作品。
ハンスがどうしたら救われたかはわからないが、幼少期は野を駆け回り過ごすのがよいと思う。
つい期待をかけてしまいがちだが、多感な時期を奪ってはいけないと思うなぁ
投稿元:
レビューを見る
中学生の頃に新潮文庫で読んだ時は、ハンスの劣等感に自分を重ね過ぎていて、ここまで繊細な自然描写がなされていることに気付かなかったな。ハンスの運命を、語り手が早い段階から示唆していることにも。なんとなく「いまを生きる」を読みたくなった。
投稿元:
レビューを見る
「くらーいお話」だけでは決してありません!
学校の教育体制などへの痛烈な批判そして、鮮やかな情景描写、恋も描かれていたために、意外性があり、満足です。
もし、私が大学受験前に読んでいたら、青年の苦悩だけに焦点が行ってしまったのでしょうが、
大学3年の今、読んだからこそ、幅広い視点で楽しめたと思います。
自分の苦しかった経験と、ハンスの体験を重ね合わせて懐かしく振りかえることもできた一冊です。
☆を一つ減らしたのは、最後の終わり方があっけなく、いまいちに感じたためです。
投稿元:
レビューを見る
ヘッセ自身の学校に対しての怨みのようなものが感じられる。
そういう怨みがましい作品は好きです。
とても面白く読めた。思春期を描いた作品だったので、思春期の人にこそ読んでほしい。
私も中高生のときにこれを読めばよかった。
そうすれば、高校を卒業した今よりも、もっとハンスに共感できただろうと思う。
投稿元:
レビューを見る
ヘッセの自伝的小説。
勉学と友情の間で悩む主人公に共感。
わたしも一人が好きなので、他人とペースを合わせるのが
無駄なような気がしているので。
投稿元:
レビューを見る
周囲の期待を一身に背負い猛勉強の末、神学校に合格したハンス。しかし厳しい学校生活になじめず、学業からも落ちこぼれ、故郷で機械工として新たな人生を始める……。地方出身の一人の優等生が、思春期の孤独と苦しみの果てに破滅へと至る姿を描いたヘッセの自伝的物語。
(裏表紙紹介文より)
***
新訳だからか読みやすかったです。
私的にはハンスの父親がハンスを労ってくれてたのがすごく嬉しかった。
学校を退学したハンスに対して厳しく接すると思ってたので。
とても共感できるとこがたくさんある話でした。
共感したうえで頑張ろうと思えるか、共感したまま引きずられてしまうか、微妙なところですが…。
投稿元:
レビューを見る
子どもの頃、少し読んで以来なんだか”苦手だなー”と思っていたヘルマン・ヘッセ。この新訳で再挑戦して、その魅力にようやく気づくことができました。自分が成長した、というのもあるかと思いますが、やはり、古典特有の古さ、とっつきにくさを感じさせない新訳が大きかったように思います。この本をよんでからは、ヘッセの他の作品や、他の古典と呼ばれる小説もよく読むようになりました。私に、”古典への扉”を開いてくれた一冊です。古典、ヘッセが苦手だと思ってる人にこそおすすめです。
投稿元:
レビューを見る
前に感想文かくために読んだんだけどあのときは新潮文庫のだったかなあ?なんかすごくむずかしくてよくわかんなかったんだよね
でもこれはやばかった!めっちゃおもしろかった!前半の神学校のところはずっときゅんきゅんにやにやしてた^^かわいいなあ~!
やっぱり男の子同士のキスとかどきどきするよ じょしだもん!
投稿元:
レビューを見る
児童文学の名作。そんな予備知識だけで読んでみたら、思いっきり、教育批判。作者ヘッセの時代には、生徒の個性を尊重する教育なんて存在しなかった。生徒を枠に当てはめることこそ、優れた教師。金八先生なんてトンデモ教師扱いだ。
都会のエリート教育からはみ出してしまったヘッセの分身、主人公ハンスは故郷へ戻る。そんな彼の劣等感を取り払ってくれたのは、故郷の友人であり、自然だった。
ヘッセは当時の教育に落ちこぼれてしまったものの、その憤慨をバネにノーベル文学賞。ある意味、良い反面教師に恵まれたってことか。
投稿元:
レビューを見る
がんばって、がんばって、ただ自分自身はそうやっていきた。
レールに縛られるんじゃない。自分の道を進むんだって。
ひらすらそういう生き方したら、なんだかこの世界自身を遮断しなきゃいけなくなって...。
学生時代に読んだら、何か変わっていたかもしれない。
すごく読んでてつらくなる。でも、みんなそう悩んで生きるんだ。
そう思う。
投稿元:
レビューを見る
「名作も読まなかな」という適当な動機で手に取った本。ほんとに、なんの情報もなく。教科書に載ってたらしいけど…そうだっけ(汗)・・・・おもしろい!!びっくりです。こんなおもしろいなんて。ストーリーはおもしろくなくて、キャラクターも特別おもしろくなくて、だけど何かが面白い。ほんと、なんでかなぁーおもしろいの。解説に日本の競争社会に似てるからだ、みたいにあったけど、でも、少しちがって、ゆとりみたいなのあるよなとおもう。新訳だから?ほかにもいろいろよむぞ!