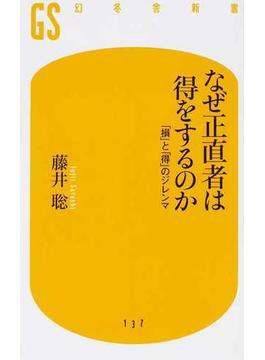「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
紙の本
なぜ正直者は得をするのか 「損」と「得」のジレンマ (幻冬舎新書)
著者 藤井 聡 (著)
落ちていた財布をネコババするなどの利己主義者が実は損をして不幸になり、正直者が得をして幸せになることを科学的に実証。利己主義者が正直者のふりをしても簡単に見透かされる心の...
なぜ正直者は得をするのか 「損」と「得」のジレンマ (幻冬舎新書)
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
落ちていた財布をネコババするなどの利己主義者が実は損をして不幸になり、正直者が得をして幸せになることを科学的に実証。利己主義者が正直者のふりをしても簡単に見透かされる心のしくみも解き明かす。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
藤井 聡
- 略歴
- 〈藤井聡〉1968年奈良県生まれ。京都大学卒業。同大学大学院工学研究科教授。専門は土木計画および公共政策のための心理学。著書に「社会的ジレンマの処方箋」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
著者/著名人のレビュー
「正直者は得をする」...
ジュンク堂
「正直者は得をする」は、倫理でも宗教でもない。社会科学的な考察の結論である。
確かに、ゲーム理論のモデルは、一見、「利己主義者・不正直者として振る舞う行為」が「正直者として振る舞う行為」よりも常に「得」をすることを、示唆する。実際に、ヨーロッパが「近代」を迎えて以来利己主義者が跋扈し、英国では「共有地の悲劇」が起こり、同様の事態は現在でも頻出する。しかし、同時に、「全員が利己主義者」として振る舞う場合に一人ひとりが得られる利益よりも、「全員が正直者」として振る舞う場合に得られる利益の方が大きいのも事実である。(社会的ジレンマ)
また、利己主義者は、他者と助け合うことができず(互恵不能原理)、いかに取り繕おうとも、利己主義者であることが「ばれて」しまい(暴露原理)、常に敗北する。そして、人間はそもそも完全なる利己主義者ではなく、そのことによって先の社会的ジレンマを乗り越えているのだ。経済学の前提は、大きく崩れる。
何よりも避けなければならないのは、利己主義者に支配された集団は集団ごと自滅してしまうという集団淘汰原理により、正直者・非利己主義者もろともに、滅びてしまうことなのである。
紙の本
共生を重んじる国民性がこの国の持続可能性の鍵なのでは
2012/01/25 04:58
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:良泉 - この投稿者のレビュー一覧を見る
いま、日本は危機的状態にあると思う。異常に長期にわたるデフレ円高により、一般の労働者はへとへとに疲れきっいる。そんな状況の中での未曾有の大災害。
これまでこの国において、長い年月をかけて培われてきた雇用や経済は、ずたずたに破壊されつつある。
そして、そんな状況の中、そんな状況を待っていたかのように、そんな状況をつけねらうかのように、悪しき思想が持ち込まれる。様々なダメージでショックを受けた国民は、それを無抵抗に受け入れてしまう。
新自由主義などと呼ばれる思想がそのようなものであり、政治手法としてはポピュリズムであろう。
「構造改革」などという聞こえのよい言葉を多用し、社会の秩序をスマート化させるかのような幻想を振りまきつつ、実際は、大企業・一部の特権階級に莫大な利益を持ち込む企みが、国民の見えていないところで着々と進められている。
そんな、“間違った”人たちの思想はどこを発して出てくるのか。
本書で著者言う。
『「人間は所詮、利己主義者である」と信じる人々は、終身雇用・年功序列の給与体系を否定する一方、成果主義を支持するようになっていく。その上、人間が利己的であるという信念に基づいて、構築されている諸理論を信じ、その結果、市場原理主義に陥り、民営化論や規制緩和、自由化、構造改革といった諸施策が、国民的人気を博すようになっていく。』
人間が個々の利益の向上のみを指針として機械的に行動する。こういったモデルから推計される社会が、フリードマンなどが提唱し、世界中にばらまいた“悪しき市場原理主義”である。
日本においても、この“悪しき思想”が蔓延し、国民の生活を悪くする一方の規制緩和が進行した。そして、その結果潤ったのは、大企業や一部の特権階級なのである。
真実はどこにあるか。
『「規制」が実質的抑制していたのは、「真っ当な消費者の行動」や「真面目な企業の行為」なのではなく、「過度に利己的に振る舞う、利己主義者の行動」だった』
人間が一般的に利己主義者なのではなく、ごく一部の利己主義者たちがこの社会を乱してきたのだ。しかしそれらの行動には、従来、社会の良識として規制がかけられていた。規制が弱い国民を守ってきた。
しかし、「規制緩和」のかけ声は、その必要な規制さえも取り払ってしまった。
人間は決して、個々に利己的な動機だけで行動を起こすわけではない。人と人とのつながりを常に念頭に置きながら行動する。自分にとっては不利となることであっても、あえて行動する。場合によっては、他人のために命を落とす者さえいる。
新自由主義を標榜する者たちは、人間の尊厳を冒涜している。
この国が、これから先も末永く持続可能な国であるために必要なものはなにか。それが良識なナショナリズムであろう。
『国民の中にナショナリズムがあるために、国民国家の中での様々な水準、領域での協力的傾向が増進し、様々な富や価値を生み出していく能力(すなわち国力)が増強していく』
全体主義に直結するような誤ったナショナリズムではなく、真に助け合い、共生の精神に通じるようなナショナリズムを育てていかなければならない。
正直者が得をすることを科学的に解明してくれる本書が、そんなことを教えてくれる。
紙の本
結果的に「正しい」ものは...
2011/08/18 08:08
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:のちもち - この投稿者のレビュー一覧を見る
成果主義、拝金主義にみられるような「利己的な」考え方は、一時的には成功するようにみえるが、結果は...最終的には「正直者」=利他主義、非利己主義の考え方をする者が幸せになりうる、という論です。どちらかというと、「なぜ利己主義は生き残れないか」という説明に多くを割いますが、なぜそれらの者が淘汰されるかというと、ひとこと=「嫌われるから」ということ。利己主義の塊のようなタイプは周りに人が寄ってこない、非利己主義に装ってもばれる...という極めてシンプルな理由づけです。
まあ、確かに。自分の周りを見てもわかりますよね。「あいつは自分のことしか考えていない」ってのは好かれるタイプではありません。すき好んで寄って行こうと思いません。またそれを少し拡張して考えれば、そういったタイプの多い組織(企業体も国家も)は、最終的には消滅する、或いは、利他主義を貫く組織が生き残る、という説明もあります。これも感覚としてよくわかります。著者はその原因として政府が推し進める構造改革や民営化といったものをあげています。大きな時代の流れ、なのでしょうけれども、その「構造改革」が利己主義思想を強化している、というのは、正直よくわかりませんが、営利企業であっても、「拝金主義」は嫌われるし、(一時的な成功を成し遂げても)その本質がいずれバレる、というのは、確かにそう思います。
消滅した古代文明を事例にあげて、そうならないためには「協調」する意識を持つ構成員の比率が高いこと、という条件をあげていますが、同じく著者が主張する「そうして変えていかないと、一部の利己主義が存在することで(利他主義を含めた)組織全体が消滅する」という危険性。こわいですね。レベルの差こそあれ、営利企業である以上は、ある程度の「拝金主義」であることは間違いないでしょう。考え方だけでも「(利他主義的な)活動の結果としての利益」という概念があれば、随分と変わってくるのかもしれません。そういう考え方がいつかきっと表にでてくる、という夢がなければツライよね。「仕事は金をもらうためだけ」というには、それに割く時間を考えたらあまりにもツラい。本書で貫かれているように、「利己主義」がいずれ退却する、ということを信じていくしか...
【ことば】我が国は...様々な形の“協力”を社会的に行い続けてきた...そうした“人々の協力”がなければ、現在私たちが“日本”と呼んでいる国そのものが、滅亡していたかもしれない。
日本人には、その根底に「協力」という概念を持った民族である、ということ。表面的な成果主義、拝金主義を受け入れてそれに邁進するよりは、もともと「持っている力」を発揮すること、これが大事かもしれない。なんとなく、だけど、「風向き」が変わってきているような気もする。
紙の本
おもしろい
2021/09/11 21:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
損と得のジレンマについて、いろいろな角度から分析されていて、面白く読むことができました。興味が湧いてきました。