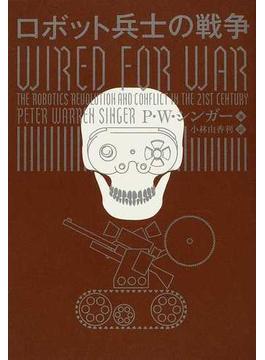紙の本
これからの戦場
2014/09/30 14:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タナ - この投稿者のレビュー一覧を見る
かつて、SFであったものが現実のものとなってゆく。
しかし、SFでは考えられないことが現実ではおきている。
この本が書かれてから更に技術は進歩してゆく。
私達の子どもの世代の戦場はどうなっているだろうと、創造をふくらませる一方。
戦争根絶は次の世代でも不可能であると言う諦観と冷笑が浮かんでくる。
投稿元:
レビューを見る
「ロボット兵士の戦争」という分厚い本を読んでみました。
内容は、無人兵器の登場がこれからの戦争のあり方を変えようとしているというものです。
無人兵器の事例として、プレデターという無人偵察・攻撃機が取り上げられています。
これまでの軍用機は、パイロットが操縦し戦闘に参加するのが常識とされてきましたが、プレデターはその概念を大きく変えました。機体は低コストであり、パイロットの訓練も非常に短く、且つ戦闘や事故によるパイロットの損失が防げることが大きなメリットです。また有人機ではできないようなリスクの高い運用が可能であることも(パイロットの安全を配慮しなくても良い戦術が可能)挙げられます。しかしながら、ネガティブな部分も当然あり、カメラによる敵の認識を行うため誤射誤爆が発生したり、パイロットの戦闘行動に対する認識が薄れ、殺傷がゲーム感覚になってしまうこと。軍人であるパイロットは安全な自国での任務となるが、メンテナンスする民間技術者は現地で作業しなければならず、危険な状況にあることなどです。(本来は軍人が戦地に居るべきなのに、立場が逆になってしまう)
地上軍のロボット兵器も含めてこのような無人兵器の登場は、これからの戦争のあり方を根本的に変えていく可能性が高く、法規や社会構造まで影響を及ぼすと予測しています。
しかし、一般人は戦争の無い平和な世界に住んでいるので、このような変化に気がつく機会がありません。
例えば日本でも発売されている自動掃除機ロボットを作っているiRobot社は、もともと軍事用のロボットを作っていた会社で、自動掃除機は民間転用の製品です。これは良い事例だと思いますが、逆のケースだって有り得るわけです。ロボットは戦争の道具としてではなく平和目的で利用して欲しいものです。
投稿元:
レビューを見る
この夏一番のインパクト。ヒトの最も嫌な仕事から解放させることが機械化の使命だとしたら、究極の適用になるし、非常に近い将来そこに至るかと思うと。
投稿元:
レビューを見る
斜め読み。
シリアで米軍の無人戦闘機による爆撃に対するデモが起こったのはこの本をまさに読んでいる最中であった。
これまでの戦争の概念は、見返し(表紙の裏)の「ある米軍兵士の一日」という描写で早速覆される。
・早朝・・・アメリカの自宅で起床、基地に出勤
・午前・・・アフガンのテロ拠点を攻撃
・午後・・・イラクを偵察
・夕方・・・帰宅、家族と食事
コンピュータ技術の進歩により、もはや戦争はロボットが行い人間は遠隔地で操作する時代を迎えた。もはやゲーム感覚であるし、実際に、近年の米軍では筋肉ムキムキのマッチョマンタイプではない、いわゆるゲーマータイプの若い兵士が増えてきているという。人間同士が戦う機会が減少しつつある現代の戦争では、求められる資質も変わってきているのだろう。
一方で、急速なハイテク化・無人化により戦争に対する「躊躇」を感じなくなる:タガが外れて戦争を抑止しようとする力が弱まってしまうことを作者は危惧している。テレビゲーム感覚で遠隔地を攻撃することが可能となっているし、それに対する現実感は乏しい。実際、ウィキリークスにより、米軍用機が一般人を狙撃している映像が公表されている。
今日現在はハイテク兵器は米軍が一歩抜けていると考えるが、やがて、中国をはじめとする各国も同様の技術、あるいはそれ以上の技術を実戦に適用してくるだろう。
兵士の命の危険が少なくなった戦争は、ハドメがきかなくなってしまうのではないか?当事者同士で無人機を敵国に飛ばし、互いに爆撃するようなことになってしまわないか?権力者が暴走したらとんでもないことが起きるのではないか?(これは今日の核兵器にも当然いえるのだが)
いずれにせよ、これからの戦争は今までの概念とは全く違うものとなる。
■その他の所感
ネットワークが軍事目的で生まれたのは知っていたが、オペレーションズリサーチやガントチャートなど経営や意思決定に用いられる一般的な手法も軍事目的に生み出されたということは本書で初めて知った。
日本のロボット技術は軍事目的ではないが、もともと他国では軍事目的に研究されてきたものだろう。日本は、「軍隊を持たない国」なので軍事目的で研究開発がなされることは他国に比べて圧倒的に少ない。つまり、国の補助もでにくいためロボット産業はもちろん、他の分野においても世界に差し置かれてしまわないだろうか。
アジアにも強力なライバルが出現している今、産学官連携をより一層強固にしていく必要がある。
投稿元:
レビューを見る
尖閣諸島の問題がなくとも、たぶん戦争は起こるんだろう。でもその姿は従来とは全く異なるかもしれない。新しい戦争ではロボット兵器が使われる。すでにそれは実践配備されているし、そのことで戦闘がどう変わるのか、この本が説明している。続きはブログで…
http://pinvill.cocolog-nifty.com/daybooks/2012/09/post-8808.html
投稿元:
レビューを見る
現代の戦争における無人兵器の役割、技術の進歩による戦争形態の変化がとてもわかりやすく書いてあります。じっくり読んだ方が楽しめます。長いし。訳も読みやすいです。ロボット工学とその影響ってすごいなぁ。近未来がもう現代になった感じ。
投稿元:
レビューを見る
淡々と書くロボット戦争。「ロボットが攻めてくる」時代の始まり。安全な戦争とテレビゲームの違いは?画面のこっちでクリックひとつで敵兵が殺せる時、何が起きるんだろう? 合理化しちゃいけないものがあるとすれば、戦争はそのひとつなんじゃないだろうか。「危険な武器なんかない、危険な人間がいるだけだ」宇宙の戦士のズイム軍曹ならなんて言うだろう?
600ページを超える分厚い本。途中で何度かもう少し短くならないかと思ったが、読み終わった今となっては許せる気分。
投稿元:
レビューを見る
2012 3/30読了。つくば市立図書館で借りた。
@sakstyleのブログ(http://d.hatena.ne.jp/sakstyle/20110608/p2)で取り上げられているのを見て以来、ずっと読みたいと思っていた本。
P.W.シンガーの著作を読むのは2冊目。
戦争における無人兵器の活用状況(第1部)と、それによって戦争になにがもたらされるか(第2部)を、気が遠くなるような量の取材に基づいて書いた本。
おかげで分厚さも気が遠くなりそうで面白いんだけど読み通すのがつらい(苦笑)
詳しい紹介は@sakstyleのブログを参照。
米軍に限定されるものの、人死が少なくなる話であり、SFチックな話(どころかSFがいかに未来を予測してきたか/影響してきたかの話もある)でもあり、著者の意図どおりわくわくさせられる部分も多い。
反面、対立する軍・テロリストにとってはロボットに殺される話であり、誤作動やバグによる事故(民間人や味方の死)、そもそも人の意思が関わってないところで殺されるってなんだ等、不安と不気味さを感じさせられるところも著者の意図通りか。
途中にあるDARPAの紹介が面白い。
国防資金を用いるはずなのにそれを忘れていないかと批判されるくらい「イカれた」研究に金を出すことがよくある。
困難な課題かバカか。
無人機操作者としてのテレビゲーム世代の優秀さについての記述も。
ただし操作・戦術面で優れていても戦争に向いているかどうかとは別かも知れない、との指摘もある。
投稿元:
レビューを見る
ロボットについて卒論をかくためには必読の本であろう。戦争とロボットについてあらゆることが書いてある。今日のテレビでアラビア語でも、ラクダレースの騎手がロボットでそれを4駆からリモコンで操作してムチを当てていた風景が放送されていた。
投稿元:
レビューを見る
単行本500ページ強の大著。読み切るのに時間がかかった。しかし、すべてをりかいできた訳ではない。著者の興味(構想)が多岐に渡るため、話題があっちこっちと絶えず行き来する。豊富な知識には触れられるが、その分商店が絞り難く、簡潔さに欠ける。たとえば 「海」を大波、小波で語ることはできる。それぞれは「海」の一部であることは理解できる。また、「海」が何であるかも理解している。しかし、大波、小波から「海」が何であるか理解できない?結論は22章、及び解説に容易にまとめれられている。
「ファイヤーフォックス」、「攻殻機動隊」、「トータルリコール」、「600万ドルの男」、「バイオニックジェミー」といったSFの世界が現実の世界に向かっている。
投稿元:
レビューを見る
湾岸戦争の真の主役は今考えるような無人システムではなく、新しい誘導式のミサイルや爆弾、いわゆるスマート爆弾だった。
アメリカ軍は特にハッキングに弱い。
これからの戦争はロボットが行うようになると、人間の心理的な負担は軽減されるだろう。
投稿元:
レビューを見る
本作は、ロボットと戦争についての本である。イラク戦争開戦当初、非常に懐疑的に見られていた無人システムは、今や戦争のあり方そのものを変えうるほど普及している。
本書は単純なテクノロジーの紹介にとどまらず、ロボットの登場が戦争というもののあり方自体を大きく変貌させる可能性を提示している。
「戦争請負会社」、「こども兵の戦争」といった現代の戦争のあり方の変化をを鋭く切り取る作品を世に送り出してきた筆者ならではの一作。
投稿元:
レビューを見る
もし書店でこの本を手に取れたら、634ページからの「解説」を最初に読むといいだろう。紹介文として書こうと思ったことはほぼ全てここで語られている。
前半では戦場で使われるロボットや無人機の歴史と現状が語られる。現状と言っても2007年頃に取材しているので、今ではさらに進化しているだろう。その展開スピードの速さも重要なポイントだ。そして後半はロボットや無人機が戦争に使われることで戦争や軍隊のあり方がどう変わりつつあるかを解説している。
前半のテーマに興味があって読み始めたが、より強く印象に残ったのは後者だった。無人機の導入は自国兵士の死傷者を劇的に減らす。しかし安全な場所からリモコンで爆撃機を操縦しているパイロットは本当に軍人として戦争をしていると言えるのだろうか?敵を殺すことができるが殺される危険はほとんどゼロという彼らは、軍人としての誇りや尊敬を得られるだろうか?
9.11で幕を開けた21世紀は非対称戦争の時代と言われてきた。だが実際はそれ以上に大きく「戦争」の姿が代わりつつある。無人の荒野で自律型ロボット同士が戦う日が来るのも、そう遠くはないだろう。はたしてそこは、戦場と呼べるだろうか。
また、しばしば戦 争に反対する理由として挙げられるのは自分や子供たちが死んだり傷ついたりする危険だ。では自分たちの安全は確保されていて、海の向こうにいる悪 い奴らをやっつけるだけなら、反対する理由がなくなるのだろうか。いや、そうではないはずだ。殺されることだけでなく、殺すこともまた忌むべきことであるはず だ。もし自分の大切な人は決して殺されたりしませんと保証されても、どこかで誰かが殺されるなら、やはり私は反対したい。
投稿元:
レビューを見る
すでに戦争はロボットとAIが主役になっていること、また、その変化によって戦争に関わるあらゆる側面、人や組織、戦略やテロリストまで、変化していることを詳細に書き連ねてある。
驚くべきとこはこの著作自体は何年も前の内容であることで、今の現場ではさらに進んでいることが推察され若干悪寒を覚えた。
かなりの厚さだが読みやすかった。全体を抑えかつ詳細に書いてあるので戦争の今を抑えるのに必読だと思う。
投稿元:
レビューを見る
一生懸命読んだ。ロボットを使うメリット、デメリット。そもそもロボットとか戦争とか関係なく、情報へのアクセス性が向上することで、管理職がマイクロマネジメントを始めてしまう、という話が面白かった。