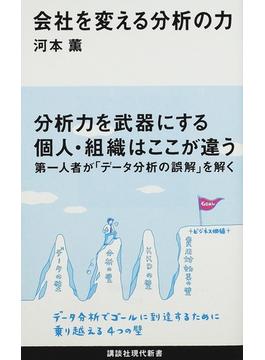紙の本
分析とは何かを教えられる本
2017/09/26 21:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mistta - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は決して分析に関する専門書ではない。
もちろん、分析の手順やノウハウなどについても触れられているが、
それ以上に、分析には、そもそも、その課題が本当に分析を
するに値することかという検討が必要なこと、
分析の本来の目的をしっかり考えることの重要性を説いており、
勉強になる。
読んで分析に取り組む意欲が湧いてきました。
電子書籍
データ分析は使ってこそ意味がある
2017/05/14 16:03
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
仕事に役立て用と思い読みました。
データを分析し、それを持ってビジネス
を動かすことの重要性が分かりました。
投稿元:
レビューを見る
データ分析の心得や分析力を高めるための思考法をまとめた本、大阪ガスのデータ分析センター所長が書かれています。
データ分析から得られた知見をどのような意志決定の参考にし、どのような効果を得ようと考えているのか。そもそも分析テーマは適切か。
より上流にまでコミットし、意志決定への寄与度を上げ、導入後の成果を最大化する。
これこそが分析プロフェッショナルだそうです。
マーケティング課題から調査目的や課題に落とし込むリサーチと本質的には同じです、そりゃそうか。
雑多な作業に追われて忘れがちなリサーチャーの存在意義を、再認識させていただきました。
それにしても大阪ガスは素晴らしい、行動観察にデータ分析。
投稿元:
レビューを見る
大阪ガスの方の本。よくあるIT業界視点ではなく工業よりなので、自分にはピッタリ。気をつけねばならない指摘が多数。「使わせる力」と「役立つことに貪欲になる」は忘れてはいけない。
投稿元:
レビューを見る
「一つの成功の近くには、別の成功のチャンスが潜んでいるかもしれません。」
最近話題の統計について書かれた本。”統計”と聞くと、数学やITを連想するが、この本では、問題発見能力、分析力、実行力がより大切だと説く。どのような分析モデルを作っても、それは今までの状況がこれからも続くとい前提に基づいているので、将来を予測することができると傲慢になってはいけない。結局それらはプラモデルと同じで、本物の現実にはなれないからである。
重回帰分析等の専門用語に対する解説はないので、この本から統計に対するスタンスを得、より技術的な本に移ればよい。統計への著者の真摯な思いは、これからも大切だと思う。
投稿元:
レビューを見る
単に分析をする統計などの知識が重要なのではなく、いかにビジネスの意思判断に貢献するかという視点を持つこと。分析が解決に役立つ問題を現場から探す「課題発見力」、分析結果をきちんと「使わせる」技術。
自分は普段からハウツー本を好むが、読んでもあまり身にならないのはノウハウだけを蓄えて、解決すべき自分の課題を設定したり、そのノウハウを普段の生活で自分に使わせたりする視点がないからだと気付いた。
投稿元:
レビューを見る
しつこいくらいまでのデータ分析に対する気構えが書かれています。
気構えオンリーですが、これから挑むに当たっての気持ちが出来ました。
投稿元:
レビューを見る
期待感を持って読み進め、3章では途中でやめようかとも思った。分析者をタイプ別に区分するってところや、言い回しがどうも受け付けない点があったから。
でも4章はよかった。好奇心をもってがんばろうという気になった。一流の分析者になる道は、品質管理部門で一流になる道にも通づると感じた。悪さを発見して指摘するだけという活動は、目の前の分析のみに終始するのと等しいから。
投稿元:
レビューを見る
技術的な話ではなく、純粋にデータ分析の結果をビジネスにどう絡めていくか、実務家としての視点から語られています
門外漢にはあまり持ち帰りうる内容がなく、プロには既に常識的になっているであろう部分が多く、対象読者層としてはやや限られてしまうのではないかとの危惧を覚えました
投稿元:
レビューを見る
データ分析の価値は問題を解決できたとき、意思決定できたときにある
ビジネスを意識した問題設定が大切
データ分析を行った際には、必ずその結果はどのように意思決定に役立つかを考える
問題は現場にある。積極的に現場に出て、担当者とコミュニケーション
課題発見力⇒人脈を通じた情報収集
投稿元:
レビューを見る
[読んだ理由]==================
Amazonでsuggestされてた本(後述)のレビュアーが言及してた。その本よりはビジネスよりとのことだったので、より実践的で役に立つかな、と思って。
データサイエンティスト養成読本 [ビッグデータ時代のビジネスを支えるデータ分析力が身につく! ] (Software Design plus)
[読んだ後の感想]==============
具体的な解析手法の詳細(解析の原理や、どういう時にどういう手法を使うべきか)についてはほぼ全く触れておらず。あくまで技術的な知識はある人を前提に、どうやって技術を業務に活かすか、の観点での話。そういう点では拍子抜け。
[備忘録]======================
■第一章:データ分析に関する勘違い
代表的な分析手法と事例:
予測型
販売量予測
医療費予測
異常検知型
機器故障予兆分析
サイレント故障分析
サーバログ解析
最適化型
車両配置最適化
在庫最適化
ワークスタイル分析
自動化型
シフトスケジューリング
プラントオペレーション
判断型
顧客ターゲティング
エリアマーケティング
Webサイトアクセス分析
発見型
口コミ分析
アクセスログ分析
コミュニケーション分析
商品分析
リスク計量型
倒産リスク計量
市場リスク計量
社外データ活用
気象データ活用
渋滞データ分析
ITや分析手法をどんなに備えても、データから問題を解明するプロセスを構想する力がなくては、意味のあるデータ分析は生まれません。
身近にいる営業マンとのコミュニケーションを通して「こういった顧客属性にはこのような商品が売れるのではないだろうか?」という仮説力、そして「その仮説が正しくても、施策として実行できなければ意味が無い」という当事者意識。
分析の価値とは端的に言えば「その分析により意思決定を改善することで得られる効用
分析手法に関するこだわりを払拭し、意思決定に役立つことだけにこだわってみてください。大切なのは、データから意思決定に役立つ材料を得ることだけ、それを繋ぐ方法は統計分析でも数理計画でも単なる見える化でもいい。そう思うと、肩の力が抜けて、分析に対する正しい価値観が芽生えてくるはずです。
過去から現在まで十分なデータ量を用意できないならば、a,b,c,dのパラメ0田を正しく推定することは難しいのです。強引に推定しても、正しく推定できないのですから、出来上がったモデルはでたらめです。でたらめな分析モデルを作るぐらいでしたら、単純でも正しいモデルを作るほうがずっと良いのです。
ビクター・マイヤー・ショーンベルガーとケネス・クキエ:「Big Data:A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think(ビッグデータの正体-情報の産業革命が世界のすべてを変える)」ビッグデータの本質について「部分計測から全数計測へ(from some to all)」という言葉で言い表しています。
ビッグデータの活用について、実際にはそれほどうまくいっていない理由は、3つある。
1つめは、必要なデータが全て揃っているわけではないことです。例えばクレジットカード会社では顧客が「どの店でいくら払ったか」のデータは保有しますが、「何を買ったか」のデータは保有しません。
2点めは、説明責任を果たしにくいことです。ビッグデー0他分析では、因果関係はわかりません。分析結果を元に意思決定する場合、その理由を経営陣や顧客に説明できないのは大きな弊害になります。
■第二章:データ分析でビジネスを変える力
ビジネスでデータ分析をする場合、どれだけ多数の知識を得ても、どれだけ角度の高い知識を得ても、それが意思決定に役立たなければ無価値です。
完璧主義の分析者は、分析誤差の低減や曖昧さの回避に重点を置きすぎるあまり、意思決定に役立つことが二の次になってしまうのです。
kaggleのようなサイトの登場は、何を意味するのでしょうか。企業や個人は、自ら高度な解析能力を持たなくてお、百万円支払えば世界中の優れた解析力を持つ専門家の力を借りることができるのです。懸賞金が定額化してきたら、数万円で世界中の分析者の能力を借りられるかもしれません。企業は、自身で解決できなくても、必要なときに懸賞金を支払えば、データ分析で問題を解明できるのです。もしかしたら、「解く力」はコモディティ化していくかもしれません。
「解く力」と「見つける力」と「使わせる力」は三位一体です。「解く力」が備わっているからこそ、溶けるかどうかのフィルターを通して「見つける」ことができますし、自らとくことで得た自信を持って「使わせる」ことができるのです。ですから、企業は「解く力」を保有する必要はあります。ただし高度な「解く力」だけで他社と差別化することは難しくなってくるかもしれません。
「勘と経験」にプライドを持ち、データ分析には懐疑的な現場の人間の心を開き、データ分析の良さをわかってもらい、使っていこうと思わせる、これが「使わせる力」です。
■第三章:分析力を向上させるための流儀
自らに問いかけてもらいたい。「この数字に責任を取れるか?この数字で会社が意思決定をしても、後悔しないか?もし、会社のお金ではなく自分の全財産を投資するならば、自分の分析結果を信用して判断するか?」
「問題分析を設定するステップ」を無意識のうちに省略してしまい、いきなり数値計算をしがち。数値計算を始める前には、必ず一呼吸置いて、今からどういう分析問題に取り組もうとしているのか明確にし、その問題をとけば意思決定に役立つか吟味しなければなりません。
分析者は、もっともっと意思決定に注目しなければなりません。自分が取り組んでいるデータ無錫は、どういう意思決定に使われるのか、どれぐらい重要な意思決定7日に感心を持たなければなりません。つまり、分析者は「分析問題」だけを意識するのではなく、分析結果の活用先である「意思決定問題」も意識しなければならないのです。
あなたも、身近な意思決定について思い浮かべてみてください。無意識のうちに、選択肢を狭く捉えている場合はありませんか。人は、しばしば選択肢を狭く捉えてしまう傾向にあります。そして、選択肢を狭く捉えてし���えば、その中で最善の決定をしたとしても、それは広い選択肢の中ではベストな決定ではないかもしれません。
Excelを使う場合において、私が心がけている点
①データと計算式は、混在させずに分ける
②計算式のパラメータは直接セルに入力せず、外出しする
③データには、単位をつける
④数式には、うう年後に振り返っても理解できるように注釈をつける
⑤子0渡韓おリンクやファイル間のリンクは、一方高のツリー構造とする
⑥不要になったデータや数式は消す
⑦ファイル名称は、それを見えればなんのファイル化わかるような名称にする
Ballpark Estimate:ざっくり計算/ざっくり理解。ざっくり理解には、かなりの探究心と暗算力が求められます。初めのうちは、ストレスを感じるでしょう。でも「ざっくり理解」できるようになると、スッキリするようになります。その「すっきり感」を覚えると、分析ソフトウェアが出力する値やグラフを、そのままうのみにすることが気持ち悪くなってくるのです。
データ分析の結果について、文章だけでビジネス担当者を納得させてみましょう。それほど簡単なことではありません。はじめに、あなたは自らの理解度の低さに気づくはずです。そして、文章を練っていくプロセスで、抽象的な理解から具体的な理解へ、断片的な理解から全体的な理解へ、表面的な理解から本質的な理解へと進化するはずです。
■第四章:分析プロフェッショナルへの道
分析プロフェッショナルと、分析スペシャリストが違う3点目は、専門性です。分析スペシャリストに専門性とはなんですか、と聞くと、「決定木分析」とか「テキストマイニング」といった分析手法を上げるかもしれません。でも、これらは方法論です。売り物にはなりません。包丁の使い方が上手いからといって、それだけでは売り物にならないのと同じことです。売り物になるのは、中華料理屋イタリヤ料理や会席料理といった得意料理です。同じように、分析プロフェッショナルは、売り物になる得意分野を持たなければなりません。たとえば「顧客離脱分析」とか「ウェブアクセスログ分析」とか「サプライチェーン最適化」とか、「この分野のデータ分析なら任せとけ!」という誰にも負けない分野を持たなければなりません。
投稿元:
レビューを見る
「経営にインパクトを与えるのはビックデータとは限らない。ビックデータは因果関係は説明ができない。」実務者ならではの視点は、自分も元実務者の端くれとして賛同できる。
投稿元:
レビューを見る
データ分析はビジネスの意思決定のためにあるのであって、たんなる分析に終わってはいけないと。「ビッグデータ」は、今までサンプル調査しかできなかったものを、全数調査にできるとも説く。
昨今のデータサイエンスブームが、よくわかる。
それにしても著者は、分析ばっかりやらされ、それがビジネスに結びつかなかったことが多かったのか、意思決定に結びつけることを繰り返し述べている。
この本に書いてある通り、分析を意思決定に繋げるためには、右脳が必要になってきているので、データ分析の本質を知りたい右脳な人達にもお勧め。
投稿元:
レビューを見る
データ分析をどのように経営に役立てるのか、
考え方によって、データ分析のやり方が変わってくる
概念的にはよくわかる本です。
投稿元:
レビューを見る
「分析の価値」=「意思決定への寄与度」x「意思決定の重要性」
ということをひたすら述べた本。
個人的には、
『データ分析を駆使したボトムアップ型経営、すなわち、現場が分析力を駆使することで現場力をさらに高めるような経営スタイルもめざすべきではないでしょうか
私は、そのような日本版「分析力を武器とする企業」を模索していくことこそが、日本企業の競争力を高めるために重要ではないかと考えます。』
という部分がグッと来た。