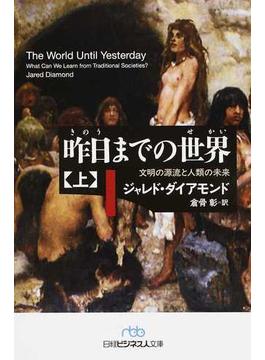紙の本
人類を考える
2019/04/18 19:33
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:怪人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本では2013年に発売されたものだが、発売当初購入後書棚に入れておいたらそのままになってしまった。最近、テレビで講師として登場する著者を見て思い出し、取り出して読了した。
まくらが長くなってしまったが、この本の内容はとても興味深くおもしろい。ニューギニアを研究フィールドとしており、ここでの経験したことが織り込まれている。家族、宗教、安全、健康など身近な話題を取り上げて文明論を展開する。生物学、文化人類学、生理学など間口と奥行きのある読み物になっており、読んでいて楽しくなる。これから、人類や地球はどうなっていくのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
人類学の碩学が取り組んだ意欲作。
高度先進工業社会が置いてけぼりにした「昨日までの世界」=伝統的社会こと未開文化にある風習を観察することで、現代の課題解決を探る。
ジャレド・ダイアモンドは、タヒチに憧れたゴーギャンやアフリカの情熱に魅せられたピカソのように、忘れられた文明の底力に取りつかれたのだろう。
子育て、高齢化社会。社会保障のモデルを先進国に探す前に、考えるべきことはあるのではないか。
投稿元:
レビューを見る
ジャレド・ダイアモンド久々の新作。「昨日までの世界」は「現代社会」でない、伝統的社会を指す。「"現代"社会」は語弊があると思うけど、要はWIRED( Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic )な社会。
高地ニューギニア人の、白人とのファーストコンタクトのエピソードが面白い。白人の野糞を見て、こいつらも同じ人間だと理解したと言うのだw。
1時間に4回の授乳、3,4歳での乳離れ、絶えず誰かが周りにいて、決して一人になることがない子供達。
諍いの解決に当事者間の感情が最優先に考慮されること。
知らないことが一杯ありました。
投稿元:
レビューを見る
相変わらず論旨が明快で、なおかつ興味深いエピソードが満載。真っ直ぐな印象を受ける爽やかな文体で、すらすら読める。
投稿元:
レビューを見る
我々は1万1千年をかけて現代文明を醸成してきたが、「現代文明」を1万1千年前と変わらず過ごす人々がおり我々の「現代文明」に遭遇したとすれば何を感じるか、非常に興味深い考察がこの本に書かれている。「もしタイムマシンがあったら」というSF古典が実際にニューギニア高地で起こり、そこから伝統的社会と国家社会の比較が可能になったのは事実は小説よりも奇なり。
『銃・病原菌・鉄』同様、ジャレド氏の洞察は極めて優れたものだが、ニューギニア高地を基にした小規模伝統的社会と国家社会の対比は千載一遇の(そして二度とない)機会であったことが分かる。上巻は領土権、戦争含め調停制度、子どもや高齢者の扱いについて分析しており、国家社会の「現代文明」に生きる我々からすると特に嬰児殺しや高齢者遺棄など残酷に思うがそれは生存と秩序を実利で兼ね合わせた結果だということが理解できる。
国家社会の「現代文明」と伝統的社会の「現代文明」は異なれど、冒頭の空港の風景は人間の環境への適応性を感じさせる一幕である。
投稿元:
レビューを見る
安心安全便利快適を志向し続けている我々はその代償として様々なものを失っている。それに気付いていながら資本主義に抗うことができずにまさに邁進し続けている。我々人類が得てきた叡智をもう一度振り返って今世界が進もうとしているのとは別の世界を志向する必要性を教えてくれる著作。
投稿元:
レビューを見る
「昨日までの世界—文明の源流と人類の未来(上)」(ジャレド・ダイアモンド:倉骨 彰 訳)を読んだ。
普段あまり読まないジャンルなので(上)を読み終わった今のこの段階では、この本がこの先(下)において私をどこまで運んでくれるのかが想像できない。
が、大いに期待したいところである。
投稿元:
レビューを見る
447ページ。
テレビやゲーム、書籍といった、外部から提供され、受け身で享受する形の娯楽で消費される時間はこれっぽっちもない。
耳が痛い。そうですよねー、受け身すぎ、楽しすぎと自覚あるんだけど。
まだ国家社会に組み込まれていない社会を観察し、その価値観や様式から多くの学びがあるという内容。まったくもってその通りだわ。
投稿元:
レビューを見る
歴史について、断片的ではなく包括的に学ぶ方法はないかと思い選んだ。
開拓されていない民族の行動様式から、高度に文明発達する前の人間社会を覗こうとする試みが面白い。
システマチックになるために全体最適を選んで抜け落ちた部分が、技術によって補われていくのがブロックチェーンなのかなとは思った。勉強したくなった。
シェアした方が経済効率がいいから塊ができる
ハッシュタグみたいなものを言い合って関係を確認するんだねー
外側を敵とすることで、中の関係を強固にしようとしてるんだろうか
貨幣も今は中央政府が管理するのが普通
贈与と返礼から、交換に変わったと
地方の暮らしは結構古典的な暮らしとの類似があるのかな
通年上の独占で繋がっているから関係が続く
機能までの世界には、全く知らない人はいないという意味で示唆的
個人間の利害関係の調整で終わらない繋がりがある
今は勝ち負けの時代だから相手の事を慮るなんてことは少なくなっている
国家社会では誰に責任があるか、民族では被害者の感情が重視される
女性というのはいつの時代も争いの元になる
投稿元:
レビューを見る
ダイアモンドにすればまさに本分たるフィールドについて書いているはずなのだが、以前の作品にあったようなズバッとした切れがないのはなぜか。ただ、昔のヒトは余所者と見れば攻撃するか逃げるかだったというのは、言われてみれば成程だが、やはり目からウロコの感はある。
投稿元:
レビューを見る
赤ちゃんがいるので、とりあえず第5章の子育てのみ。素晴らしく面白く興味深い。この著者の本ははずれなしです。
スリングなどで常に抱っこ(スキンシップ)、泣いたら10秒以内に誰かが反応、一緒に寝る、集団で育てる、何をしても個人の自由(適者生存)、異年齢の遊び集団、大人の模倣の遊び、勝敗を競わない
フランスの子育ての本を読んだばかりで、色々違う点も面白かった。
今日で0歳四ヶ月だけれど、狩猟採集民の子育てと、フランスなどの現代的な子育ての、良いところどりをできたら嬉しいし楽しい。
投稿元:
レビューを見る
著者が著者だけに期待したんだが、とにかくリズムが悪く読みづらいので、テーマに引き込まれない。戦争・紛争・係争・子育てと、面白い主題なんだから、もっと生き生きダイナミックに展開できそうなもんだけどな。上巻3分の2で挫折。
投稿元:
レビューを見る
「昨日までの世界」とは、人類の祖先とチンパンジーの祖先が進化のたもとをわかった約600万年前から、農耕社会へ移行した約1万1000年前までの人間の営みのことを指す。
ニューギニアなどの伝統的社会はこの「昨日までの世界」の生活の特徴が残っている。
本書は、伝統的社会と西洋社会を対比し、人間のあらゆる営みについて論じることで、両者それぞれの長所・短所を炙り出す。
上巻は主なトピックは、争い、子育て、高齢者の扱い。
多数のエピソードが紹介されていて興味深い部分もあるのだが、内容が微細すぎて精読はできていない。
投稿元:
レビューを見る
個人的にはジャレッドダイヤモンド4作目。面白い。今回は、伝統的社会と現代社会を比較しながら、その相違点や類似点を探していき、最終的に現代社会の課題解決の提言をしていく作品になっている。伝統的社会があまりに現代と違いすぎる部分があり、ある意味自分達の価値観も現代社会の仕組みの中で出来上がっていったものだと気づかされる。
以下、個人的に面白いと思ったこと。
・現代は車や電車、飛行機などで遠方に行けるし、街中で見かける人はほとんど見知らぬ人。だけど伝統的社会の人々は人生をほとんど自分たちの周りで送り、見知らぬ人と会う機会も少ない。それ故の問題解決の仕方、争いの仕方などがある。
・現代は子供の行動は教育と遊びで完全に分けられているが、伝統的社会では子供は集団の中で、遊びながら学んでいくことが多い。そしてその利点もある。
・文字がない伝統的社会において、老人たちは歴史や知識の伝達者として重要な役割を果たしている。
投稿元:
レビューを見る
マロとビリーの事件についての賠償の流れは、傷ついた遺族を慰め、謝罪を実現させ、物質的な補填もされ、こんな事例があるのかと感嘆した。被害者・加害者の双方が忍耐強く冷静で、誠実であり、交渉のまとめ役も有能だったからこそ実現できたかなり高度な解決だと思う。(これが一般的なケースなのか、交渉決裂することの方が多いのかは、わからない)
一方で賠償で収まらなかった場合は終わりのない報復戦争に発展してしまうという事実は、高度な交渉術とのギャップも大きくショックであった。中央集権政府の登場で伝統的社会の戦闘がなくなってしまったということは、当然ながら彼らが凶暴で野蛮だから戦闘をしているのではないわけで、現時点で国家社会に生きる人々も何らかの理由で無政府状態になってしまえば同じような状況にたやすく陥ってしまうということだろう。
赤ん坊が泣くと10秒以内に誰かがあやして泣き止ませるという話は面白かった。授乳かオムツ替えか何らかのトラブルだけでなく、純粋にスキンシップを定期的に求めるために赤ん坊は泣いているのかもしれないし、それが免疫や精神的な成長などに関わっている可能性はあるかもしれない。