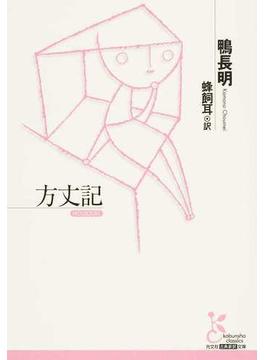電子書籍
ただただ「分かりやすい」
2019/12/02 16:54
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ワシ - この投稿者のレビュー一覧を見る
望月通陽氏のよく分からない表紙、地味な上に「現代語訳だけしましたが?」といったどこか投げやり感も漂う構成。
分かりやすく、読みやすく、もうひと味欲しい!というのも正直な印象。こうしてみると「故・橋本治がどれだけ偉大だったか」がよく分かる。
現代では差別語扱いの部分だけ、意味なく大胆な意訳にチャレンジしてみたり。
解説もウィキペの誤変換・誤読・出典なしを引っ張ると、デキの悪い学生のようなことをやっているのでご注意。
ほぼ読み下しただけの文章を”訳”と言って良いものか。初見の方にはツマラナイ作品だと思わずにいて下さるよう切に願うのみ。
もっとも権勢争いの経緯、天変地異や大火の被害とその推測、執筆往事を知るための資料・図表は他社の類書より充実していて、このバランスの悪さがもったいない。
…さて「公家も貴族も貧乏くさい直垂なんか着て」とあるが、現代の我々の衣服なんて作者からみたら貧相どころの騒ぎじゃないよね(違。
下鴨神社で後継争いに敗れた作者が、神職神役を捨てて「出家」して、メモ魔と化すのは結構日本らしいように思う。
達観でもなく、世をはかなむでもなく、生き抜いた証であることはお分かり頂けるはず。
天変地異は克服するすべもない。まずは現状を肯定してそこからを考えるよりないのかも知れない。
本書には実際に起きた事しか書かれていないのだから…。
さて、大宰府の跡取りが國學院を二浪二留して余裕で神職に収まったり、祝詞も読めない大社の宮司がすごい嫁さんを貰ったり、実の姉を刀の錆にした八幡宮だったり。
どうも諍いというのは時代を選ばない。
紙の本
解りやすい
2018/10/06 21:06
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみしょう - この投稿者のレビュー一覧を見る
訳が とても解りやすい。和歌や訳者エッセイも付いて、一層 鴨長明が身近に感じられた。
そして 災厄の様子も 地図まで有り、手に取るように でした。
投稿元:
レビューを見る
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にはあらず
すべてのものは生まれては滅び、変化する。
世の中では何ひとつ安定したものはなく、すべてのものは移りゆく。そのなかでいかに生きればよいか
ということ考えて、方丈記を書いた
そして晩年は山の中の暮らしに愛着を抱く様子を記すがそれすらも違うのではないかと思いつつ終わっている。
悲しいことも嬉しいことも、いつかは褪せていく。
そして私自身も変わっていく。
不幸だとか幸せだとかそんな単純なことではなく、変わっていくのです。
投稿元:
レビューを見る
放送大学の島内裕子先生の薦めで、方丈記を読もうと思い、本書をだいぶ前に購入した。
解説、原文、現代語訳、関連著作、地図、年表と至れり尽くせりだ。たしかに、鴨長明を身近に感じられた。また、彼のような晩年は羨ましく思う。
投稿元:
レビューを見る
方丈記
現代語訳がシンプルでいい
こうして俗世に向けて書かざるを得ない執着をまだもっていたことは確かとしても、この程度しか書くことが残ってなかったということも確かだろう
実は大したことは何も書いてないことがすごい
ただ、「人」と「栖」として、住む処、所在とでもいうか、それを人と同じレベルで意識しているところが面白い、と指摘している解説が面白い。なるほど。
普通は身分や名誉や財産や、といった社会的意味のものをいいそうなところを、栖、とは
投稿元:
レビューを見る
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。」原典を最初に読んだ。古文には違いないが、苦手な自分でも大意が理解できる平易な文章。鴨長明が実体験した大地震を含む災害の描写は、時期的に東日本大震災の記録とオーバーラップする。希望する官職に就けず、運がないと思いながら方丈の庵で生活する部分に、今の自分の来し方行く末を思い、長明のような暮らしも悪くないと感じる。
投稿元:
レビューを見る
4月の予定が6月に延期。栄枯盛衰、無常観を書き連ねた書物かと思ったけど、ちょっと違ってた。それもあるけど、ちょっとしたルポルタージュ風暮らしの記って感じだった。
投稿元:
レビューを見る
人生は無限に続くものではないことを実感する中高年になってから読むと、なかなかに味わい深いものがある。現代文なのも良い。
投稿元:
レビューを見る
1.この本を一言で表すと?
著者の隠居生活のエッセイ本
2.よかった点を3~5つ
・読経に気持ちが向かないときは、思いのままに休み、なまける。(p39)
→そんな生活してみたい。
・世界というものは、心の持ち方一つで変わる。(p48)
→このような生活に慣れれば満足なんだと思う。
・もし、気に入らないことがあったら、簡単によそへ引っ越せるようにという考えから、そのようにしている。(p37)
→そんな生活してみたい。
・自然災害の描写は具体的でわかりやすかった。
2.参考にならなかった所(つっこみ所)
・なぜ世間から離れた場所にこじんまりと住んでいたのか?世間に対する憎しみのような物があったのではないか?
・このような生活自体に迷いがあったのでは?
3.実践してみようとおもうこと
・
5.全体の感想・その他
・最初の感想は達観した人生だと思ったが、訳者エッセイ、解説を読むと、なぜ方丈記を書こうとしたのか疑問に思うようになった。
本当に達観したのなら、わざわざ方丈記を書き残す必要は無い。
・人生、社会に対する絶望感のようなものを感じる。
投稿元:
レビューを見る
私には素直で行き届いた現代語訳に感じられ、解説を含め本全体として伝わって来るものがありました。深刻な自然災害が急増する中で、以前より身近になったのかもしれません。個人的には、幼い少年と友だちになるようなタイプだったんだ、というところが一番ぐっときました。
投稿元:
レビューを見る
今でいうとテント生活、もしくはブルーシートの家に住んでいるのだろうか。60代の男性がひとりでひっそりと暮らす。そんな暮らしも悪いものではない、というのだが。あまり魅力的な暮らしとは思えなかったが、本当にこれでいいのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
「日本3大随筆」にも数えられる、古典の名作中の名作。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という書き出しも非常に有名で、日本で義務教育を受けた人であれば誰もが1度は眼にしたことがあるはずだ。わたし自身もこの書き出しに引きずられて、読むまでは本作は徹頭徹尾無常観を綴っているのかと思っていたが、かならずしもそういうわけではなく、後半では今でいうブログのような感じで、タイトルにもなっている「方丈」における隠遁生活や、そこでの感情が率直に語られている。俗世から離れ仏道を極めるために出家したのに、かえって草庵に執着してしまい、それもまた仏道に背くことであるという記述は、なるほどと思いまた深いと感じた。また、本作は「災害文学」としても知られており、著者がじっさいに見た竜巻や地震の様子がつぶさに描かれていて、なかなか興味深い。なかでも饑饉の様子は凄惨極まりなく、現在は世界各地からの観光客で溢れかえる京の街中に、牛馬が通れないほど屍体がゴロゴロと転がっていたという記述は、想像するだに恐ろしい。そのほか、急に遷都が決まったあとのバタバタとした様子など、当時の社会を知るうえでの貴重な史料となっており、その観点からも興味深く読むことができた。
投稿元:
レビューを見る
方丈記の
ゆく河の流れは絶えずして〜
の文章が好きで、手帳にも書いている。
有名なところのみ。
全部読んでみると方丈記って長いんだなという事を知った。
鴨長明は自然を愛して、自分の気の向くままに、一人だけの小さな草庵で暮していたようだ。
今からずっと昔の鎌倉時代の人でさえ、現代人と何ら変わりなく、お金持ちを見ると惨めな気持ちになったり、ボロを着ていると恥ずかしいと思う。
そんな気持ちになるくらいなら、町から離れて一人きりで暮らす。そうすれば天気や四季の移ろいや自分の食べるものなど、それだけに気を配っていれば良いと言う事になる。
自分はそんな生活は現実的にはできないけれど、心の中では鴨長明イズムを持って伸びやかにいきたいなと思った。
投稿元:
レビューを見る
こんなにも鴨長明に親しみを覚える日が来るとは思わなかった。
悠々自適の生活、移りゆく自然を愛で和歌と琵琶を嗜む穏やかな日々。それなのに俗世への想いを捨てきれない鴨長明の葛藤、生きる上での苦悩…。作者の息遣いと共に、学校の授業では分からなかった『方丈記』の魅力を知ることが出来た、記念すべき一冊。
投稿元:
レビューを見る
鴨長明の時代も見栄だの映えだのあって、でもそんなもんいつか無くなるんだよって。貴族だって立派な家が燃えたら無一文。マウンティングレースから降りたんだけど、ちょっと未練がある。昔から人間って変わらないのだ。