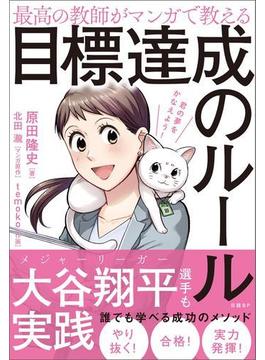学校の管理教育と混同しないでほしい。
2020/04/04 15:33
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七慢 - この投稿者のレビュー一覧を見る
原田氏の著作は読めば読むほど最新の心理研究理論に沿っていると思える。
原田氏の紹介する記録表を勝手解釈する人間には,「毎日の記録」など学校に提出する類しか連想しないだろう。
しかし,最初に目的をしっかり規定しない人間に,結果を達成できるだろうか。
特に注意しなければならないことは,「心を強くする」のルーティンである。ここは潜在意識を扱うので,理解されがたい。真実は,ルーティンこそ成長MINDSETを作る秘訣なのである。
表面だけしか読まなければ,「原田メソッド」を管理道具としか見ないであろうから,理解しやすい本書を十周くらいは読むべきである。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つばき - この投稿者のレビュー一覧を見る
夢を叶えるためには成功したときの自分のイメージだけではなく、夢を叶えたことで周りがどう感じるか、どうなるのかを想像することが夢を叶えるために必要な要素になるとは考えもしませんでした。
具体的な目標設定だけでなく、夢を叶えるための日々の目標を書くこと(毎日の過ごし方)で自信を持つことの大切さも書かれていて目から鱗でした。
自分の夢を叶えたいと思います。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽち - この投稿者のレビュー一覧を見る
かわいい漫画と文章のバランスがよくとても分かりやすいです。
試したいことがたくさんありました。
目標達成に近づきたいです。
投稿元:
レビューを見る
①過去から未来を考えるのではなく、
なりたい未来から今を考える。
②2軸マトリックス
社会的他者←→私
縦軸↑見えるもの
↓感情(見えないもの)
3日坊主でもいい。5日坊主、7日坊主となっていけばいい。やめたらまた始めたらいい。
③掃除をする→場をきれいにする→清める
投稿元:
レビューを見る
謙虚と傲慢は紙一重。当たり前の継続がどれだけ難しいことか。継続がどれだけ大きな力となるか。再確認した。
投稿元:
レビューを見る
目標達成のために、頭の中の未来のイメージを整理するという内容の本。
自分だけじゃなくて、他者がどう感じるかも考えて整理するというのは確かに、モチベーションがあがるのにいいのかもしれない。
オープンウィンドウ64というツールは大谷翔平も利用して、成長していったらしい(大谷マンダラと呼ばれてるそう)。ここまで頭の中を整理して、言葉にあらわせるというのはすごいなと思った。頭もいいんだろうなぁ。
そういえば、宮崎駿の監督の作品にはよく掃除のシーンがでてくると書いてあって、そうだっけ? と思って思い出してみると、確かによくあった気がする。精神論っぽいけど、掃除をすることによって心もキレイになるとのことで、確かに掃除は大切なんだろうなと思った。自分も整理整頓が苦手なんで、もうちょっとうまくキレイにできるようになりたいと思う。
三日坊主でもいいというのは、確かにいい考え方だと思う。まずはやってみることが大事だろうし。
ところでこの漫画、オチがこういうビジネス本の漫画っぽくない終わり方でビックリした。未来の自分を助けたと思ったら、過去の自分を助けることになったということなんだろうか。
投稿元:
レビューを見る
①夢かなシート
上 見えるもの
下 感情
右 私
左 誰か
として、4つのフレームを作り、
目標を考えてみる。
たすき掛けの法則がある。
右上、すなわち自分の見えるものの目標
(例えば売り上げ20%アップ)だけではだめで、
斜めの(たすき掛けの法則)誰かの感情部分も
掘り起こす。
(例えば上司が喜ぶ。お客様に商品を喜んでもらえる)
みたいな認識まであると、がんばりがきくようになる。
バランスが大事。
これは、今まで考えたことがなかった。
今までは、カテゴリー分け、
仕事、家庭、社会貢献、健康、自分
みたいな目標の立て方をしていたけど、
これは目からうろこだ。
特に、感情に着目する、という点。
いや、ときに考えることではあるんだけれど、
考えているだけでなくて、紐づけして記入する
ことで、よりはっきりと自分の中に落ちるんだと思う。
自分バージョンの夢かなシートを作る。
②オープンウィンドウ64
よくあるマンダラチャートってやつ。
大谷選手のはあまりにも有名。
ポイントは、
心
技
体
生活
の4要素をバランスよくすることだそうだ。
また、周りに書くのは実践志向で。
大谷選手のだと、「運」の周りに
ごみ拾い
と書かれている。これは〇。
~する、と書いてあるから。
さらによくするには、行動目標まで設定する。
○○までに~~する
〇回~~する
のように。
数値化。
③日誌
日誌には、
1今日必ずやること
2今日必ずやることがうまくいくために行うこと
(ここまで前日に書く)
3今日のよかったこと
4今日「ありがとう」といわれた言葉
5今日をもう一度やりなおせるなら
(その日を振り返って書く)
前日準備の大切さを実感している。
だからこそ、1、2は必要なのだ。
ここまでちゃんとしていないが、私も前日の夜には
次の日のTODOリストを作ってから寝ている。
これをしておくだけで、朝起きたときだらだら
しなくてすむ。
覚えているつもりでも、
朝起きて、TODOリストを見るのと見ないのでは
全然違うのだ。
3,4,5も、3行日記と似ている気がする。
順番を考えると、脳的には
反省→うまくいったこと
の方がいいのかもしれないが、
自分に合った方を選べばいいのだと思う。
④ルーティンチェック
これは挫折した経験あり。
ルーティンにしているものを書き出し、
できたかどうか〇をつけてチェックする、というもの。
面倒だった・・
これできる人すごいと思う。
見なければいけないものが多くなると、
本当にだめになる。
パソコンのデスクトップに書き出し、
やっているので、今のところそれでいいか。
投稿元:
レビューを見る
原田式目的・目標設定用紙などの書き方などを漫画の部分で分かりやすく説明してある本。その後の解説も重要ポイントのみ簡潔にまとめてあるので、活字が苦手な人にも取りかかりやすい。初心者向けなので、その他の細かいメソッドなどについても知りたければ、別の本を読む必要あり。
心をつくるという観点を中心に構成されている。心を使う、心をきれいにする、心を強くする、心を整理する、心を広げるの5段階。
目的・目標設定→態度教育・奉仕活動→実践→反省→他人とシェアというながれ。
投稿元:
レビューを見る
「マンガで解説」の手法を知りたくて、この本とライザップの2冊を購入。マンガで解説では無く、事例のストーリー部分がマンガで、解説は文章だった。
目標達成術に関しては、所々にストロークなど有名な心理学の考え方や掃除の精神などを織り混ぜつつ、これなら何となく目標が達成できそうな印象を受けました。
ホントは実際にやらないと意味は無いのですが、読み終えた頃には既に目標達成した気分に。。
投稿元:
レビューを見る
原田先生の目標達成の技術が
マンガで分かりやすく吸収出来る。
書くことによって頭の中のイメージが
整理され、やる気が高まり、
気づきの能力も高まる
自分を変えることで、夢が叶う
そのための心の使い方、作り方
自分自身のために
チームのために
家族のために
いろいろなところで活用できるメソッド
投稿元:
レビューを見る
良い事も多く書いてあるが体育会系特有の謎理論もチラホラあり自分自身で咀嚼して活用する必要があると感じた。
今月末にミーティングで使用する為2週目読み始めます。
投稿元:
レビューを見る
1時間程度で読めて、かつ漫画部分が想像より心に刺さる。具体的方法に関しては知らない人は具体的行動に移すにはハードルは高いと思う。以後の自分のための思考としてはためになる部分が多いと思う。
投稿元:
レビューを見る
ゴリゴリの方法論ではなくて、「心」を主軸に目的を考えさせて目標を立て、自信をつけるためにも小さな行動を毎日積み上げていく、ということを理解した。
目的・目標の4観点(横軸に自分/他社、縦軸に有形/無形)、オープンウインドウ64、日誌(必ずやること、必ずやることがうまくいくために行うこと、良かったこと、ありがとうと言われた行動、今日をもう一度やり直せるなら)、ルーチンチェック表というツールも有効に感じた。
あとはやるかやらないか、それが問題だ。。。
投稿元:
レビューを見る
1.主体変容
「自分を変える」とは、自分の考え方や物事に取り組む姿勢や態度を変えることです。これを「主体変容」と言います。そう言ったのは「経営の神様」と称えられたパナソニックの創業者、松下幸之助さんです。
2.五つの心づくり
自分の夢や目標の実現のために、自らを導く方法が、「五つの心づくり」です。「心を使う」「心をきれいにする」「心を整理する」「心を広くする」「心を強くする」です。
3.改善行動と自己肯定感
自己肯定感が高いと、失敗を恐れずチャレンジし、困難に直面したときも前向きにとらえて立ち直っていけるといわれています。「もし、もう一度やり直しができるならば、どうする?」と改善行動を考えていくことは、自己肯定感を下げずにキープすることにつながるのです。
4.目的・目標設定
目的は「方向」です。目標は「距離」です。
今の自分と目的を結び、そこに階段を入れる。その階段を上っていくのが目標達成です。
まずは目的をはっきりさせる。つまり「何のために」を定めることが重要。
その生徒には「親孝行したい」という目的があって、だから「砲丸投げ日本一になって、奨学金を得る」という目標を達成しようと考えた。
つまり、目的が一番、そして目標は二番です。
5.目的・目標の四観点
「心を使う」ための一番大切なポイントは、目的・目標設定を四つの観点で考えることです。目的・目標を「有形=見えるもの」「無形=感情」の軸と、「自分=私」「社会他者=誰か」の軸とで考えていきます。海外の教育でも「目的・目標の四観点」を説明すると「これは素晴らしい」と評価をいただきます。
6.たすきがけの法則
四観点には「たすきがけの法則」があります。
「社会他者・無形」が大きくなると、「自分・有形」が促進されます。「社会他者・無形」をしっかり認識すると頑張れるようになるのです。これは人間が誰しも持っている善なる気持ちです。
それから「自分・無形」の感情が豊かに増えると、精神的にも余裕が生まれて、「社会他社者・有形」が促進されます。
「人のために」「誰かに喜んでもらいたい」「何かの役に立ちたい」という思いばかりが強くなり過ぎると、今度は自分自身への「振り返り」や「見立て」が甘くなります。
「目標は達成できなかったけど仲間がほめてくれた」「目標に向けて取り組む自分を見て家族が喜んでくれてうれしい」…… 気持ちや感情が満たされるだけで終わってしまい、結果がついてきません。
「自分・有形」だけではいけない。だけど、それをおろそかにはできない。やはりバランスが大切なのです。だからこそ四観点で目的・目標を考える必要があります。
7.オープンウィンドウ64(大谷マンダラ)
オープンウィンドウは、8×8=4のマスに、目標達成に向けた具体的な行動を書き込んでいくツールです。「目標達成のためにやるべきこと」を自分で考えるツールです。
オープンウィンドウ」は、まずシートの中心に、あなた(またはあなたを含む集団)がなし得たい目標を一つ書きます。次に、その目標の達成に必要な要素をその周りの八つのマスに書き込みます。これを「基礎思考」と言���ます。基礎思考では、結果を生み出す要素である「心・技・体・生活」の4要素がバランスよくちりばめられているとベストです。
次にこの八つの基礎思考を、放射状に伸ばした八つのマスに写し、その達成のために行う具体的な行動を周囲8マスに書き込んでいきます。「○○する」という形式で行動を示します。これを「実践思考」と言います。
「大谷マンダラ」にもまだ足りないところもあります。何が足りないのか。それは行動目標の具体化が十分でないことです。あいまいな単語や、抽象的な目標に終わっている部分があるのです。ほとんどの書き込みに数字や日付が入っていません。
8.心のコップを上に向ける
スタジオジブリの宮崎駿監督の映画には、よく掃除のシーンが出てきます。ほぼ必ずといっていいほど主人公は掃除をする。洗濯をするシーンも多いですね。そして掃除や洗濯をして次のステージに進んで行く。掃除が大切な行動になっています。
掃除をしたり、ごみを拾ったり、整理整頓をしたり、「きれいにする」という行為は、人の心もきれいにします。汚れた部屋や荒れた街にいると人の心はすさんでいきますが、清掃や整理整頓が行き届いた中で暮らしていると、人の心は晴れやかになります。
「学校職場再建の三原則」①時を守る ②場を清める ③礼を正す
「時を守る」「場を清める」「礼を正す」が身について、清掃・奉仕活動を自然にできるようになると、「心のコップ」が上を向いていきます
心を濁らせるものには、慢心によるおごりがあります。
勘違いしてはいけないことは、一見、謙虚な人と傲慢な人は対極にいるように思えますが、実はそんなことはなく、実際には紙一重だということです。
謙虚なままで居続けられれば、絶え間ない成長が期待できますが、これが実に難しい。
志を立てて、謙虚に努力して成功すると、傲慢になり、慢心を生み、成長が止まり、失敗につながる。その失敗を反省して、また謙虚にやり直しても、成功して気を抜くと、また成長が止まってしまう。
だからこそ、このマイナスの連鎖に陥らないように自分をしつける。そのカギが「成長の三原則」です。
9.未来志向への転換
過去を中心に考えても結果は出ません。過去の失敗はておく。「過去思考」から抜け出して、「未来思考」に変えるのです。
正しい未来思考から出てくる「やる気」こそが本当のモチベーションです。未来に対して「やれる」「やってみよう」と気づけば、前に進んでいけます。だからこそ未来を鮮明に描くことが大事なのです。
未来思考で物事を考えて、過去の失敗やマイナスの感情は整理し、自らの可能性を信じて行動していきましょう。
10.日誌で自信を育てる
未来に向かっていく力は自信で支えられます。では自信とは何でしょうか。
自信は2種類あります。自己効力感と自己肯定感です。自己効力感は、「やれる」「やれそうだ」という自分の能力に対する自信であり、自負心とも呼ばれています。自己肯定感は「失敗しても、自分の価値を見失わない」「自分大好き」という自尊感情・自尊心です。
この二つの自信を高めるにはどうしたらいいか。答えは二つあります。
一つは、あなたが所属する集団を、お互いをほめたり、認め合���たり、頑張りを讃え合えるような集団にし、そこにいるだけでイキイキ、元気になるようにするのです。
もう一つは「自画自賛」です。
一日を振り返り「今日のよかったこと」を1個でいいから書き出す。それが自己効力感アップにつながります。
それと「今日やったことで、人から「ありがとう」という言葉をもらったあなたの行動を1個でいいから書き出す。それが自己肯定感アップにつながります。
原田メソッドの日誌は、毎日の予定や行動を記録するだけでなく、自己効力感と自己肯定感の二つの視点から、「今日のよかったこと」「ありがとうと言われた行動」を記入する欄があります。
11.パフォーマンスの方程式
パフォーマンス=「スキル」「やり方」「方法」×「気持ち」
「気持ち」の種類は二つあります。
・プラスの気持ち=元気で生き生き、前向きに、ポジティブシンキング
・マイナスの気持ち=不機嫌、被害者意識、やらされ感、ネガティブシンキング
ご機嫌で働くこと。
笑顔は人を幸せにします。幸せなオーラを出している人には、みんなが心を開きます。
同じ仕事でも、どんな気持ちで行うかが大切だということが、おわかりいただけたと思います。
12.心の栄養
前章で説明した「心を広くする」には、視点を他者に向け、感謝し、分け与え、助ける、貢献するという意味が込められています。そして他者への働きかけとしてもう一つ重要なのが「ストローク」です。ストロークとは、「心の栄養」を意味します。体に栄養が必要
なように、心にも栄養が必要なのです。ストロークがたくさんやり取りされる職場、学校、部活、家庭はイキイキ元気になります。そしてパフォーマンスも結果として高まるのです。
また、「その一言を待っていた」と感じることができる、信頼できる相手からの的確なアドバイスや声かけほど、ありがたいものはありません。人の心のど真ん中に響く、そういった質の高い声かけを、私たちは「プラチナストローク」と呼んでいます。
13.ルーティンチェック
目標達成への行動を決めて、続けることができたかどうかを測るのが、原田メソッドのルーティンチェック表です。自分で「できた=○」「できなかった=x」をつけながら、セルフマネジメントします。「△」はありません。「○」の比率によって耐力、継続力が
わかります。今でいうレジリエンスです。
不思議なことに、「○」の比率が86%以上になると、目標達成がぐっと近づきます。86%という数字は、今までの経験値です。でも86%なのです。
よい行動は習慣化してしまうことが重要です。人間の行動のうち、自分で意識している
行動は3%にすぎず、97%は無意識の行動だと言われます。よい行動を習慣化して無意識に行えるようになれば、97%の潜在意識を使うことができます。
14.予測と準備
ここ一番の大事なときの自信を支えるものの第二は、「予測と準備」です。
成功する人は、最低最悪の状況を予想し、最高の準備を行い、楽観的に対応します。
失敗する人は、楽観的に予想し、最低の準備でサボり、悲観的に対応します。
投稿元:
レビューを見る
目標達成における基本的なマインドセットなどをまとめた本。
やや精神論っぽく聞こえるかも知れないが、社会人1年目や学生とかにとってはいいかも。