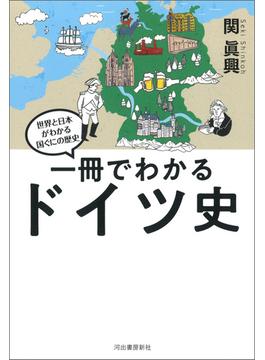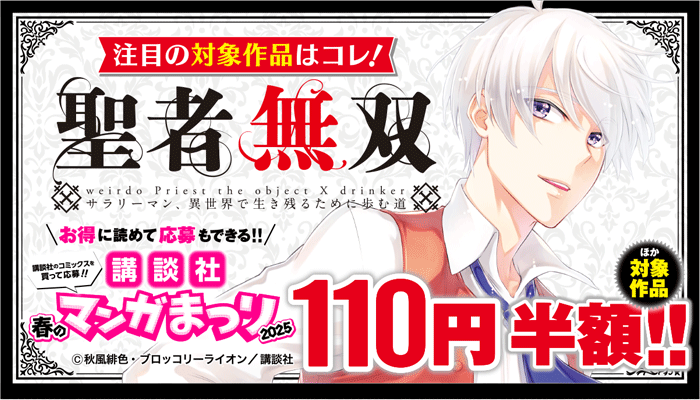投稿元:
レビューを見る
ザックリではあるがドイツの成り立ちから、周辺国との関係についての歴史。
小国の集合体がドイツとなったが、戦争を通して変化していく様も参考になる。
投稿元:
レビューを見る
「ベルリンは晴れているか」という第二次世界大戦の終戦直後のドイツを舞台した小説を読んだのがきっかけで、
ドイツの歴史に興味が湧き購入。
学生時代には、世界史の偉人達の名前が頭に入らず…
それ以来の歴史を学ぶ機会となったが、
本としては読みやすい。
教科書としても、ところどころに日本の同じ頃こんなことありましたーの解説で、対比が面白かった。
世界と日本の文化の差、島国としてのメリットやデメリットがあるなぁと痛感。
今回はドイツ史だったが、同シリーズでアメリカ、イギリスもあるそうだが、またの機会に読んでみたいと思う。
特にアメリカは移民で創立した国だし、広大な土地を一つの国にまとめあげる歴史は戦国時代にも通ずるので、面白そう。
投稿元:
レビューを見る
『一冊でわかるドイツ』関眞興 河出書房新社 2019.11 記録2020.3.6
ドイツ祖先の最初は古代ローマ帝国。ローマ帝国の2大川ライン川とドナウ川。向こう側は異境だった。その住人がゲルマン人。BC50代のローマ軍人カエサルのゲルニア(独・ポーランド・チェコ)を遠征した記録、
『ガリア戦記』にゲルマン人の生活が載っている。
3世紀~。地中海の東方にササン朝のペルシャ帝国が登場。
4世紀の末。ゲルマン人は人口増と食糧不足でドナウとライン川を越えてローマ帝国に侵攻。ゲルマン人の大移動。ローマ内で出征していたゲルマン人のオドアケルが476年に武力で西ローマを退位させる。西ローマ滅ぶ。
ゲルマン人の社会は4世紀ごろに10ほどの集団に分かれる、各集団に国王や首長がいて大移動を指導。最大勢力のメロヴィング家のクロ―ヴィスがフランク王国をつくりクローヴィス1世となる。
フランク王国は戦争によって領土を拡大する。
ゲルマン人は北アフリカにヴァンダル王国をつくる。現在のスペイン辺りに西ゴート王国をつくる。ライン川周辺にフランク王国をつくる。
9世紀。1族の内紛で分裂。三つのうちの一つの東フランク王国がやがてドイツになる。
ボニファティウス。7~8世紀ドイツの東部でキリスト教を広めて、今のドイツの信仰心の基礎をつくる。
7世紀ごろ。アラビア半島で預言者とされたムハンマドがイスラム教を興す。アラブ人はイスラムの団結を強めるために、周辺地域を攻める。イスラム教徒は西ゴート王国を滅ぼす。
フランク王国を強大化させるがピピン3世の息子のカール。カールはイスラム教と闘い、8世紀後半にフランク族の王となり今の仏・独・伊一帯を統一。
教皇領を巡ってイタリア半島の有力貴族と対立するローマ教皇をカールは助ける。見返りに800年のクリスマスに5世紀依頼途絶えていた西ローマ帝国の冠をカールに授け、カール大帝になる。
カール大帝は814に死去、フランク王国内で争い843に西・中部・東に分割。
西ローマ皇帝の地位は東フランク王国に引き継がれる。西ローマ皇帝は10世紀ごろからドイツ国王とイタリア国王を兼任する。
3つのフランク王国はどの国王の力も諸侯並み。王は諸侯のまとめ役だった。
10世紀半ばにドイツ国王になったザクセン家のオットー1世は当方が侵入したマジャール人を破りローマ教皇との関係強化を図る。962にオットーはローマ皇帝の称号を授かる。ドイツ王国は神聖ローマ帝国になる。
オットー以降の皇帝を決める選挙は対立が起きて13世紀は皇帝が選ばれない期間「大空位時代」。
14世紀半ば。有力な諸侯や聖職者7人が選帝侯になり、7人の選挙で皇帝を決めるルールを作った。当然自分たちで抑えれる権力が低い人物を選んで選定は形式的になる。
諸侯は自分の領土では権力を使えるので小さな国家ができる。領主君主。幕末体制に似ている。
皇帝は立場を強めるためローマ教皇のいるイタリアを支配しようと遠征し、不在になるのでドイツはさらにバラバラになる。
農業を中心の社会。荘園で農民は自��自足の生活をしている。移動を禁止されており農奴と呼ぶ。荘園の畑、春耕、秋耕、休耕の三圃制。農法が発達して農業革命が起きる。
11~13世紀末。ヨーロッパの十字軍(イスラムにとられた聖地エルサレムを取り戻す遠征軍)ドイツ騎士団の活動は東ヨーロッパに広がり農民も東へ移り住むようになる。
神聖ローマ帝国を継承するハプスブルク家も協会を支配下に置くためのイタリア政策を行う。スペイン・フランスもイタリアへの進出を狙い15~16世紀半ばまでイタリアを巡る争いが続いた。
ルネサンスの始まり。十字軍や北イタリア商人の活動で14世紀には神聖ローマ帝国に東ローマ帝国からヘレニズム文化がもたらされた。ヘレニズムとは「ギリシャ風」の意味。キリストが生まれる前のギリシャ時代の文化を示す。
ヘレニズムがヨーロッパで再注目されるのをルネサンス(仏語で再生)
ヘレニズムの人間の自由・個性を尊重する風潮。人文主義(ヒューマニズム)。
ルネサンスの代表的な建物はバチカン市国のサンピエトロ寺院。この建物の建築資金を集めたい教皇は贖宥状を売る。これにいかるのがザクセン生まれのルターが1517に「95か条の論題」を発表。
ルターは教会から破門、カール5世から撤回せよと圧力を受けるが屈しない。ルターは教皇と対立していたザクセン選帝侯から保護を受ける。聖書を独語に翻訳して大衆が読めるようにする。
多くの方言がドイツにあったがザクセンの官庁で使われた言葉で翻訳されて独語の基礎となる。宗教改革へつながる。
1524農民たちが決起。減税と賦役の軽減を訴える。ルターの「神の前に万人は平等である」に背中を押される。1525に反乱は領主たちに鎮圧される。
宗教改革の頃、神聖ローマ帝国の皇帝カール5世はスペイン王でもある。イタリアの領有を巡って仏と対立。体外で忙しくルター派は拡大する。1529、帝国会議で皇帝がルター派の布教禁止を宣言。ルター派の領主がプロテスト(拡大)する
ルター派はプロテスタントと呼ばれる。
カール5世(カトリック)とルター派(プロテスタント)の対立。1546~47にシュマルカルデン戦争。カール5世の勝利後も争いは続きアウクスブルクの和議が結ばれる。領邦や都市ごとにカトリック・プロテスタント選ぶ自由の原則が生まれる。
オーストリアの名前の由来は東辺境伯領のオストマルクに由来する。辺境伯とは国境を防衛するべく置かれた軍事拠点に派遣される住人の呼び名。オストマルクが12世紀ごろオーストリア公国となる。
ハプスブルク家はいまのスイスあたりの発祥。アルプスの高地はヨーロッパの交通が交わり重要地点。ハプスブルク家がオーストリアを支配するとスイスの人々は抵抗。3つの州が結束して200年以上にわたる戦いで15世紀に独立。
ハプスブルク家出身のルドルフ1世が1273に皇帝になる。その後に対立が起きて15世紀以降はハプスブルク家が皇帝の座を独占するようになる。ハプスブルク家は領土を拡大させて神聖ローマ帝国は名前だけの形骸化した存在に。
カール5世の死後、ハプスブルク家はスペイン系とオーストリア系に分裂する。1568にスペイン系ハプスブルク家の支配するネーデルラントが独立しようと闘う。ハプスブルク家は敗れてネーデル��ント独立。
プロイセン。オーストリアと同じくエルベ川の東の守りを任されていた。ルーツ①ブランデンベルク辺境伯。ルーツ②は当方植民の農民を守り教化するドイツ騎士団が先住民のプロイセン人を追い払い、名前を継いでプロイセン公国をつくる。
ローマ教皇の支配下である。
ホーエンツォレルン家のアルブレヒトがドイツ騎士団団長に。1523にカトリックからルター派に改宗。1525にローマ教皇の支配を受けない世俗国家プロイセン公国とドイツ騎士団国となる。
1618。ブランデンベルクの公国とプロイセン公国は合体。ブランデンベルク・プロイセン公国になる。
1701、オーストリア(ハプスブルク)と仏(ブルボン家)が争う。スペイン継承戦争。ブランデンベルク・プロイセン公国はオーストリアに協力して見返りに王号の使用を認められる。プロイセン王国になる。
領邦国家のひとつボヘミア(チェコ)の王としてハプスブルク家のフェルディナント2世が指名される。1618に彼を王と認めないボヘミアの一派がプラハ城のハプスブルク家の役人を窓から落とす事件が起きる。
30年戦争が始まる。オーストリアにボヘミアは打ちのめされる。戦争は仏の参戦で泥沼に。1648にウエストファリア条約
ウエストファリア条約は領主が領地の宗教を選べる内容。領邦国家の数は300以上あったと言われる、
神聖ローマ帝国の領土は失われて形だけになった。ハプスブルク家から脱していたスイスとオランダも独立を承認。
ルイ14世。1688に仏軍は独との国境にあるアルザス・ロレーヌに侵攻。神聖ローマ帝国のレオポルド1世はアウクスブルク同盟でスペイン・オランダ・スウェーデン・イギリスと組んで何とか撃退。1688~97.
オーストリア大公で神聖ローマ帝国のカール6世は1713に自分の家系がハプスブルク家の家督を相続できるような法律を作った。
1740.カール6世が死去。マリア・テレジアがオーストリア大公に。
これにザクセン選帝侯とバイエルン選帝侯が反対する。プロイセン王国のフリードリッヒ2世がオーストリア領のシュレジエンを攻める。オーストリアの弱体化を狙う仏とスペインも仲間に。
オーストリアはハンガリーと共に戦い、バイエルンを占領。ザクセンと同盟になる。
1745.カール7世が死去するとマリア・テレジアの夫がフランツ1世として即位。その年にプロイセンと講和条約。プロイセンはかろうじてシュレジエンを確保している。
オーストリア継承戦争のあとマリア・テレジアはとられたシュレジエンを奪還したい。だが単独でプロイセンには勝てない。敵対する仏との仲を改善。
マリーアントワネットを後のルイ16世こと皇太子ルイに嫁がせる。プロイセンのフリードリッヒ2世を嫌うロシアとも同盟を組む。
1756プロイセンと戦争。7年に及ぶがシュレジエンを奪還できなかった。
18世紀後半 啓蒙専制君主。プロイセンのフリードリッヒ2世。オーストリアのマリア・テレジア、その子供ヨーゼフ2世。自らの指導で市民を教育せねばと政治改革を行う。
18~19世紀。プロイセンではカント。ビュルテンベルク公国ではヘーゲル。ヘーゲルを継ぐマルクス。ショーペンハウアー。ニーチェ。フロイト。
音楽はバッハ。ハイドン。モー��ァルト。ベートーベン。ウィーンは音楽の都。
文学界では疾風怒濤(シュトゥルム・ウント・ドラング)がはやる。人の感情の動きを重視する作風が一世を風靡。フランクフルトのゲーテ『若きウェルテルの悩み』。ビュルテンベルクのシラーの『群盗』。
7年戦争後、1789.7.14にフランス革命。仏はオーストリアに宣戦。
1793.1月にルイ16世処刑。10月にマリーアントワネット処刑。
1794.クーデターで仏の新政府、オーストリアにナポレオンが宣戦して1797にライン川を仏にとられる。
講和条約2年後にナポレオンは再度オーストリアに攻める。1801にオーストリアは敗北。北イタリアを取られる。
1804.フランスの国民投票でナポレオンは皇帝になる。
1806.ナポレオンはドイツ西部を取り込みライン同盟をつくる。同盟といえどドイツは言いなり。これで神聖ローマ帝国は事実上滅亡。すでに形骸化していたがナポレオンがトドメをさした。
敗れたプロイセンは国内改革を進める。ドイツ経済は仏が支配する西側から発展していく。フランス革命の影響でドイツ人だというアイデンティティが形成していく。フィヒテの「ドイツ国民に次ぐ」とい講演で教育の改革を行う。
1812 ロシアにナポレオンは敗れる。プロイセンやオーストリアや他の領邦も加勢してライプツィヒの戦いで連合軍はナポレオンに勝利。
ナポレオンをエルバ島送りに。エルバ島を脱出したナポレオンはワーテルローの戦いでプロイセンやイギリス・オランダの連合軍に敗れてセント・ヘレナに流され生涯を終える。
ウィーン議定書でフランスとスペインは倒された王制を復活させる。だが神聖ローマ帝国はナポレオン中小の連邦がなくなり復活できなかった。
1815.6.8.ドイツ連邦に生まれ変わる。35の君主国と4つの自由都市。君主国には5つの王国(オーストリア・プロイセン・ザクセン・ハノーファー・バイエルン・ビュルテンベルク)。他に大公国・公国・侯国がある。
経済の発展で流通が盛んになり、通行税の負担が問題になる。連邦内の関税同盟がまとまって経済面ではドイツ統一の可能性が見える。
オーストリアはどことも関税同盟に加わらず、プロイセンとの格差が広がる。
1845~47.ヨーロッパで食糧危機。1848に仏で2月革命。ドイツの3月革命は失敗する。
オーストリアは1853クリミア戦争で領土を取れず1859はイタリア統一戦争で領土の一部を取られる。連邦内ではオーストリアを見限り、プロイセン中心に統一すべきという声が大きくなる。
ドイツ統一を目指すオットー・フォン・ビスマルク。プロイセン王に即位したヴィルヘルム1世は自分の後援である保守勢を強めるべく、パリ駐在の大使ビスマルクを呼んで宰相に任命する。
国家統一のために軍事行動を行うと演説で述べ、鉄血宰相と呼ばれる。オーストリアを排除してプロイセンを中心とする方針だ。
1864.ビスマルクはオーストリアと共にデンマークを倒す。2年後、支配を巡る対立でプロイセンとオーストリアの普墺戦争。オーストリアを破りオーストリア側に就いた国を占領してきたドイツ連邦をつくる。
親オーストリア派のバイエルンなどの南の国々が残る。
1870.プロイセンがフランスと開戦。普仏戦争。セダンの戦いで勝利したドイツ軍はパリを攻めて翌年開城させる。
18711.18。ヴェルサイユ宮殿にてドイツ帝国の成立を宣言する。ビスマルクはバイエルン国王ルートヴィヒ2世に城の建築資金を与えて見返りとしてヴィルヘルム1世をドイツ皇帝に推挙させる。ドイツ統一の達成。
ドイツから締め出されたオーストリア。ハプスブルク家が弱体化。第2の有力民族のハンガリー人との連携を強める。1867にオーストリア・ハンガリー帝国成立。
帝国内でチェコ人・セルビア人は冷遇されており、1878にセルビアがオスマン帝国から独立。
ドイツ帝国は22の君主国と3つの自由市からなる。人口と領土の2/3がプロイセン人。皇帝は代々プロイセン人が継ぐ。皇帝はプロイセンの首相を選んで宰相に任命する。
58議席のうち、17がプロイセンに配分される。
ビスマルクは1882にドイツ・オーストリア・イタリアの3国同盟をつくる。
ヴィルヘルム2世は積極的な政策を進める。保守的で意見の合わないヴィルヘルムを解任。
1890.プロイセンの憲法をモデルとする大日本帝国憲法が施行。岩倉具視の欧米視察。共和制のフランス。立憲君主制のイギリスと比較。結果的に君主の権限がつよいプロイセンの憲法が天皇を中心と考える日本のモデルとして採用。
バルカン半島を狙うロシアとドイツ。オスマン帝国から領土を回復させたいセルビア・モンテネグロ・ギリシア、
ブルガリアは1912にバルカン同盟をつくる。オスマンとの第1次バルカン戦争。オスマン帝国は敗れてヨーロッパの領土をすべて失う。
バルカン同盟は勝ち取った領土の配分を巡って同盟内で対立。第2次バルカン戦争が起きる。
1914.6.28。オーストリア皇太子夫妻がサラエボでセルビア人の青年に射殺される。オーストリアはセルビアに宣戦。
ドイツはオーストリア側につく。その背景、仏とは対立しているし、植民地ではイギリスと対立している。ロシアとの関係も堅調状態にある。ロシアが動員令を出すと呼応してドイツ社会民主党が戦争賛成に。
ヴィルヘルム2世は戦争を決断。ロシアとフランスに戦争をしかける。ベルギーにも仕掛けるとイギリスは怒り、英国とも戦争に。
山東半島で日本軍に敗れる。1915中立のイタリアが仏についてイタリア戦線がひらく。オスマン帝国とブルガリアは反ロシア路線なのでドイツに味方する。
1917にロシア革命で社会主義政権のロシアはドイツと条約を結んで戦線から離脱する。ドイツには追い風になり勢いを西側諸国にぶつけるが、米国の援助を受けるフランスは強くドイツは負ける。
1918.11.11。パリのコンピューニュの森で休戦協定。4年3か月の戦争は終わる。
ヴィルヘルム2世は弾劾されて退位が検討される。オランダに亡命する1918.11.8。ドイツ帝国は半世紀で崩壊する。
1919 ドイツ共和国成立。
1919.6.28。ヴェルサイユ条約。領土の13.5%・人口の10%を失う。
1919.1中央党・民主党が組んだ「ワイマール連合」という連立政府が政治を行う。中部のワイマールで国民議会を開かれるのでワイマール共和国と呼ばれる。
初代大統領は社会民主党党首のエーベルト
200-250兆円の賠償金が払えない。紙幣を印刷し続けてインフレに。
1914。1マルクで買えたものが1兆マル��に。ハイパーインフレ。新通貨レンテン・マルク発行でインフレを抑える。
1923。ヒトラーのミュンヘン一揆。
1925。エーベルト死去。選挙でヒンデンブルク大統領誕生。やがて強引な整形運営で社会民主党を内閣から排除する。
ドイツ帝国主義の精神を継ぐ軍人や官僚はワイマール憲法に反対だった。ナチスの前身「国家社会主義ドイツ労働者党」に社会主義が入っているのは社会主義を望む人を取り込みたっかたら。実態は社会主義など無関係。
ドイツ国内のユダヤ人は50万人ほどで人口の1%以下だった。ニュンベルク法で1935、ユダヤ人の公民権を奪う。ドイツ人との結婚禁止に。水晶の夜。
1945.5.7 ドイツ降伏
1947。4か国外相会談で米英仏はソ連と対立。ソ連以外の3国は西ドイツをつくる。
米国のマーシャルプラン(ヨーロッパ経済復興援助計画)連合国は新ドイツマルクを発行。ソ連も東で新しいマルクを発行するが価値が低いとみなされるので、西ベルリンにいたる道を封鎖「ベルリン封鎖」1949まで続く。
東ドイツは植民地の様だった。ただし非ナチス化されてプロイセン以降のユンカー制度は解体される。ソ連にならい集団農業が取り入れられる。
東ドイツの指導者はモスクワ帰りのヴァルター・ウルブリヒト。秘密警察のシュタージ。
1953 スターリンの死後、東ベルリンで反政府デモが起きる。スターリン死後の3年後のソ連トップのフルシチョフがスターリンの政策を批判。スターリンに苦しむポーランドやハンガリーでは脱社会主義を求めて反ソ暴動。
1961.8 ベルリンの壁で通行遮断
1962 キューバ危機
1989 ベルリンの壁崩壊
1990 東西ドイツ統合
2005 メルケルはドイツ初の首相
投稿元:
レビューを見る
ドイツのおおまかな流れはわかったように思う。領土の拡大があったとしても基本地続きなので、イギリスに比べ格段とイメージしやすかったように思う。
このシリーズ読んでて思うが、その国の学校の歴史の教科書ってどんな感じで書かれているのだろう?ドイツの教科書の歴史の場合ナチス関係がどうかかれているかも気になった。
投稿元:
レビューを見る
30数年前に3年半ほど住んでいたドイツ。何度か成り立ちを理解しようとするのだが、ヨーロッパの歴史は複雑すぎて、どうにも頭に入らない。この本を読んでなんとか頭に入るのは近世、ビスマルクくらいからだなあ・・・ しかし、私たちが住んでた頃の話もこうした歴史の1ページになっているのに感心する。そうか、全然理解できてなかったが、そういう事情だったので、ベルリンの壁が崩れたのは突然だったんだと納得。その日のテレビを見てて思い切り驚いたのを思い出す
投稿元:
レビューを見る
わかりやすさに振り切った初歩中の初歩を学べる入門書といった印象。ドイツ史は偏った知識しかなかったけども難なくスラスラと読めました。
大まなか情報しかなかったから本当に初心者さん向け。あと文化面も一緒に学びたい場合はルネサンス、バロック、ロマン派くらいしか言及されてないので向かないかも。
でもこの本のおかげで大まかな内容は理解出来たので、専門書を読む前のワンクッションのような役割をしてくれるとってもいい本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
ほぼ高校の世界史で理解できる範囲で、ゴート族からスタートして神聖ローマ帝国、プロイセン、からの東西ドイツを通史にした本。
文句なしの星5つ。
簡素な記述ながら、
「何を説いて何を省いたか」
を思うと、生半な知識では書けない内容。
読後、『戦後処理とは』と自国を顧みる材料ともなるだろうし、それこそが主体的に歴史を学ぶということ。
投稿元:
レビューを見る
高校の時に世界史が好きだったので、読んでみた。面白かった。
忘れている知識が結構あって、古代から現代までのドイツの歴史の流れを確認できた。他のヨーロッパや米露とドイツの国際関係も歴史が分かると理解できます。
ドイツはなかなか苦難の国だな、と改めて思いました。
投稿元:
レビューを見る
ざっくり以下の事が書かれていて、参考になりました。
フランク王国
ドイツ王国
神聖ローマ帝国成立
ナポレオン
神聖ローマ帝国滅亡
ドイツ連邦成立
ビスマルク
近代ドイツ帝国成立
ヴィルヘルム2世
WW1
帝国崩壊
ドイツ国成立
ヒトラー
WW2
ベルリンの壁
東西ドイツ統合
メルケル
投稿元:
レビューを見る
元予備校の先生が書いた、フランク王国が出来るところからメルケル首相が2013年に社会民主党と連立を組むまでのドイツの歴史。「『ドイツとは何だ』と初めて思った人に向けて、その歴史をわかりやすく紹介」(p.3)したもの。
本の装丁の感じや、イラストのタッチが柔らかく、入門者向けの歴史の本、という感じだが、本当に「ドイツとは何だ」と「初めて」思った程度の人がこの本を読んだら、思ったほどよく分からないんじゃないだろうか、とかやっぱりおれ世界史苦手だわ、と思ってしまう本だった。もうこれ以上は分かりやすくならないのだろうけど、なんか教科書を読んでるみたいに頭に入って来なくて、割と苦労する。世界史の勉強ってこんなものなのかな、と思った本。イラストはおれ好みだった。激しい歴史の場面なのに人物の目が点だったり、かわいいとまではいかないけど、ソフトなタッチ。p.51の「ボヘミア人の一派が、プラハ城にいたハプスブルク家の役人を窓から落とす事件」(pp.50-1)のイラストがあり、この窓のこの場所におれは行ったことがあるらしいが(と、一緒に行った人が後でこの本を読んで言ってた)、まったくおれはそれを覚えていないくらい、歴史が頭に入らないらしい。そんなおれでも、とりあえずドイツ史で重要な人物として、ビスマルクを解任したヴィルヘルム2世、という人物は印象的だった。領土拡大を目指したけど、イギリスに譲歩した?というあたり、よく分からないけど、とりあえず「20世紀のドイツが進む道を決めたのは、ヴィルヘルム2世」(p.114)というくらい重要な人物らしい。ビスマルクとヴィルヘルム2世、ということで、名前くらいは頭に入れたい。最後はオランダに亡命したらしい(p.132)。第一次世界大戦時の徳島県の「坂東俘虜収容所」の話は、なんとなく聞いたことがあったが、「今もドイツと徳島県の交流は続いています」(p.125)というくらいのものらしい。徳島に一度行ったことあるけど、ドイツを感じるようなスポットには行ったことがなかった。
第二次世界大戦時のナチスの本はいくつか読んだことがあるが、この本では本当にあっさりと書かれている。もしかするとあっさり過ぎることが頭に入ってこないし、教科書的な感じになってしまう原因なのか?とも思った。もちろん「1冊でわかる」という趣旨に沿うにはそうならざるを得ないということも分かるけど。
最後に旧東ドイツの話をあんまり知らなかったけど、「ソ連の属国のような東ドイツの政治体制を支えたのが、秘密警察組織のシュタージ」(pp.194-5)ということで、第二次大戦後にヨーロッパの中に、そこまでの体制があったのか、と思った。
あとは今のドイツについて知らなかったことと言えば、「かつては徴兵制を採用していましたが、2011年に中止」(pp.140-1)とか(そんな最近まで徴兵制だったの)、「アンゲラ・メルケルは、もとは旧東ドイツの物理学者」(p.211)(旧東ドイツの人なの?しかも物理学者!やっぱり理系の人は文系をカバーできるんだ)とか、断片的な情報として面白いと思ったところはあった。
もう少し別のドイツ史の本を読めば、この本で書かれている全体像が頭に入ってくるようになるのかもしれない。(21/06/13)
投稿元:
レビューを見る
図書館で。
2、3時間で読めるシリーズ。ドイツ版。
っと言っても、フランク王国、オーストリア・プロイセン、ドイツ連邦、近代ドイツ帝国、ワイマール共和国くらいまでは固有名詞ばかりであんまり頭に入ってこなかった。
基礎が足りなすぎるのか? 他の国のものも読んで理解を深めよう^_^
投稿元:
レビューを見る
ドイツ史の入門書。世界史の教科書からドイツ史の重要な部分を抜き出したような本。噛み砕いた平易な文書で書かれているので、初学者や中高生にも読みやすいと思われる。イラストが所々で使われており、堅苦しさを感じさせないようになっている。
ドイツ史に興味を持っている方やドイツの歴史を整理したい人におすすめの一冊である。
投稿元:
レビューを見る
両国の外交関係樹立ととらえられている日本と当時のプロイセンの
「修好通商条約」締結が、1861年1月24 日に実施されました。
そして2021年、ドイツと日本の両国の友好関係が160周年となりました。
この機会にぜひドイツの歴史を学んでみたらいかがでしょうか?
薬学科 Kさん
投稿元:
レビューを見る
歴史や地理など、社会に対して全くと言って良いほど無知な私だが、ある映画を観てドイツの歴史に興味を持ち本書を手に取った。
1900年以降の部分しか読んでいないがかなり面白く、理解もしやすく書かれており、とても勉強になった。
WWI、WWIIに至った経緯、EU(EC)発足までの経緯、など、大人になると知っていて当然のような知識すら欠落している私にとって、本当に勉強になった。
ヴィルヘルム2世に興味を持ち、ネットで調べてみると、ロシアにはもっとポンコツなトップがいたようなので、近いうちに本シリーズのロシア史も読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
七選帝侯。皇帝選び。強い候補者を選ぶと、自分たちの権利を制限されるため、穏健な弱い候補者を選ぶ。毎回、弱い皇帝になる。▼フン族の侵入を防ぐため東の辺境(オストマルク)を置く。後のオーストリア。▼ハプスブルク家のルドルフ1が皇帝になり大空位が終った(1273)。ハプスブルク家が皇帝位を独占するようになるのは15世紀から。▼国の序列。王国>大公国>公国。▼シュレスヴィヒ・ホルシュタイン。ドイツ人85万人、デンマーク人15万人。ビスマルク(プロイセン)はオーストリアと協力してデンマークから同地域を奪い、プロイセンとオーストリアの共同管理とする。▼バイエルン(州都ミュンヘン)。オーストリアと国境を接する。当初は親オーストリア、反プロイセンだった。▼オスカー・シンドラー。ドイツの実業家。ナチス党員にもかかわらず、自分の工場で働くユダヤ人を救う。『一冊でわかるドイツ史』
黒海にドニエプル川。カスピ海にヴォルガ川。▼モンゴル人は税金さえ払えば、領土を奪おうとしなかったため臣下としてふるまったが、ドイツ騎士団は領土を奪ってカトリックを布教しようとしたため戦った。▼イヴァン4(モスクワ大公国の君主)。自分が病気になったとき、一部の貴族が別の人物を君主にしようと画策。怒ったイヴァン4は、裏切った貴族たちの土地を没収した。▼アナスタシア。ロマノフ朝最後ニコライ2の末娘。レーニンによりニコライ2一家全員銃殺。従者や主治医も銃殺。▼ジョージア。ソ連崩壊前に独立(CISにも入っていなかった)。しかし2008年南オセチアの親ロシアの人々が武力蜂起。ジョージ内部で紛争に。ロシアが南オセチアを支援したため、国際紛争に。EUの仲介で停戦。南オセチアは独立を宣言して「アブハジア」を名乗る。国家としての承認しているのはロシアなど僅かな国のみ。▼クワス。微炭酸の飲み物。アルコール1%。ライ麦と麦芽を発酵。『一冊でわかるロシア史』
ポーランド。軍人コシューシコ(アメリカ独立・フランス革命・ポーランド分割への抵抗)。作曲家フレデリック・ショパン。科学者マリー・キュリー。▼チェコスロヴァキア。ローマカトリックのフランク王国に対抗するため、モラヴィア王国はビザンツからギリシア正教の宣教師キュリロスを招いた。作曲家スメタナ。小説家フランツ・カフカ。小説家カレル・チャペック(ロボット)。▼ハンガリー。ハンガリー王ラヨシュ2世(モハーチ戦いで戦死・スレイマン1)。墺からの独立運動の指導者コシュート・ラヨシュ。作曲家フランツ・リスト。数学者フォン・ノイマン。写真家ロバート・キャパ。肉野菜煮込みグヤーシュ。▼ルーマニア。英雄ヴラド3世(ドラキュラのモデル)。キャベツ肉巻き煮込みサルマーレ。▼ブルガリア。肉野菜ポテト焼きムサカ。▼ウクライナ。英雄サハイダーチヌイ(コサックの指導者)。『一冊でわかる東欧史』
3-4世紀は小氷河期で穀物や牧草が育たず食糧難。東では農民反乱で漢が滅び、西ではフン族が東欧に侵入、ゲルマン人が西ローマを滅ぼした。p.52▼ドーヴァーではなくノルマンディーの理由。ドイツ軍の防衛が手薄だった。ドイツ占領下のパリに最短距離で進撃できた。p.170『なぜ、地形と地理がわかると世界史がこんなに面白くなるのか』