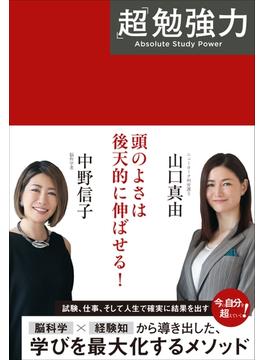結局努力しかない
2021/01/22 13:53
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さな - この投稿者のレビュー一覧を見る
7回読み等、自分の能力を上げる為には、結局努力しかないということでした。
投稿元:
レビューを見る
山口真由さんの7回読み勉強法を取り入れて、試験勉強に大いに効果を発揮しました。
そして、山口真由さんの学びに対する考え方を知りたくなりました。
そして、さらに脳科学の中野信子さんの考えも知ることができるため、この本を読みました。
この本で、印象に残ったことは次の通りです。
・学ぶよろこびを持つことで、今の自分を超えた地点にたどり着ける。…中野さん
・努力と勉強が本来持つ力とは、まさに不安や恐怖を乗り越えて前を向く力を与えてくれる。…山口さん
自分なりにまとめると、
学ぶことにより、今の自分を超える。自分の範囲を広げる。
そして、それにより誰もが何度も経験するであろう不安、恐怖を前向きに乗り越える自信がつく。
とてもいい本でした。
投稿元:
レビューを見る
二人の著者が、子供の頃からどのように勉強してきたのかを振り返りつつ、読者にも応用できるよう一般化を目指した本。勉強を楽しんでいる子供の特徴に、父親の教育への関わり方が共通していると言われているところが、興味深かった。父親が積極的に子供への教育に関わり、しかもよく話をする父親の子供は勉強をしっかりやっているというのだ。おしゃべり上手で教育パパ。
山口さんの勉強法の一つ、一冊の本を七回読み理解を深める「7回読み勉強法」が紹介されている。こんな方法をどうやって思いついたのか?とも思うのだが、論より証拠で実践してみたいと思った。詳細知りたい人は是非本書でご確認を。
著者のお二人はともに東大をご卒業されている。しかも超優秀な成績で。でも、天才ではなく、人一倍勉強に時間をかけてきて、脳みそを磨き上げてきたという。こんな人達でも、かなわないようなすごい人はいるというコメントがあった。そんな人達がいてくれるおかげで、我々凡人も助けられていることがあるのだろうなぁ。
投稿元:
レビューを見る
メディアで活躍されているお二人の共著で、なおかつお二人とも東大を卒業されている経歴から、自分や家族の勉強法のヒントになれば、と思い読み始めました。
山口さんの「7回読み読書法」は具体的で試してみたくなる方法でした。
全体的には、
「そりゃあ東大生だもんなあ、、賢いよね、、」
「もともと持っているものが違うし」
「そもそも凡人は果たして自分の勉強法を確立できるのか、それを迷わず信じて続けられるのか」
などと、
どうしても、思いながら読んでしまいました。
お二人が幼少期から他の友人達に馴染めず、悩んでいたことがある、と語っておられますが、それも、
「やっぱり東大に行くような秀才は、小さい頃から他とは違うんだよね、、、」
と、やはりどこか自分たち凡人とは次元が違う感じがして、
とてもいい事を語ってくださっているのでしょうが、
どうしても、自分の身に置き換えて考えることができませんでした。
表紙に「頭のよさは後天的に伸ばせる!」と書かれているのですが、実際の本のテーマとずれている気がして少し期待ハズレでした。
投稿元:
レビューを見る
おふたりの勉強の捉え方を知ることができました。
私もこれからいろいろなことを学んでいきたいと思っていたので、そのヒントが少し掴めた気がします。
投稿元:
レビューを見る
山口さんが書かれてい事は以前読んだ本にも載っていた事が殆どだったので新たにビビっと感じる文章は無かったのだが、中野さんの勉強法「義務としての学び・喜びとしての学び」の二層構造の話や「エピソード記憶」勉強前に「地図を作る」等、自分に役立つ情報が多かった。その中でも「どんなことでも楽しんだもの勝ち」という言葉はこれからの自分のテーマにしたいと思っている。
投稿元:
レビューを見る
勉強が出来ない…のではなく、ちゃんと勉強本を読み込めていないだけだと気付かされた。
本に書かれている通り、ひたすら繰り返し勉強本を読むと、なるほど!
急に理解出来る瞬間が訪れる実感があった。
学生時代に気付けてれば…なんて思いもしたが、これからの勉強にしっかり役立てていきたい。
投稿元:
レビューを見る
勉強の出来る著者お二人の勉強への考え方を学べる本。
勉強へのモチベーションをあげたいときにおすすめ。
投稿元:
レビューを見る
東大卒の二人が勉強を軸に過去を振り返り、勉強と自分の関りを話し合う本。
印象に残っているのは彼女たちの勉強エピソードで、自分の想像の遥か上を行くものであり、強烈で圧倒された。とても真似できない。
歩きながらでも勉強するし、スキマ時間を見つけて勉強するし(時間効率に対する執着が、時間に「スキマ」があることを発見させるのだ!)、もっと言えばストレスで血尿が出ても勉強するし、どれだけ辛くても努力することを止めない。なんかもう無茶苦茶な修行して、リミッター外して、傷つきながらも強くなっていく、そんなストーリーを読んでいるような感覚だった…
なるほど。だから"超"勉強力なのか。確かに一般の勉強力を超えている。
投稿元:
レビューを見る
元々、山口真由さんの7回読みや考え方に興味があり読みました。
この方の努力には脱帽です。
後半の中野信子さん、山口真由さんの対談形式の中身もなかなか面白く読めました。
今仕事でも、資格試験の真っ最中なので勉強するというスタンスを作る上でとても参考になりました。
読んで心に響いたところ
・「頭が固い」「発想力がない」と悩む人は、必要な情報量が足りていない
・天才でない人が成功を掴むためには、努力するしか手段はない
結構、ストイックな感じはあるけど勉強というものに対する考え方、やり方は参考になります。
そして、自分の様な一般人には未だに大学に行き学んでいるという話がすごく新鮮で、自分の仕事に関する資格試験を勉強するっていう考えはあったけど、興味のある分野・趣味の延長での勉強って言うのがなんだか衝撃でした。
投稿元:
レビューを見る
両サイドから何回も出てきた、「結局学ぶこととは自分を知ること」ってのがハイライトかなと。
成功体験系の読み物の「こうすればうまくいく!」みたいなものがビミョウなのは言うまでもなく。そこで最近だと科学的なアプローチをまとめたものも増えてきたけど、まあそれもデータを平均にならした結果であって自分がその分布のどこに位置するのかってのとはまた別の話だよねって話なので。
方法論は結局自分で試行錯誤して自分に合ったものをってことだなあ。
投稿元:
レビューを見る
この手の本はよくあります。私も何冊か読んだことがあります。
本を読んでないなと思うと、こういう本を読んでモチベートさせます。
ただ、この本は今までのものよりよかったと感じています。
山口真由さんのことが非常に参考になりました。
東大卒の頭の良い方でテレビでもよく見かける方ですが、
天才型ではなく、根っからの努力型ということがわかります。
特に、自身でそれを言ってるだけの人は説得力に欠きますが、
それを中野信子さんが言っている点が説得力になります。
その努力の方向性がとにかく本やテキストを読むことと言っています。
1回でわからなければ、2、3回、そして、7回読むと書いてあります。
回数はどうでも良いですが、最初はどういう目的で読み、
次にはどういう目的で読み、最後はどういう目的で読むのかが参考になります。
それが記憶の定着にも繋がるとのことです。
ただ、そのベースになるのは読解力です。
その読解力は幼少期からの読書によるものということです。
それは今更、私には追いつけないですが、それでも参考になりました。
今からでもできることとしては、飛ばし読みをしないということ。
少なくとも内容をしっかり理解する読み方をする場合には読み飛ばしは厳禁。
理解ができてない人は読み飛ばしていることが少なくないとのこと。
実際に、私もそれだと思います。勝手に推測してしまうことで誤解するのです。
最後に、このやり方は山口さんのやり方で皆に当てはまらないことを
伝えています。私もそう思うが、アレンジすれば、私も使えると感じました。
以下は私の備忘メモとして、1〜7回目の読み方を残しておきます。
1回目、文章を1行1行読むのではなく、情報が集中している箇所、漢字を拾っていくように流し読むイメージです。
2回目、全体の構造がより頭に入ってきて全体像がとらえられるようになります。
3回目、全体の構造、アウトラインがより鮮明になります。
4回目、頻出するキーワードに注目しながら普通のスピードで読んでいきます。
5回目、キーワードとキーワードのつながりに注目します。
要旨を掴む作業が読書においてとても重要なので、4,5回目の2回に分けて行うわけです。
6回目、細部に目を向けていきます。キーワードの意味、関連性や具体例を正しく理解していきます。
6,7回目は内容を要約し、記憶に定着させます。
投稿元:
レビューを見る
頭のよさは後天的に伸ばせる!試験、仕事、そして人生で確実に結果を出す。今の自分を超えていく!脳科学×経験知から導き出した、学びを最大化するメソッド。
投稿元:
レビューを見る
私が小さい頃はまったくもっていなかった考えを
もって二方は成長されてきたんだと感じた。
この本を読んで私が気づいたのは、
私はいつのまにか
努力している自分が好き
になっていたということ。
勉強が好きだと思っていたが、
勉強している自分が好きだったのか…
私も好きなものを突き詰めたい。
投稿元:
レビューを見る
二人とも「勉強」という科目で成果を出してきた人。
仕事ができる人とは違う。
特に山口氏はそのように見受けられ、勉強を仕事にされた経緯が分かる。