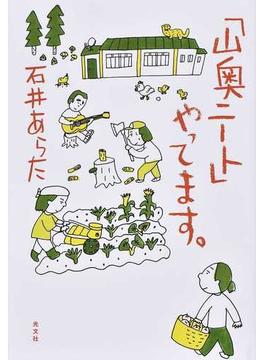紙の本
未開の道を開拓
2020/05/20 22:11
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
学校や会社に馴染めなかった若者たちが、自分たちで暮らしを切り開く姿が逞しいです。常識に縛られることのない、多様な生き方について考えさせられます。
紙の本
「山奥は心の避難所」
2021/04/17 14:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sio1 - この投稿者のレビュー一覧を見る
読み終わった後、なぜか歌人萩原慎一郎の「滑走路」を思い出した。
1人のお爺さんの夢から始まったニートの山奥生活。山奥生活の実態(2章/鹿を捌くと眠れなくなる)やメンバーがニートになった経緯(3章/余は如何にしてニートとなりし乎、働いたらお金が減った)等は新鮮でスッと引き込まれる。
「労働に向いていない人は働けば働くほど周りに損害を与える」という気持ちは誰もが一度は感じたことのある感情のような気がする。生きていると心が折れそうになることはしばしばだが、皆向き合い方は様々。
心を傷つける他人もいれば、支え合える他人もいる。山奥という自然が、心を傷つける他人からの避難場所なのかもしれない。
紙の本
山奥ニートは「じゃない人」
2021/02/18 06:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:チップ - この投稿者のレビュー一覧を見る
山奥の廃校で共同生活をする若者たち
福祉を受けるほど働けないわけじゃない
会社員になるほどはたらけない
自分で起業するほど積極的じゃない
自分で死ぬほど消極的じゃない
できる人とできない人の間の できるけど疲れてしまう人
社会の網目から零れ落ちた人たちの声
テレビで見たときは「共同生活って疲れそう」と思ったけど、こういう生活が合う人がいて、そういう人たちの受け皿があるというのはいいと思った。
過疎化する地域をこれからどうしていくかを考えるヒントも豊富にあった。
紙の本
出来ないものは出来ない
2022/04/06 08:16
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:マリコ - この投稿者のレビュー一覧を見る
今の僕の状況と似て非なるものがありました。それでも、こんな生活は出来ない。今の暮らしをベースに頑張っていきます。
投稿元:
レビューを見る
山奥で暮らすニートの方々を綴ったエッセイ。どうして山奥に行くことになったのか、どんな暮らしを日々しているのかも書かれている。田舎だから、村八分的なことをされているのかと思ったけど、地域住民の理解?もあり仲良く生活が出来ているようだ。
ここに出てくる人達は、優しい人が多い気がする。他人にあまり関心がないのもその理由かも。労働をしないことで初めて見える、社会があることを知れた。
投稿元:
レビューを見る
和歌山県の山奥にある元・小学校校舎を使って、共同生活をしている人が、その生活を綴った一冊。
「何かの宣伝だったり、何かのメッセージがあるわけじゃないです。これはただの生活(p.6)」
と筆者自身が書いている通り、基本的にはどういう生活をしているのか、またそこに来た人たち(筆者含む)がどういう背景を持っているのかを書いている一冊。
よって、この本について云々することは、そこにいる人の生活や人生を云々するようなところがある。結構評論しにくい一冊です。
ただ、興味深かった点が2点。
1点目は「別に農業に興味がある人が集まったわけではない」こと。畑もやっているみたいなんですが、それで自給自足なんて全然できてないし、それを目指してるわけでもない。
自然豊かな場所ならではの楽しみ方をしている人もいるみたいだけど、それよりは土地が余っている場所だからこそなにかあった時に人(それは場合によっては共同生活しているメンバー)から物理的に距離を取りやすいことをある種の魅力としてとらえている感じがする。
2点目は「創設者や協力者の要所要所に教育関係者が出てくる」こと。
この組織の創設者の「山本さん」は養護学校の教員を務めた後、私財をつぎ込んでこの共生施設の設立に奔走した人。いま共生施設がある元小学校の校舎の所有者である「西村さん」も元教員。いまこのNPOを運営していて、この本を書いた元ニートである著者・石井さん自身も両親は教育者で、教員養成の大学生をやっている途中でドロップアウトした人。
教育関係者の主流は「管理型」で、それを心よく思っていない人でもある程度の管理は学校運営上仕方ない、と思っている。
そういう人たちの一部が「土地が余っている田舎だったら、お互いの心理的負担がかかりすぎない距離感を保ったうえでやんわりした行動生活空間をつくれるのではないか」と考えて動いている、それは意外でもあり興味深くもあった。
多分、自分はこの共生施設にいる人より「もっと一人になりたい人」で、自分の居場所はここじゃないんだろうな、とは正直思った。
ただ「田舎の方が、本来人と人の距離は取りやすい」からこそアウトドア方向に興味が向いている点で自分と方向性は似てるし、それでちゃんと「コミュニティ」と「一定の自立した経済圏」が成立することを「山奥ニート」は証明してくれている。
その事実は…似た感覚を有している人たちにとって「ダメなら山奥に戻ればいい、っていう心の保険(p.253)」としてはかなり強いかな、と。
投稿元:
レビューを見る
テレビ放送もあって、人気ですぐに空きが埋まってしまう状態のようです。そこで、その近くに新たな拠点を設ければいいような気がするのですが、なかなか難しいと思います。機会や人材に恵まれて実現したような気がするんですよね…
投稿元:
レビューを見る
「山奥ニート」はビジネスでもイデオロギーでもイベントでもなく日常、という力の抜けたスタンスがいい。何をして、というより、何をせずに生きるか、という引き算の試み、面白く読んだ。
投稿元:
レビューを見る
題名だけでは想像つかない、でも面白そう!と思って読んでみました。
なるほど、こんな生き方もあるのかと、
こういう場所があってもいいなって思いました。
投稿元:
レビューを見る
都会暮らしと田舎暮らしというのは対局のようなイメージがあるが山奥ニートはその中間のような存在。
こんな生き方もあるんだなと感心しつつ、自分の常識を囚われないようにしないとこれからの世の中には対応できなくなるなと思いました。
ひとつだけ本の中から引用させてもらいます。
★★★★★★★★
これから先の50年、何があるかなんて誰にもわからない。
年金制度が破綻するかもしれないし、円が暴落するかもしれない。
一番いい備えは、怪我や病気をした時のために貯金することではなく、自分ができることを増やしていくことなんじゃないだろうか。
ここに住んでいると、どうもそう思えてならない。
★★★★★★★★
本当にそう思います。
投稿元:
レビューを見る
もし自分が若者で独り身であれば、この山奥でニートしてみたいです。
和歌山のとんでもない山奥の限界集落で暮らす15人のニート。お互いゆるく協力し合って生きています。仲間がいれば山村の生活も満たされるだろうなと想像は容易いです。
僕は結構色々先の事考えて不安になってしまうタイプなので、ずっと山奥で暮らしている事に耐えられなくなってしまいそうですが、同じような仲間がいればその不安も和らぎそうではあります。
1人当たり月に18,000円あれば生活できると聞くとめちゃめちゃリーズナブルでありますが、実際に生活費稼げるのかなと心配になりますね。しかし農業は人手が必要なのでバイトは結構あるようです。年間で30万もあれば生活出来てしまうと聞くと、現在の自分の生活と何がちがうのかなと首を傾げます。
自分の為に時間を使って、しっかり生活は賄う事が出来る。それであれば金銭に換算される価値以上に世間の人々は時間を切り売りして生きている事のなるのでしょう。読んでいると羨ましさでぐったりします。ほんと楽しそう。
ニートと聞くと情けない感じしますが、この実行力は実社会以外で発揮されるわけで、価値観の違いで別の次元の経済圏が出来ているという事なんでしょう。日本国と交易していると捉えればまさに新しい生き方だと思います。まあ彼らはそんなこと考えないでゆったり生きて行きたいんでしょうけどね。
投稿元:
レビューを見る
最近話題になっているのでご存知の方も。
新型コロナで、それまでの価値観が大きく変わった今。
普通の生活に生きづらさを感じていた「ひきこもり」「ニート」の新しい選択の一つ。
初めは、発達障害や、ニートの社会復帰などに資材を投げ打ってNPO『共生舎』を立ち上げていた老人が突然病で亡くなる。。。
初めは、親元から離れ、自分時間と自分空間を確保するための逃避に近い移住だったが、しばらくして、土地に根付き、限界集落と化した、少ない住民と触れ合ううちに、お金をさほど必要としない反面自由度の大きな暮らし方が自分にしっくりくることを発見した彼らは、存続するために何をすれば良いのかということに初めて立ち向かう。
いろいろな生き方を経てこの地にやってきたニート達。
それぞれの、能力も様々。
彼らの暮らしの一端を覗き見よう。
生きるということの、一番必要なこと。
必要だと言われたことで、実はいらなかったもの。
価値観が変わり、それがコロナ対策にも合致してたりするから、面白い。
投稿元:
レビューを見る
なるほど、こんな生活もあるんだなと。
第1章から順番に読むとちょっと退屈になってきたので、ここに住むニートさんらのインタビューの章を読み始めると、なんとなくイメージが湧いてくる。
なるほど、こんな生活、生き方もあるんだね。
投稿元:
レビューを見る
ニートという言葉の概念が変わった。
誰にも寄生しないで生きてる人なんていないんじゃないかなぁ。
・これから先の50年、何があるかなんて誰にもわからない。〜 一番いい備えは、怪我や病気をしたときのために貯金することじゃなく、自分ごできることを増やしていくことなんじゃないだろうか。
・結局のところ、本当の安心というものは、いつ死んでもいいような心構えをすることなんじゃないか。そのために好きなことをやって、死ぬ瞬間に後悔しないようにしたいと思った。
・人にはそれぞれ、自分に合った履き物がある。〜
靴に足を合わせるんじゃなく、足に靴を合わせなきゃいけない。昔わらじを自分で編んだように、自分に合わせた履き物を作る。そうすれば、足は傷つかず、どこまでも歩いて行ける。自分専用のわらじをじっくり作る、そのための時間と場所が必要だ。
・自分が働くことに納得していなければ、なんだって苦痛だ。
投稿元:
レビューを見る
20201010 タイトルで想像するより健全な内容。ある面、これからの生き方のサンプルになりそう。良い事ばかりで無く、国民としての視点が入ると難しい事になりそう。NPOの形式だから何とかなっているのだと思う。