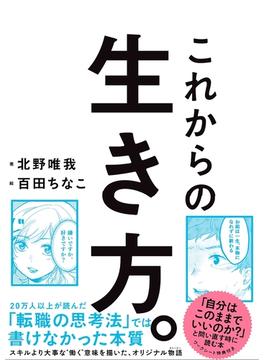前半 マンガ形式!読み手に優しいビジネス書です
2020/08/10 16:57
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:丼OK - この投稿者のレビュー一覧を見る
漫画、自己分析シート、漫画登場人物への5年後インタビューという様式が、働く人の価値観や生き方という根元的なテーマへと、優しく導いてくれて読みやすいです。
第1章「漫画編」
百田先生の作風である日常エピソード表現が、登場人物のキャラクターに あるある感を吹き込んだ感じで、共通認識を得る準備が整います。
第2章「ワーク編」
漫画編の登場人物に込められていた“14の労働価値”や“4つのキャリア型(スキル、意志、チーム、バランス)”が解き明かされると共に、読み手も自己分析をしてしまいます。
チーム型キャリアの3つのポイントの“行動→動機→価値観を見る”は、秀逸です。
巻末付録の登場人物への5年後インタビューは、ニヤッとしながら読み始めましたが、自然と実在人物のイメージを感じていました。
明日から、“何を優先して時間を使うか”感性を磨いていこうと思いました。
投稿元:
レビューを見る
特にいいなぁって思ったフレーズは、
“It's not the things we do in life that we regret.....
it is the things we do not."
.
死を間際にして、僕達が後悔すること、
それは、自分がしたことではなくやらなかったことだ
(ランディ・パウシュ)
やるかやらないかで迷ったらやってみる。
自分の将来なんて誰も分からないから、
とりあえず行動量をあげていこう、と思えた。
人のキャリア観を知ったり、自分は何を大切にしているか?を整理する本にはなったが
何か今後の行動にヒントがあったか?というのは微妙かなーというかんじ。
投稿元:
レビューを見る
人間関係の問題はなくなることはありません。その解決方法として、分断するや受け入れるなどと書かれている本は無尽蔵にあります。それは正論で一見簡単そうです。だからできる人はできる。これは当たり前の話ゆえに悔しい現実。この本は根本的なところに触れていて、「合わないのはなぜ合わないのか、価値観のベクトル」を分析できるように説明してくれます。共存していけるし、今の場所が絶対ではないと、自分の視野を広げてくれます。背中の押方ってこのような方法が気持ち良いんだと思います。
投稿元:
レビューを見る
【スキル型のキャリアの人間の生き方】
・20代まではスキルを磨くことで行きていける
・30代以降は、自分よりも単価の安い人との差別化要因が必要
・30~40代までに自分の「応援したいテーマや人を見つける」
→いろんな人に会い、夢や事業に関する話を聞く。
自分がどれくらい共感したか、応援したいかをメモ
メモを見ながら共通点探し
最も応援したく、自分ができることも多いものを見つける
・人が自分のやりたいことが見つからないのは、ほとんどの場合、まだ充分に多種多様な人と出会っていない(=判断材料がない)だけだ
→判断材料がない中で選ばない。まずは選ぶための情報収集をする。
・”感性”とは
→違いに気づく力。
→主観的に体験したことを、客観的に分析する。
→なにが違うのか。過去と今の自分の違い。できる人とできない人の違い。
・過去ではなく、これからどう生きるかが問われる
→人生が長期化している。
→過去の時点での違いは人生において99%誤差でしかない。
→自分が時間効率を無視してでも「やりたい」と思えることを見つける
→「やりたいこと」があると、肩書や人との差異なんて気にならない。(=ヒトではなくコトに向かう)
・好きなことを好きっていうのは勇気がいる
→否定される可能性もはらんでいる。
・なぜ働くのか?自分は何を求めているのか?
投稿元:
レビューを見る
大好きな北野さんの作品。
これからの生き方という壮大なテーマを、前半は漫画、後半はワークを通して自分の価値観に気づいていく。
おすすめの一冊。
投稿元:
レビューを見る
漫画で流れを見て,ワークに落とし込むスタイルの本。ワークの解説に漫画を使う場合もあるけれど,この作者はわかっていると思う。
それは作者の「物語の価値とは、生き方のパターンを認識し、そこから自分の人生への学びに転化させることができること」(p225)という言葉。
僕も他のフィクションを読んでいても常にそれを意識しているので激しく同意。
そしてこの本の面白いところは,巻末付録にある。登場人物たちのその後まで描いてるところにある。
物語を読んでいて,もうちょっと知りたいというところまで公式で叶えてくれているのもいい(同人誌を読むモチベーションに近いかも)。
まぁ,この漫画の登場人物たちは転化させるのには個人的にはちょっとコツがいりそう。
そこが自己啓発書系として位置づけられるこの本の狙いだと思って読みすすめる。考えることが重要なのだと思う。
僕の分析結果は労働価値分析で近いのは編集長で,キャリアはバランス型。
労働価値分析はそこからどうこうということはないけれど,やってみると意外な発見がある。
ある程度自分のペースで仕事しながら,最先端のものというよりは,広くいろんな人に役に立つものをつくる/提供する/つなぐことをしたいんだと気づいた。
投稿元:
レビューを見る
20代とか若年層向けっぽい。私はもはや自分はこのままでいいのか?みたいな時期ではないので特に刺さるってことはなく、…そりゃそうだろ。という感想だった。
でも価値観ってものを漠然と捉えていたので、細分化して考えるきっかけにはなった。
いつも思うけど、ビジネス書の漫画って見にくい。
商業誌(コミック)の漫画と比べるとってことなので仕方ないけど。
投稿元:
レビューを見る
これからの生き方。/北野唯我、百田ちなこ
前半は漫画、後半はワークという面白い一冊。
どうキャリアを築き、どう生きていくか、考えるためのヒントをくれる本。
前半の漫画では、いろいろな仕事の価値観を持ったキャラクターが登場し、それぞれの考え方に触れる。
後半はそれを踏まえて、自分は誰に近いか、どんな価値観を持っているかを探り、これからの生きる道標を見つけていく。
キャリア戦略はスキル型、意思型、チーム型、バランス型の4タイプに分類される。
自分はバランス型。この型は自分の軸が相対的に弱いことが課題。まさにその通り。
このタイプが20-30代で特に身につけるべきことは、
・早い段階で、人を率いる経験を積むこと
・きちんと成果をアピールする術を身につけること
だそう。
このタイプは平時のリーダーシップを持っていて、ほかの型の人間をバランス良く育てることができる。
成果をアピールする術を身につけるために、
①これまでやってきた仕事、成果を紙に書き出す。成果を出すために必要だったスキルも書き出す。
②自分のレジュメ、履歴書を普段から作っておく癖をつける。
③20-30代のうちに人を率いる経験を積んでおく。
さて、生き方、キャリア系の本を読んでだいぶやるべき事が見えてきた。
あとはやるのみ。ローランドのいう、
やるかやらないか、ではなく、やるかやるか。
投稿元:
レビューを見る
20代〜30代にかけて会社や組織でそれなりの経験を積んでくると、その後のキャリア形成や人生そのものについて見つめ直す機会が増えてくる。
まさに本書は「これからの生き方」にヒントを与えてくれる。そして「働く人への応援ソング」でもある。
著者は人並外れた感性と分析力で、働き方のスタイルを「スキル型」「意志型」「チーム型」「バランス型」と4つのパターンに分類し、課題と解決策をわかりやすく提示する。
上から目線の押し付けがましい言葉でない。あくまで寄り添う姿勢で。北野さんの謙虚な人柄なのだろう。
序盤を漫画パートで展開する作風は非常にユニーク。人によっては読みづらいかもしれないが、中盤以降の伏線となっていて納得させられた。気持ち良い読後感。
※しかし、友人によると前著「転職の思考法」と重なる部分があるそうなので注意。
投稿元:
レビューを見る
「自分がどう生きたいかを決める(気づく)ことが人生を豊かにする」ということがこの本で北野さんが伝えたいことだと感じた。
このことがものすごく丁寧に伝えられている印象で、構成が緻密に練られていることが伝わってくる。さらに3章では北野さんの熱量も伝わってきて、熱さと丁寧さが両立しているところがすごいと思った。
・どう生きたいかということは論理で証明できるものではない
・感性をお金に変えることは技術であり、学ぶことができるもの
上の2点をこの本では個人について述べているが、企業についても同じことが言えると思った。ビジネスでは「論理的であること」や「どう稼ぐか」が重視されることが多く、会社にとっての「生き方」にあたる企業哲学のような感性的なものが忘れられがちだと思う。そうなると社員は働く意義が見出しにくくなり、違和感をもって働いている会社員の理由の多くはここにあるのではないかと思う。
また、特に漫画編とインタビュー編を読んで、北野さんの人に対する洞察の深さや鋭さに感服した。本当に人に興味があって日頃から人を観察し分析しているんだろうなと想像するが、何故そこまで人に興味を持つようになったのかの背景や、普段どのように人を見ているのかを聞いてみたいと思った。
投稿元:
レビューを見る
漫画でとっつきやすい入り口を作ったいわゆる「キャリア論」の本。
構成を紹介すると、
第一章 漫画編(物語編)
第二章 ワーク編(自己分析編)
第三章 独白編(生き方編)
以上の全三章からなる。
まずは特徴でもある漫画の紹介から。
舞台は出版社。情熱だけで突っ走る主人公「小林希」の葛藤が描かれている。
この漫画だけでも、実はかなり感情を揺さぶられた。そこには、いかにも現代サラリーマンの姿がリアルに表現されている。自身が働いている姿を、なにより客観的に見ることができた気がした。そして思った。
「大人たちがこんな風に見えてたら、今の子どもが働きたくないと思うのもムリないな」
プライベートを犠牲にして、しかも大切な人との約束さえ中断してまで、職場からの電話にでる。そして、当たり前のように呼び出され断ることもできない。
そんな場面からこの漫画は描かれる。
これって本当に必要な事なのか?
ここまでして仕事をした方が本当に幸せになれるのか?
豊かになれるのか?
今の若者にこそ読んでもらいたいと思う。そして、こんな働き方、こんな生き方をどう考えるのか?
第二章、第三章では自己の分析方法とそこからどういう点に気を配る必要があるかを教えてくれる。
人生に迷う前に、もしくは迷っている人にできるだけ早く読んでもらいたい一冊。
投稿元:
レビューを見る
2020.9.12読了。タイトルに惹かれて。この本を読んだことで何かが大きく変わる、というわけではなくて、考えるため、そして行動していくための材料になるような本。『これからの生き方』については、今後も定期的に考える機会を取っていかないといけないと感じた。
投稿元:
レビューを見る
「転職の思考法」を書いた北野唯我氏のビジネス本。漫画編、ワーク編、独白編の3編に分かれている。
漫画編では実在の人物をイメージしたキャラクターたちの漫画が描かれている。
ワーク編では漫画編で登場したキャラクターの内面を深掘りし、彼らの関係性や価値観の分析を通じて、自分のキャリアや労働に関する課題、価値観を見つめ直すことができる。
独白篇は著者である北野唯我氏が「これからの生き方」を考えるようになったきっかけやこの本を書いた理由を独白するパートとなっている。
14の労働価値や4つのキャリアタイプ(スキル型、意思型、チーム型、バランス型)の話は、「このままでいいのか、転職しようか」など今後のキャリアについて悩んでいる人達にとって非常に有益であると思う。いきなり転職などの行動に移る前に、自分が仕事に対してどの価値観を重要視するか、自分はどんなキャリアタイプなのか、を明確にしておくと今後の課題や対処法、取るべき行動が見えてくるのでオススメだと思う。「自分はこのままでいいのか?」と問い直す時に読む本に相応しいと思う。
投稿元:
レビューを見る
唯野さんは、転職の思考法から愛読してます。
この本もなかなかおもしろい。
大きく良かったのは2点。
・人間同士の違いを、価値観という本質から語っている
・新しい時代の生き方を、唯野さんなりのロジックで語っている。価値観を満たすための本業+アルファ、そして自分が強みとする点を起点とした成長のポイント
自分としては、上記2点から、仕事における人間関係と人への向き合い方、仕事にしたい趣味のあり方、直近仕事に於いて強化すべきことやアクションプランなどがなんとなく具体化できました。
生き方が明確に決まるというような特効薬にはなりにくいが、生き方や働き方を考えるための気づきが得られる本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
自分の役割は、働く一生のなかで何度も変える必要がある。
人は自分よ身の丈にあった場所を自然にえらぶ。
人の生き方は、複数の価値観が混ざり合ってできている。