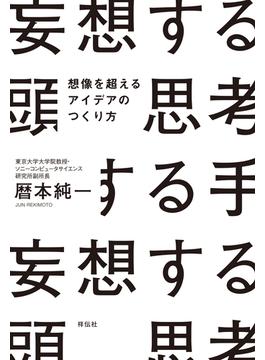投稿元:
レビューを見る
アイデアを形にする方法を、具体的な例をあげて説明してくれる本。
具体例は、仮想的な例示ではなく、著者の過去の経験なので、参考になる面もあるが、時代が違っていると感じるところもある。
まだ自分でアイデア整形方法をしらない若い人向けの本です。
「とりあえずブレストしましょう!」という人に読んでほしい。
(著者はブレストもマインドマップもマンダラートも否定している。)
なかで紹介されている、「みんなが知らなそうな面白いものを持ってきて紹介する」会議は面白そうなので是非やってみたい。
短文で読みやすいので、1時間くらいで軽く読めます。
投稿元:
レビューを見る
天使度と悪魔度
素人のように考え
玄人のように手を動かす
課題解決ではなく
妄想から生まれるもの
投稿元:
レビューを見る
ブレインストーミングで考えていることは妥協で合ったり、協調を生んでいる可能性がある。一人で深く考えることでアイデアが生まれる。
既知と既知の組み合わせ
最初からこの課題の解決のため、と作ったものは多くはない。最初はこれができたら面白そうから入っている。
自由にアイデアを考えて実行し、それがうまくならなければ別の方法や必要な検討をするだけ。
難しく、一方で効率的によいアイデアを考えようとしすぎていることを教えてくれた。
投稿元:
レビューを見る
https://note.com/planaria_/n/n58c3b2540ee7
***
本書とはずれるが、関連して連想したことメモ:
「やりたいこをやる」好奇心からイノベーションが生まれるということは事実であろうし、本書では技術開発に焦点を絞って語られているが、この手の話を聞いて考えてしまうが、大学教授(特に国立大学)の研究費を増やせといった類の話が大学側からよく出ているのをニュースで見聞きすることだ。曰く、「将来何が役に立つのかは分からないのだから、基礎研究や明確に役に立つ対象ではない研究にも金を回せ」のようなことだ。
まぁ言いたいことは分かるし事実でもあるのだろうが、国の税金をどう分配するかは納税者たる国民が決めるべきであり、国民の代表者たる政治家が主導権を持って決めるべきだ。経済的には役に立たないが人類の知を深めるような研究の推進に金を回すような懐の深さは国にもあってもいいとは個人的には思うが、それはあくまでその時の国民がそう考えたらの話であって、学者が上から目線で金を寄越せというのはおかしいし、学者は、何に役に立つかが分からない研究ならせめて、人類の知にどう貢献するかや、その研究の学問的面白さを一般国民に分かってもらえるよう努力すべきだ。
それが出来ないなら趣味や寄付を自ら募って活動するべきだろう。…とまぁ、本書のテーマから話がそれてきたのでこの話はこのへんで。
投稿元:
レビューを見る
アイデアのつくり方については「みんなが知らなそうな面白いものを持ってきて紹介する会議」(必ずしも「みんなが面白いと思うもの」でなくてもかまわない)にすべてが集約されているような気がした。中途半端にブレストをやると、参加者の気持ちを忖度する方向に流されやすいというのは多くの人が経験していると思う。
流して読むと、実績ある著者に基礎研究の大切さを説いていただいたという印象しか残らないかも。自分の置かれた環境を妄想しながら読むと楽しかった。
投稿元:
レビューを見る
タイトルにある「妄想する頭」はそうだろうな、と思うのですが、「思考する手」の意味がわからず、手に取りました。
周りに流されず、自分の中で「問い」を持ち続けることが重要、でも同時に手触り感、現場感がないとイノベーションは生まれない、というのが私なりの理解です。
自然と手が動くものって何だろうと自分に問いかけながら、日々の仕事などに当たると違った世界が見えてくるかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
スマホを持っている人であれば一度はやったことがあるであろう、写真を二本の指をつまむように操作して拡大・縮小するスマートスキン機能を発明した、ユーザーインターフェイス研究の第一人者である暦本純一さんの著書。「妄想」を通して未来を生み出す思考法を解説した一冊で、「妄想」を文章化しアイデアとして具現化する手法が語られる。難しい本かなと思ったが、難解な用語はそれほどなく、アーサー・C・クラークやアインシュタインの格言を引用して説明されたりと、内容は非常にわかりやすかった。
投稿元:
レビューを見る
発想法の本だが妄想することから始まるアイディアということで今までにない斬新な考え方だと思う。とても参考になる意見だ。脳に電極を埋め込んでコンピューターと繋ぐ時代、新しいアイディアは何かしら世の中のバランスを崩すようなところに価値がある、未知なものに対する好奇心、振動によって人を誘導する代杖、人間拡張としてのヒューマンAIインテグレーション、If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it. 馬鹿げたように見えないアイディアには見込みがない、非真面目な路線の確保、人間のサイボーグ化等全てがぶっ飛んでいる。しかしそこにオリジナリティがあるのだと思う。
投稿元:
レビューを見る
・イノベーションのスタート地点には、必ずしも解決すべき課題があるとは限らない
・素人のように発想し、玄人として実行する
・やりたいこと=クレームは1行で書ききる「DNAは二重らせん構造をしている」「口腔内の超音波映像を解析すればしゃべっている内容がわかる」
・クレームを書くうえで「高機能な」「次世代の」「効率的な」「効果的な」「新しい」といった正しいけれどあいまいな表現は避ける
・面白い手段を思いついたなら、後からそれを解決策として使えそうな課題を探せばいい
・本当に音声タイプライターが必要かを試すために、裏の仕組みを人間で代替して評価を取った
・好きなものが3つあれば妄想の輪が広がる。他人の目を意識した面白さを追求するのではなく、自分の問題から始めるのがいいと思う
・眼高手低:高い理想を持ちながら現実をよくわかっている or 批評ばかりで技術は低い
・問題解決の糸口となるひらめきだけでなく、アイデアの種となる妄想もまた、手を動かすことで生まれる。「眼高」は「手低」の前にあるとは限らない。「手低」が「眼高」を呼ぶこともある
・そもそも何をしたかったのかを忘れていると、思いがけない展開のチャンスを逃す可能性がある。手段の目的化はどんな分野でもしばしば起こる。ある目的のための手段を考えているうちに、その手段を完成させること自体が目的であるかのように錯覚してしまうのだ
・能力の拡張
・変化する状況に応じて情報を与えるウェアラブルコンピュータのことをコンテクストウェアと呼ぶ
・妄想は、現時点での最先端から始まるわけではない。むしろ現実の世界に対して違和感を抱くところから始まる
投稿元:
レビューを見る
アイデアをカタチにする本、といったら少し陳腐な言い方かもしれない。
むしろ、個人がイノベーションを起こすための本、くらい早大にいった方が良いのかも。
こういった本はあまり読まないのですが、
著者のことが気になっていたので、読んでみました。
著者は、iphoneなどのスマートフォンの画面上で、
日本指で画面を大きくしたり小さくしたりする技術を開発した人(らしい)。
このアイデアは、スマートフォンが出てくる前に思いついて、開発したらしく、
それもある意味スゴイと言わざるを得ない。
そんな著者がどうやってイノベーションを起こすかについて述べた本。
タイトルにあるように、最初は妄想がダイジ。
そして、その妄想をすぐにカタチにしてしまうことがダイジ、とのこと。
「なるほど、デザイン思考に近い考え方かな…」と思っていたら、
課題先行で物事を考えると、思考が制限されてしまう、とか、
選択と集中だけだと、面白い発想が出てこない、とか、
今のビジネス界隈に生きる人にとっては、耳の痛い話も。
なるほど、確かに一理あるな、、とも思ってしまいました。
リソースは有限なので、結局はバランスなのでしょうが、
こういった考えに触れておくこともとても重要だと思います。
いい本でした。
著者の本がまた出たら、読んでみたいですね。
投稿元:
レビューを見る
アイデア発掘するのに必要な地頭を作るのに適した本。ビジネス書だけどアイデアがほしい作家にも助かる一冊。
投稿元:
レビューを見る
タイトルとおり、アイデアのつくり方の参考になりそうな一冊です。とはいえ凡人にどこまでできるか、という問題はありますが。
著者はいまや現代の生活では不可欠となったスマホの画面を指で操作するインターフェースを開発した人物とのことで、iPhoneが発売される何年も前のことだそう。そういった実績のある人の言葉だからでしょうか、やはり説得力がありますね。
いわゆるビジネス本にありがちな「こうすれば成功間違いなし」的な力説をしているわけではなく、考え方の作法というか、ポイントを丁寧に解説してくれています。
「ブレスト」についても盲目的に信用するのではなく、著者なりの視点で批評がおこなわれており、その考え方の道筋は参考になります。
ただ、この手のアイデア創発系の話しは自分ひとりの力だけではなく、周囲の人の協力も不可欠で、この場合、周囲の人にもこの本の内容をある程度は理解いただく必要がある(理解いただいたほうがより良いというべきか…)のでしょうけれども、この点、意外とハードルがあるような気がします。職種や職場のカルチャーによりだいぶ左右されそうだなと、そんなことが気になってしまいました。
投稿元:
レビューを見る
発想ってこういうことか〜! すごい! 今ならなんでも作れそうな気がする!(気がするだけ)
イノベーションを起こそうと一生懸命になっている組織はたくさん見てきたけど、まじめに取り組むだけでは妄想は広がらないんだなあ。どうすれば発想の「天使度」を高められるかだけでなく、広げた妄想をどう研ぎ澄ませていけばいいかも丁寧に書かれているから、アイデアを必要とするすべての人に役立ちそう。プロとしての技術を磨きつつ、同時に無邪気さも持てる人でありたい。
【読んだ目的・理由】メルマガで勧められていたので
【入手経路】買った
【詳細評価】☆4.6
【一番好きな表現】だから私は、何度も失敗を重ねながら手を動かす時間は「神様との対話」をしているのだと思っている。天使のようなひらめきは、腕を組んで考え込んでいてもやってこない。手を動かしながら、神様に向かって「こうですか? これじゃダメですか? やっぱり違います?」などと問いかけ続けると、いつか神様が「正解はこれじゃ」とひらめきを与えてくれる。そんなイメージだ。(本文から引用)
投稿元:
レビューを見る
妄想することを忘れてしまう、もしくは無駄だと諦めている自分がどこかにいたことを思い知りました。目的意識を持つ、課題解決を図ることが重要であることは間違いありませんが、そればかりに囚われてしまうことは、自身の足かせになっているのかもしれません。書かれている内容の中で、「手を動かす」「言語化する」ということを述べておられ、他の方のお話を聞いた際にも挙げられていたことでした。しかし、作者自身の研究を踏まえて紹介されていることで、より鮮明にその言葉の意味が伝わりました。この本との出会いは偶然でしたが、素晴らしい出会いになりました。
投稿元:
レビューを見る
スカッとしてブラブラしている人・時間を許容する社会。
未来を生み出す妄想の時間軸を感じたときに鳥肌が立った。
素人のような妄想と玄人の実現力、これに傾ける情熱と時間。
例)自動運転、1995年に実験
◯イノベーションのスタート地点は課題設定からとは限らない
・真面目:課題解決型、想像、未来予測、SDGs
・非真面目:面白い、妄想、想定外、自分の価値観
◯悪魔のように細心に!天使のように大胆に!
悪魔度:技術の高さ
天使度:発想の大胆さ
◯妄想は人から与えられるものではなく、自分でやりたいこと
◯妄想を実現に向かって動かすのは「言語化」
・絵や図などのビジュアル:HOW
・言語化:アイデアの原点であるWHAT, WHY
◯やりたいこと=クレームは1行で言い切る
・検証可能な仮説として
・検証は最短パスで(例 音声入力の要否は、音声認識技術が成立する前でも検証可能(裏でタイプライターが入力))
◯発明が新たな必要を生む
◯既知×既知の組合せを増やす。未知への感度を上げる
・他の人とはアイデア出し(ブレスト)をするのではなく、インプットを増やす
・他の人が知らなさそうなおもしろいものを紹介し合う会議
◯失敗は自分が取り組んでいる課題の構造を明らかにするプロセス
◯眼高手低:高い理想を持ちながら、現実もよくわかっている
手を動かさないと失敗さえできない。失敗によって問題の構造が見えてくれば前進だ
◯アイデアにこだわらずピボットする
・天使度を上げる:二次元通信→スマートスキン
・視点を変える:振動によって人を誘導する→仮想力覚
・逆転の発想:プリンターの紙送り→光学マウス
・トレードオフのバランスを崩す:高精度かつ広視野角をあえて崩す→高視野角HMD
◯そもそも何をしたかったのか:椅子の「形」にとらわれるのではなく「機能」を考える
◯妄想は、現時点での最先端から始まるわけではない。むしろ、現実の世界に対して違和感を抱くところから始まる
◯「キョトン」は大事だ。自分の妄想やアイデアが、他人の価値軸とは違う価値軸の上にあることを、表している。