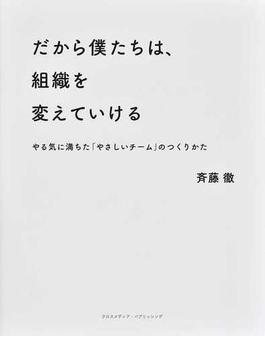「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発売日:2021/11/29
- 出版社: クロスメディア・パブリッシング
- サイズ:19cm/303p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-295-40625-9
読割 50
紙の本
だから僕たちは、組織を変えていける やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた
著者 斉藤 徹 (著)
組織を変える旅にでかけよう。今を知るために産業史をたどり、技術進歩がもたらしたパラダイムシフトを考察。その上で、知識社会にふさわしい組織のあり方を説き、変えるメソッドとし...
だから僕たちは、組織を変えていける やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた
だから僕たちは、組織を変えていける
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
組織を変える旅にでかけよう。今を知るために産業史をたどり、技術進歩がもたらしたパラダイムシフトを考察。その上で、知識社会にふさわしい組織のあり方を説き、変えるメソッドとして最新の組織論を体系化して紹介する。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
斉藤 徹
- 略歴
- 〈斉藤徹〉起業家、経営学者。株式会社hint代表、株式会社ループス・コミュニケーションズ代表。ビジネスブレークスルー大学教授。著書に「ソーシャルシフト」「BEソーシャル!」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む