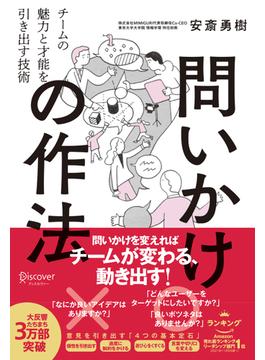投稿元:
レビューを見る
発売されたばかりの一冊。
「問いかけ」のメカニズムからその組み立て方、投げかけ方まで学ぶことができます。
「問いかけ」の奥深さについて考えさせられる良書です!
現場で実践に繋げるための手引きも掲載されており、「実践してこそ!」という想いが伝わります。
「問いのデザイン」とともに強くお勧めできます!
投稿元:
レビューを見る
1.自分の問いかけをレベルアップさせるため、自分の質問で相手の感情を刺激するためにはどうしたらいいのかを考えるために読みました。
2.ファクトリー型組織として成功してきた日本にとって、現代は危機的状況に陥っていることは周知の事実です。そして、コミュニケーションが大事なことも周知の事実です。しかし、なぜ変われないのか?それは、「質問する側」に問題があり、お通夜ミーティングを繰り返してしまうからです。
本書では「問いかけ」とは相手に光を当てるスポットライト的な存在として例えながら述べています。問いかけのやり方1つ変えるだけで相手の感情を刺激し、心理的安全を作ったり、信頼関係を築く一歩が生まれます。
では、実際にどのように問いかけていけばいいのか、その具体的な方法を述べています。
3.自分が問題意識していた部分を突いてきた本でした。普段から、聞くことを意識し、いかに相手の話を引き出すかだけを考えていました。しかし、それだけでは新しいアイデアを生むことはできないですし、チームが成長することはありません。大切なことは、「相手の感情を刺激するために多く発言してもらうことに加え、心理的安全作ること」です。私の場合、もしかしたら相手が嫌々話している可能性があったので、本書を2ヶ月に1回振り返りながら自分の会話をレベルアップさせていきたいです。
投稿元:
レビューを見る
こだわり&囚われ
そのこだわりに関心を向ける
囚われる空気をほぐす心理的安全性配慮
「さー自由に話してください」→おつや状態
自由すぎて不自由になっている。
ハシゴというアシスト。
足場の問い。問いの問い。
「意外に効果のあった方法はなんですか」
「友人として教えて欲しいのですが、、」
行政から委託された研修で黙る受講者から言われたことば。
「お前にとって『地域』って何だ」
勝手に行政の管轄で地図に線を引いていた。
地域住民の目線では、日頃から地域をまたがない移動なんてあり得ないし、行政区分に沿って風景を見ていないから前提からわからないと言っていた。
投稿元:
レビューを見る
問いかけでいかに人々の考えを引き出すのかが書かれている。
その中でまず、個人や集団を見取るという部分は教育にも生かせる部分が多い。
また、その場に応じた問いかけで素直な本音を引き出すことで思考を深めて行く流れがよくわかった。
その集団、その時にあった問いかけや場づくりで一人ひとりの個性や良さが発揮できるように自分自身の言動を見つめ直したいと感じた。
投稿元:
レビューを見る
意見の出ないミーティング、お互いの顔色を伺いながら正解を探すミーティング…なんだかなぁ、と思う会議、ミーティング、打合せの類は数え切れない経験してきた。そんな中で心理的安全性というビッグワードに答えを求めてしまうこともあったが、本書では「心理的安全性がないから意見が出ないのではなく、問いかけの仕方を変えることで意見が出やすい雰囲気をつくることは可能ではないか?意見が出やすくなると、自ずと心理的安全性も高まるのでは?」という仮説のもと「問いかけのしかた」に焦点を絞って様々なコツ、考え方が丁寧に書かれている。
具体的なノウハウももちろん試してみたいが、心理的安全性を高める、という何をしたらいいか分からない状況から問いかけの仕方を変える、というところに足場を掛けてくれている点が一番この本の良いところだなと思った。
投稿元:
レビューを見る
問いかけによって、「とらわれ」と「こだわり」を見つける。自分1人の力では勝てない時代に、周りの人間の力を100%引き出すことが求められる。
基本定石として以下を意識するだけでもアクションが変わる。
・相手の個性を引き出し、こだわりを尊重
・適度に制約をかける
・遊び心をくすぐる
・凝り固まった発想をほぐす
シナリオを想定していた自分にとって、大きな気づきであった。
これらを達成するための具体的な手法もたくさん紹介されている。
パラフレイズ、仮定法、バイアス破壊
素人質問、ルーツ発掘、真善美
誰かのアイディアを引き出したい方にぜひお勧めしたい。
投稿元:
レビューを見る
周囲の人々の魅力と才能を引き出し、一人では生み出せない、チームとしてのパフォーマンスを発揮するためには、ミーティングをはじめとして、チーム内の人々に問いかけをして、情報共有、意見交換をしていくことが重要である。そんな重要な問いかけの技術について解説したのが本書。具体的な方法が書かれている。
問いかけの基本定石としては、「相手の個性を引き出し、こだわりを尊重」、「適度な制約をかけ、考えるきっかけを作る」、「遊び心をくすぐり、答えたくなる仕掛けを施す」、「凝り固まった発想をほぐし、意外な発見を生み出す」などがある。またミーティング前の目的とミーティングでの理想の光景(活発な意見交換、若手の発言)を考えておくことで、ミーティングは充実する。目的は「情報共有」、「すり合わせ」、「アイデア出し」、「意思決定」、「フィードバック」などがあげられている。問いかけの技術を今後、意識しておきたい。
投稿元:
レビューを見る
コミュニケーションは聞くと話すというやり取りで成り立っているところ、質問を何のためにしているか?を深く考えさせられる1冊。
相手の考えを探るには傾聴が基本であるが、この本では問いかけをすることで、相手がより自分の考えを整理して、探究できるようになるためのアプローチ方法が書かれている。
ぜひ精読し、実践しながら身につけていきたいスキル。
入社3-5年目、はじめて部下を持つ人におすすめ。
投稿元:
レビューを見る
適切な問いかけは自分自身にもチームにもよい気づきをもたらし、引き出せるものがあるはず。まずはこの本の例を取り入れて型を覚えていきたい。小さくてもチームに変化をもたらして、いつかはチームにぴったりのオリジナルなパターンを編み出せるとよいな。
投稿元:
レビューを見る
問いかけによってワークショップは活性化する。
問いかけは技術であり、知識として知っているのと知らないのではかなり差がつくと思うのでビジネスパーソンは読むべき。
なかなかボリューミーですぐに身につく内容ではないので図書館で借りるよりかは買うことをオススメします。
投稿元:
レビューを見る
「問いのデザイン」の実践編の位置付けの本。
もともと買ってはいたが、この春にマネジャーになって壁にぶつかることが増えてきたので一気に読んだ。
本は納得感がある。あとは、実践してみてから感想を書きたい。
投稿元:
レビューを見る
会議の場、1on1の場、日常のFBなど色んな場面で使える考え方
「こだわり」と「とらわれ」は本書のように問いかけをしてもらわないと気づきにくい部分だと思う
考え方や具体例も多く載っているので、日常に使う
イメージがわいた
特に誰かと真剣に向き合い、相手の考えを聞きたいとき、思考を促したいときに読んでほしい
持
投稿元:
レビューを見る
問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術
著:安斎 勇樹
仕事は「自力」ではなく、「他力」を引き出せなくては、うまくいかない。問いかけの技術を駆使することによって、周囲の人々の魅力と才能を引き出し、一人では生み出せないパフォーマンスを生み出すことが、現代の最も必要なスキルのひとつである。
ひとりの実績を磨くよりも、「問いかけ」によるチームの力を高めていったほうが、結果として「あの人と一緒に働くと、気持ちく良く仕事ができる」「あの人のチームだと、良い成果が出せる」「あの人のもとでは、次々に良い人材が育っている」といった「自身の評価」へとつながり、活躍も広がり、他社の才能を活かしながら働くほうが、圧倒的に仕事が楽しくなる。
本書の構成は以下の5章から構成されている。
①チームの問題はなぜ起きるのか
②問いかけのメカニズムとルール
③問いかけの作法①見立てる
④問いかけの作法②組み立てる
⑤問いかけの作法③投げかける
各々の個を最大限に高めるために「問いかけ」を使い、それぞれを繋ぎ合わせる中で、チームとしての最大の成果をえるためのスキルが説明されている。問いかけのルールである見立てる・組み立てる・投げかけるという順序と具体例が記されており、どれかを組み合わせながら最適な「自分たちの問いかけ」を模索していくことができるつくりとなっている。
コーチングやティーチング、チームマネジメントの概念についても「問いかけ」という視点からわかりやすく紹介されている。
自身や自組織に合う組み合わせを見つけながら試行錯誤するだけでも確実にチーム力は高まる。それほど具体的な現場で活かせる知識が丁寧に記されている。
投稿元:
レビューを見る
●ミスを恐れるのではなく、試行錯誤を楽しみ、失敗から学ぶ
●具体的にヒアリングする
(例)
•普段の商談で大切にしてる事は? ❌
•これまでの商談で意外に効果があった工夫は?◯
●評価の食い違いは、価値観のズレから生まれる
●チームに必要な変化とは目標も現状の、ギャップから生まれる
●着飾り過ぎないシンプルな問いかけも忘れない
投稿元:
レビューを見る
「問いかけ」に特化したファシリテーション本。ファシリの最重要要素なので下手なファシリ本読むならこの本を薦めます。「問い」の重要さは散々語られるけどこの本ほど何を・どのように問いかけ、反応をどう受け止めれば良いか問いかけにまつわる一連の流れをわかりやすく構造化して解説している本に初めて出会った。特に「見立てる」「組み立てる」「投げかける」の3ステップは実際に問いを発する前までの準備が大切であることが端的に理解できて良い。ファシリテーターだけでなく、コンサルや教師や医師など広く対人支援に関わる職業の新人育成にも活用できる視点だと感じる。