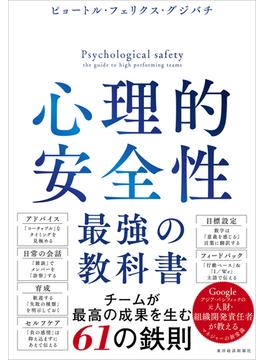投稿元:
レビューを見る
「心理的安全性」が職場でも大事だよね、と誰もが言うようになった昨今、どこかでお薦めされたこの本を読んでみた。心理的安全性の第一人者のエイミー・エドモンドソンの本はすでに読んでいるが、やや実践に寄った本も読んで知識補完するのもよかろうという目的。
著者が、ピョートル・フェリックス・グジバチという名前だったので、てっきり翻訳ものかと思ったら、日本でベンチャ企業を立ち上げた起業家で、日本のビジネス文化にも沿った内容にもなっている。
本書は第一部 理解篇、第二部 マインドセット篇、第三部 実践編、と言う構成になっている。
【理解篇】
理解篇では、エドモンドソンの主張に沿って「心理的安全性とは何か」が解説される。
「対人関係においてリスクのある行動を取っても、『このチームなら馬鹿にされたり罰せられたりしない』と信じられる状態」だとエドモンドソンは心理的安全性を定義する。怒られる心配がない単にぬるま湯につかったような組織ではないということでもある。相手を傷つけないことが心理的安全性が高いわけではない。かえって心理的安全性は、意見の対立を促すべきものなのである。
著者は、心理的安全性の本質を、「自分にも相手にも誠実であること。それによって一時的に対立が生じたとしても、相互理解が深まり、人間関係が構築されていくこと」だとする。そのためには、多くの企業で掲げられているパーパスやミッション、ビジョン、バリューを明確にしておく必要があるという。単に題目のように唱えられているだけでなく、そうした構造について腹落ちした明確な理解を共有しておかないと心理的安全性が保たれた組織にはならないというのが著者の主張である。目的や目標を言葉で明確にすることで、ハイコンテクストな対応、つまり忖度がなくなるのである。
心理的安全性を確保するために重要なこととしてもうひとつ著者が挙げることが「人」と「タスク」を区別し、「人にやさしく、結果に厳しく」のアプローチである。これが心理的安全性の土台になるという。また、その人にとって、「自分に居場所がある」と感じられることが重要だという。その意味で、一般的に個人に対して厳しいと考えられている外資系企業の方が心理的安全性が健全に保たれている場合が多いという。マネージャ(管理職)は、「人」を管理するのではない、「プロセス」を管理するのであり、その先にある「結果」を管理するのだ。「人」に対して使うべき言葉は「管理」ではなく「支援」だと著者はいう。メンバーが最高のパフォーマンスを発揮するための環境を整えることこそがマネージャの役割なのである。そして、これは当然のことだが、マネージャ、特に中間管理職層の心理的安全性が確保されているのかどうかが、組織の心理的安全性が確保されるかどうかに大きな影響を与えるのである。
以上、理解篇で挙げられた心理的安全性に関する内容は、エドモンドソンの本の内容にも沿った上で、適宜分かりやすく別の言葉でまとめられたものになっている。
【マインドセット篇】
まず大事なこととして自己認識とそれに関わる相互認識を挙げる。適性がない仕事、もしくは���りたくない仕事の職場で心理的安全性を高めることは難しく、成果が出なければますます心理的安全性は下がっていく。自分が最も力を発揮できることに集中することがとても大事になってくるのである。そのためには、パーソナルブランディングの確立の重要性を強調する。自分の得意領域や価値観、信念、期待感を周りに伝えていくことによって、心理的安全性は確保され高まっていくのである。そして、その逆として、相手の価値観、信念、期待感を認識し、尊重することが大事であり、それが実現されているような組織を目指すべきなのである。
そのために、マネージャは自ら積極的に弱みも失敗も含めて自己開示をしてくことが重要になる。その上で、メンバーに興味をもつことが推奨される。メンバーと相対するときには、確証バイアス、ナイーブ・リアリズム、過剰自己評価、親和性バイアス、楽観主義/悲観主義バイアス、などのアンコンシャスバイアスを謙虚になって排除して相手を理解しようと努めないといけない。
心理的安全性とは何かを理解した上で、どういった関係性を築いていくのかが組織構築のコンサルタントらしくまとめられていると言える。
【実践編】
実践編では、マインドセット篇で整理をした組織内での関係性をどのように実現していくのかの具体的な方法が示される。管理職としてのコミュニケーションと目標管理のスキームがそれである。
心理的安全性を保つには目標設定のスキームとしてOKR (Objective & Key Result)を薦める。本人にとって望ましい目標は、望んでやりたい目標であり、かつ努力しれば達成できる目標である。OKRについては他にも詳しい本がいくつもあるが、高くかつ意義のある目標をいかに設定するのかと、それをどのようにフォローしてフィードバックして回していくのかが簡単に説明される。
【まとめ】
本書に書かれていることはひとつひとつは意外なことは書かれていない。心理的安全性についてもとてもオーソドックスなものであるし、そこから導かれたコミュニケーションメソッドも無理のない道理の取れたものである。そしてまた、それらを実践することは自らを振り返ってみてできていないことでもあることは確かである。ここで、それはわかっているとして納得するのではなく、その実践が難しいこと、実践できていないことが多いことを謙虚に認識して、それを実践するためには自然にそういった行動ができるようになるまで自らに腹落ちさせることだと理解した。そのためにどうするのか、が頭を使って考えることなのだろうと思う。
-----
『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』(エイミー・C・エドモンドソン)のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4862762883
『チームが機能するとはどういうことか──「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ』(エイミー・C・エドモンドソン)のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4862761828
投稿元:
レビューを見る
最近読み続けている、「心理的安全性」に関する一冊。相手を役割として捉えるのではなく、一人の人間として接し、対話することが大切。上司にも、同僚にも、部下にも読んでもらいたい一冊でした。
投稿元:
レビューを見る
マネージャーだけてなく、どんな立場の人間にとっても勉強になる本。パーパスや仕事に対する価値観や相手起点で対話すること、「人に優しく、結果に厳しく」など、一社会人として学ぶことが多かった。
投稿元:
レビューを見る
ポイントは心理的
損を受ける制度があるからやらない ではなく 損受けそう、受けるかどうか分からないからやらない 物理的な有無ではなく心理的なもの。
目に見える形を作ることが対策ではなく雰囲気、環境、習慣を作ること 日々少しずつしかないか。
自分にもメンバーにも役割を明確にしておくこと互いに関心を持つこと
投稿元:
レビューを見る
コミュニケーションの問題だけでなく、職場の構造が明確になっていることが必要という指摘は新鮮でした。
また、あとがきの、日本は役割文化で、ひとりの人間としてよりも役割の方が重要視されるという話もすごく納得でした。
一方、対話のよい例として挙げられているものが、論理的過ぎてやや冷たく感じられました。自分が上司にこう言われたら、ちょっと距離を感じてしまいそうです。
外国人の著者の良い点と残念な点、両方を感じる一冊でした。
投稿元:
レビューを見る
◯構造を明確化する
・ビジョン、ミッション
・チームの目標と役割
・評価の基準
・仕事の役割分担、ゴール、業務内容
これらの構造がしっかり、チームに共有されていることが重要。
構造が明確な職場は、互いに意見が言いやすく、心理的安全性をもって働きやすい。
目標に意義をもたせることも重要、目標達成によって会社・組織・本人にどんな意義があるのかを対話する。無機質な数字を意味のある目標に変えられるのが最高のマネージャー。
◯承認欲求を満たし、下げない
・人には承認欲求がかならずあり、承認されることで居場所を自覚し、職場を安全を思い居座る
・「人」と「事」を分けて考える。仕事にダメ出し、人にダメ出さない。
・自己認識をさせると仕事が楽しくなる。自己認識は得意・不得意、得意の業務への結びつき、そしてそのことへの他者感謝を伝えること
・プライベートをお互いに知っている、言動の背景を理解することも承認欲求を高める
・人を管理するのではなく、支援すると考えると、自然と承認欲求を高める発言や行動をとれるのでおすすめ
◯来させるな、会いに行け
・話し方のコツは、相手の場所に「会いに行く」こと。
・貝合も相手に合わせる
・この2つだけで「その気持だけでも嬉しい」「自分に合わせようとしてくれている」と思ってもらえる。
◯相手を否定するための「なぜ」を多用しない
・なぜなぜ分析は、IQを否定したり、誠実さを疑うような場面でたくさん使うのは有害になる
・「なぜ」という単語だけで終わらせず、自分はこういう風におもったんだけどどう?。もしくはチャーミングになぜすることが重要
・ラポールが気づかれていれば気にしないで良い
◯問題やトラブルについて
・悪い報告を受けたら罰より対話が先
・悩みや困り毎はすぐ解決策を伝えないこと、まず理解されていると相手に感じてもらうまで待て。
・本人の中にすでに答えがあるかどうかを見極めることも重要。すでに策があるなら、それを引き出すのが先。
・相談された側がすでに答えがある、自分のほうが正しいという考えがあるとバイアスにやられるし、メンバーの成長に繋がらない
・それらすべてを引き出して解決策がないなら、それでようやく一緒に解決策を考えるターン
◯ハイパフォーマーに注力せよ
・仕事ができない人をなんとかしようとしない。
・効率的観点はもちろん、仕事ができないひとを力づくでなんとかしようとすると、心理的安全性が下がりさらに生産性が下がる
・人に優しい職場とは甘い職場ではない。成果に向けて正しい設計ができるのが優しい職場
・ローパフォーマーに注力して成果が下がることは、ハイパフォーマーの心理的安全性に悪影響しかない
・ハイパフォーマーに集中し、彼らがいかんなく実力を発揮し、成長していけるために心理的安全性を考えること
投稿元:
レビューを見る
「心理的安全性」とは心身が脅かされる危険性なく自分の意見を自由に発言できる状態である。建設的批判ができる職場は、強い。著者が説くそうした職場の前提条件は「自己認識
」「自己開示」。自分の取説を伝えて相手を「ひとりの人間」としてよく観察し興味を持つ。一周回って昭和の飲みニケーションに近いことを最先端のGoogle出身者が力説しているのは面白い。他方で本書を実行できるマネージャーはコミュニケーション能力が高く、上司・メンバーともに共通理解がない場合は自身のみで「心理的安全」を確保することはなかなかに険しい道だ。「ちゃん付かさん付か」のエピソードはマネージャー側に相当精神的余裕が求められることを示している。書いてることは至極当然であるゆえにラポール構築は一筋縄ではいなかない。
投稿元:
レビューを見る
管理職の人は必見。職場全体の生産性を上げるために、マネージャーとして必要な鉄則が沢山記載されている。ぜひこの本を読んで、研修などで受検した性格アセスメントの結果を、ご自身の「取扱説明書」としてチームメンバーに配布のうえ、1on1を沢山取り入れて欲しいと願う。自分がそのような立場になる可能性は今のところ低いのだが、もしなった場合は絶対に実践したい。
数年前までの私は、職場の心理的安全性をぶち壊す典型的な問題児であった。残業時間は部署の中でダントツに多く、36協定も違反していたし、何回も体調を崩して、常に愚痴っていた。職場で大きい声を出したこともあった。これでは、どれだけ成果を出しても、評価が低くなるのは当然である。
ただし、人間だからこそ、ケアをしてあげなければ、頭で分かっていても、多忙のあまり精神は少しずつ壊れていくものではないのだろうか?過酷な環境を、「タフアサインメント」の一言で片づけて良いのだろうか?(私の言い訳だろうか)
この本を読んで、あの激務だった時期に、毎日抱いていた負の感情を思い出した。
・自分のSOSは誰にも聞いてもらえない。
・上司や先輩に意見を言っても無駄。いじられるだけ。
・自分の忙しさは、どうせ誰も分かってくれていない。
・とにかく腹が立つので、SOSをPRしたい。
心理的安全性が保障されていない、そして評価の軸が曖昧な職場だったのではないだろうか。まあ、自分が得られなかったものに対して、今更クヨクヨしても意味は無い。むしろ自分は、心理的安全性を求める立場から、心理的安全性を「お膳立て」する立場になるのかも知れない。そうやって自分を前向きに奮い立たせ、明日も通勤するしかないのだ。
投稿元:
レビューを見る
ダメ出しになりがちな「フィード・バック」に対して、予め失敗しやすいポイントを共有することを「フィード・フォワード」というのを初めて知った。グジパチさんが所属していたGoogleの心理的安全性を醸成するための試みが紹介されている。何度も読み返したい一冊。
投稿元:
レビューを見る
心理的安全性=「楽しくやさしい職場」ではない!という言葉にハッとしました。仲良しこよしではなく、お互いが高め合える、建設的な意見の対立ができている職場であれば、成果も出やすいのだろうと思う。威圧感だけを発してる人に読んでもらいたい。
投稿元:
レビューを見る
心理的安全性に関するマネージャ向けの本です。マネージャ向けではありますが、「はじめに」に記載されているの考え方はフォロアーにも読んでもらいたい内容です。
実際に心理的安全性を高める取り組みをする際、「はじめに」~第1部「理解編」をそのまま要約してチーム内に展開しようと思えるほどまとまっています。
第2部「マインド編」、第3部「実践編」はマネージャ自身が心がける内容になっています。
著者の本は初めて読みました。海外の方と思うのですが、日本の会社の実情をよく見られているなと感じられました。
投稿元:
レビューを見る
ラポールがあれば言葉の使い方はそれほど問題にはならないというのは確かにそうだなと思いました。また、マイクロアグレッションについても言及があり確かにそうだなと思いました。ハラスメントがこれだけ浸透して明確に問題と扱われるようになってのち、それらは判断が難しいマイクロアグレッションに移行してきているように思います。そしてそれらは明確に診断することが難しくても、ラポールの構築に関わらずその場面に遭遇したら皆ある程度わかるように思います。そのイライラだったり人を見下しているというネガティブなエネルギーは言葉じりや表情からあふれてくるので。それってアンコンシャスバイアスで本人が自覚したら治る。というのとは明確に違うかなぁと思います。その辺は明確に分けておかないとそういったことに直面してる人々にいくらサポートするような対応をしてもポジティブバカと見做されかねないので気をつけたいなと思います。
投稿元:
レビューを見る
心理的安全という言葉をここ数年で聞くようになり、読破してみた。
心理的安全は、仕事だけでなく育児など人に関わること全てに通じる考え方だと思う。何度も読み直したい。
投稿元:
レビューを見る
心理的安全性とは対立のない平和な状態ではなく、対立が生じても大丈夫だと安心しながら自分らしく振る舞うことができる環境である。
そのためには、自分の価値観と信念を開示し、メンバーの価値観を理解しようと関心をもって集中し、人として尊敬しつつプロセスを管理して結果には厳しくすることが重要であるという。
語られる内容が違和感なくすんなり入ってくる良書だったが、いかんせん内容がシンプルで、強烈なパンチに欠けるため星3つ。
投稿元:
レビューを見る
人格を否定するのではなく、行動に対して評価する。
目標設定は
1,望んでやりたい目標である
2,努力すれば達成できる
マネージャーが管理するのは、プロセスと結果であり、人の管理ではない。