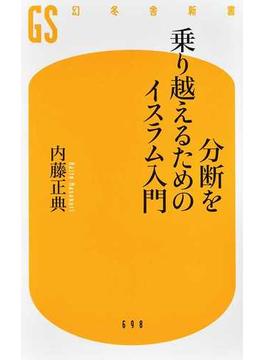「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
分断を乗り越えるためのイスラム入門 (幻冬舎新書)
著者 内藤 正典 (著)
1400年前に誕生し、いまだに「生きる知恵の体系」として力を持ち、信者を増やし続ける宗教・イスラム。その教えの強さはどこにあるのか。世界の3人に1人がイスラム教徒になる時...
分断を乗り越えるためのイスラム入門 (幻冬舎新書)
分断を乗り越えるためのイスラム入門
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
1400年前に誕生し、いまだに「生きる知恵の体系」として力を持ち、信者を増やし続ける宗教・イスラム。その教えの強さはどこにあるのか。世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代の、必須教養としてのイスラム入門。【「TRC MARC」の商品解説】
21世紀に入り欧米諸国にとって最大の脅威はイスラム勢力だった。だが、欧米がイスラムを理解せず、自分たちの価値観を押しつけようとしたことが、対立をより深刻にしたのは否めない。1400年前に誕生し、いまだに「生きる知恵の体系」として力を持ち、信者を増やし続ける宗教・イスラム。その教えの強さはどこにあるのか。暴力的・自由がない・人権を認めない等、欧米が抱くイメージはなぜ生まれ、どこが間違っているのか。世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代の、必須教養としてのイスラム入門。【商品解説】
21世紀に入り欧米諸国にとって最大の脅威はイスラム勢力だった。だが、欧米がイスラムを理解せず、自分たちの価値観を押しつけようとしたことが、対立をより深刻にしたのは否めない。1400年前に誕生し、いまだに「生きる知恵の体系」として力を持ち、信者を増やし続ける宗教・イスラム。その教えの強さはどこにあるのか。暴力的・自由がない・人権を認めない等、欧米が抱くイメージはなぜ生まれ、どこが間違っているのか。世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代の、必須教養としてのイスラム入門。【本の内容】
著者紹介
内藤 正典
- 略歴
- 〈内藤正典〉東京都生まれ。東京大学大学院理学系研究科地理学専門課程(博士課程)中退。同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。一橋大学名誉教授。著書に「となりのイスラム」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
書店員レビュー
読めばムスリムへのイメージが変わる本である
ジュンク堂書店福岡店スタッフさん
新型コロナのパンデミック、ロシアのウクライナ侵攻という世界規模の災厄の中で
ムスリムはどう動いてきたか、どう考えてきたかを取り上げなから、
イスラムについてわかりやすく説明している。
一見、厳しくも怖いイメージのイスラムだが、代表的な教えは、
「アッラー以外に神はいない」と信じ、一日5回の礼拝、弱者のために喜捨をすること、
ラマダン月に断食すること、一生に一度メッカに巡礼することとなっている。
もちろん戒律を破るとそれなりの罰はあるが、それは私達が法律を破ったときと同じことだ。
ムスリムはこれらの教えを異教徒へ強要しない。
逆に、西欧文明が悪いというのではないが、
西欧は、自分たちの思い込みや、絶対的な優位性を持つ自分たちの規範性を異教徒へ押しつけ、従わせようとしてきた。
そうしたことで、今日のムスリムとの共存が難しくなってきたのである。
その分断を、イスラムを正しく知ることで乗り越えようと筆者は説いている。
紙の本
イスラム世界をおっかなびっくりで見ているから、日本の経済成長が止まったままなのか
2023/08/04 10:41
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
イスラム世界というのは、日本人にとってわかりにくいというより、遠い世界と思い込んでいる。本書は、現代イスラム研究者として、マスコミにも登場されている方が、日本人の多くが陥っているだろう誤解(そもそも知らないという方が正しいか)を解くために書いた入門書である。特に、アメリカ等がイスラムというとテロリストやイスラム過激派、さらに得体のしれない存在のように宣伝していたことから、遠くのものと思い込んでいることは間違いないだろう。しかし、私たちの周囲にはイスラム教徒(ムスリム)の方が多く生活している。目次を見ると、
はじめに - 世界宗教となったイスラム
第1章 イスラムはパンデミックに強い
第2章 強さの源泉はどこにあるのか
第3章 「見えない楽園」の力
第4章 イスラムは「遅れている」のか?
第5章 イスラム世界とウクライナ戦争
第6章 イスラムと暴力
第7章 ムスリムは西欧をどう見ているのか
第8章 西欧はなぜイスラムを嫌うのか
第9章 分断を超えてムスリムと付きあう
おわりに - 分断の時代にイスラムに学ぶ となっている。
以上のように、第1章はイスラムの解説や前史的な論述でなく、パンデミックに強いというところから始まる。日本でも新型コロナウィルスの感染者が多く大変だったが、マスクをしたり、手洗い、うがいの習慣がそれなりに定着していることから、死者が思ったより少なかった。イスラムでは預言者ムハンマドの教えに従い、「敵」をつくりだすことが少なく、ステイホームや清潔保持を励行したという。自粛警察というのは出なかったのであろうか。日本では宗教といえば仏教、神道であるが、経営の厳しい社寺が多い。キリスト教は規模でいえば小さい。旧統一教会等が宗教団体と言われると一歩引いてしまう。しかし、イスラム教は世界的にみて信者が増えてるというから、それなりの魅力があるのだろう。例えば、アフガニスタンのタリバン政権が、再び女性の教育を受ける権利を侵害しだしていると聞くと、イスラム教だからと思ってしまうと、イスラムに女性の教育を禁じる教えはないとする。宗教と国家の関係をどうするのかによって変わり、イスラムの教えとは違って、家父長的な価値観で政権運営をしているのかという点を考えないといけないので、どこかのプロパガンダに乗せられないようにする努力が必要なのだろうか。ロシアのウクライナ侵攻も、イスラム世界から見ると違って見える。日本人の生き方として、イスラム世界の多くの方とどうつきあっていくのか。国家の場合は外交をどう進めるのかということになる。今後の日本社会の発展や経済成長にもかかわることと思う。一読してほしい本である。