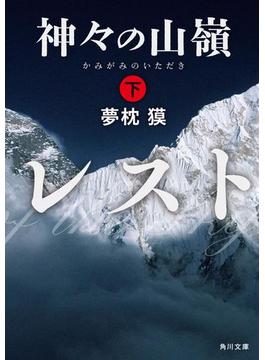夢を追う登山家の情熱に感動!
2016/01/17 13:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:AYA - この投稿者のレビュー一覧を見る
命がけでエベレストに挑む二人のこころの葛藤と必死さが痛いほど伝わってきました。また、羽生丈二という人物に謎が多く、次の展開をハラハラしながら読み進むため、これだけ長い小説でも、すぐに読み終わってしまいました。何かに夢中になるって素晴らしい、と思い出させてくれる作品です。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:坦々麺 - この投稿者のレビュー一覧を見る
エベレストを征服するために、スプーンの柄を削りギリギリまで軽量化する。マイナス30度、40度の世界で睡眠をとる。風に吹き飛ばされないよう岩にしがみつく。自分には不可能であろう。多くの人も不可能であろう。しかしこの小説を読んでいると不思議にエベレストにしがみついている。この小説に出会えたのは、大きな財産だと思う。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しゃお - この投稿者のレビュー一覧を見る
登攀中の羽生の手記には鬼気迫るものを感じたし、頑なさには深町とともに頭を抱えた。
だが、ラストの羽生とマロリーのシーンではぐっと胸が熱くなる。死してなお、羽生の凄まじいまでの情熱と執念を感じたからだ。
二冊ともかなりのボリュームで、内容的にも重いが、映画化にも期待したい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:よよん - この投稿者のレビュー一覧を見る
初めての山岳小説でした。もっと山登りばかりの話かと思いましたが、読んでみると山の壮絶さと登山者達を巻き込んだサスペンス風と言ったところ。そういう意味では、もっと登山の過酷さを乗り越えたり遭難したりするのかと思って読み始めただけに肩すかし感はあります。しかしながら中々楽しめました。
投稿元:
レビューを見る
音やにおい、空気の色までなんとなく想像できてしまうほどのリアルで洗練された情景描写にとても驚きました。
羽生の生き方はとても苦しいのだけれど、うずうずしてしまうくらいかっこいい!
結構分厚いのですが引き込まれるようにいつの間にか読み終わってました。また読みたい!
投稿元:
レビューを見る
羽生丈二の不器用でありながら
ブレない格好よさに圧倒される。
人は、自分にどれだけの欲求をもつことができるのか。
ひたむきに生きれば生きるほど、
それは飽くなきものになるのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
エヴェレストに登っている描写は山に登ったこともない私でもまるで登っているような臨場感があり、すごく引き込まれながら読みました。
なぜ山に登るのか。答えはないのでしょうか。
投稿元:
レビューを見る
がっつり、読み応えがある作品でした。
登場人物も容易に想像でき一気に読破してしまいました。
山の描写がリアルで自分がエベレストに挑戦してるような錯覚に落ちるような感時でした。
投稿元:
レビューを見る
映画を見てからようやく下巻まで読破。振り返ってみると、映画の全体のストーリは原作通りなんだよね。でも、なんであんなに駄作になったんだろう。原作ではやはり環境の過酷さがいやと云うほど書き込まれていて、だからいい作品に仕上がってように思う。ただ、少し記述がしつこいとは感じた。
投稿元:
レビューを見る
もう、言葉にならない。山って、登山家ってこんなにすごいのか。こんなに一生懸命生きたことある?
羽生、深町の息遣いが聞こえてくるような、本当に生々しいドキュメントのよう。登山家にとって登ることは生きることなのか。自身への挑戦なのか。
最後の再会は、息をするのを忘れるほど没頭して読む。こんな再会が待ってたなんて。
うまくレビューが書けない自分がもどかしい。。
映画見たいなあ。
投稿元:
レビューを見る
長い…。
夢枕作品は初めて読みましたが、どのテーマでもこんなに長く語り調が続くのでしょうか。
小説でもルポでも描く対象との一定の距離が必要になると思うのですが、触れるのが剣呑なほど先鋭的な人間を描く場合は特に距離を意識しないとならないと思います。
羽生がいくらすごい人間でも深町がすごいすごいと騒いでは興ざめです。
彼の感情の揺れがいちいち安っぽく感じられて下巻後半部分は白けてしまいました。
高峰登山を描くには余計な言葉はいらないなと痛感します。
エンタメ部分と登山部分の温度差にも違和感があり、なじめない物語でした。
投稿元:
レビューを見る
実在の登山家マロリーとアーヴィンはエヴェレストの頂上を踏んだのか、その謎を中心に山岳カメラマンの深町が天才登山家の羽生のエヴェレストへの挑戦をおう。
エヴェレスト冬季南西壁無酸素単独登山に挑む
作者は構想後20年もの年月を経て書き上げた作品
それだけの価値はあり、引き込まれて、一気に読破した。
最期の羽生の遺体のポケットにあったチョコレートた干しぶどう、素晴らしいエンディングだった。
投稿元:
レビューを見る
audibleで聞いたせいだろうか、物語自体は面白いが、いちいち説明が長いし、繰り返される。その中身もいわゆる男性読者向けのハードボイル系とでもいうんだろうか?男らしさ溢れる表現、男らしさ溢れる思想で、聞いていて違和感満々。ただその効果もあってか、高い場所へ登るための苦労というものはしっかりと伝わってくる。
小説や漫画だともう少し楽しめたのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
後半は
カメラマン深町は登山家羽生を追い、とうとうエベレスト南西壁冬期無酸素単独登頂を目指す
深町はどこまでついていけるのか…
それなりにトレーニングを積んだが、もちろん天才クライマー羽生とは比較にならない
羽生は8年間もかけて入念に準備をしてきたのだ
尋常ではない緊迫感がひたすら続く
氷塊、クレバス、雪崩、落石、垂直の岩壁…、凍傷、強風による低体温症、どんどん酸素は薄くなり、高度障害が出始める
読んでいるだけで苦しくて辛い
(軽い高山病の記憶がよみがえる そんな時でさえも、食事は喉を通らず、頭痛と吐き気がし、筋肉が鉛のように動かなくなる
次の一歩を出すのに使うエネルギーが足りず辛い この何百倍の辛さかと想像するだけで倒れそうである)
ここでの高山病の恐ろしさをピックアップしてみる
ちなみに富士山標高は3776メートル、エベレスト標高は8848メートルである
以下は本文からの抜粋
〜4000メートル越えた場所であっさり死ぬことも珍しくない
6000メートルが人間が順応できる限界か
ここを越えた場所に長時間滞在すると、大量の脳細胞が死んでゆく
ヒマラヤ登山は生物にとっての極限状態を日常に体験することだ
人によって高山病の症状が出る高度はまちまち、かつその時のその時で高度も違う、体調にも左右される
スタミナがあっても、高山病になればベースキャンプにさえ、たどり着けないことも…〜
その中で山頂アタックできるのは、体力だけでなく、強靭な精神力と強運(天候も含め)が必要である
そう最後は神に許された人間だけ…なのかもしれない
登頂中、カメラマン深町が羽生と直に接し、羽生のある意味生きる姿を目の当たりにして、深町は自分と向き合うことができたのだろう
その後、彼は何らかの答えを導き出していく…
何で人は山に登るのか…
不思議である
何で生きるのか…と同じ質問だ
何度か自問自答したことがある
大雨と暴風の中、「二度と山に行かない」と何度も心に誓いながら、とにかく早く終わらせるためだけに、無我夢中で歩いたこともある
1日、10時間以上、10Kg以上の荷物を担いで、山行した後、かわいそうな足の潰れたマメを見ながら、もうここまでの縦走はいいんじゃないの?
と自問自答する
参考計画を立てても行きたくなくなる…
こんなことの繰り返しで山に登っている自分が何だか可笑しい
答えがなくてもいいのだ
趣味で登山をする程度でさえも不思議な力にどうやら取り憑かれる
さてここからは番外編
ネパールについての知識
シェルパは職業的な名称だとずっと勘違いをしていた
シェルパはネパールのソロ・クンブ地方に住むシェルパ族を指す
「東の人」という意味の種族名とのこと
頑健な肉体と、高地に順応した心拍機能に着目し、イギリスが1900年代初めに、ガイドやサポーターとして雇ったのが始まり
イギリス人は彼らに英語を教え、登山道具を与えた
このようなシェルパと呼ばれる山岳ガイドが成立してゆく過程は、グルカという���士集団が成立してゆく過程と似ている
グルカはイギリス陸軍に設けられた、ネパール人兵士の外国人部隊のことだ
こちらもグルカ族といういくつか部族の総称である
山岳部に住む民族のため、シェルパ族同様、
肉体は頑強、肺活量、忍耐力などの基礎体力が他の部族より優れる
地上最強の部隊と呼ばれた時代もある
いずれもネパール人でありながら、外国人のために生まれた職能集団である
経済的に貧しいこの国は、外貨をこのように得ている
そしてもちろん一番の収入源はヒマラヤを中心とした観光である
トレッキングから、外国人登山隊がおとしていく外貨や入山料なとである
入山料だけで約100万円以上である(日本の富士山にそんな制度はない)
ネパールは世界最貧国のひとつであり、カースト制、民族格差、教育問題、民主化など、様々な問題を抱えている国である
ネパールの国を垣間見れたことも興味深かった
どうも小説部分より、登山とネパールにフォーカスを当ててしまったが、一般的には小説としても充分楽しめる作品だろう
極寒の地でありながら、非常に暑苦しい世界が展開する
ヒリヒリする痛みを感じながら、息苦しさと、突き上げてくる熱い思いとともに一緒に冒険できる
そんな内容であった
誰に何と言われようとも、自分が納得した人生を送るための手段なんて人それぞれだ
そんなことをこの小説は教えてくれる気がする
但し、残念ながら個人的にカメラマン深町に全く共感できず…
昔読んだ鎌田敏夫氏の小説を読んでいるみたいで、もうそういう熱くて青い感じは受け入れられる年齢ではなくなったなぁと客観的に冷静にしか読めず…
もう少し若いころに読んでおくべきだった(笑)
投稿元:
レビューを見る
素晴らしい!
ハラハラ、ドキドキして、先を読みたいんだけど、読みたくない!みたいなw
みんなが絶賛するのは当然だわねぇ〜。