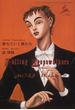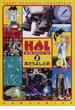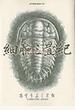バイシクル和尚さんのレビュー一覧
投稿者:バイシクル和尚
紙の本墜ちていく僕たち
2002/05/10 01:31
読んでしまう僕たち
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
たまたま家にあったインスタントラーメンを食べると性別が変わっちゃって、大変だぁ(森調)。といったいくつかのストーリーが連続性をもって展開されるという、少し変わった趣向の本。京極夏彦氏の「どすこい」と同様の手法である。性別転換というテーマだけをとりあげれば、いくらでも深刻に書けるのにそこをさらりと、あえてこだわらずに軽くあしらえるのがこの人の面白さであろう。しかしそこに登場してくる人物達は決して明るいとは言い難い。誰もが軽いのだが、やはりどこか暗い部分を持った人間で、社交性に乏しく内向的な人なのである。作中の人物達は自分自身にとんでもないことが起こっても決して慌てない、取り乱さない。死んでしまっても落ち着いている。この不思議な「軽さ」が読み手にも不思議な感覚を植え付ける。読んでいて面白かったと思う、しかしどこか寂しくなってしまった。
2002/03/14 22:08
天国か地獄
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
さえない中年男が電車で行き着いた先は「うろしま駅」。そこはセックスが挨拶代わりというぶっ飛んだ町だった。道行く人がところかまわず、人目はばからず皆セックスしている。男はそこで魅力的な女子高生「ユマ」と出会う。男はユマと事を成さんがために必死に彼女を追い求めるが、「絶倫男」と噂されてしまった彼はそのために他の女性とのセックスにあけくれなかなか本懐を遂げられない。ユマとの再会、そして彼の行き着く先は…。
SF短編に定評のある福山庸治氏の新作である。彼の短編にはセックスをテーマにしたものも多いが、これはまたそれとは別物。なんと言っても最初から最後までセックスで首尾一貫。ここまで徹底したものは珍しい。あくまで下品なのだがそれを感じさせないのは彼独特のセンスがあるからだろう。映画にすればウディ・アレンそのままである(主人公の顔もメガネででかっ鼻)。ともかく彼の不思議な物語に一度触れていただきたい。セックスのように病みつきになる魅力を感じられるかもしれない。
紙の本黄色い本
2002/03/08 12:09
このコマの白さが
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
素朴な絵とストーリーで人を引き付ける高野文子の新刊。読書好きの少女が出会った本「チボー家の人々」の登場人物ジャック・チボーと内心で語り合う。
素朴な日常と少女の空想の対比がどことなく不思議でそこがたまらない。この人のマンガの魅力は徹底した日常の描写にある。例えば、蚊を追って叩くその手を布団に擦り付けるそんなサイレントな描写、記号化した日常の一コマを端的に表現する、そんなところがスゴイ。ページのどこにもこんなことあったようなといったデジャヴを感じさせられる。それが全体的な不思議感をうみだすのだろう。ノスタルジアを描かせたら天下一品。そういう点でも「黄色い本」はお勧め。ぜひ一読あられたい。
紙の本トニーの背骨はよく曲がる。 1 改訂版 (Beam comix)
2002/03/08 11:38
「弾丸(ブレッド)をないがしろにする男」っていうセンスは好きなのだが
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
古本屋の店員「トニー」、彼の裏の顔は賞金10億ドルの懸かった殺し屋だった。毎日殺し屋に命を狙われる彼だが、そこは持ち前の驚異的な体(よく曲がる背骨)で次々と返り討ちにしていく。
全編通してアングラなバイオレンスストーリーなのだが、カテゴリーに分けるとこれはギャグマンガなのだろう。ギャグと断言できないのはあまり笑えないからだ。どこかに暗さがにじみ出ている。それが魅力なのかもしれないが。絵も拙い、もう少しうまくやればもっと面白くなるのにと少し残念である。
紙の本カスミ伝Δ 1
2002/02/25 04:31
もはや感服の域
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
唐沢なをきの真髄である。全編実験的手法をもちいたいわば唐沢なをきだけに許された反則ともいえるマンガ。この人は全部版画でマンガを作ったり、炊いたご飯の上に岩のりでマンガを描いたりとまさにやりたいほうだいなのだが、一度ファンになってしまうとやめられなくなってしまう。次は何をやってくれるんだろうという期待感に苛まれてついつい買ってしまう。思いもよらない手法を使われたりすると、読んでいて、あっやられた! と思わずにはいられなくなる。こんなマンガ家は他にはいない。
作者はネタについて人に先を越される恐怖が常につきまとっていると何かの本でいっていたが、読者にとってもそこが勝負なのである。もはや熟練ともいえる域に達した唐沢イズム、ファンならずとも必見。
紙の本と学会年鑑 2002
2002/02/25 04:03
祝10周年
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
と学会とは山本弘を会長とするトンデモマニア集団なのだが、学会だけあって発表がある。本書は2001年に行われたその例会での発表のえりすぐりである。内容は各会員が見つけたトンデモアイテムを発表する、というかツッコミをいれまくるというものである。トンデモというのは作者の意図とは別の意味で楽しめるものと、と学会では定義されているがすでに学会が設立されて10年も経つのにまだこんなトンデモを見つけてくるかと驚かされた。しかし初期のと学会の著作である「トンデモ本の世界」等に比べると若干のパワーダウンは否めないところではあったがそれでもやはり面白い。ファンはもちろんの事ながら「と学会? なんじゃそりゃ?」という人にもお勧めである。
紙の本HAL 2 はいぱああかでみっくらぼ (Gum comics)
2002/02/16 01:54
これも新しい教科書?
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「まんがサイエンス」でお馴染み、あさりよしとおの科学マンガ。なのだが、本書は子供向けのそれとは少し様相を異にする科学マンガ。
なにしろ注意書きがあり、それには「このマンガには一部真実が含まれている場合があります」とある。つまり中に書いてあることはほとんど嘘ということなのだ。確信犯的なトンデモ本といってもいいだろう。正確な知識を持っていないと笑うことはできないギャグ。とはいっても、中には専門的なネタもあるので、これどこまでウソだ? と首をひねってしまうものもある。そんなときはやっぱりほかのなにかで調べてしまう。そう考えると、やはりためになる科学マンガなのかもしれない。ある意味完全に大人向けのマンガ。
2002/02/04 03:06
センチメンタルユーモア
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
久々あさりよしとおの新作。理系マンガ家として知られる著者だが、本作もテーマは「三葉虫」でありこの人しか描けそうもないマンガである。続きモノではなくオムニバスで一回一回の世界観もバラバラであり、雑誌連載時は毎月新鮮で楽しみにしていた。ギャグに徹底したものもあるが、この人の持ち味はやはりどこか寂しさを伴ったギャグであると思う。1ページ前で大笑いしてページをめくるとオチはどこかうら寂しい、思わせぶりな一コマで終わる、そういったギャップが私にはたまらないのである。またサイレントなコマも妙技も作者ならでは、ほかには真似のできないところであろう。そのあたりも含めて一番気に入ったのが、その8佐藤君の場合。すこし脱構築気分になってしまいました。
2002/02/04 02:27
怪人アラマタ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
20世紀には数多くのミステリー、謎とされる物事があった。中にはでっち上げのものも少なくなかったが、それでもいくつかは未だ謎とされるもの、完全に解明されていないものが残されている。本書ではその代表的なものについて著者荒俣宏氏が考察しこれぞ、といえるものを文字通り20世紀の「ミステリー遺産」として礼賛している。時代を問わずこの手の話は巷の人気となり、最近でもテレビや雑誌で特集が多く組まれ関連の本も多い。その中でも荒俣氏は権威たる存在で、氏の本はやはり面白い。
氏の面白さの裏打ちというべきその凄さは、なんといってもその知識の豊富さである。この本について言っても、ひとつひとつの短いチャプターにおいて実に多くの資料がちりばめられている。この一冊を読むだけでもいっぱしの「通」になった気分が味わえるのである。確証されたものに価値を見出す現実に嫌気が差したら、ふと振り返って20世紀の遺したミステリーに目を向けるのもまた面白い。「嘘臭い」と思いながらも人が魅きつけられてやまないミステリーの数々、百家争鳴の現状のなかそれらについて現時点での正確な知識が本書で味わえる。さすが「帝都の怪人」である。
紙の本ひいびい・じいびい
2001/12/05 22:43
新装版でも新鮮
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「あ」から50音順で頭にその語のつく事象について作者の思いつくままに展開されるギャグオムニバスとでもいえばよいのだろうか。とり・みきだからできる、とり・みきにしかできないギャグでいっぱいである。「あ」から「ん」まで徹頭徹尾とりイズムである。
読んでいけばわかるのだが本書の展開は単なる徒然ではない。一単元ごとがSFであることにとどまらず一冊の本としてリンクを伴ったSFなのである。最後まで読んでもわかったようでわからない、この溜飲下がらないところがとり・みきの魅力ではないだろうか。
紙の本中陰の花
2001/12/05 22:22
その深み、拡がり
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
禅宗の僧侶の小説家が芥川賞を受賞した、と聞いたことが本書を手に取ったきっかけであった。読んでみるとなるほどこれはと納得させられてしまった。「本物」の僧侶であるという奥行きがあちこちで見て取れる。著者は禅宗の僧侶という宗教家になる前にいろいろな新興宗教のたぐいも研究し実際にその内側に入って見聞きし、独自の宗教観を作り上げていると聞いている。そのような著者の求道心が本書にはフィードバックされていて非常に面白かった。私も若輩ながら僧侶の肩書きを持っている。現代日本仏教は儀式に重きがおかれてしまいどうしてもその裏側、目に見えないところにあるものには目が向けられなくなってしまっている。著者はそのような風潮に「小説」という形で一石を投じたのではないか。仏教の教え、死とは、など考えるのも億劫になることに迷いながらも真摯に取り組む著者には感動を覚えた。今後の活躍が期待される。
2001/08/04 17:14
芥川的自殺なのか
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1970年代のアメリカ、デトロイトを舞台とした青春小説。五人姉妹の末っ子セシリアの自殺をきっかけに歯車が狂い始めるリズボン一家。一家の退廃は残された4人の姉達の連続自殺で幕を閉じる。70年代という不安定な時期に不安定な思春期を迎えた姉妹、そしてそれに対処しきれなかった両親。幾つもの不安定が重なった結果は当然の如き死であった。
内容はタイトルから一目瞭然であるのだが、その異様さもタイトルに負けず劣らずであった。流れ的には、姉妹に恋していた少年達が後日談として彼ら自身でまとめた「事件」のレポートを報告する形で進んでゆくのだが、こういう形式にも作者の巧さが感じられた。この作品、映画化もされていて(「ヴァージン・スーサイズ」)それも見たが原作にほとんど(というよりも全く)手の加えられていないものであった。そういう点でもかなり完成度が高かったのだろう。
あと気になったのが主題である5つの自殺がさらりと書き流されているところであった。5つもの死がほんのちょっとの文量で収められている。しかし物語全体としてはそれでしっかりと整合がとれているのだ。5人姉妹の自殺は当たり前のことのように受け止められる、そしてそれが70年代以降のアメリカの衰退を示唆している。20代の死因の一位が自殺である今の日本の現状を踏まえてみても読む価値はあるかもしれない。
紙の本なつのロケット
2001/08/04 16:14
なんか感動しちゃいました
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
慕っていた型破り教師の退職をきっかけに、少年達は先生の「教育」を肯定するために、また自分達の「可能性」を肯定するために世間をアッといわせることを計画する。それがロケットだった。
あさりよしとおの守備範囲である科学をテーマとした作品だが非常にすっきりと纏まっていたのは意外であった。持ち味であるハイレベルなブラックユーモアはほとんど無く他の作品とは全く異なった、いわゆるストーリーマンガとして完成している。こんなのも描けるんだなあというのが率直な感想。「カールビンソン」のノリも好きだがそのノリを排除したこういうのも、またいい。同じ科学を扱うマンガでも学習向けの「まんがサイエンス」、背理的で無責任な「はいぱああかでみっくらぼ」、そしてこの「なつのロケット」やはりあさりよしとおはスゴイ。
学習マンガと有害図書、両方描けるのはこの人ぐらいなもんだろうなあ。
紙の本11人いる! 新編集版
2001/06/28 10:20
名作は色あせず
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この作品、名作であるという存在は知っていたのだがなぜか今まで読むことが無かった。SFというものはタイムリーに読まないと一気に風化してしまうという意識があった。名作と呼ばれるものを読んでたとえ面白くても「当時」のイメージがつきまとうと。しかし、読んでみると考えを改めさせられてしまった。ちっとも古くない。それどころかひとまわりして新しさを感じてしまった。
確かにストーリーはありがちといってしまえばそうなのだが、情報制限下において他人を「信じる、信じない」というジレンマというのは社会学の永遠の命題でもある。そのような王道を無理なく、しかも短編と言う形で仕上げているのが素晴らしいし、なんといっても面白い。
お約束的テーマの中で読み手をひきつけるのはやはり設定がしっかりしているからなのだろう。キャラクターがそれぞれはっきりとしているし、展開もスムースである。なにより読み手に対する親切心がそれを引き出しているのだろう。
私は今まで読まなかった事が悔やまれた。少女マンガという枠をとっぱらって読める、文句なし「名作」である。
紙の本スプートニクの恋人
2001/06/25 21:32
あちらがわ、こちらがわ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「すみれ」にとって人生の全ては小説であった。おしゃれも恋も人付き合いでさえも無関係のこと、小説を読み、書くことがすべてであった。そんな彼女と友達であった「僕」は完全にすみれに恋をしていた。しかしすみれにとって「僕」は完全に友達であった。すみれを抱き愛し合いたいと願う「僕」とは正反対に、すみれは性欲すら無かった。そんなすみれの人生が180度転回する出来事が起こる。すみれは恋をする、当然に性欲を伴った恋を。ただその相手は13歳年上の「ミュウ」という女性であった。すみれは初めての、しかも同性を相手とする恋に迷い、喘ぎながらも幸福を感じる。しかしすみれの欲望が頂点に達したとき事件はおこる。
僕とすみれとミュウ、それぞれの外的世界と内的世界での葛藤と錯綜。村上春樹自身が言うところの「あちら側の世界」がテーゼとなっている物語である。小説というファクターが中心に据えてあることもあって、著者独特の表現が所狭しと現れてくる。その点でいえばファンは十分に満足できるだろう(しかし私は村上春樹の「たとえ」方が大好きではあるが、いささか胃もたれぎみ)。ストーリー展開はさすが絶妙で、ある意味サスペンス的な楽しみもできた。ページを早くめくりたいという衝動で、あっという間に読んでしまった。ただそれだけにラスト(スパート)のあっさり感には少し不満が残った。
おいてけぼり感、確信犯的なものなのか、もっと「考えろ」ということなのか、それもこの小説の楽しみ方の一つか。