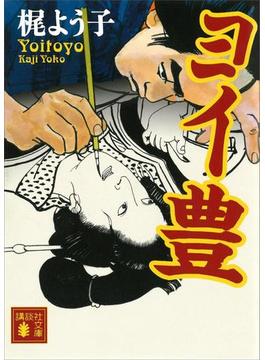ヨイ豊
著者 梶 よう子
元治2年(1865)、清太郎の師匠・三代豊国の法要が営まれる。広重、国芳と並んで「歌川の三羽烏」と呼ばれた花形絵師だった。歌川の大看板・豊国が亡くなったいま、誰が歌川を率...
ヨイ豊
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
元治2年(1865)、清太郎の師匠・三代豊国の法要が営まれる。広重、国芳と並んで「歌川の三羽烏」と呼ばれた花形絵師だった。歌川の大看板・豊国が亡くなったいま、誰が歌川を率いるのか。弔問客たちの関心はそのことに集中した。清太郎には八十八という弟弟子がいる。粗野で童のような男だが、才能にあふれている。己が三代に褒められたのは、生真面目さしか覚えがないのに。──時代のうねりに、絵師たちはどう抗ったのか!
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ジャポニズムの話をもう少し
2024/06/02 14:52
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
終盤、明治になって主人公四代目が卒中のため描けなくなり、浮世絵もどんどん時代遅れとなり、次第に息絶えてゆくような雰囲気となったところに登場する、フィナーレ的なエピローグがとても良い。
ジャポニズムの話がもう少し欲しかった。四代目が守ろうとした江戸文化 浮世絵が、ゴッホを始めとする印象派の画家たちにどれほどの影響を与えたのか、もう少し丁寧に書けば、努力が無駄でなかった との印象をもっと強調することができたような気がする。
読み応えあり
2018/12/28 12:40
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kkk - この投稿者のレビュー一覧を見る
出だしで少し躓く感じはありますが、中盤から終盤にかけての展開が素晴らしい。タイトルの意味がわかった時にまた新しい感動がこみ上げます。
忘れられた豊国
2024/12/25 15:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:森の爺さん - この投稿者のレビュー一覧を見る
江戸後期の浮世絵界を席巻したのは歌川派であり、歌川豊国は歌川派における大名跡であるが、有名ないのは初代と三代となった初代国貞であり、本書の主人公である四代は殆ど忘れられた存在といっても良い感がある。
私が四代目を知ったのは、一ノ関圭の書いた漫画「茶箱広重」の中で江戸末期の浮世絵界の大御所であった三代豊国死後の話として娘婿である二代国貞が後継者として役不足であり、病気のため「ヨイ豊」(ヨイヨイの豊国)と世間で呼ばれている話であり、著者はその四代目の発病後の呼称を題名としている。
四代目の履歴としては、最初に二代国政を名乗り、次に岳父の名跡を継いで二代国貞というサラブレットぶりなのだが、何しろ技量が岳父に遠く及ばない真面目が取り柄の人物であることは本人自身が自覚しており、むしろ弟弟子である破天荒な八十八こと後の豊原国周の方が技量では勝っている状況で、役不足の婿殿は幕末と明治という時代の荒波の中で、豊国一門の重鎮として生きていかねばならないという構図である。
大名跡である豊国の継承を巡る婿殿と八十八との辛辣なやり取り、躊躇っていた名跡を継がねばならなくなった理由等、役不足の婿殿の悪戦苦闘は三代豊国一門の話とは言え、幕末から明治という時代の流れに翻弄され、やがて衰退していく浮世絵界を物語っている印象も受ける。
名跡を継いだ後に病気に倒れ、利き腕が不自由になった婿殿(ヨイ豊)が何とか絵を描こうとする執念は鬼気迫る感がある。
ついでながら歌川派と現代日本画との関係については、本流である三代豊国では無く三代と仲の悪かった歌川国芳→月岡芳年→水野年方→鏑木清方→伊東深水の流れで継承されており、三代豊国の流れで無いことも歴史の皮肉とも言える
伝統の灯を絶やすな!
2021/06/03 10:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:のりちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
清太郎の江戸絵に対する思い。そして歌川一門を守らないとという情熱がほとほとと伝わってくる小説だった。
明治の世で見向きもされなかった浮世絵が逆に海外で評価されるという皮肉も描いている。