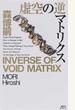露地温さんのレビュー一覧
投稿者:露地温
| 12 件中 1 件~ 12 件を表示 |
紙の本黄泉がえり
2003/01/21 02:34
黄泉がえり
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
梶尾真治の古くからの読者として、梶尾真治はリリカルで叙情的なSF短編の名手であり、その一方で残酷だったりばかげた笑いに満ちた短編も書く器用な作家という印象をもっている。そしてそのどちらの場合もSFらしいセンス・オブ・ワンダーに満ちた世界を繰り広げてくれる作家である。
話はタイトルの『黄泉がえり』通り、黄泉から死人が帰ってくる現象が、熊本地方で起こり、それによって巻き起こる出来事とその行方を描いた話だ。死者の甦りということで、ホラーという括られ方もしているようだが、純然たるSFである。前作の『OKAGE』も、不可解な子供の大量失踪が立て続けに起こり、「お陰参り」に例えて「OKAGE現象」呼ぶという話のためか、やはりホラーとかホラーファンタジーと呼ばれていた。別にジャンルを何にしたからといって面白いことには変わりはないのだが、少しばかりホラーめいた題材だとなんでもホラーと呼んでしまうホラーブームは気に入らない。そんな流行廃り、ジャンルの括りに関係なく面白い小説なのだから。
梶尾真治の二つの資質、叙情的な部分とブラックユーモアの要素とでは、前作の『OKAGE』が後者の要素が強くエンターテイメントに徹していたのと対照的に、『黄泉がえり』は前者の叙情的な要素が強い。死者が甦り、自分たちの元に返ってきたときに人々はどういう対応をするのだろうか。もちろんゾンビのような姿で甦れば別だが、生前の元気な姿で戻ってきたら。そんなバカなことはないと否定するかもしれないし、驚くだけかもしれない、パニックになるのか、あるいはすんなりと受け入れられるのかもしれない。この物語で死者がどう受け入れられていくかは読んでのお楽しみにしておくが、それが「あるいはそういうものかもしれない」と思わせるように描かれる。
甦った人たちとそれを迎える人たちの間に巻き起こる事件は、ユーモラスであり滑稽でちょっぴり悲しい。そしてそれは本人達には天地のひっくり返るような出来事であるが、ごく日常のちょっとした出来事のようにあくまで淡々と描かれている。悲しい出来事もその悲しさを大げさに盛り上げようとはしない。あくまで叙情的に静かにユーモアを交えながら悲しさを描く。だからこそ感動があり、そして人が人を想うということはどういうことなのか考えさせてくれる。
紙の本オーガスタの聖者たち
2003/04/01 01:21
人生とは何かを語るゴルフ小説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ロースクールに入学したチャールズ・ハンターは、他のロースクールの学生同様に夏休みに法律事務所で実習生として働くことになる。そこで与えられた仕事は、その事務所の共同経営者であり、アマチュア・ゴルフ界の偉大なゴルファーだった今は亡きボビー・ジョーンズの古い書類整理だった。古い書類整理から得られたのは、偉大なゴルファーの足跡ではなく、ありふれた法律資料の整理でしかないように最初は思えたが、その中から誰にも知られなかった一人の偉大なゴルファーの記録が見つかった。その幻のゴルファー、ボウレガード・ステッドマンが知られていなかったのは、彼がその才能を見せる前に殺人犯として追われたからだった。
物語はロースクールの学生チャーリーの回想として書かれる。チャーリーが古い書類整理でステッドマンという幻のゴルファーが殺人犯として追われたこと、彼を信じたボビー・ジョーンズとの友情、そしてその結果ステッドマンの記録に残されていない偉大なスコアの数々が明らかになってくる。
果たしてステッドマンは本当に殺人犯だったのか。ジョーンズはどうして彼を信じ助けたのか。ステッドマンは逃亡生活を続けながら、ゴルフを続け、一体どんなスコアを残したのか。そうしたことがだんだんに明らかになってくる。
殺人の話が出た時点でミステリ的な展開をするのかと思ったらそうではなく、むしろジョーンズとステッドマンの友情とゴルフ勝負の話が続く。語りが回想であるのと、語られる物語が古い書類の中に残された昔の出来事のため、派手な展開もなく抑えた文章で淡々と書かれているのだが、全然飽きさせることはない。
話の中心はいつしかゴルフの話になるのだが、ゴルフをしたこともなければ特に興味を持ったことのない者にも面白く読ませる。もちろん、ゴルフファンには堪えられない話なのではないかと思わせる部分も多々あり、きっと自分にはそういうエピソードの魅力は100%は判らないだろうと思って残念に思った。しかしゴルフを知らなくとも十分に面白い物語になっている。
書類箱が空になる頃には、偉大なゴルファーでありながら歴史の表舞台に経つことのなかった一人の男の人生が浮かび上がる。そして書類箱に埋もれてた過去の話から、主人公のいる現在に話の中心は移り、殺人事件の真相を巡って法廷ものミステリのような展開になり、最後に明らかになる真実はちょっとしたドラマである。ミステリ的な要素をもっているが、しかしやはりこれは「ゴルフ小説」だ。ゴルフに興味のない者までゴルフ好きにさせてしまうくらい面白い「ゴルフ小説」だ。
ゴルフ小説の中ではゴルフは人生なのである。だからゴルフを知らなくても面白いのかもしれない。
紙の本スーパー・カンヌ
2003/03/16 18:18
ビジネスの理想郷で暴かれる人間の本性
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
物語の舞台はスーパー・カンヌという実在の場所だが、最新のビジネス都市と化した近未来である。この時代では単なるビジネス都市ではない、ビジネスエリートにとっての理想郷となっている。理想的なのはここで働くビジネスマンたちには、オフィスにいるときに仕事に専念できる快適な環境が用意されていることによる。オフィスで働くことが最高に快適であり、高級住宅に帰るのも、シャワーを浴び、睡眠をとるためだけなのだ。そして、自主的な警備員達と至る所に設置されたカメラで監視されたこのビジネス都市では犯罪は起こらないはずだった。
この都市に「ぼく」が妻のジェインとともにやってくることから物語は始まる。ジェインは、スーパー・カンヌで足りなくなった医師の後任としてやってきたのだ。前任の医師は、この完璧なはずのビジネス都市で銃を乱射して何人もの人を殺していた。飛行機事故で足を痛めてた「ぼく」は昼間の退屈を紛らわすことが半分、前任の医師の謎めいた行動の理由、そして拭いきれないビジネスのユートピアに対する疑問などを抱えて、事件の真相を追うのだった。
ここで描かれる都市はどこか歪んでいる。カメラで監視された社会といえば『1984年』を思い出すが、監視され制限を受けるわけではない。表向きは本当に理想的な社会のようにも見えるのだ。しかし、何か違和感を感じながら主人公とともにこの世界を動き回るうちに、裏側の世界が顔をだす。それからが俄然面白くなってくる。
面白いのはミステリー的な謎を追う興味もあるけれど、むしろこのビジネス都市にある奇妙な論理に主人公が時には反発し、時には取り込まれていくことで、人間の心理を暴き出していくからだろうか。性悪説的な、人間には必ず暴力的な欲望があるかのような描写は、J.G.バラードの得意技といっていいだろう。ある程度否定できないものの必ずしもそうは思わないのだが、バラードの物語を読んでいるとまさにそれこそが人間の本質のように思えてくる。
訳者あとがきによれば、結末に対して「英米の読者は、そうくるか!と膝を叩いた人と、これはどういうことだ!と激怒した人に分かれ、その中間はあまりいなかったらしい」という。ぼくは前者であったが、膝を叩くということはなかった。バラードのもつある種諦めたような世界観からすると、この結末はなんとなく予想通りという気がしたのだ。しかし、この結末で終わることで読者は希望を持つことができるような気がする。何かが変わるかもしれないという希望を持つことが。
紙の本霊玉伝
2003/03/12 19:49
痛快無比の中国ファンタジー
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
バリー・ヒューガートによる中国幻想ファンタジーの第2作目。第1作『鳥姫伝』で活躍した李高(リーカオ)老師と弟子の十牛が再び活躍する。十牛は『鳥姫伝』では依頼人の立場だったが、『霊玉伝』では弟子となっていて、この物語を書き留めている。いわゆるワトソン役である。話自体は独立してるので、『霊玉伝』から読んでも一向に問題はないが、どうせなら『鳥姫伝』から読むことをお勧めする。
さて、どんな話かというと説明が難しい。あらすじを書こうとしても、話が入り組み過ぎていてあらすじにならないのである。もちろんあらすじを全部書いてしまうような無粋なことをするつもりはないのだが、話の発端だけ書いてもそのあとの話は全く想像がつかないので、紹介にはならないのではないかと思う。ちなみに、文庫裏表紙の紹介文はどうなっているのか見てみる。
「(前略)彼らのもとに哀国にある寺の管長が血相を変えて駆け込んできた。750年前に死んだはずの悪名高き暴君、笑君が復活して仲間の法師をありえない手口で惨殺したというのだが?! この怪事件の真相を探るため、笑君の墓へと向かった十牛たちは、そこである不思議な“玉”の存在にたどりつく(後略)」
まさにその通りの発端なのだが、この発端自体がそんな単純じゃない。いくつものエピソードの積み重ねが相互に絡み合いながら語られるのだ。李高老師の家での大騒ぎの宴会、そこで起こるちょっとした事故というか殺人。死人は大金と麻薬のテングタケを隠し持っていた。続いて安酒場でシビレタケによる刃傷沙汰のエピソード。その酒場で、文庫の紹介文にもあった、寺の管長が事件の依頼をしてくるのだが、それには司馬遷の手稿の贋作が絡んでいる。冒頭の数十ページですでにこの混乱具合だ。こういう風に、小さな事件が相互に絡み合って、話が進んでいるのか脱線しているのかよくわからないまま話は続いていく。
しかし一旦物語が動き出すと、ノンストップの痛快ストーリー。笑君復活の謎がゴールであることを忘れてひたすら突き進むことになる。事件を解決するために行った先々で別の事件が巻き起こり、その場の危機を乗り越えて、冒険冒険の連続だからだ。そうした大活劇のあとにくる結末では、不思議なことに、一見無関係に思えたいろんな話が繋がってしまうのだからものすごい。これはもう紹介文とか書いても面白さは伝わらないだろう。とにかく、痛快無比の冒険と伝説の融合した中国ファンタジーを堪能できるので騙されたとも思って読むべし。
紙の本陋巷に在り 8 冥の巻
2003/02/09 21:43
顔回を待つ冥界での試練
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
孔子の弟子顔回が活躍する伝奇歴史小説の第8巻である。子蓉という媚術を使う女呪術師との戦いがいよいよ終盤に差しかかる。当初、子蓉は何人もいる敵のうち一人で魅力的な脇役の一人程度に思っていて、これほど長い対決が続くとは思っていなかった。しかも対決が続くだけではなく、本巻での重要なシーンへ導く役目を果たしていて、『陋巷の在り』全体で実はかなり重要な人物であったと認識する。
前巻に引き続き、媚術に蝕まれたよ(女編に予)を救おうとする話であるが、タイトルに「冥の巻」とあることから想像がつくように、顔回は死者の国<冥界>へと降りていく。そこで描かれるのはスーパーヒーロー顔回ではない。神の前には微力な存在でしかない人間として描かれ、冥界に行くだけでも大変な苦労をする。神話などに冥界から死者を連れ帰る話はいくつかあるが、そこでも試練は描かれているとは思うがここでの描写はそれらと較ぶべくもない。あるいは、神話で簡潔に書かれた試練を、生者の行くべきではない世界に行くことがいかに想像を絶することであるかと描きこんでいるといってもよい。何しろ1冊丸々が冥界へ赴くエピソードに費やされているのである。
ここで酒見賢一のすごいところは、その描きこみの中で作者自身が顔を覗かせて語り出す部分があるのだが、そこでこれが作り話であると言い切ってしまうところである。その上で、<気>について語り、生死について語り、神話について語る。様々な中国の歴史について引き合いに出す。それらを元に、これは作り話だといいながら、話に厚みを持たせていく。おかげで読者は安心して物語の中に入り込んでいける。
最初に書いた、子蓉が重要な人物であったと認識したというのは、顔回がここで遭遇するある試練−−問答が非常に重要だと思われるからだ。孔子があまり語ることのなかったという仁や天命についての議論は、『陋巷に在り』における『カラマゾフの兄弟』の「大審問官」にもあたる重要な場面と思われる。その割に顔回の心は揺れ動かされるばかりではっきりした答えがあるわけではないのだが。次巻に持ち越される話の中で、その答えが出てくるのであろうか。
今更いうまでもないが、非常に良質な物語である。困ったことに、肝心な処で話は終わっていて、早く次の巻を読みたくなるのが欠点である。とはいえ、それは良質の物語である証拠なので欠点とはいえないのだが。
紙の本劫尽童女
2003/01/28 02:57
昔懐かしい少年マンガのノスタルジー
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タイトルや表紙の画からは想像がつかないが、超能力少女を主人公にしたアクションも交えたジャンル小説である。こういう典型的なジャンル小説というのは、恩田陸の小説としては珍しい部類だと思う。ファンタジー大賞でデビューし、ファンタジーからミステリやSFの狭間を縫ったような小説を発表し続けている恩田陸だが、その小説の形態はよく言えばジャンル小説の持つ型から逸脱し、悪く言えばまとまりの悪い作品が多い。そんな中で、『劫尽少女』は珍しくジャンル小説的な作品だと言える。
『劫尽少女』を読んでいて、まず思い浮かべたのは、近年映画化もされた往年のテレビドラマ『逃亡者』とかスティーヴン・キングの『ファイアスターター』である。その次に思い浮かべたのは大友克洋の『童夢』や『アキラ』。そして最後に思い浮かべたのは、石ノ森章太郎の『サイボーグ009』のような昔懐かしい少年漫画だった。もちろんそれにはそれぞれの理由がある。特殊な能力を持った少女が逃げるとシチュエーション、さらには超能力者の描写から、そして最後にはその物語の背景のどこか漫画的な設定の部分から連想したといえる。例えば、「ZOO」という秘密組織の存在や、主人公遙を助ける高橋シスターが「VOLUME2 化縁」のラスト近くで見せる印象的なシーン。それらには、B級映画のようなノリを感じたが、むしろ昔懐かしい少年マンガの世界が思い浮かべたのだ。
恩田陸はデビュー作『六番目の小夜子』をはじめとして、少年ドラマシリーズに対するオマージュのような作品が何作かある。それに対して、『劫尽童女』の、超能力を持つ少女がその力故に追われ、苦悩しつつ、しかし最後には追っ手と戦うという話は、昔懐かしい少年マンガに対するオマージュとは言えないだろうか。
珍しくジャンル小説的作品だというのは、主人公や主人公を囲む人物達がみな強いキャラクターを持っていて、キャラ小説という印象も強い。これもまた恩田陸作品では珍しいことではないだろうか。このキャラを配置すれば、続編をシリーズ作品化することも可能である。あくまでジャンル小説ではなくジャンル小説的といったのは、『劫尽童女』はジャンル小説として書いたなら最低でもこの倍の長さに膨らむ話だと思う。しかし、恩田陸はこの作品を単純にそういう風には書いていない。5つの章からなるが、それぞれの作品の間の時間は省略され、各章はむしろ連作短編といえるような独立性を持っている。これは季刊雑誌という刊行の間が長い雑誌に連載されたという理由もあるのだろうが、限りなくジャンル小説に近づきながらジャンル小説に終わらせない恩田陸独特のスタンスなのかもしれない。
結末は、昔懐かしい少年マンガが、ただ戦いのシーンだけでなく感動を持って終わったような、充足感を与えて終わる。たった一冊の小説なのに、何冊にもわたって書かれた物語のような充足感がある。これはまた新しい別の恩田陸作品の形という気がする。
紙の本青の炎
2002/12/25 01:13
ホラーの先にあるもの
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
文句なしに面白い作品である。だからその面白さについて敢えて書く必要はないと思う。代わりに、角川ホラー大賞でデビューした貴志祐介の作品だが、ホラーではなくてミステリにジャンル分けされていることについて書いてみたい。
考えてみれば、元々貴志祐介の作品にはミステリ的要素が強い。『十三番目の人格−ISOLA−』では多重人格の少女の十三番目の人格磯良を巡って謎解きのような展開をするし、『黒い家』ではやはり黒い家で何が起こっているかその犯人について次第に明らかになるような展開だし、『天使の囀り』では頻発する自殺事件の理由と天使の囀りが何なのかという謎が中心に据えられている(『クリムゾンの迷宮』は未読)。
そして逆に『青の炎』にしても、探偵が出てきて謎解きをするような典型的な推理小説ではなくて、主人公が完全犯罪を目論んで殺人を犯すが、完璧に思えた殺人のトリックがささいなことから破綻していくといういわゆる倒叙もののミステリになっている。突如主人公の少年の家庭に男がやってきて、それが結果的に少年が犯す殺人の動機になるのだが、そういう理不尽な脅威が訪れるというのはホラー的だ。
ホラーを非常に類型化していうならば、その脅威に対して逃げたり、恐怖におののくしか手がなくて、最後に武器を手に立ち上がり、最後に生き延びるという型があるかもしれない。その型に当てはめて考えてみるならば、『青い炎』では早くに武器を持ち、立ち上がる。そして一度は勝利を得る、いや勝利を得たかのように見える。だが勝利したかのように見えて、心理的にも、また別の脅威が現れるという点でも、決して勝利を得ることはできていなかった。主人公は、結局はうまく逃げようと立ち回っていくことになり、これは思えば典型的なホラーの物語構造になっている。
典型的なホラーがモンスターのような理不尽な存在との対決だとするならば、そのモンスターを倒すことで主人公は正義の側にいることができる。しかし、貴志祐介のホラー作品では『十三番目の人格』が多少超常的な現象を含んでいるとはいえ、どの作品も主人公を襲う恐怖の存在は単純な敵としてのモンスターでもなければ、存在自体が理不尽な<なにか>だったりすることは少ない。
『青の炎』では、殺人に至る緻密な計画などが細部にわたって描写されることで、ミステリといわれるのかもしれないが、『青い炎』はこれまでの貴志作品のホラーの延長に在る物語で、そして貴志作品のホラーの延長として必ず突き当たるのが当然の物語だと思える。別にジャンル分けにこだわる訳ではないのだが、ホラーからミステリに鞍替えしたのではなくて、貴志作品の目指しているものの先にある当然の結果だなという気がしたので、書いてみた。未読の『クリムゾンの迷宮』を読むともしかしたら、その間がさらに明確に見えるのかもしれない。
それにしても、『青い炎』に辿り着いてしまった貴志祐介は、次に何を書くのだろうか。結構気になる。
紙の本切り裂きジャック
2003/03/24 03:06
切り裂きジャック伝、あるいは検事側の証言
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『検屍官』シリーズのP・コーンウェルが、「切り裂きジャック」の正体を明らかにするノンフィクションである。気になるのは、ずっと犯人が判らなかった殺人鬼の正体を、なぜ今この時期に判ったのか、本当に真犯人なのかという点である。
結論から言えば、コーンウェルは真犯人を突き止めたと言っていいと思う。被害者たちがどういう生活をしていて、どのように殺されたのか、とても100年以上前のこととは思えないほど詳しく書かれている。特にコーンウェルの得意とする検死結果の分析は詳しく、この時代に十分な検死が行われなかったにも関わらず、その限られた情報の中から多くのものを引き出している。そして資料だけではなく、切り裂きジャックの残した手紙などをDNA鑑定にかけるなど、科学的捜査も行っている。
これらの調査は、切り裂きジャックに対する興味本位の推理・推測ではなく、むしろ今まで現代の科学捜査のメスが入らなかった100年以上前の事件に対する再調査であり、検証といっていい。資料の再調査に加え、現代の科学捜査による裏付けを行って出た結果からは、この真犯人を今ならば検挙し裁判に持ち込めるだけの信憑性はありそうだ。
しかし決定的な証拠として欠けることに、コーンウェルの名指す真犯人のDNAが残っていないのである。切り裂きジャックの出した手紙から採取したDNAはあるのだが、真犯人と目される人物のDNAの方が手に入らないのだ。そうなると、限りなく状況証拠は揃っているが、それが真実と言い切ることができない。被疑者はおろか、当時調査をした警官、医師、証人の一人も残っていない。切り裂きジャックの真犯人が誰だか判ったとしても、裁くこともできない。誰にも真実はわからないのだ。
コーンウェルは、そんな事件の犯人をなぜ7億円以上もかけて追求しようとしたのだろうか。それは切り裂きジャックの犯罪が、現代の猟奇的な犯罪と同じ問題を呈してるからだと思う。切り裂きジャックは、コーンウェルの書くきわめて現代的な猟奇殺人と似たような事件を起こしているのだ。警察をあざ笑いながら残酷な犯行を重ねた犯人がその罪を逃れることを許すわけにはいかない。たとえそれが100年前の事件であり、既に死者となり、罪を償わせることはできなくとも、せめて真実を明らかにすることが必要だと考えたのだろう。
『切り裂きジャック』を読み始める前には、きっといくつものデータを積み上げて犯人を徐々に絞っていき、犯人が浮き彫りになっていくような構成なのではないかと予想していた。しかし、実際には最初の章で犯人が明らかにされてしまう。そのあっけなさには気が抜けてしまったほどだ。100年前の事件を再調査していく経過をサスペンスタッチで描いて、意外な真犯人を提示する読み物にすることもできたはずだが、コーンウェルはそういう書き方をしなかったのだ。
逆に犯人の素顔を描写しながら、切り裂きジャックが殺した人たちの周辺を含めて詳しく描写し、犯人がなぜそういう行為をとったのかという検証を重ねていく。まるで「切り裂きジャック伝」のような趣だ。あるいは別の見方をするならば、検事が様々な証拠を重ねて陪審員たちに犯人の行為を問うかのような描写といってもいい。むしろこの方が近いかもしれない。『切り裂きジャック』をこういう書き方で書いたということにも、なんとしても真相を明らかにしたいというコーンウェルの気持ちが現れているように思う。
切り裂きジャックは、今では伝説化されミステリアスな存在、アンチヒーロー的な存在になっているように思う。コーンウェルはそれを憎むべき猟奇殺人犯として白日の下に晒そうとした。しかし死者は裁けない。静かに逃げ延びた犯人の姿が描かれているような本書の最終章には虚しさを感じざるをえなかった。
2003/01/31 02:48
森博嗣らしさを堪能できる一冊。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
森博嗣の短編集の一冊。森博嗣の作品は、長編小説よりも短編小説の方が、森博嗣らしさがはっきりと判る。この短編集も同じで、特に最初に収められた「トロイの木馬」はいかにも森博嗣らしい作品だと思う。
「トロイの木馬」は、バーチャルリアリティが当たり前になり、会社勤めもデートもバーチャルな世界で行い、実際に会うことが少なくなっている未来が舞台である。そこである種のコミュニケーション手段を提供しているサーバがハッキングされる。手段はいわゆる「トロイの木馬」がきっかけになっていて、主人公がだんだんに真相に近づいていき、そして当然のことながら意外な結末が待っている。だが森博嗣らしい面白さは、そのメインのストーリーよりも、この物語の背景になっている未来社会での架空のシステムの描写にある。そのシステムについて書かれていることは、コンピュータハッキングあるいは現在のメールサーバなどの知識のある人には想像がつくけれど、それ以外の人にはたぶんちんぷんかんぷんな話だと思うのだが、それを「当たり前のように」書いているのだ。「トロイの木馬」については、コンピュータシステムについての知識があるかどうかで、楽しめる割合が全然違ってしまうのである。そういう意味では、これほど読者にとってハードルの高い小説というのも珍しいと思う。そして、そういうストライクゾーンが狭い特殊な小説を書いてしまうあたりが、いかにも森博嗣らしいと感じてしまう。
他に6作収められているが、いずれもミステリらしい起承転結がある。日常の不思議な出来事、ハードボイルド探偵もの、ダイイングメッセージ、誘拐の身代金の受け取りトリック、といったような話がそれだ。しかし、ほとんどの話にはそういうメインストーリーと別にもう一つ趣向が凝らしてある。回文がたくさんでてきて回文だけでも楽しめるような話やら、幽霊譚になっているものなど。そして極めつけは、最後に収められた「いつ入れ替わった?」で、犀川&萌絵シリーズ長編版で結論の出ていなくて気になる二人のその後が、少しばかり垣間見られることだろうか。
そんなわけで、この一冊も森博嗣らしさを堪能できる一冊である。
2003/01/07 01:24
いい意味で期待を裏切ってくれる面白さ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
西尾維新については比較的評判がいいという印象があったので少しばかり期待を持ちながら読み始めた。しかし読み始めて思ったのは「あまり期待しない方がいいんじゃないか」ということだった。それはどういうことかといえば数え切れないほどいろいろとある。語り部「ぼく」は戯れ言ばかりいっていると自嘲する、そのキャラクターしかり。一緒にいる天才技術屋玖渚友(くなぎさ とも)と共に孤島「烏の濡れ羽島」へと招かれるというシチュエーションと、その島の名前。そこには他に四人の天才達が島の主人赤神イリアによって招かれていたという、さらなる非現実なシチュエーションと登場人物達の名前、などなど。
孤島に赤神イリアとそのメイド達、五人の天才とその付き添い二名(うち一人は「ぼく」)の十二人が集まった。となれば連続殺人の始まりが予感される。新本格に相応しい舞台でこれはこれでいいのだが、天才が集まるとか、その天才達の背景などがマンガチックで近未来的で、物語にしても嘘っぽい嘘に固められすぎているのが、期待しない方がいいんじゃないかという予感を感じさせたのだ。
そして第一の殺人が起こると、そこで提示されるのは謎にもならない謎で、嫌な予感が的中という感じがした。戯れ言を言っているのは「ぼく」だけじゃない、この物語自体が戯れ言じゃないかと思ったわけだが、それが最初の罠だったというのが読後の感想になる。結論から言ってしまうと面白かった。まんまと作者の術中にはまったという感じだ。最初のトリックも次のトリックも簡単に判ってしまう謎にもならないトリックなのだが、そんな単純な謎の先には裏があってその裏にも裏があってと、いい意味で最後まで期待を裏切ってくれる。
もうひとつ面白いのは、第一作ということで登場人物の役割が読者にはっきりしないのをいいことに、最初は戯言遣いの「ぼく」がワトソン役で天才技術屋玖渚友が名探偵かと思わせて、途中から名探偵が最後に出てくるような話を匂わせる(実際登場人物一覧には「人類最強の請負人 哀川潤」の名前が挙げられている)。こちらも予想を裏切る役割分担になっている。
単純なトリックも罠、「ぼく」が戯れ言をいってるのも罠、うまいこと作者の張り巡らした蜘蛛の巣に絡まったようで楽しく読めた。
2002/11/05 01:31
4巻は重たい結末、そしてこれからの序章。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ハリー・ポッターシリーズ第4弾。ハリーは14歳、ホグワーツの4年生になる。冒頭、今まではマグルである叔父の家でのドタバタ騒動から話が始まったが、ホラータッチの空き家の怪事件から物語がスタートする。ヴォルデモート復活の気配が見え隠れして、今までよりよりハリー対ヴォルデモートの対決がメインになりそうな雰囲気である。そして、いつも通りのどたばた騒動に戻るのだが、ここでもちょっと違うのはホグワーツに戻る前に、クィディッチのワールドカップ観戦というエピソードが入るところ。サッカーのワールドカップの尋常でない騒ぎ方が嫌いだったので、小説でまでワールドカップかというのはちょっとうんざりする。それに加えて、ファンタジーにしては現実的すぎてちょっとガッカリする。元々ハリー・ポッターの世界はそんな感じなのでいまさら言うことでもないのだが。
以降、ホグワーツに行ってからの学生生活はいつもと同じように話が進む。闇の魔術の防衛術の先生が新たにやってくるのもいつも通りだし、ハリーたちの日常がつづられる中で小さな事件がポツポツと起こり、それらがすべてジグソーパズルのピースのように最後にパチッと収まる辺りはいつもと同じだ。ちょっと違うのはクィディッチの試合に代わるイベントがあることと、ハリーたちが恋に目覚めるくらいか。
ハリー・ポッターシリーズはそんなに大きな広がりはなくて、ジグソーパズルに例えたみたいに、一つの枠の中にきっちりとピースが埋まっていくように、謎や伏線が綺麗に枠に収まっていく感じがあって、そこがとても好きである。1作目から3作目にかけて、1作目のちょっとしたエピソードが2作目、3作目で繋がっていくということに感心していて、あとになればなるほど、どんどん面白くなってきたと思ってきた。しかし、そういう点からすると、4作目はそれほどでもなかった。闇の魔術の防衛術の先生が毎回変わるあたりとか、ある程度パターン化してきているというのもあるかもしれない。それと、結末がある意味中途半端な感じがするのかもしれない。次作に続く序章で終わっている感じで、終わりであるけれどこれからの物語の始まりでもある。
ハリー・ポッターシリーズは、僕はファンタジーというよりむしろ学園ミステリだと思っている。そしてすべてが丸く収まるとってもハッピーエンドの物語であるとも。どうも4作目以降は、とってもハッピーエンドという点ではちょっと違う物語になっていく感じがする。というか、4作目の終わりを読むと次作以降に悲劇の予感を感じてしまう。1作目、2作目のハッピーエンドはごく普通なのだが、3作目の終わりはもうほとんど諦めていたことをハッピーエンドに持ち込む仕掛けがあって、あくまでハッピーエンドに持ち込むところにファンタジーを感じていた。そこからすると、4作目でも悲劇を残さずに最後までハッピーにまとめるべきだったんじゃないかと思っている。甘ちゃんといわれようが、その脳天気なまでなハッピーエンドが好きなのかもしれない。しかし4作目をそうしなかったし、4作目はあくまで序章という感じがする。となると、5作目以降はあんまり楽しく読めないんじゃないかという心配がある。あくまで推測なんだけれど。
あと翻訳で、フランス語なまりなのか、「わたーしのおばーさまのものでーす」とかそういう紋切り型な訳はちょっと鼻についた。
紙の本グレイヴディッガー
2003/03/24 02:41
スピーディな展開で読ませるが、リアリティが欲しい
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
プロローグで、「第三種永久死体」という死んだときのままほぼ完全に保存された状態の死体が発見され、さらにその死体が盗まれるという事件が描かれる。そしてその謎は宙ぶらりんのまま本編は始まる。
主人公は小悪党の八神俊彦。なぜか仏心を起こして骨髄ドナーに登録し、折しもその骨髄移植のために病院に行こうというその前日のことだった。他人に貸していた自分の部屋に戻ると、その男は死体となっていた。しかも単純な殺しではなく、煮立った風呂の中に死体は浸かっていたのだ。
一体何が起こったのかと訝しむ八神の元に謎の男達が現れ、突然襲いかかってくる。なんとか男達から逃げ出した八神は、病院へと向かうのだった。八神が明日までに病院に辿り着かなければ、彼の骨髄を待つ患者は死ぬことになるのだ。一方、死体が見つかったことにより警察もまた八神を重要参考人として手配していた。そしてそれだけでなく、警察は同じような奇妙な変死体を続けて発見していた。どうやら謎の変死体は、甦った死者−−グレイヴディッガーが異端審問官を皆殺しにしたという伝説と同じ殺し方で殺されているようだ。
次々と起こるグレイヴディッガーによる殺人事件の謎は? そして、警察と謎の男達から追われる八神は無事に病院にたどり着くことができるのか?
といった話。グレイヴディッガーの謎は冒頭の死体消失とも話が繋がり、刑事警察と公安警察の捜査で謎を解いていく一方で、八神のスピーディな逃亡劇が繰り広げられる。八神の逃亡劇は次から次へと展開が速いのはいいのだが、かなりご都合主義的な展開が多く、荒唐無稽な感じがしてしまう。地道な警察の捜査によって真相が見えてくるところは面白いのだが、八神の話と警察の話が繋がり、犯人が見えてくる辺りでは、どうも事件の真相解明が消化不足という感じだ。特に最初の死体消失、グレイヴディッガーの必然性などが断然物足りない。
終盤、山場が何度かあるのだが、いずれも荒唐無稽かご都合主義といった感じで、スピーディな点だけは認めるが、正直いってがっかりした。漫画だったら面白く読んだのかもしれないけれど、もう少しリアリティが欲しいところだ。
| 12 件中 1 件~ 12 件を表示 |