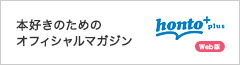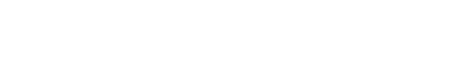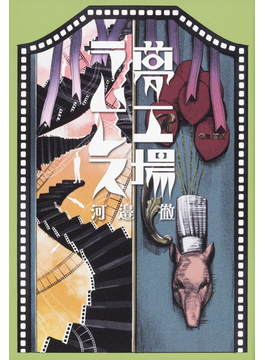第2話
- その4
- その3
- その2
- その1
【夏の思い出と洋介とLOOP】
次の日の朝、俺は土曜日にもかかわらず早く目が覚めてしまった。受験生になってから、学校のない土日でも早起きする習慣が体に染み付いていた。
朝起きても、心が少し興奮しているようだった。昨日の船の上から観た流星の景色が、まだ目の裏に焼き付いて離れない。宮島の上空を流れゆく箒星。洋介の喜ぶ顔も、真希の感動する顔も、おじさんの驚いた表情も、まだすぐそこにあるみたいだった。人類はすごい奇跡を起こしたものだ。
起き上がってリビングまでやって来ると、那月が朝食を食べながらテレビを観ていた。彼女が休日に起きてくるなんて珍しい。どこかに出掛けるのだろうか。
「どっか行くん?」
俺はとりあえず尋ねてみた。
「……寝ぼけてんの?」
容赦のない返し。予想外の返答に、俺は普通の会話さえできなくなってしまったのかと焦りを覚える。よく見ると、彼女は制服を着ているようだ。学校に行くのだろうか。
『今夜は人工流星が流れます。幸運なことに天気もよく、壮麗な流星が見えることが予想されます──』
テレビからは、どこかで聞いたニュースが放送されている。目をやると、昨日と同じアナウンサーが同じことを言っている。
「何これ、録画?」
「は? 録画したニュースを朝から流すアホがおるん?」
辛辣という言葉がぴったりなことを那月は言った。
父さんと母さんはどこかに出掛けたのだろうか? 机の上にはハムのサラダとスクランブルエッグが載っている。俺はとりあえずトースターに食パンを入れて、タイマーをグリっと回す。同じ時間に設定したつもりでも、なぜか食パンは焦げる時と焦げない時があるから注意しなければならない。
ギギ、と椅子を引く音がしたのでリビングを見ると、妹が立ち上がってカバンを肩に担いでいる。
「じゃ、行ってきます」
昨日と同じように、那月は俺から逃げるようにして家を出ていった。
おかしい。見覚えのあることばかりが起きている。テレビでは、昨日観たのと同じレストランが紹介されている。真っ白なクロスも、火の点いていないキャンドルも見覚えがあった。それから画面はスタジオに戻った。
『花金の選択肢として、皆さんも世界初の人工流星を観るために、大切な人と夜空を見上げてみてはいかがでしょうか?』
「……花金?」
その瞬間、俺は背筋がゾクッとした。
今日は土曜日のはずだ。昨日学校の後、みんなで人工流星を観に行ったのだから。
おかしい。夢でも見ているのだろうか。
夢かどうか確かめるため、自分の頰をつまんでみた。こんな漫画みたいなこと、生まれて初めてした気がする。
痛みは感じる。ここは夢ではない。もしかして、昨日の出来事が全て夢だったのだろうか。
今日が本当に金曜日なら、学校に行かなければならない。俺は戸惑いながらも、昨日と同じ朝食を食べて、いつものように学校に向かうことにした。
俺は夢の中にでもいるような違和感に包まれていた。一時間目は英語の授業だ。先生は昨日と同じところを教えている。さすがに昨日の今日なら、授業の内容も覚えているものだ。ある一つの物語を読み込み、その中に出てくる文法の用法を学ぶ。
「このwouldの意味は、ここでは仮定の意味を表していますねー」と、先生が抑揚のない声で、今日も淡々と授業を進めている。
周りを見渡してみるが、クラスには誰も俺のように戸惑った顔をしているやつはいない。誰か俺と同じように、一日丸々という強烈な既視感に包まれているやつはいないのだろうか。見る限りでは、みんないつもと何も変わらない様子で過ごしているようだった。
時間通りにチャイムが鳴って、昨日と同じ一時間目が終了した。
そして、もし本当に時間が繰り返しているのであれば……。
「りょう、りょう!」
廊下側の窓のところに立っていたのは、予想通り洋介だった。彼はまたズカズカと教室に入って来た。
「今日だよ今日、人工流星。どこに観に行こうか? 広島駅のビルのとことかよく見えるらしいな。今日も朝、テレビでやってた」
洋介は聞いたことのあるセリフを言いながら、腕を組んでいる。
「……なんじゃ、体調悪いんか?」
俺の表情があまりにも変だったからか、洋介は昨日と違うことを言った。
「いや……大丈夫」
「それならええんじゃけど。今夜行こうな。……推薦の合格通知きたんじゃろ?」
こいつ、またこんな姑息な真似を。
「いや……うん」
少し迷ったが、今日は素直に答えてみた。
「じゃあせっかくじゃけぇ、今日天文部に報告したらどうじゃ? 場所については、もう一回山波先生と連絡とって……」
「待て、洋介。ちょっと相談がある」
俺は洋介の話を遮った。
「……何じゃ改まって?」
「おかしいのは俺の頭かこの世界か……」
「……?」
何と説明すればいいのかわからず頭を抱えた。しかしこの場合は、はっきりと事実を伝えた方がいい。
「洋介、俺の時間がループしとる」
「……は?」
涼しげだった顔は、半分笑っているようで、半分呆気にとられているような顔になった。もう出会って三年目になるが、初めて見た表情だった。
「……いや、何言っとるんじゃ」
「今日が全部昨日と同じなんじゃ。同じ日が繰り返されとる。おかしいじゃろ?」
「おかしいのはお前の頭じゃ。そんなこと言われても信じるわけないじゃろ」
洋介の反応は正しい。簡単に信じてもらえるようなことではないだろう。わかっていながらも、伝わらない歯がゆさが胸に湧き上がってくる。
「でも、全部見たことあることばっかりなんじゃ」
「ほいじゃ、なんか証拠とかはないんか? 昨日見たもんとか」
「証拠……」
俺はしばらく考えてから、昨日あったことを思い出していた。何か今日が繰り返していることの証拠となるものはないか。
「そうじゃ……非常ベルが鳴る……」
「非常ベル?」
「そうじゃ! 誤作動じゃったらしいんじゃけど、もうすぐ鳴るはず……」
ジリリリリ!
けたたましい音が鳴り響いた。洋介が意味もなく天井を見上げる。それから、俺の方を見て信じられないという顔をする。
「そしたらこの後、体育の竹中が話し出して……ちょっとキレ気味で、誤作動って放送するはず」
すぐにベルは鳴り止み、校舎全体に放送が流れた。
『ただいまの非常ベルは誤作動です。災害等は起こっていません。繰り返します、ただいまの非常ベルは誤作動です……』
昨日と同じ、ちょっとキレ気味の声が響いた。
「……ほんまにループしとるんか?」
俺はこくりと頷いた。
「相談聞いてくれるか?」
「……もちろんじゃ」
どうやら洋介は信じてくれたようだ。どこか少し嬉しそうに見えるところが気になるが。
誰かにこんな話をしているところを聞かれたら、俺は確実に頭のおかしいやつだと思われてしまう。俺たちは放課後、誰もいなくなった教室で会って話をしていた。
「これまで、昨日と全く同じことが起こっとるってことか?」
「そうじゃ。朝やってたニュースの内容も、授業も全部昨日受けたのとまったく同じじゃった。俺もまだ夢見とるみたいで現実感ないんじゃけど……」
俺は自分で言いながら、本当におかしなことを言っている自覚はあった。
「ってことは、りょうは昨日、もう人工流星を観たんか?」
「うん。俺と洋介と真希の三人で観に行った」
「おおーじゃあ、今日もう一回観られるってことかぁ。なんて羨ましいやつじゃ」
洋介が吞気に言った。窓の外から野球部のランニングの声が聞こえてきた。部活が始まったようだ。
「それどころじゃない! こんなんおかしいじゃろ。一体俺に何が起きとるんじゃ!」
俺は説明しながら、半ばパニックになっていた。昨日のことを思い出せば思い出すほど、不可解な現象が起きていることがわかる。
「……ちょっと待て、そうじゃな。俺は一つ仮説を立てた」
洋介が何かを思い付いたようだった。俺は藁にもすがる思いで、洋介の言葉に集中した。
「どんなんじゃ?」
「ほら、俺ら去年の夏に発表したじゃろ。長野まで行ったやつ」
「天文部の活動発表会か?」
「そう。そこで話した神話の物語でもあったじゃろ。天体と時間の流れは、昔から密接に関わっとるもんじゃって。やけぇ、人工的な流星なんてものを人間が作ったから、本来の時間の流れが狂ってしまった可能性は考えられんか?」
「そんな、たかが人間が作ったもんで……」
その時ふと、以前詩織が言っていたことを思い出した。
──でも宇宙さん側から見ると、人工的とか気にしてないと思うよ。
「確かに……人間が作った流星が時間を狂わせるか……」
そう言ってから、俺は首を横に振った。
「いや、やっぱり、神話を真に受けたらいけんじゃろ」
「俺だってまだ半信半疑じゃ。でもりょうの中で時間がループしとるなんて、もう神話レベルの現象じゃ。神話みたいなことが起こっとるなら、神話みたいな話でも信じんといけんじゃろ」
「……確かに」
洋介の言うことはぶっ飛んでいるが、このおかしな状況を考えると、その可能性も捨てきれない気がしてくる。
「りょうはその人工流星を昨日既に観たんじゃろ? なんかその時違和感はなかったか?」
「違和感……。わからんわ。普通に感動しとった」
ふむ、と洋介は眉間にシワを寄せてさらに考え込んだ。真面目に俺の力になろうとしてくれていることが伝わってくる。静かな教室に、イーチ、ニー、サーンという準備運動の伸びやかな声が外から響いてきた。
「幸運の星の下に生まれたとかいう言葉もあるじゃろ? 生き物はそれぞれ自分に対応した星があるって説じゃ。そう考えると、ほんまに人工流星に何らかの影響力があって、ただ一人りょうにだけ変な影響を及ぼしたとしても、おかしいことじゃないかもな……」
「そうじゃなぁ……」
なんとなく考えられる原因はわかってきた。それに、昨日あった特別なことと言えば、やはり人工流星しか思い当たらない。
「でも、俺はどうすればええんじゃ」
ループするなんて、もうファンタジー小説の世界だ。魔法の鍵や、失われた時の歯車でも見つけ出さなければいけないのだろうか。
「多分な、りょうのループは人工流星をなんとかせんと永遠に繰り返されると思う。そういえば神様からそういう罰を受ける神話も、調べた資料の中にあったな……。永遠に同じ時の回廊を歩かされ続ける。周りは何も変わらない同じ日が繰り返され、一人だけ年老いて死んでいく」
「……」
俺は真剣に想像してみた。俺だけが気がつけば年寄りになっていて、みんなは変わらず同じ毎日を過ごしている。かなり怖い。二日目にしてもう恐怖のどん底だ。洋介は少し遠い目を俺に向けている。
「お前も災難じゃな……」
「他人事みたいに言うな。変なことを言うからぶち気味が悪いんじゃ! だいたい、俺は何も罰を受けるような悪いことはしとらん」
俺は大きな声で抗議した。洋介に抗議しても仕方ないのだが。
「……まぁ、別に明日が来ないと困るってこともないんじゃないか?」
「困るわ。明日は……詩織の誕生日じゃな」
「あ……そうじゃったか」
洋介は気まずそうに言った。
そうなのだ。永遠に今日が続くのであれば、詩織の誕生日が来ることはない。俺は明日、広島の大学に行くことを、ずっとそばにいることを、ちゃんと彼女に伝えようと思っていた。そう、昨日人工流星を観て決意したのだ。
「……りょう、さっき夢見とるみたいって言ってたよな? それなら、夢じゃ思ってちょっと試してみんか?」
「何を?」
「人工流星を止めるんじゃ」
あまりに突拍子もないことを言うので、俺は一瞬無言になった。外からカキン、と小気味いい金属バットの音が聞こえた。バッティングの練習をしているのだろうか。
「洋介……それはあまりに現実的じゃなさ過ぎる」
「そうでもせんと、りょうは永遠に同じ今日を生きることになるんじゃろ?」
「そうかもしれんけど……じゃあまず、どうやって止めるんじゃ?」
「そんなもん、電話して頼んだらええじゃろ。今日流れ星を流すのはやめてくださいって」
「絶対そんなんじゃ止まらん」
俺は呆れて、ため息をつきながら背もたれにもたれかかった。木の椅子がキイ、と鳴き声みたいな音を立てた。
「じゃあの、言う通りにせんと爆弾を爆発させるって言ったらどうじゃ? 絶対止まるじゃろな」
俺は洋介の内なる猟奇的な部分を発見し、逆に戸惑っていた。
「そんなことしてみろ、完全に犯罪者じゃ。仮に明日が来たとしても、刑務所で迎えることになるじゃろな」
「ダメか?」
意外と真剣な顔で聞くので、どこまで本気なのかわからなくなる。
「そりゃそうじゃ! ってかお前、昨日ぶち嬉しそうに写真撮りまくっとったぞ。流星を見上げてた他の人も歓声上げとった。そんなみんなが楽しみにしとるもんを止めるのは、絶対いけんじゃろ」
「そうかぁ……」
どこか残念そうである。
「それなら、りょうが人工流星の力が働かんところまで逃げるってのはどうじゃ?」
「……どういうことじゃ?」
「これも去年の発表で言うとったことじゃろ。北半球と南半球では見える星座やその位置が違うって。北極星は南半球ではそもそも見えんしな。じゃけぇ、星がそこで暮らす人に与える影響も違う。もちろん星占いも」
「今から飛行機乗って南半球に行くんか? 大事じゃの」
「いや、先生も言っとったが、流星は星って名前が付いとるけど、大気圏での現象じゃ。人工流星が観測できるのは、たかが直径200キロ程度の範囲じゃろ? そこから離れれば、きっとりょうはループから抜け出せるはずじゃ。雨に濡れたくなければ、雨の降っとらん地域まで逃げるみたいなもんじゃな」
直径200キロ。どこが円の中心かわからないが、方向によってはここから80キロも離れれば、人工流星の影響は受けずに済むかもしれない。南半球まで行くことに比べると、意外と現実的である。
窓の外から、イコーゼー、と大きな野球部の掛け声が聞こえた。
──去年 夏
ジュニアセッションは、その夏、俺にとって最も大きなイベントだった。他校の生徒の前での発表が終わり、その後俺たちは近くのペンションに宿泊することが決まっていた。スターペンションと呼ばれる、長野県と山梨県の境にあるその宿泊施設は、星好きのお兄さんが経営していて、夜はみんなで天体観測をしたり、お兄さんから星の解説を聞いたりすることができる。
ペンションに着くと、みんなで暖炉のある一階の広いスペースに集まって、施設の説明を受けた。二階にベッドのある部屋があり、それぞれグループごとに分かれて宿泊する。
「みなさん運がいいですね。夏場は雨の日が多いんですが、今日は星がよく見えそうですよ」
ペンションのお兄さんは山波先生の教え子らしかった。
この辺りは星が綺麗に見えることで知られているので、このペンションに星を観に来る一般の利用客も多いようだ。世の中に天体好きはたくさんいる。その絆も強い。お兄さんと山波先生は、仲良さそうに話し合っていた。
ペンションの庭に設置されている、高さ三メートルもあるドームの中には、四十センチの大口径望遠鏡がある。順番に中に入らせてもらい、ベガ、アルタイル、デネブの夏の大三角形を観測させてもらった。こんなに大きな望遠鏡で星を観るのは初めてだったので、それだけで特別な時間になった。
狭い場所でみんなで集まっても、暑いとは思わなかった。ここ最近の蒸し暑い夜のことを思うと、神様からの贈り物のように涼しい夜だった。昼間の柔らかい太陽の温もりがまだ土に残っていて、それが足の裏から伝わってくる心地がする。俺たちの声で目を覚ましたのか、遠くで一匹、蟬が鳴き始めた。なんだか自然と仲良くなれている気がした。
詩織も隣でしきりに楽しそうにしている。好きな人と一緒にこんなところに来れたことが、一番の神様からの贈り物かもしれないと思った。
お兄さんからの説明が終わった後、俺は一人でペンションを出て、広い庭の端にあるベンチに座っていた。ペンションから少し離れると、一帯は本当に真っ暗だった。街明かりに邪魔されないので、星が都会よりもずっと明るく見える。
俺は覚えた夏の星座を指でなぞった。星や星座の名前を知ると、夜空を見上げるのがさらに楽しくなる。あれが射手座、あれがさそり座、あれが天秤座。夏の星座は、比較的形がわかりやすい。天秤座の形をなぞっていると、この前詩織に、心はシーソーという話をしたことを思い出した。詩織は笑って、そんな暗い考え方やめてよと言っていた。
「何しとるん?」
突然本物の詩織が横から現れて、俺は思わずビクッとした。詩織はいつも足音を立てずに歩く。髪が少し濡れているのは、風呂に入ったからだろう。
「びっくりした。一人でゆっくりしとるだけじゃ。詩織は?」
「……なんか部屋におるのが勿体ないと思って」
詩織は長袖のパーカーを着ている。俺も長袖のTシャツを着ていたが、ずっと座っているとそれでも少し肌寒く感じる。
「高校の屋上から見た星空もぶち綺麗じゃったけど、ここはもっと綺麗じゃねぇ」
詩織は俺の隣に座って、星空を見上げた。
「発表に向けていっぱい調べたけぇ、なんか賢くなった気がするね」
俺たちは様々な資料を読み込んで、かなりの量の星の知識を詰め込んだ。
「私あの話、昔から好きじゃった。亡くなった人はみんな星になるって話」
「ああ、世界中、いろんな地域でそういう考え方があったみたいじゃな」
詩織は確か、出会った頃にもそんなことを言っていた気がする。
国や地域によって様々な星の言い伝えがあるが、その中でも、祖先が星になって見守っているというのは、世界中で聞かれる伝承だった。
「まだ交流のなかった世界の国々でそういう考え方があったってことは、人間が本能的に知っとることなのかなって思うの。誰かが亡くなったその夜に、あの天の川の中に、一つ星が増える。星になって、大切な人をいつでも見守ってる。素敵じゃない?」
「ロマンチックじゃな」
本当はガスが燃えて、光っているわけだけれど。立派な電波天文台を見学した後に申し訳ないが、そんな現実は、この美しい星空の前には何の意味も持たない。
「私思うんよ。みんなが一緒に星空を見上げることができたら、ほんまに世界が平和になるじゃろって。私たちが感じとる悲しみなんて、ちっぽけなもんじゃ」
詩織は、心からそうだと信じているような顔で言った。
「それなら喜びだってちっぽけなもんじゃない?」
「もう、また子どもみたいなこと言わないの」
彼女はまたお姉さんぶった口調で俺を叱った。ふっと微笑んで、続ける。
「星空を見とるとね、私一人が抱えてる小さな悲しみなんて忘れて、誰かと一緒にいる喜びを大切にできる気がする」
不意に、ベンチの上の俺の手に、詩織は手を重ねた。冷たい手をしていた。
「冷たいで。寒くない?」
「寒くないよ。私ね……」
詩織は何かを言いよどんでいるようだった。小さく首を振って、それからまた話し出した。
「……例えば、私はあんまり運動はできないけど、そうじゃなかったらりょうと仲良くなってなかったって思うと、これも別にいいかなって思うの。神様はそんな風に、上手くバランスをとってくれとるんじゃろ」
詩織が急に真剣な顔でそんなことを言うから、俺はなんて返せばいいかわからなかった。
「俺も……そう思う」
俺は呟くように言った。俺も、詩織と出会っていなかったら、こんな風に心許せる仲間もできなかった。俺の顔にあざがなければ、こんな星空を観ることはなかった。詩織と出会ってから、自分のことも少しだけ好きになれるようになった。今日、人前で当たり前のように発表できたこともそうだ。今までの自分なら考えられない。全部隣に、詩織がいてくれたからだった。
だけどその気持ちは、なかなか上手く言葉になってくれない。
「……悲しみも、喜びも、きっと何か理由があるんじゃろな。物事っていうのはそういうもんじゃ」
俺が頑張ってしぼり出した言葉は、自分でも呆れるほどに、伝えたかった気持ちから遠い場所にあった。それでも詩織と目が合うと、不思議と言葉にできなかったことまで伝わっているような気持ちになる。俺が続けて何かを言おうとした時、すぐ後ろから甲高い声が聞こえた。
「こらー、またイチャイチャしとる!」
振り向くと、真希が庭の真ん中でこちらを指さしている。後ろで洋介が「邪魔したんなって……」と小さな声で言っている。
「イチャイチャしとらん。星観とるだけじゃ」
そう言う俺の横で、詩織は笑っている。二人の手はしっかりと繫がれたままだった。
「ねぇ、夏じゃけぇ、みんなで花火しよう」
真希の声は、まるでくすぐられているように楽しそうだ。
「こんな僻地のどこに花火が売っとるんじゃ」
俺は呆れながら言った。
「だから、持ってきたの」
真希は後ろ手に隠していた、パッケージに入ったままの花火を取り出した。
「え、お前それ丸ごと持ってきたんか」
自信満々で真希は頷いた。
「それ、パッケージから出したらもっと小さくなったのに」
洋介が冷静に言った。
「……あ、確かに」
いや、そういう問題ではないだろう。
「ってかそもそも、星空を観に来て地上で火遊びするやつがおるか」
俺はそう言うが、詩織は花火というキーワードに、とても好意的な表情をしている。
「せっかくじゃけぇ、夏らしいことやろうよ。ね、りょう」
強く手を握りながら詩織が言った。そう言われると、俺は断ることなどできるはずもない。
「まったく、女子陣には敵わんな。一人で男三人分くらいの決定権があるわ」
水の調達を頼まれた俺と洋介は、ペンションの入り口近くにある水道まで、バケツに水を汲みに向かった。女子二人はパッケージを開けて花火を取り出しておくらしい。モナとレオンも呼んでくると言っていた。
「ま、しゃーない。女は強いわ」
「お前、絶対将来尻に敷かれるのう」
天文部にいる時は、こうして男二人、女二人で役割が分かれることが結構多い。だから洋介は俺のいろんなことを知っているし、俺も洋介のことを知っているつもりだった。
「うわー、めっちゃ星綺麗な。こんな時に花火なんて、ある意味冒瀆じゃな」
不意に見上げた星空に、洋介は感嘆の声を漏らした。メガネの向こうの涼しげな目が、大きく開かれている。俺はそんなことを言いながらも、大事そうにバケツを抱えている洋介の姿に苦笑した。憎まれ口を叩いても、いいやつなのだ。
「洋介はほんまに星好きじゃな。なんかきっかけあったん?」
「星好きなことに、きっかけがあるやつなんて少ないじゃろ。花が好きな人も、動物が好きな人も、好きだから好きなだけじゃ」
「……まぁ、確かにそうじゃな」
めんどくさそうに言った洋介の言葉に納得していた。俺たちはどんなことにも理由を求め過ぎるのかもしれない。
「……でも、きっかけというか、昔は単純に喜んでくれるのが嬉しかったな……」
洋介は蛇口をひねって、また夜空を見上げながら言った。水道から水がチョロチョロとこぼれ出し、バケツに溜まっていく。
「誰が?」
「ん……母親じゃ。やっぱ女は光るものとロマンチックなものが好きなんじゃろ」
洋介は頭を搔いている。確か洋介の両親は離婚しているはずだ。二人で暮らしていると聞いたことがある。
「二人なら、お母さんもいろいろ苦労したんじゃろな。運転手しとるんじゃろ?」
俺もバケツをもう一つ置いて、蛇口をひねりながら言った。水が手にかかると、思ったより冷たくて驚いた。
「そうそう、タクシーの運転手」
「なんか珍しいよな」
「珍しいのは仕事だけじゃないけぇ。離婚しとるなんて今どきよくあるかもしれんけど、そもそも父親がおらんってのはなぁ」
洋介はまるで他人事のように言った。
「……何それ?」
その言葉の意味が、俺は一瞬わからなかった。
「……父親はほんまにしょーもない男でな。子どもはできたけど結婚はしたくないって言ったらしいわ」
「……そんなこともあるんじゃな」
「そんな状況で子ども産むって、多分大変じゃったと思う。でも逆に今思うと、喧嘩ばっかりの仲悪い夫婦よりもマシじゃったかなって思っとる。たまにそういう話聞くじゃろ? 家帰ったら喧嘩しとるとか、DVとか」
「……まぁ、いろんな家庭があるよな」
家庭にはそれぞれ事情がある。幸せそうに見える家庭でも、息苦しく思っている人もいる。
「じゃあ小さい頃に、お母さんと星観に行ったりしてたん?」
「んー、わざわざ行ったりしたことはないけど、どっか行った帰り道とかにな。俺が星の話をしたらぶち喜んでくれて、こんなんで笑ってくれるんじゃったら安いもんじゃ思って」
いい息子だ。俺にはこんな風に、誰かのために何かに詳しくなろうとしたことがあっただろうか。
「まぁきっかけと言えばそれかもな。もし叶うなら、俺は将来天文学者になりたいって思っとる。今は趣味みたいなもんじゃけど、そういうのが研究できる大学に行きたいな」
洋介のお母さん、こいつ、こんなこと言ってますよ。いい息子ですよ。
「りょうのきっかけは詩織じゃろ? お前が詩織に初めて部室に連れてこられた時、挙動不審にも程があったぞ」
「いや、途中から部活に入るって緊張するじゃろが!」
俺は洋介を精いっぱい睨みつけたが、洋介はカラカラと笑っていた。
話している間に、水がバケツから溢れ続けていた。俺たちは急いで蛇口を閉めて、なみなみと汲まれたバケツを持って庭に戻った。「遅いよー」と真希が怒っていた。
二年生の夏、俺たちは自然の星々が目を細めるくらいに、地上で眩しい人工の光を放った。真希が言うところの──「青春の星」というやつだったかもしれない。
詩織も柄にもなくはしゃいでいて、俺はこんな幸せ、知らなかったと思った。
──現在
電車の四角い窓の向こうを流れる夕暮れの景色を見ながら、俺はそんな去年のことを思い出していた。コトコトと線路の上を走る電車の音は、今の俺の心境とは裏腹に悠長な雰囲気を醸し出している。
俺と洋介はJR山陽本線、岩国行きの電車のシートで揺られていた。どの方角へ行けばいいのかわからず、とりあえず山口方面へ向かう電車に乗ればいいだろうと考えたのだ。
車内は空いているのに、扉の前で立っている人もいた。
「……付き合ってくれてありがとな」
俺は隣で無言で携帯をいじっている洋介に礼を言った。俺一人で行けばいいものを、洋介は付いてきてくれたのだ。
「ええよ」
洋介は今日の人工流星を誰よりも楽しみにしていたはずなのに、変わったやつだ。少し申し訳ない気持ちになりながらも、それでも今は彼の優しさに助けられていた。
洋介は携帯をじっと見ながら、何か考え事をしているような顔をしている。俺はなんとなく、ずっと黙っていてはいけない気がして、何か話を振ろうと思った。受験生の話題と言えば、やはり進路の話だ。
「……そういえば、洋介は進路どうするん? やっぱ去年言ってたみたいに、大学で天文学を勉強するんか?」
「いや……普通の大学に行くことに決めた」
洋介は携帯から目を離すこともなく、あっさり言った。
「なんで? 去年の夏はあんなに言ってたのに」
そう、あの夜、彼は自分の将来について語っていた。天文学者になりたいと。
「あれから俺もいろいろ情報収集してな。山波先生にも相談したりして。そしたら、ほんまに専門の勉強しようと思ったら、行ける大学も結構限られてくるみたいじゃ。東京には専門の大学はあるけど、そこはとんでもなく勉強できんと難しいみたいで」
洋介は携帯から目を離して、振り返って窓の外の景色を眺め始めた。真面目な話をするのが照れ臭いのかもしれない。ほとんど沈んでしまった太陽が、空に弱い光を放っている。
「あと、天文学者は食ってくのが難しいみたいじゃ。やけぇ今の時代は、他の仕事しながら研究してるアマチュアの天文学者が多いんじゃと。そしたら研究内容も自由に選べるし。ほら、山波先生みたいに、地学の教員しながらってのも多いみたいじゃ。ま、俺もそういう道もあるなって考えてな。やけぇ、大学で教職取ることなったら、学校の先生ってどんなんか教えてな? あ……でもりょうは先生になるんは止めたんか」
俺が東京の大学への推薦をもらったことを、唯一知っているのが洋介だ。
「いや……俺はやっぱもともと言ってた通り、広島で教育の勉強しようと思っとる」
「あれ、推薦は?」
「……蹴ろうと思う」
そう言った俺の顔を見て「それは前代未聞じゃな……」と洋介は驚きながら呟いた。電車が駅に停車し、二人の乗客が降りていった。扉が閉まり、またゆっくりと動き出す。
「何があったんか知らんけど、まぁ、その方がりょうの家族も喜ぶかもな。俺もお前が広島にいてくれた方が楽しいわ」
家族はそんなに関係ないけど、と俺は思いながらも曖昧に頷いた。
「俺もな、親が一人しかおらんけぇ、それもあって広島を離れることはできんわ。恩返しもせんと」
さすが、母親思いの素敵な息子だ。
「そういえば、洋介のお母さんは星好きって言っとったよな? 今回の人工流星は一緒に観んでええんか?」
「……そうじゃな」
何気ない質問だったつもりが、どこか引っ掛かるような返事が返ってきた。思い出してみれば、昨日も同じような違和感を覚えた気がする。
「何かあったん?」
「……なんも」
また、窓の向こうに目をやる。ますます怪しい。
「喧嘩でもしたか?」
洋介は黙って外の景色ばかりを見ている。太陽は完全に沈んで、空は徐々に暗くなってきていた。電車は、また次の駅で停車した。今度は降りる人も乗る人もいなかった。洋介はずっと何かを考えているようだった。
「……聞いてくれるか? なんか説明するのも恥ずかしいんじゃけど」
彼は前を向いて、観念したようにしばらく目を閉じた。もちろん、と俺は言った。
それから洋介は、母親と最近何があったのか話してくれた。
電車はコトコトと音を立て、緩やかな振動をシートに伝えている。
俺は全部聞き終えて、思わず大きなため息をついた。
「……お前が悪いわ」
「……やっぱそう思うか? でも、なんか改まって謝れんのじゃ」
「なんでそれを先に言わんのじゃ……」
去年の夏、夜空の下で話した洋介の顔が、今の洋介と重なった。本当はあんなにお母さんのことを大切に思っているくせに。
俺は居ても立ってもいられなくなって立ち上がった。
「どこ行くんじゃ?」
「次の駅で降りよう」
俺は洋介の顔も見ずに言った。
「は? なんで?」
「お母さんに謝りに行くぞ」
二人の喧嘩の経緯はこうだった。
洋介のお母さんは、毎日遅くまで仕事をしている。廿日市市は昼間は観光客が多く、夜は広島市内の繁華街から自宅までの長距離利用者が多い。最近は特に忙しいようで、仕事から家に帰っても、相当に疲れ切った様子であるらしかった。
洋介は初め、心配する気持ちで「少しは休んだら? 無理して働かんでええ」と言ったらしい。二人暮らしで、何かあっても頼れるのはお互いしかいない。
するとお母さんは「大学進学もあるけぇ、そういうわけにはいかんよ。受験生にバイトもさせられんし」と言ったそうだ。別に深い意味を込めて言ったことではないのだろうが、その言い方が洋介には引っ掛かるところがあった。
「いや、別にそんなに俺のために頑張ってもらいたくないし」と返すと、「なんじゃその言い方。お母さんが働かんと暮らされんじゃろ」とお母さんは怒って声を荒げた。もともとあった相手を思いやる気持ちはどこかに消え去っていた。口論は続き、最後に洋介は言い放った。
「無理して俺のこと産むからじゃろが」
言葉が口から離れた瞬間、洋介は既にしまったと思っていた。洋介のお母さんは「……そうじゃな」と言って、もう何も言い返してこなかった。
それからというもの、二人の間に会話はないらしい。お互いしか、一緒に暮らす家族はいないというのに。
俺は洋介の母親思いの性格を知っている。本当はそんなことを言うつもりはなかったはずだ。
伝えるって難しい。不器用なやつである。
嫌がる洋介を引っ張って、俺は次の駅で下車し、逆方向の電車で引き返すことにした。帰ってくる途中、俺はずっとダウンロードしたばかりのタクシーの配車アプリの使い方を調べていた。普段タクシーに乗ることがないので、使い方がわからなかった。しかし今どきのアプリはすごいもので、タクシー会社の気に入った運転手を指名することもできるらしい。利用者が運転手を評価することができて、その評価を見てタクシーを選ぶことも可能になっている。これは……運転手も大変な時代の到来である。それでも、態度の良くない運転手が淘汰されていくのはいいことかもしれない。
「ほんまに行くん……?」
「行く。お前が一人で行けんって言うからこんな面倒なことしとるんじゃ」
洋介は申し訳なさそうに、シートに座って下を向いている。俺もさっきまでは洋介に付いてきてもらっていた立場だったのだが。
「りょう、これから戻っとると流星から逃げられんくなるぞ」
洋介は腕をまくって腕時計に目をやった。
「このタイム感ならギリギリ間に合う」
俺は携帯アプリを操作しながら言った。今広島駅へ引き返して、急いでまた電車に乗れば間に合うはずだ。
「でも……金曜の夜じゃろ? どうせ仕事しとるわ。客乗せとるのに流れ星どころじゃないじゃろ」
「広島西タクシーじゃったな?」
「うん。でも俺が呼んでも絶対来んって」
「俺が電話する」
俺はアプリ内で、洋介の名字である「小久保」を探す。そこまで多い名字ではないので、見つけるのは難しくなかった。
「小久保響子って名前か?」
「……あったん?」
「うん。めっちゃ評価高いで」
「……まじで」
洋介はさっきまで興味なさそうにしていたくせに、身を乗り出して俺の携帯を覗き込んでいる。画面には利用者が投稿したレートが書かれてあり、洋介のお母さんはかなり評価が高いようだった。仕事ぶりが丁寧なのだろう。
「頑張っとるんじゃな……」
洋介は小さく呟いた。普段親が仕事をしている姿など、見る機会なんてなかなかないものだ。間接的にでもそれを見た洋介の言葉には、様々な感情がもつれ合っているようだった。
手違いを避けるために、俺は予約の電話をした。「相沢」と予約名を伝え、運転手の指名をする。場所は広島駅だ。車内での通話はマナー違反だが、電車に乗ってる人も少ないので、緊急ということで許してもらおう。
「はい、行き先はファミリーマート宮島口店までお願いします」
「なんでそんな場所に?」
予約をしている俺の横から、洋介が尋ねる。俺は電話を切った後に言った。
「いいロケーションを見つけ出すのが、天文部のサガらしいぞ」
広島駅に着いて、駅前のロータリーでしばらく待っていると、タクシーがやって来た。
運転席から、想像していたよりもずっと若い女性が現れた。
「相沢様ですか?」
こんな高校生相手でも、丁寧な態度で応対してくれる。見た目は若いが、芯のしっかりした人のような印象を受けた。
「……はい、配車を依頼した相沢です」
俺は物怖じしないように言った。
「ありがとうございます。宮島口の方でしたよね? どうぞ」
洋介のお母さんは、素早く後部座席の扉を開いてくれた。
「……すみません。実は、宮島口に連れていってほしいのは僕じゃないんです」
「えっと……どちら様が乗車されるのですか?」
お母さんは笑顔を崩さずに、俺に尋ねた。
「後ろにいる、僕の大切な友達を連れていってください」
お母さんは視線を後ろにずらした。そこに立っていたのは、現在絶賛喧嘩中の息子だった。
俺は洋介をタクシーに押し込んでから、急いで駅へ戻った。
意外と時間がかかってしまった。さっき乗った普通電車ではもう間に合わないだろう。俺は咄嗟の判断で新幹線の切符を買い、鹿児島中央行きのさくらに飛び乗った。次の停車駅は、新山口駅である。
まさかこんな事情で、一人で新幹線に乗ることになるとは思わなかった。当然初めてのことなので、切符を買うのにも緊張した。
新幹線の座席に座ってから、やっと気持ちが落ち着いて、俺は洋介のことを思った。
お母さんにとっては青天の霹靂だろう。まさか息子がお客さんとしてやって来るなんて。洋介も洋介だ。あそこまで来て、無言でタクシーに乗り込んで、まるで「俺は無理やり連れてこられたんだ」と言わんばかりの態度でシートに座っていた。今どんな会話をしているのか心配である。
いや……心配すべきなのは俺自身の方だ。人工流星は不確定なことが多い。計画していた範囲通りに、ぴったり流れるようなものではないのかもしれない。
窓の外では、街の光が飛ぶように流れていく。
これは、昨日とは全く違う一日だ、と俺は思った。
同じ日が繰り返されているとしても、そこで起こる出来事は変えられるのだろう。もうこれ以上今日が繰り返されないためにも、急げ、と新幹線の尻を叩きたいくらいだった。
時刻が、昨日星が降り始めた二十一時に近づく。
俺は窓に手で囲いを作り、額をくっつけ、真っ暗な空を覗いた。
明るい星がいくつか輝いているのが見える。一番明るいあの星は、きっとシリウスだ。太陽を除いた恒星の中で、全天で最も明るい星。
携帯の時計が二十一時を示す。
流星は……どこにも見えない。
俺はそれからずっと注意深く夜空を眺めていたが、動く光は一つも見えなかった。方角は間違っていない。昨日はあれだけくっきりと見えた流星が、どこにも見えないのだ。
どうやら間に合ったらしい。
俺は肩に入っていた力を抜いて、背もたれに体を預けて深く呼吸をした。
これで、俺の運命は流星の影響を受けずに済むはずだ。
程なくして新幹線は新山口駅に着き、俺は下車した。ホームに降り立って、すぐに広島方面のホームに移動する。こうしてすぐに逆方向へ移動するのは、今日だけで二回目だ。もし俺を後ろからつけている人がいたら、おかしな行動をとるやつだと思うだろう。
ホームで立っていると、携帯に通知が来た。メッセージが届いている。
[仲直りできた。謝れたし、俺の思ってたこと、将来のこと、いろいろ話せた。多分俺、今日の機会を逃してたら後悔してた。りょう、ほんまにありがとう]
伝えるって難しい。だけど、伝えるって大切だ。
二人の間でどんな会話が交わされたのか、俺は知らない。
それでも、過ごすべき人と同じ時間を過ごせたのだ。間違いなどないだろう。
俺は苦労して来た道を戻り、家に帰った。今日はまるで小旅行みたいだった。向こう側で改札を出なかったとはいえ、一人で新幹線に乗ったのも初めてだったのだ。広島駅で切符を入れても改札を出ることができなかったので、駅員に正直に「新山口に行って改札を出ずに帰ってきました」と言うと、しっかり二千円ちょいの帰りの運賃も請求された。当たり前のことだが、高校生には手痛い出費である。
「ただいまー」
俺がリビングに入ると、那月が一人でテーブルに座っていた。何をするでもなく、ただぼーっと座っている。
「何しとるん?」
俺が声を掛けると、彼女はやる気のない仕草で、顔だけをこちらに向けた。
「……お兄にちょっと聞きたいことがある」
何だろう、珍しい。自分から質問してくるなんて、いつぶりのことだろうか。
「男って、好きじゃない人ともデートするもんなん?」
那月は思い出したように、不満そうな顔になって言った。
「フラれたん?」
「……フラれたっていうか……私のことは妹みたいで、彼女としては見れないって。先に言えばいいのに」
妹よ、それはつまりフラれたのだぞ。
「一緒に流星観に行くとか、その時点で恋人じゃろ。何なん男って」
きっと、先輩的な人にフラれてしまったのだろう。普段は憎たらしいのに、意外と可愛いところもあるものだ。
「こっちはそんなこと言われても、簡単に受け入れられんし」
今度は今にも泣き出しそうな顔になっている。よし、ここは一つ、兄らしいところを見せよう。
「……思わせぶりな先輩もいるもんじゃな。でも那月のいいところをわかってくれて、大切にしてくれる人は他に絶対いるよ」
なかなかいい兄なのではないだろうか。俺は少し顎を上げて、頭の中のイケメンな兄らしい仕草をしてみた。
「……きも」
ちらっとこちらを見て那月は言った。なぜそうなる。
しかし、今夜は流星の下で、いろんなドラマがあったらしい。
つづく
≪-テキストは横読み-≫
Profile

WEAVER 河邉徹(Dr.)
1988年6月28日、兵庫県生まれ。関西学院大学 文学部 文化歴史学科 哲学倫理学専修 卒。
ピアノ、ドラム、ベースの3ピースバンド・WEAVERのドラマーとして2009年10月メジャーデビュー。バンドでは作詞を担当。
2018年5月に小説家デビュー作となる『夢工場ラムレス』を刊行。
WEAVER公式HP:
http://www.weavermusic.jp
Books
OTHER