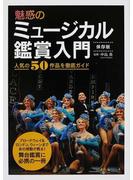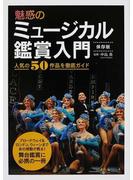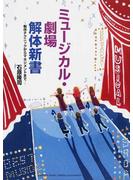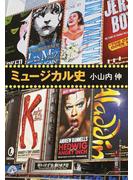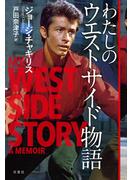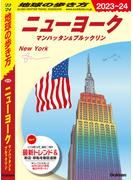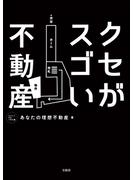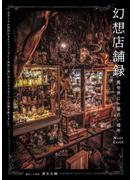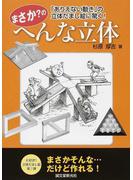ブックツリー
Myブックツリーを見る本の専門家が独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの”関心・興味”や”読んでなりたい気分”に沿ってご紹介。
あなたにオススメのブックツリーは、ログイン後、hontoトップに表示されます。
ヒップホップ本5冊はこれ!
- お気に入り
- 4
- 閲覧数
- 8052
日本人ラッパーの本というのがかなり出版されてる。内容はラッパー個人の自伝が多い。アウトロー的なイメージが強いみたいで、書店によってはヤクザ系の本と同じジャンル扱いされてる。そんなヒップホップ本の中から面白かった5冊を紹介。
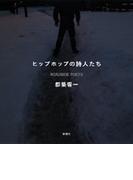
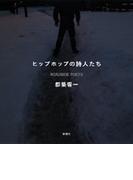
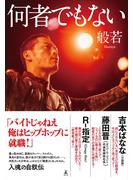

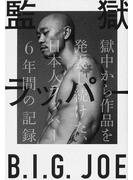
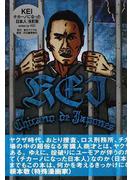
背景をしっかり理解したい!という方にオススメのヒップホップ入門本
- お気に入り
- 13
- 閲覧数
- 767
今や世界各国のお茶の間で聴かれるようになったヒップホップ。聴いてみたいけどいまいち入り口がわからない・・・という人も多いことでしょう。そんな方のためにヒップホップがしっかりと理解できる、選りすぐりの本を紹介します。その背景を理解してから聴く名曲たちは、あなたの魂を揺さぶるはずです。
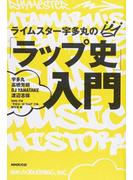
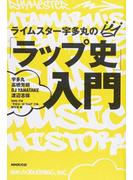
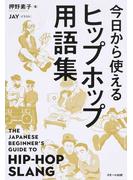
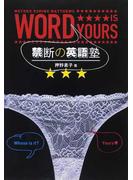
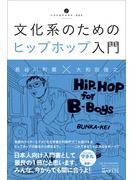
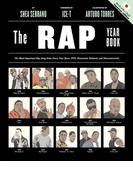
西洋の芸術史に革新をもたらした日本美術。ジャポニスムについて学べる本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 85
19世紀後半から20世紀前半にかけて、欧米諸国では、浮世絵や工芸品などの日本の美術が大きく注目されました。この現象は「ジャポニスム」と呼ばれ、芸術家たちの制作技法や作品の様式のみならず、庶民の生活嗜好にまで広く流行し、現代にもその影響の名残が見られます。ここでは、ジャポニスムを理解するうえで参考になる本を紹介します。
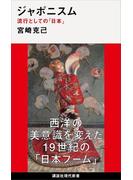
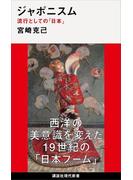

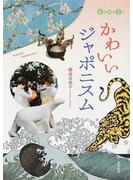
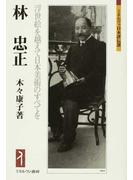
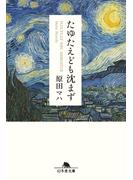
写真と言葉。「批評家」中平卓馬の横顔を現代から眺め直す5冊
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 13738
日本の戦後写真史において、実作/理論の両面で存在感を放った写真家・中平卓馬(1938-2015)。約20年ぶりの開催となる大回顧展「中平卓馬 火―氾濫」(東京国立近代美術館にて2024年4月7日まで開催)に関連し、中平が自らの眼を通して探索した写真と言葉の相互関係をより豊かに受け止められるようになる5冊を紹介します。






みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 741
古くからみちのく(北東北)の村々で親しまれてきた、素朴で味わいある風貌の民間仏たち。それらに焦点を当てた「みちのく いとしい仏たち」展(東京ステーションギャラリーで2024年2月12日まで開催)に関連し、東北を旅した僧や学者たちの息遣いと、庶民の祈りの拠り所≒仏像、そして彫刻を巡る営みの不思議を感じる5冊を選びました。



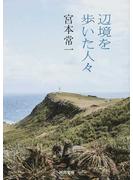


「教授」が遺した旋律、そして言葉。音楽家・坂本龍一の生涯をたどる本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 471
2023年、71年の生涯を終えた坂本龍一。世界中の人々の心を動かす音楽を生み出し続けた彼はまた、理想の社会についての啓蒙も晩年まで続けていました。世界の古典音楽を超え、自己表現を超え、新たな音が響き合う社会を求めて実践した道のり。これから坂本龍一に出会う方にもオススメの、彼の人生の足跡を追うことができる本をそろえました。


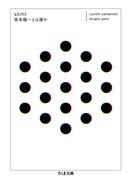


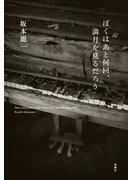
ヨーロッパの雰囲気を感じて、今すぐ旅に出たくなる本
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 506
クラシック音楽や印象派の作品など、日本でも身近に感じられるヨーロッパが発祥の芸術作品は数多くあります。実際に訪ねて、生で触れてみたいという方も多いでしょう。ここでは、音楽、アート、写真、小説とさまざまなジャンルから、ヨーロッパへの憧れを掻き立ててくれる本を集めました。旅行前の予習にもオススメです。






「保存・修復」の視点から、美術館スタッフのニッチな奮闘を覗き見る5冊
- お気に入り
- 81
- 閲覧数
- 38020
美術館の社会的役割のうち普段注目される機会の少ない、所蔵作品や文化財の「保存」。ダリをはじめ同館所蔵作品の保存・修復のプロセスを見せていく諸橋近代美術館「ミュージアム・ワークス─みんなの知らない美術館」(2023年11月12日まで)の開催に際し、普段見えにくい美術館の仕事の現場のニッチな醍醐味に出会える本たちをご紹介。
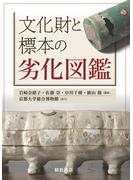
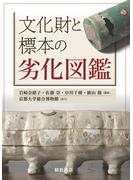

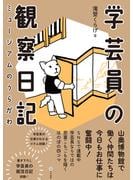


「映画」がもっと楽しくなる、スタッフワークに触れてみる
- お気に入り
- 19
- 閲覧数
- 40760
脚本、音楽、美術、撮影、映画は様々なディテールでつくられている。意外な小道具や名作、名場面を生み出す技術など、映画を愛する人々が語る、プロフェッショナルな世界を魅力的に伝える本の数々。


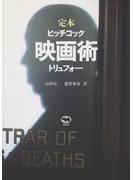
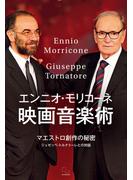


映画監督の本5冊!
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 810
映画監督が書いた小説や自伝は数多く出版されてる。オレも仕事柄だいたい読んでるがぶっちゃけ面白くない。監督は映画撮ってなんぼでしょ!そんなわけでとりあえず5冊あげてみた。
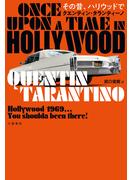
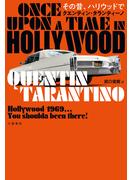
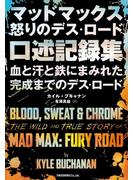

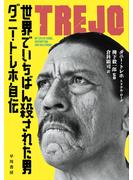
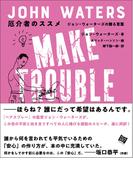
文化財を守る、受け継ぐ、蘇らせる。職人の知恵と最先端の技術を知る本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 516
文化財には仏像や城郭、絵画や工芸品などさまざまなものがありますが、継続的な修理や修繕があってこそ価値が保たれます。こうした文化財の保護に国や自治体が取り組み始めたのは明治以降のことで、時代の変化によってその手法も様変わりしています。昔ながらの職人の技と最先端の技術の融合による新たな文化財保護の世界を覗いてみましょう。





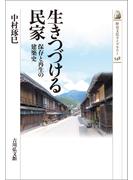
米国と世界の真実を写し、記録するための激闘。ピューリッツァー賞関連書
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 629
ピュリツァー賞とは、報道・文学・音楽を対象としたアメリカで最も権威ある賞の一つ。特に報道においては、大賞に当たる公益部門や時代の象徴的な一瞬を切り取った特集写真部門を擁し、世界でも最高峰の栄誉と目されています。逆境の中で社会へ一石を投じ、賞を受けた記者やカメラマンたち。その熱い信念に触れることができる本を集めました。
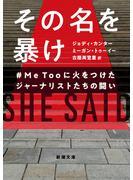
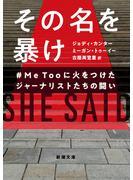
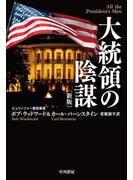



「縫う」を通して、未知の時空間を行き来させてくれる5冊
- お気に入り
- 20
- 閲覧数
- 12683
東欧の国々の民俗衣装や日用品、近現代の作家の刺繍作品やオートクチュール──「刺繍」を軸に、多様な時代・地域の手仕事に触れられる「糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。」(新潟県立万代島美術館で2023年7月17日まで開催/25日より静岡県立美術館に巡回)に関連し、縫う行為から人の生活と思考を紐解く本を紹介します。
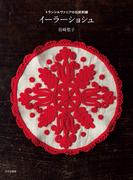
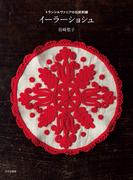
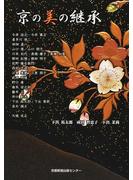

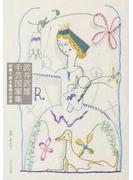

映画秘宝とは別の映画関連の本!
- お気に入り
- 0
- 閲覧数
- 8779
映画秘宝が廃刊になって数年経つ。復刊するとかしないとか噂はあったけど、もう雑誌は難しいのでは?秘宝のようなお笑い映画本ではなく、シリアスな日本の映画界の裏側を暴露するタブー本の方が面白い!
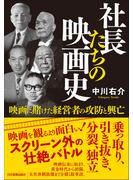
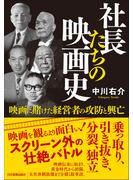




魔法を広げる、創り出す!「ウィザーディング・ワールド」をさらに楽しむための本
- お気に入り
- 4
- 閲覧数
- 489
小説『ハリー・ポッター』シリーズをもとにした世界観「ウィザーディング・ワールド」。今では映画やテーマパーク、グッズに舞台、ゲームとさまざまなメディアでも世界中の人々を魅了しています。原作初巻が刊行されてから25年以上を経てなお魔法のように広がり、形を変えて創造されています。その秘密を紐解き、さらに夢中になれる本を紹介します。
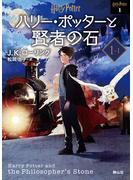
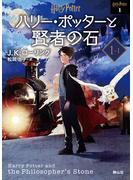
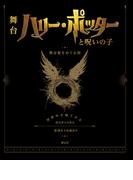

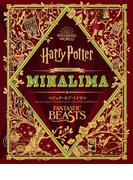
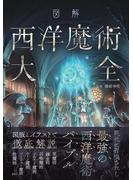
デジタルイラストを楽しもう!辞書感覚で使えるお助け本
- お気に入り
- 6
- 閲覧数
- 677
誰でも手軽にデジタルイラストを描くことができる昨今、辞書感覚で携えておきたい本を集めました。デジタルイラストは無料動画などでも学べる時代ですが、「あの操作はどうだっけ?」と気になったときに、サッとページ開けば参考にできる本は心強い存在です。ぜひ作業の相棒にしてください。
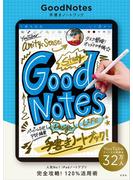
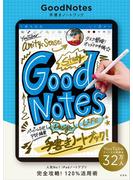
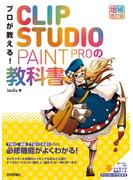
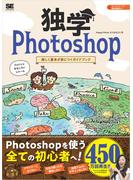
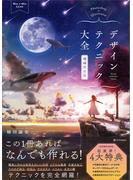
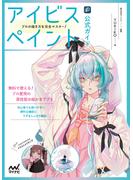
「わからん」ままでも現代アートとの接点を発見できる5冊
- お気に入り
- 19
- 閲覧数
- 19963
日本を代表する現代美術コレクション「タグチアートコレクション」を集めた展覧会「タグコレ 現代アートはわからんね」(角川武蔵野ミュージアムで2023年5月7日まで開催)。解説や空間構成など、現代美術は苦手という人にもその存在をぐっと身近に感じさせる工夫に満ちた本展の関連書籍と併せ、興味の先に一歩踏み込む5冊を選びました。
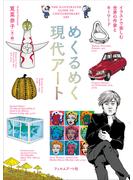
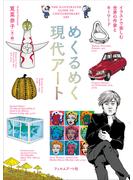
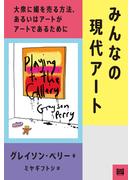
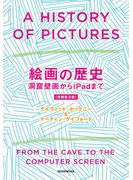
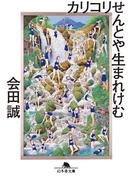

職人の世界を知る本
- お気に入り
- 50
- 閲覧数
- 31072
リモートで十分? AIを活用? そんな昨今の仕事環境と正反対なのが、「職人ワールド」。時代が変わっても、人による手づくりでしか生み出せないものがあります。それは「丁寧」「長持ち」といったワードと親和性が高く、実は今こそ求められているのかもしれません。「職人」「手仕事」に興味のある方に刺さりそうな本を紹介します。
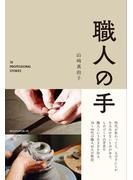
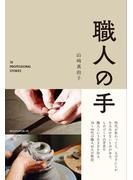
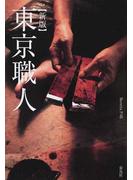
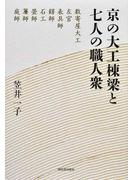


「描きたい&描けない」を解決!動画連動のイラスト技法書
- お気に入り
- 17
- 閲覧数
- 1601
コロナ禍の行動規制などもあり、「イラストや絵」を始める人が多いそうです。ただ、技法書やノウハウ本を買っても、なかなか描けない&上達しないといいます。そんな悩みを解消してくれるのが、YouTuberとしても活躍する漫画家やイラストレーターの技法書。現役ならではのテクニックやノウハウを、動画と共に確認できるのがメリットです。


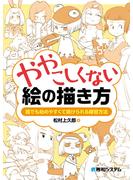
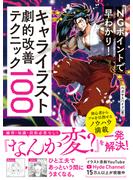
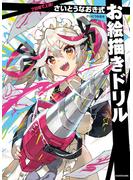

魅惑のインク沼へようこそ!手書きのよさを教えてくれる本
- お気に入り
- 12
- 閲覧数
- 1581
マンガもイラストも宛名書きもデジタルが主流の現代にあって、ここでフィーチャーしたいのは手書き(手描き)のよさ。やり直しがきかないことはマイナスに感じるかもしれませんが、だからこそ「インク」には楽しい面もたくさんあるのです。読めばインク沼にハマってしまうこと必至の本を紹介します。



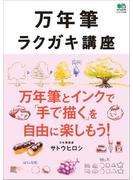
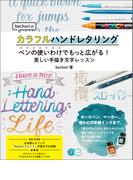
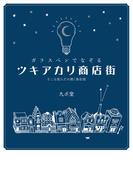
手も眼も使って考え、暮らす──現代のデザイナーの思考回路を覗き見る5冊
- お気に入り
- 9
- 閲覧数
- 10858
生活のなかでの観察・思考や、アイデアを形にするまでの密かな知的興奮。「デザインスコープ─のぞく ふしぎ きづく ふしぎ」(富山県美術館で2022年12月10日〜2023年3月5日開催)の参加作家が登場したり書いた本を中心に、つくることとその手前にある日常の見方のそれぞれの個性が浮かび上がってくる5冊を選びました。


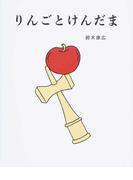

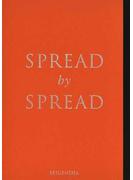

個性的な女性たちが大活躍!はじめての誉田哲也
- お気に入り
- 4
- 閲覧数
- 710
『ストロベリーナイト』で一躍脚光を浴びた誉田哲也。警察小説の書き手として有名になりましたが、実は青春小説やホラーなど、幅広いジャンルを執筆しています。特徴としてよく挙げられるのは女性の描き方で、個性的で魅力ある女性を数多く登場させています。そんな素敵な女性たちが活躍する小説をそろえました。
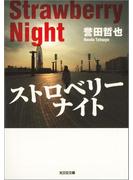
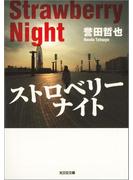

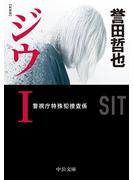

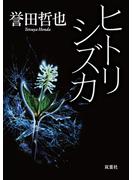
人はなぜ音楽に惹かれるのか。哲学や科学から見るユニークな音楽論の本
- お気に入り
- 19
- 閲覧数
- 1605
つらいときや悲しいとき、音楽に癒されたという人は多いでしょう。スポーツ選手が集中力を高めるために、競技の前に音楽を聴く姿も珍しくありません。人間には音楽が必要だ、というのは誰もが賛成すると思われますが、その理由をはっきりと知る人は少ないかもしれません。音楽が持つ力の源に哲学や科学の視点から迫る本を紹介します。



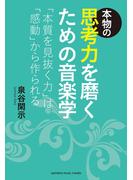


ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊
- お気に入り
- 6
- 閲覧数
- 8810
言わずと知れたポップ・アートの旗手ウォーホル。1956年の初来日時の京都と彼の接点にも目を向けた大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館で2022年9月17日~2023年2月12日開催)に際し、日本の作家や芸術家たちがウォーホルに向けた個人的な眼差しが時代背景とともに垣間見える5冊を選びました。
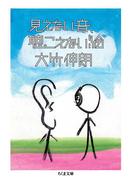
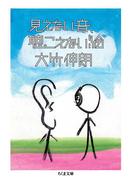


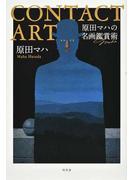
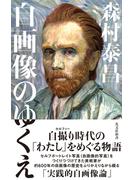
アートを近くに感じる本【Bunkamuraセレクション】
- お気に入り
- 65
- 閲覧数
- 37312
知らなかったことを知ると、毎日が違う色をして輝きだすように感じます。もしかしたらそれはアート作品をひとつ手に入れ、共に暮らす喜びと似ているかもしれません。さまざまなジャンルの展覧会を開催するBunkamura Galleryスタッフが選ぶ、さまざまな切り口の5冊。知れば知るほど近くに感じる。そんな嬉しさを感じる本です。


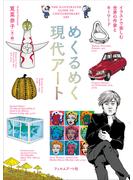



美術をおいしく味わう5冊【Bunkamuraセレクション】
- お気に入り
- 108
- 閲覧数
- 20450
美術や美術館に親しみはじめた方へ、お料理を楽しむように美術をおいしく味わう本をおすすめします。美術館にまつわる物語や、作品に描かれたおいしいもの、画家のおいしそうな絵画と創作の源泉を知る本など。小説から美術史まで、奥深く味わいゆたかな美術の世界を、ご一緒にお味見してみませんか。
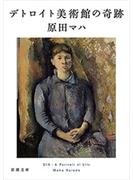
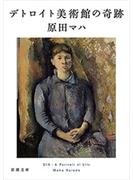
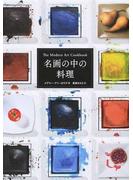

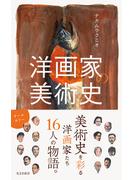

海外戯曲はじめて読むならこの5冊【Bunkamuraセレクション】
- お気に入り
- 29
- 閲覧数
- 5677
戯曲は長編小説ほどは長くはなく、詩よりは難解ではありませんが、演じられて初めてわかることがたくさんある文学形態です。それを楽しむには、読みながら劇世界に没頭し、演じることと同じように作品を味わうことが必要かもしれません。そこで、何度も読み返したくなる、日本語の美しさや楽しさのある戯曲を選んでみました。
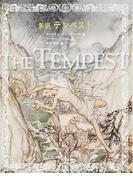
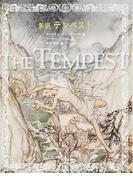

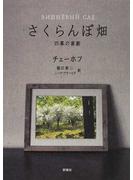
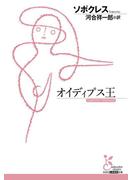

“クラシック音楽に親しみたい”とお考えの方にお薦めの5冊はこれだ!【Bunkamuraセレクション】
- お気に入り
- 45
- 閲覧数
- 5462
日本は、子どもたち全員に音楽教育を行うという世界でも稀な国の1つにも関わらず、クラシック音楽ファンが一向に増えないのは、音楽の授業が楽しくないから。というわけで、 “クラシック音楽はこんなに楽しい”ということを改めて教えてくれる5冊を選択。音楽室に飾られていた作曲家たちの厳しいイメージが変わること請け合い!






初めてミュージカルを観る前に読むとより楽しめる5冊【Bunkamuraセレクション】
- お気に入り
- 22
- 閲覧数
- 18171
歌って・踊って・感動して!どのアングルからも楽しめるエンターテイメントがミュージカル。これから見始めたいと思っている方にも、食わず嫌いの方にもお勧めの5冊です。日本での空前のミュージカルブームに加えて、『ラ・ラ・ランド』をはじめとしたミュージカル映画が注目をあびている今、あなたのお気に入りの1作にぜひ出会ってください。