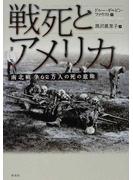孤読から共読へ:書物の共同体のために
- お気に入り
- 106
- 閲覧数
- 14603
「知の冒険に身を投じ、他者を知るために、書物は最良の道具です。それは誰でも容易に手に取ることができ、電気も必要とせず、移動も収納も簡単です」とル・クレジオは語った。人間が肉体を持つ限り、モノとしての書物も容易にはなくならないのだろう。紙世代の作家や思想家が書物と読書、書店について語ったことを振り返ってみる。【選者:小林浩】






アート・オブ・ライフ、生きかたを創る芸術
- お気に入り
- 34
- 閲覧数
- 4603
人生を芸術作品のようにして創りだし生きる人たちがいます。いや、人間だけではありません。動物も、鉱物や星も、オブジェも、思想も、それが存在していることが一箇の芸術のようになることもあるでしょう。「芸術」といっても千差万別。まだ見ぬ芸術もあるにちがいありません。【選者:堀千晶(ほり・ちあき):仏文学者】


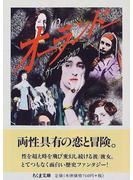
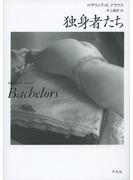


オーウェル、ディストピア、そして楽観主義なき希望へ
- お気に入り
- 40
- 閲覧数
- 3936
フェイクニュース蔓延やロシアのウクライナ侵攻など、『一九八四年』を彷彿とさせる事件に事欠かない現代は、ディストピアが実現した時代なのだろうか? 困難な状況のなかでなお希望を追い求めたオーウェルとウィリアムズ、そして彼らの試みを現代に継承する道を模索する5冊を紹介する。【選者:秦邦生(しん・くにお:1976-:東京大学准教授)】
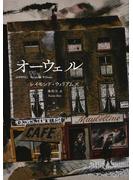
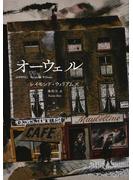



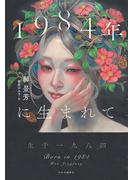
誰でもよいあなたへと宛てられる言葉
- お気に入り
- 19
- 閲覧数
- 2280
2021年に惜しくも亡くなったフランスの哲学者ジャン゠リュック・ナンシー。その哲学の独自性はどこにあるのか。膨大な数の著作を、「誰でもよいあなた」=「不定の二人称」という切り口から読み解き、その先にあるものを見据えるための5冊を紹介する。【選者:伊藤潤一郎(いとう・じゅんいちろう:1989-:日本学術振興会特別研究員PD)】






なぜ〈国籍〉にこだわるのか、抗いの歴史を読む
- お気に入り
- 22
- 閲覧数
- 1708
かつて在日外国人のほとんどは、植民地支配の結果渡日した朝鮮人のほか、中国や台湾出身者でした。祖国の戦乱と分断の痛みに苦悶しながら戦後日本を生きたこの人びとにとって、国籍とは、そして日本の外国人法制とは何を意味したのでしょうか。当事者たちの声を伝える5冊を選びました。【選者:鄭栄桓(ちょん・よんふぁん:1980-:明治学院大学教授】






俗流「現代思想」ではない、本当の68年5月の思想へ
- お気に入り
- 43
- 閲覧数
- 9102
安直な流行への追従と商業主義の下で消費されてきた「現代思想」の流れと手を切り、1968年5月革命の熱気を宿す哲学・思想を、あくまでも文献と文脈に忠実であるがゆえに急進的な政治性から目を背けることなく捉えること――それこそが新世代の研究者の使命なのである。【選者:鹿野祐嗣(しかの・ゆうじ : 1988-:神戸大学助教)】
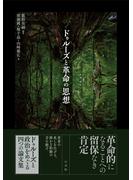
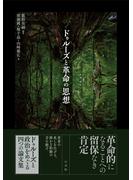

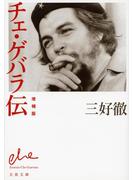
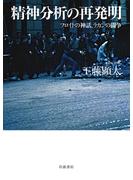

気候運動と現代思想
- お気に入り
- 15
- 閲覧数
- 2903
気候危機への対応は、経済・社会・政治・文化の今日的ありようを支え貫く種々の不公正と不平等の根本的な改革なしではありえない。全世界の多数多様な抵抗の歴史と実践と絡み合い、問題意識を先鋭化させる気候運動に学び、そこから思索する手がかりを与えてくれる著作を紹介する。【選者:箱田徹(はこだ・てつ:1976-:天理大学教員)】
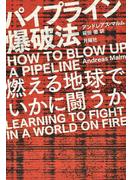
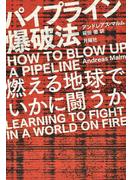

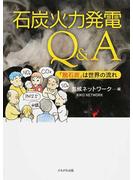
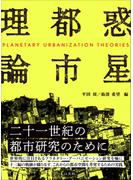

意味の断崖に立って:なぜ今シェリングなのか
- お気に入り
- 25
- 閲覧数
- 2951
「世界の全体は理性の網に捕捉されている。しかし問題はいかにして世界はこの網に入ってきたのかである」。シェリングの思索が今も私たちの心を捉えるのは、彼が世界システムというウロボロスの円環の底へダイブし、その秘密を手にして生還した数少ない哲学者の一人だからである。【選者:浅沼光樹(あさぬま・こうき:1964‐:哲学)】
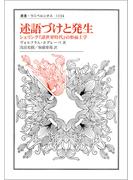
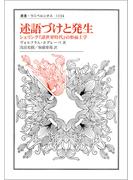




断絶と孤絶の時代に抗して他者について考える
- お気に入り
- 54
- 閲覧数
- 3469
憎悪と分断が無限に噴出する現代社会。そのような状況でなお他者への責任を引き受けること、しかもそれを制度化された民主主義やコミュニケーション空間とは別のかたちで考えること。困難な試みですが、断絶を越え他者とともに在ることへの希望がそこにあります。【選者:吉田健彦(よしだ・たけひこ:1973‐:東京農工大学非常勤講師)】



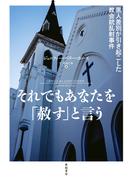


条件としての人間を哲学する
- お気に入り
- 45
- 閲覧数
- 4225
“人間”と総称される一群にとことん愛想を尽かした哲学者、思想家たちは、にもかかわらず、その一群を律する諸規則やメカニズムについて思索を重ねることをやめませんでした。彼らは何を予期して何を諦め、また、そうした予期と諦念を繰り返したすえに、あるいはその直中で、何を見出したのでしょうか。【選者:布施哲(ふせ・さとし : 1964-:名古屋大学准教授)】




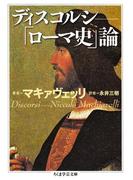

コンテナから神話へ、五千年以上を遡る5冊。
- お気に入り
- 50
- 閲覧数
- 4158
かつてなく当たり前に、かつてなく大量にモノと情報が世界を駆け巡る時代に私たちは生きています。今後、ますますその勢いは増していくでしょう。情報とモノの濁流に身を洗われながら、ただ流されるのではなく抵抗するために、押し寄せるその怒涛に目を向けてみるのはどうでしょうか。拙著『書物と貨幣の五千年史』と副読本4冊をご紹介します。【選者:永田希(ながた・のぞみ:1979‐:著述家・書評家)】






現代フランス哲学――トリスタン・ガルシアとその周辺
- お気に入り
- 35
- 閲覧数
- 4833
「フーコー・ドゥルーズ・デリダ」の時代が終わり、現代は「ポスト・ポスト構造主義」の時代と称されることもある。カンタン・メイヤスーらによる「思弁的実在論」の動向が注目されるようになってからも久しいが、現代フランス哲学は単純にこれに還元されるものなのだろうか?【選者:栗脇永翔(くりわき・ひさと:1988-:フランス文学・思想)】






フランス現代哲学裏街道一番地を訪ねる
- お気に入り
- 31
- 閲覧数
- 4063
フランス現代哲学といえば、といった定番の影には、常に参照され続ける裏街道があった。そのなかでもとりわけ知られざるものだったのはフランスの数理哲学の系譜であり、その端緒には、アルベール・ロトマンとジャン・カヴァイエスがいた。そしてこの系譜の端には、バディウ以後に広がる近年の多様で広大な議論の海が開けている。今回はその険しきも悦びに溢れた道を案内してくれるだろう本たちを紹介しよう。【選者:近藤和敬(こんどう・かずのり:1979‐:鹿児島大学法文学部准教授】






哲学と地理の関係を考えるための五冊
- お気に入り
- 66
- 閲覧数
- 6596
哲学は古代ギリシアで生まれた。この独特な思考の営みはなぜエーゲ海のほとりで誕生したのか。古代ギリシアは海の上に広がる商業空間であると同時に、民主政の実験が行われた地でもあった。こうしたことは何か意味をもつのか。哲学を新たな角度から考えるための五冊。【選者: 大久保歩(おおくぼ・あゆむ: 1972-: 哲学・政治理論)】


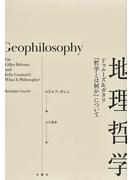

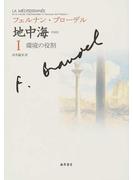

2020年代の「都市」を彷徨するために
- お気に入り
- 24
- 閲覧数
- 2386
自由に出歩くことのできない都市とともに2020年は幕を開けました。これからの都市を、私たちはいかに考えることができるのでしょうか。書をもって再び街を歩く日のために、都市のありかたを考えなおすヒントとなる5冊を紹介します。【選者:仙波希望(せんば・のぞむ:1987-:広島文教大学講師)、平田周(ひらた・しゅう:1981-:南山大学准教授)】
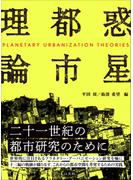
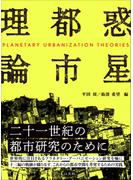




ベンヤミンの問いを受け継ぐために
- お気に入り
- 34
- 閲覧数
- 3309
ベンヤミンが危機と向き合いながら繰り広げた批評的な思考は、言語、芸術、歴史をその可能性へ向けて根底から問うものです。翻訳とともに語り出される言葉を、技術と結びついた芸術を、想起から紡がれる歴史を、彼の問いを受け継ぎながら考える手がかりとなる五冊をご紹介します。【選者:柿木伸之(かきぎ・のぶゆき:1970–:西南学院大学教授)】






国家と宗教の関係について考える
- お気に入り
- 35
- 閲覧数
- 2719
「世俗」と「宗教」という二分法自体に疑問を差し挟み、それが成立する言語的空間自体を「世俗主義」というイデオロギーとして告発する、宗教人類学者タラル・アサド。彼の近著『リベラル国家と宗教』を出発点に、国家と宗教の関係について考えてみる。【選者:[カリ]田真司(かりた・しんじ:1966- :國學院大学教授)[カリ]は草かんむりに列】


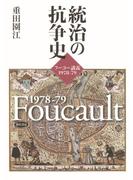



政治とポップカルチャーの古くて新しい関係を考える
- お気に入り
- 39
- 閲覧数
- 4016
政治とエンタテインメントの関係はメディアテクノロジーの進展により飛躍的な変化を遂げています。現実と虚構の境界がさまざまな仕方で揺らいでいるいま、そこにはどのような可能性と陥穽があるのでしょうか。政治とポップカルチャーが交錯するダイナミックな地平を探るために、いま改めて手にとってほしい5冊を選びました。【選者:清水知子(しみず・ともこ:1970-:筑波大学准教授)】


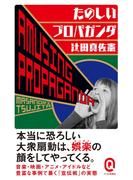
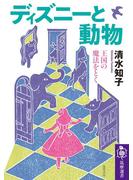


植民地の群衆から第三世界の民衆へ
- お気に入り
- 24
- 閲覧数
- 2431
ソーシャル・メディア誕生の前後で、集まることの政治性は変化したのだろうか。「暴徒」や「群衆」としてフレームアップされるのはどのような人びとなのか。19世紀半ばのイギリスの植民地統治から20世紀半ばの冷戦と植民地解放闘争の時代に遡って考えてみたい。【選者:吉田裕(よしだ・ゆたか:1980-:カリブ文学/文化研究)】


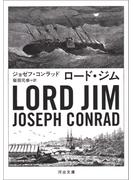

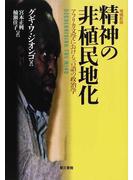

カトリーヌ・マラブーによる哲学の可塑性
- お気に入り
- 40
- 閲覧数
- 5313
カトリーヌ・マラブーはドイツ・フランスの近現代哲学と脳科学の可能性を探究する哲学者。ジャック・デリダのもとで執筆した博士論文『ヘーゲルの未来』以来、形の贈与と受容の運動を示す「可塑性」概念に着目してきました。マラブーの思索とともに、哲学の変形可能性を体感してみましょう。【選者:西山雄二(にしやま・ゆうじ:1971-:首都大学東京教授)】





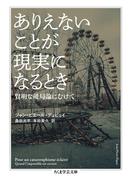
全体性に抗い、穴を穿つために。
- お気に入り
- 35
- 閲覧数
- 2963
「個と全体」は哲学の重要なテーマであり、政治的な「全体主義」に対しては様々な研究があります。個人の行動履歴がデータベース全体の一部になるような現状にも、どこか息苦しさを感じないでしょうか。全体性に穴を開け、風通しを良くしてくれるような著作を選びました。【選者:中村大介(なかむらだいすけ:1976-:豊橋技術科学大学准教授)】






シモンドン哲学を「二回り、三回り外」へと開くために
- お気に入り
- 19
- 閲覧数
- 3635
ジルベール・シモンドンは、第二次大戦後のきらびやかな思想潮流に乗ることはなかったものの、現代的なポテンシャルがあったのか、21世紀になって「再発見」されつつある哲学者です。ここではシモンドン哲学をすこし外へと開いてみるための5冊を紹介します。【選者:宇佐美達朗(うさみ・たつろう:1988–:日本学術振興会特別研究員)】


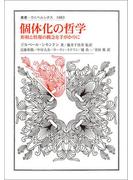

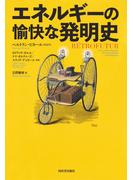

国際的なことは個人的なこと:ジェンダーが世界を動かす
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 3039
国家安全保障、外交、貿易、植民地化と脱植民地化、軍事占領。これらはすべて「ある種の私的関係とされるものに依存している」と政治学者エンローは論じます。「高度な政治力学」(とされているもの)を日常生活から読み解くジェンダー研究書5冊をご紹介します。【選者:望戸愛果(もうこ・あいか:1980-:立教大学アメリカ研究所特任研究員)】




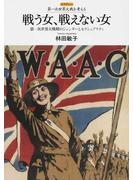
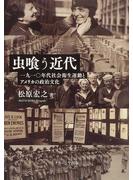
現代フランス哲学のなかに息づくドイツ哲学
- お気に入り
- 44
- 閲覧数
- 4681
20世紀以降のフランス哲学の成立において、いわゆる3H(ヘーゲル、フッサール、ハイデガー)をはじめとする近現代ドイツ哲学の輸入が決定的な役割を果たしたことはよく知られています。そこで、その輸入過程を教えてくれる重要な本をご紹介します。【選者:峰尾公也(みねお・きみなり:1986-:早稲田大学非常勤講師)】


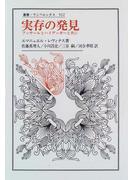



愛と哀悼――不可能なものの共同体のために
- お気に入り
- 20
- 閲覧数
- 3036
(友)愛をめぐって、あるいは死を、神を、恍惚をめぐって、現代フランスの哲学者ジャン=リュック・ナンシーが、いまなお多方面にインスピレーションを吹き込んでやまぬ思想家ジョルジュ・バタイユと格闘する。二人の磁場に引寄せられたいくつかの書物を紐解いてみよう。【選者:柿並良佑(かきなみ・りょうすけ:1980-:山形大学専任講師)】


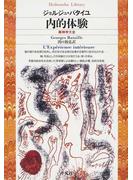



「真理(真実)」と「生」の関わりを考える
- お気に入り
- 43
- 閲覧数
- 5964
気候変動や感染症拡大の状況のなか、科学的知見は人々の行動にいっそう影響を与えている。他方、政治経済的な要請が科学的見解に反する形で人々の行動を促すときもある。「正しく(真理とともに)生きる」とはどういうことか、古代から今に至る議論を手がかりに考えてみたい。【選者:大橋完太郎(おおはし・かんたろう:1973-:神戸大学准教授)】



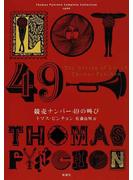


P4CからC4Pへ
- お気に入り
- 26
- 閲覧数
- 3618
子ども、患者、女性、動物、異文化、等々――哲学は前世紀以降、みずからの歴史が見落としてきた存在を考えなおし、救い上げることでどうにか命脈を保ってきた。哲学者が子どもに教えを授けるのでない。子どもが哲学者に発想を授けてくれるのである。P4C (philosophy for children)からC4P (children for philosophy) へ。【選者:澤田哲生(さわだ・てつお:1979-:富山大学人文学部准教授)】




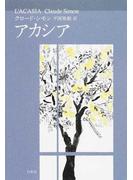
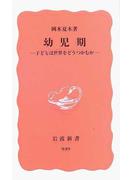
女たちの英文学――個と、集合性と
- お気に入り
- 40
- 閲覧数
- 6245
ジェイン・オースティンにヴァージニア・ウルフ――世界的に知られる女性作家を生んだ「英文学」。同時にそれは、無数の女性たちによって読み継がれ、支えられてきました。女性作家研究だけではない、多様なアプローチの研究によって再発見された女性たちの姿をご紹介します。【選者:中井亜佐子(なかい・あさこ:1966-:一橋大学教授)】





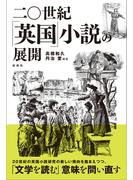
哲学カフェには考えるに値する論点があるか?
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 4955
「哲学カフェなんてたんなるおしゃべり会でしょ」――そんな陰口をときどき耳にします。何を隠そう私自身がこの疑念を完全には払拭できていません。それでも、アウトリーチのようにたんに哲学カフェを行なうだけではなく、この営みが含みもつ思想的な論点を考え、書き留めたい。そんな思いを叶えるにあたって裨益した本をご紹介します。【選者:三浦隆宏(みうら・たかひろ:1975-:椙山女学園大学准教授)】



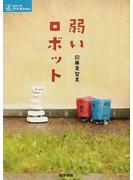


紙幣の肖像に選ばれたハリエット・タブマンて誰?
- お気に入り
- 7
- 閲覧数
- 3735
ハリエット・タブマンは奴隷として生まれ、一人で逃亡した後、仲間の奴隷たちを命がけで救い出したことで知られています。文盲で持病があったのに一度も捕まらず、南北戦争ではスパイとして活躍しました。彼女の人生や時代背景について知るための、いま購入可能な五冊を選んでみました。【選者:篠森ゆりこ(しのもり・ゆりこ:1967-:翻訳家)】