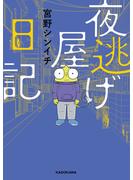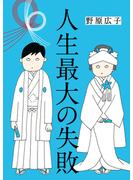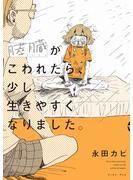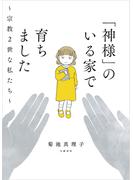ブックツリー
Myブックツリーを見る本の専門家が独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの”関心・興味”や”読んでなりたい気分”に沿ってご紹介。
あなたにオススメのブックツリーは、ログイン後、hontoトップに表示されます。
日本を代表するファンタジー作家・上橋菜穂子の壮大な物語を堪能できる本
- お気に入り
- 10
- 閲覧数
- 1011
作家であり文化人類学者でもある上橋菜穂子は、児童文学からファンタジー、SFまで幅広い作品を発表しています。彼女が描く物語の最大の魅力は、架空の世界でありながら、時代背景や歴史・文化が詳細に描かれ、「本当に存在しそう」と自然に思えるほどの説得力にあります。彼女の紡ぐ架空の世界は、壮大でありながら現実の社会問題が見え隠れしているのも特徴です。代表作である「守り人シリーズ」の『精霊の守り人』は、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、野間児童文芸賞新人賞、路傍の石文学賞などを受賞しています。上橋菜穂子が作り上げた世界を一緒に旅しましょう。
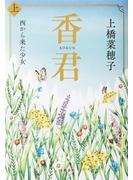
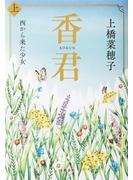
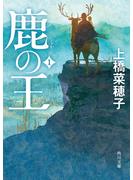
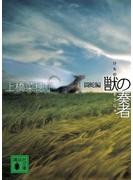

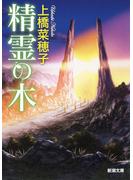
物事の見方がぐっと深まる。わかりやすくて読みやすい社会学の入門書
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 166
社会学とは、社会のあらゆる事象を対象にするため範囲が膨大で全容がつかみにくいもの。しかし、社会学を知ることで、歴史や時事問題、ふだんの生活で起こるあらゆる事柄に対する解像度がぐっと深まります。興味はあるけど、いったいどんな学問?と思っている方にぴったりの入門書を紹介します。


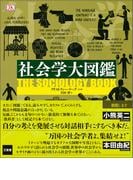
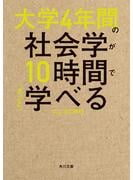


現代を逆照射する。はじめてのディストピア海外小説
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 823
ディストピア小説には現実を寓話的に描くことで批判したり、未来を予見したりする側面があると言われています。数ある傑作の中には、今ある現実がいつディストピアに変わってもおかしくない!という危機感を感じさせるものも多くあります。今の現実がディストピアにならないための教訓が得られる、そんな海外小説を紹介します。
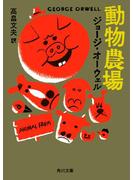
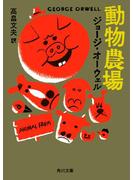


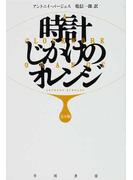
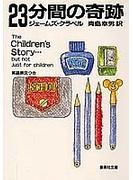
日々のモヤモヤを吹き飛ばす!女性が前を向く力を与えてくれる本
- お気に入り
- 3
- 閲覧数
- 382
社会の常識はマジョリティの意見によって形成されるもの。そのため日常生活は、多数派にとって快適に暮らせる工夫で満たされています。先進国の中でもジェンダー・ギャップ指数の低い日本では、女性はいまだマイノリティといえるかもしれません。ここでは、さまざまな立場の女性たちをエンパワーメントする本を集めました。
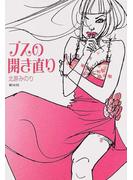
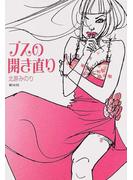

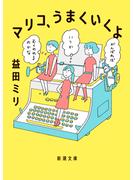


社会学者・宮台真司の思想をたどる入門書
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 337
日本の社会学者として、トップクラスの知名度を誇る宮台真司。彼の名が知られるきっかけとなったのは、1990年代中頃に急増した援助交際についての分析でした。扱っている題材ゆえに賛否が多いですが、彼の著書を読めば、論理的で実効性のある議論をしていることがわかるでしょう。ここでは、宮台真司の思想をたどるための入門書を紹介します。


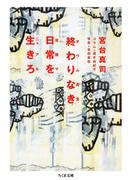


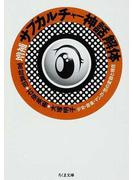
思い出の品々からお墓まで・・・実家の片づけが気になったときに読む本
- お気に入り
- 10
- 閲覧数
- 949
大量の荷物と暮らす親や空き家になった実家が、気になったことはありませんか?「いつか実家を片づけなければ」と思いつつ、先延ばしにしている方にオススメの本を紹介します。効率的な片づけ方から、親や親戚との軋轢を避ける方法まで、親が健在でも、亡くなったあとでも参考になるはずです。読めば片づけがはかどり、気持ちも軽くなるでしょう。
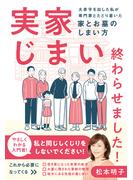
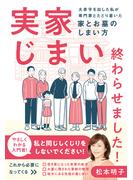

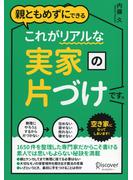
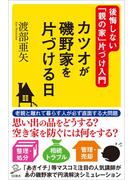

《どこかではないここ》にある「自分のココロスタイル」のために読みたい本
- お気に入り
- 18
- 閲覧数
- 3468
2020年代という新たな時代が始まりました。個性の輝きが総体の美しさを創り、ダイバーシティ&インクルージョンは一人ひとりのチカラで育まれていきます。《ここではないどこか》ではなく、《どこかではないここ》にある自分のココロスタイル――その栄養となる書籍をセレクトしました。生きることについて、いまじっくり考えてみませんか?





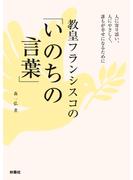
脅威?それとも救世主?AIについて理解を深めるための本
- お気に入り
- 21
- 閲覧数
- 3758
スマホが天気を教えてくれたり、ロボットが掃除をしてくれたり、人工知能(AI)の発達で世の中は便利で快適になってきました。ところが「人工知能の進化は人類の終焉を意味する」と、天才物理学者のホーキング博士はかつて警告しています。AIは人類の脅威なのか、それとも救世主なのか。AIについて理解を深めることができる本を紹介します。
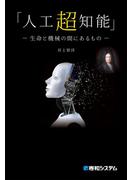
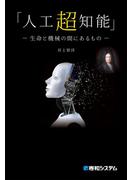

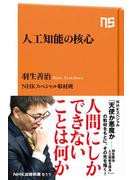

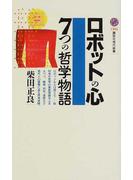
現代イギリスの文化と不平等を明視する
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 3884
先進諸国が多文化社会へと変容していくなか、文化と不平等の関係を扱う文化研究への関心は高まる一方です。イギリスの21世紀の研究動向を中心に、最新の文化研究から見える社会のいまをご紹介いたします。【選者:相澤真一(あいざわ・しんいち:1979-:中京大学現代社会学部准教授)、磯直樹(いそ・なおき:1979-:日本学術振興会特別研究員)】



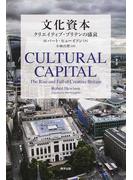
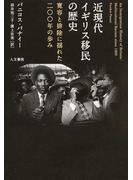

カルト教団に関わる人間模様から、人間の弱さや罪深さを考えさせられる小説
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 16642
人は背負いきれない悲しみや苦しみを感じると、心のよりどころを求めてしまう生き物なのでしょうか?時にどう考えても怪しいものや科学的根拠のないもの、目に見えないものを信じて身を委ねてしまいます。新興宗教やカルト宗教を題材にした物語を通じて、人の心の弱さ、罪深さについて考えさせられる小説を紹介します。
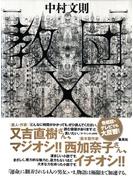
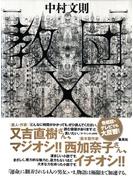
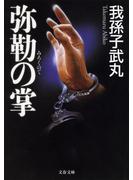
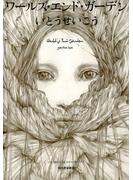


アメリカとは結局どんな国なのか?その成り立ちと現在を知る本
- お気に入り
- 0
- 閲覧数
- 28
拡大する経済格差、人種差別、テロの脅威、政治対立などにさらされて、アメリカの民主主義が揺れています。長年、世界の警察として国際関係に関与していたアメリカの変化に、世界も大きく動揺しています。アメリカとはどのような国なのか、この先どうなっていくのか。日本の政治経済にも大きな影響を持つアメリカを知るための本を選びました。





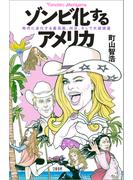
まずは新書から始めよう。民主主義をイチから学べる入門書
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 67
昨今、民主主義の危機がさまざまなシーンで叫ばれています。ポピュリズム、コロナ禍における政府の強権、非民主主義国家の代表的存在・中国の台頭など、明らかに民主主義に対する信頼度が揺らいでいる状態です。ただ、民主主義は何度も危機に陥りながら、復活してきた政治形態であるのも事実。改めて民主主義を知るための、入門向けの新書を紹介します。
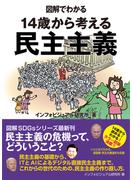
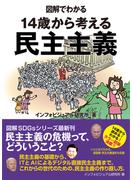




これから投資を始めたいあなたに!新NISAの活用術が学べる入門書
- お気に入り
- 0
- 閲覧数
- 56
非課税期間が決められているなど、多くの制約があったNISA。2024年からの新NISAはいつでも口座開設が可能となるなど、利用のハードルがぐっと下がりました。そこでここでは、新NISAの制度やこれまでとの変更点をまとめた本を紹介します。これまで使っていた方もこれから始めてみたい方も、一緒にNISAを学びましょう。
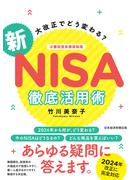
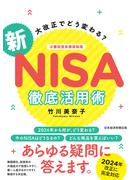
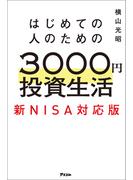
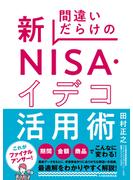
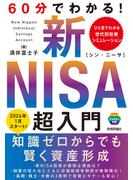
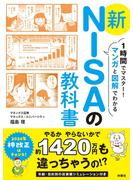
加速する現在のAI技術を学ぶ。生成AIの入門書
- お気に入り
- 0
- 閲覧数
- 47
1950年代以来、半世紀以上にわたって研究されてきたAI。ここにきてディープラーニングなど、方法論のブレイクスルーが続発し、現在盛り上がっている生成AIにまでその技術は進化しました。生成AIとは学習データをもとに、コンピューター自身がコンテンツを考え出す新しい技術。そんな生成AIについて学べる入門書をそろえました。




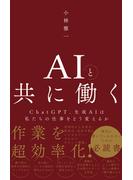

疲れた、時間がない、娯楽と情報が多すぎる?迷える現代人の読書を考える本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 219
本が読みたい、読むべき、なのに・・・。読書離れや書店の衰退が叫ばれる昨今、一人ひとり、さまざまな理由で本に手が届かなくなっていることでしょう。しかしそうした現状に対し、原因や実態を的確に言語化しつつ寄り添ってくれる本も存在します。これからも前向きに読書を続ける、その支えにもなってくれる本を紹介します。






家事育児の分担にセックスレス・・・すれ違う夫婦を描いたコミック
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 134
夫婦のすれ違いを描いたコミックを集めました。すれ違う理由は、セックスレスに家事育児の分担などさまざま。長い結婚生活の間に、ほとんどの夫婦が直面するであろう問題が取り上げられています。それぞれの夫婦の問題への向き合い方、それによって関係がどうなっていくのかが読みどころです。夫婦関係に悩む方の参考になるかもしれません。
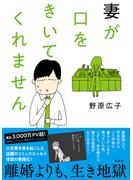
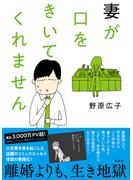

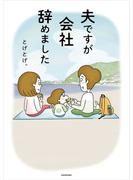
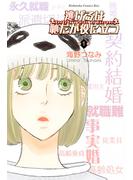
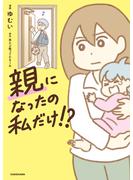
予備群も入れると約2000万人!?糖尿病の正確な知識がわかるようになる本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 73
予備群も入れると約2000万人にもおよぶと言われている糖尿病患者。ここでは、国民病ともいえる糖尿病を知るための本を集めました。発症しても初期のころは自覚症状は少ないですが、気づいたときには腎症や網膜症などの重大な合併症を招き、なかには失明、人工透析に至る人も少なくない非常に怖い病気です。糖尿病について、正確な知識を知ることから始めてみましょう。


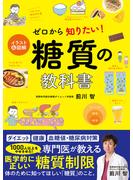
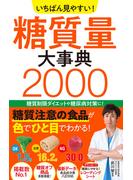
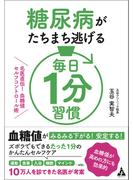
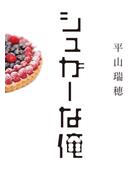
「その言い方ちょっと」と思ったら。マイノリティが社会に対抗するための本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 181
差別や格差を訴えたとき「どっちもどっち」「そんな言い方じゃ聞いてもらえない」と、事実よりも言い方や態度を問題にするような批判に出会ったことはありませんか?有色人種や女性など「マイノリティ」の立場の人ほど、そんな目に遭いやすいと言われています。ここではそんな言葉に対抗するための、実用的で機知に富んだ本を集めました。



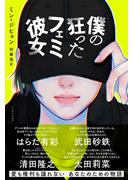

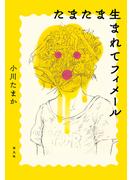
資産を増やしたい。素人でも投資が正しく学べる本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 93
「人生100年時代」「老後資金に2千万円必要」といわれ、誰もが投資の知識が必要な時代です。しかし、いざ投資を始めようと思っても、なかなかハードルが高いもの。そこでここでは、投資を始めるにあたって読んでおきたい入門書を紹介します。読めば、投資への第一歩を後押ししてくれるはずです。
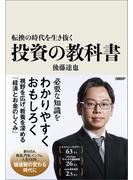
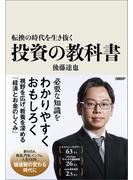
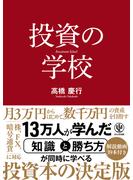

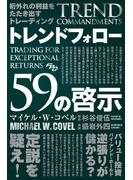
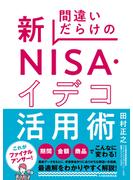
多様化はここから。海外出身作家による「日本」を知ることができる本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 227
第二言語として日本語を使用する作家や、日本在住の海外出身作家による本の刊行が増えています。それら本は日本語を使って日本について書かれているのに、ちょっと不思議なイメージが立ち上ります。同じだけど、少し違う。これからの共生社会を考えたい方にオススメの本を紹介します。


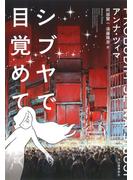
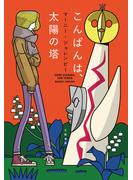
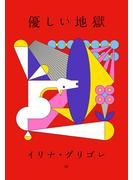

窮屈さを感じていませんか?女性の身体のままならなさを描いた物語
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 210
自分の身体は、生涯つき合っていかなければなりません。しかしなかには、周りの視線が気になっていたり、コンプレックスを感じていたり、身体の存在を窮屈に思っている方もいるはずです。特に女性は、そのストレスにさらされる場面も多いはず。ここでは、そんな「女性の身体のままならなさ」を描いた小説を紹介します。


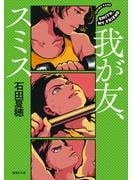
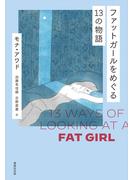
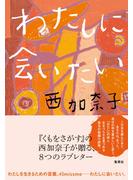
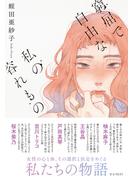
無意識に人を傷つけてしまう前に。自分の差別意識と向き合うための本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 141
互いの差異をそのまま受け止め、尊重しながら共生することは、よりよい社会を作るために必要不可欠な姿勢です。しかし多様性が重要だと叫ばれる現代においてもなお、人は無意識のうちに差別をしてしまいます。そこでここでは、差別とは何かを問い、自分の差別意識と向き合うために読んでおきたい本を紹介していきます。
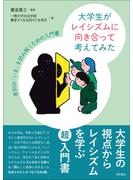
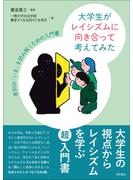
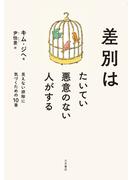

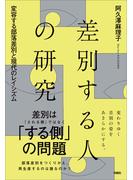

ナチスの暴走から理性を分析。フランクフルト学派を知るための本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 83
ヒトラーという独裁者の下で行われたユダヤ人虐殺をはじめとするナチスの暴虐は、ドイツ国内はもちろん、国外でも未だに問題提起を投げかけています。関係者の多くがユダヤ人ということでドイツからアメリカへの亡命を余儀なくされ、亡命先で研究を続けたフランクフルト学派。現在にも通じるその業績を知ることができる本を紹介します。


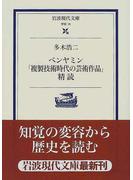



その役割とは?自衛隊の現状を知るためのノンフィクション
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 71
1954年に発足された自衛隊。発足当初から現在では、自衛隊の任務や役割は大きく様変わりしています。そうしたなかで自衛隊員は何を見てきたのか?ここでは、特殊な世界に生きる自衛隊員の素顔を知ることができるノンフィクションを集めました。読めば、自衛隊の現状が見えてくるはずです。





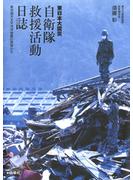
それって本当に正しいの?デマや誤解を検証する術を学べる本
- お気に入り
- 4
- 閲覧数
- 226
メディアやSNSで一度は見聞きしたあの話、こんな情報、自分でも広めたくなる説。しかし、それは本当に正しいものですか?事実よりも印象が先行してしまいがちなこの社会でたしかな知識を得るには、事実を自ら検証する作業が重要です。誤解や流説を看破するのに役立つ良書を紹介します。



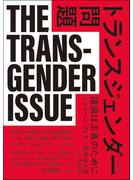


ままならない体で物語り、生きる。重度障害について考えさせられる文学
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 220
さまざまな人生を記す小説や文学のなかでも、車椅子や介護を必要とし、寝たきりで日々を過ごす重度障害者に関する作品は、数こそ限られているものの古くから存在します。心身の苦しみや差別にさらされながら綴られた文章は、社会全体の障害者観に一石を投じています。そんな強靭さと鋭さを備えた本を、ぜひ一度手に取ってみてください。


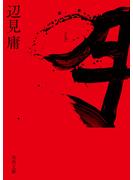
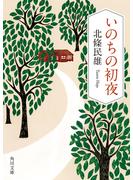

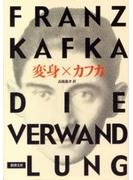
これからの人も渦中にいる人も読んでおきたい介護の参考書
- お気に入り
- 3
- 閲覧数
- 202
身近な人や自分の介護を考えるときに役立つ本をまとめました。ひと口に介護といっても、在宅や施設、遠距離・・・と、事情は人それぞれ。多様なケースの介護本を集めています。介護制度、遠方の親にできること、金銭問題や接し方など参考になる情報が満載です。介護に悩む方は解決のヒントを得られ、これからの方には必要な備えがわかります。
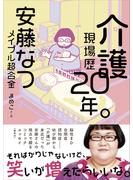
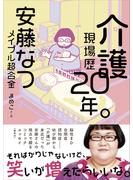
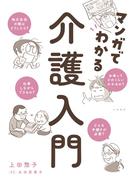
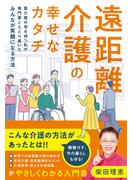

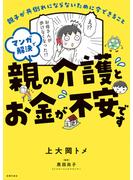
異文化との共生を探る。日本で働く外国人と住みよい社会を作るための本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 183
日本で働く外国人は2023年に初めて200万人を超え、今後ますます増えていくことでしょう。お隣さんが外国人ということも珍しくなくなるはず。とはいえ、定住する外国人と日本人の相互理解はまだ十分ではなく、トラブルも耳にします。どうすればお互いを知り、住みやすい社会を作ることができるのか、そのヒントが得られる本を紹介します。
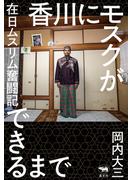
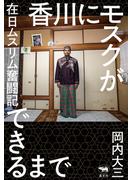


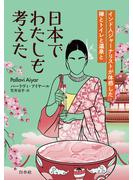

国家を持たない最大の民族「クルド人」を知るための入門書
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 253
昨今、日本国内でも難民問題に揺れるクルド人。その存在を、あなたはどこまで知っていますか?4000万人という一国家規模の人口がありながら独立は叶わず、世界中に離散し、辛酸をなめる民族です。どのような意見を持つにせよ、まず知るべきはその複雑な立場と歴史、そして当事者たちの現実。その入門的な本を紹介します。



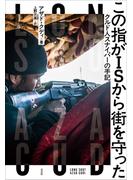


ヘビーな内容でも読みやすい!はじめての社会派コミックエッセイ
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 1069
宗教二世、児童虐待の本と聞くと、深刻でヘビーな内容で、手に取るのもためらいそうになります。しかし、コミックエッセイならマンガ仕立てのストーリーとイラストのおかげで、ポップかつ読みやすい仕上がりに。あなたの知らない現実社会を、コミックエッセイを通して覗いてみませんか?