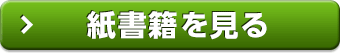- 電子書籍ストア hontoトップ
- キャンペーン・特集一覧
- 阿部和重×伊坂幸太郎『キャプテンサンダーボルト』
キャプテンサンダーボルト
阿部 和重(著), 伊坂 幸太郎(著)
税込価格:【紙書籍】1,944円/【電子書籍】1,599円
いったい何が起きたのか?
阿部和重と伊坂幸太郎、現代を代表する人気作家の二人が、四年を費やして執筆した合作書き下ろし長編900枚。
2010年代、最強のエンターテインメント作品。

キーワードを見逃すな!『キャプテンサンダーボルト』特報動画!
写真家・浅田政志×『キャプテンサンダーボルト』短編映像
写真家・奥山由之×『キャプテンサンダーボルト』短編映像
ダンサー、映像作家・吉開菜央×『キャプテンサンダーボルト』短編映像
2人の人気作家が、どのようにして出会い、どうして合作を手掛けることになったのか――?
4年間の合作執筆を通じて感じたことなどを聞かせていただきました。

進行:株式会社コルク 代表取締役副社長・三枝 亮介氏

―― 伊坂さんはお客さんの前で話すのがほぼ初めてとなりますね。
阿部 緊張、してそうですね。大丈夫ですか(笑)。
伊坂 いやいや……大丈夫です。
―― 会場のみなさんに事前に質問を書いていただきました。どんどんそれに答えていただければ。まずは、作品には犬が登場して印象的ですが、その経緯は?
伊坂 もともとは、原稿を書いている途中で僕がふと、ふたりで楽しく書いているけれど、これを女の人が読んでも面白いのかな? と思って阿部さんにそう言ったら、すごく動揺されてしまって。
阿部 人生で五本の指に入るほどうろたえました。僕の作品は女性受けが悪いとしばしば指摘されるので。今回は伊坂さんと一緒だから頼りにしていたら、伊坂さんのほうからそう言われてしまった。どうしよう! と考えた結果、犬とか出すのはどうですかね? ということになった。結果的に、犬を出すことで話が生きたのでよかった。
伊坂 後半の展開なんて、もう犬頼みですからね(笑)。

―― ライバル意識はありますか、というご質問もきています。
伊坂 はい、ありますね。
阿部 年齢も近いですし。
伊坂 僕からすると阿部さんはすごい人なので、嫉妬なんかもすごくありました。だからご一緒できてとにかくうれしい。
阿部 僕のほうがデビューは先なんですが、すぐに伊坂さんがヒュッと走って先に行ってしまった(笑)。ただ、作品世界に対する共通点はけっこうあるんじゃないかと、勝手に思っていました。好きな映画とか小説も重なっていて、親近感はありましたしね。その伊坂さんが僕の『ピストルズ』という小説を読んでくださって、感想までいただいたことが、この合作につながっていったんですよ。
伊坂 今回の作品では、お互いの書いたものをどんどん改稿していきましたけど、これはやっぱり阿部さんとじゃなければできなかったと感じます。僕が「こういうふうにしたらいいんじゃないか」ってアイデアを言ったときに、人によっては何でもオーケー、オーケーと言うかもしれないけれど、阿部さんの場合はちゃんと「それはよくないよ」と言ってくれる。頭ごなしじゃなく、作品のためを思って「よくない」と言ってくれるんです。
阿部 我々はどちらも、かなりスタイルのはっきりしたタイプの作家だと思うんですね。そのふたりがひとつの物語を書くというのは、かなり繊細なものが求められるところがある。ギリギリのバランスで組み立てられているところがやっぱりあるんです。書いていると、ふたつの正解が出てきちゃったりするわけで、そういうときにどうするべきかと議論にはなった。ただ、よかったのは、話していてお互いイチから説明する必要がないところ。同業者でもそういうことって案外珍しい。同じ業界に属していても、けっこう説明しないと伝わらない場合もありますから。そういう意味でも、伊坂さんとでないと合作は不可能だったなと感じていますね。

―― プロットづくり、執筆、推敲という過程、それぞれどんな気持ちでしたか。
伊坂 最後の改稿がたいへんでしたね。書き上げてから、まず僕が全部一気に直して、そのあと阿部さんが直していったんですけど、その段階で問題点がたくさんあった。ふたりで意見の違うところもあって、ほんとうに頭から煙が出るような感じでした。
阿部 合作だからこそ、微妙に重なっていないところがやっぱりあって、そこを調整しないと辻褄が合わなくなってしまう部分もあって。客観的に読んでみると、お互いに同じことを想定しているようでいて、やはり重なっていない部分もあるんですよ。小説というのは、絵があってそれを見ながら書いてるわけじゃなくて、言葉を頼りに作品世界を想像し、それをさらに言葉に置き換える作業ですから。逆にいえば、よくこれがひとつにまとまったものだなと思います。そういう意味でも「奇跡の合作」だという実感がありますよ。
伊坂 阿部さんが根をつめて改稿している時期に、夢を見ましたよ。阿部さんの家へお邪魔するんですけど、そこで阿部さんがシチューを煮ている。よく見たら、原稿をぐつぐつと煮ていて、「もう少しでできるよー」って。僕は夢のなかで思いました、「そうか煮込むのか。さすが阿部さんは違うなあ」。
阿部 おいしくできていたらいいんですけどね。

―― おふたりはなんて呼び合っているんですか? との質問もありますが。
阿部 バラしちゃっていいのかな。僕は、「コウチャン」と(笑)。
伊坂 僕は「カズ」ですね(笑)。いえいえ、ふつうに呼んでいますよ。でも、けっこうお互いに褒め合いますよね。ほかに誰も褒めてくれませんから。ふだん作家はひとりでやっているのに、こんかいはふたりでいられるというのがとにかく楽しくて。
阿部 作家同士だと、素直に言葉を信じられるところはありますよ。

―― 作家の仕事は通常、本が発行されるまでがメインですが、今回は刊行後もプロモーションを積極的にされていますね。どのようなことを?
伊坂 各地で書店回りをしています。まあ、思い出作りみたいな面もあって。あと、僕にとって珍しいのはトークショーですね。こういうのは得意じゃないので。でもがんばってやろうと思ったのは、今回の作品は合作ということで、企画モノと捉えられる恐れもあった。そう思われたらさびしい。なぜなら、僕も阿部さんも、これはすごく面白いものだと思っているので。本気なんだっていうことを伝えられる場があるといいなと考えていて、こういう苦手なこともやってみることにしました。
阿部 そこは課題でしたね。本気感がとにかく伝わってほしかった。それで伊坂さんは、執筆途中からトークショーもやってみようと積極的に提案してくださって。
伊坂 はい。いま、それをちょっと後悔してますけど(笑)。いや、でも感慨深いです。この作品はいつ完成するのかなと思いながら、ずっと長くやってきたので。
―― おふたりはどうして作家になろうと思われたのかも、教えてください。
伊坂 本を読むのが好きだったので、自分でも書いてみたいと思ったんですよ。だから、発表したいというよりは書きたいという気持ちが強かった。ただ、書いたら誰かに読んでもらいたいとも思うので、賞に応募したという流れですね。
阿部 僕はもともと映画が好きで、子どものころから映画を作る側にいきたい、映画監督になりたいと思っていたんですね。実際に映画の専門学校にも通いましたし。そのときにシナリオを書いて、友達に見てもらうみたいなことをやっていて、そのうちに書いて物語の表現をすることの面白さを感じるようになっていった。そこからですね、小説を意識するようになり、ただ書くだけでも表現できるんだなと気づいた。
―― いまの自分を小学生のころの自分が見たら、どう思うでしょうか。
伊坂 びっくりしているんじゃないですかね。ふつうの小学生だったので。なんでこんなところで話しているの? って。
阿部 僕はこんな、ずいぶん恥ずかしいことになってしまって……。実際、僕には2歳半の子どもがいるんですけどね、その子に見せられる小説がないんですよ、これまで書いてきたものの中には。子どもにあまり読ませられない作品ばかり。今回、伊坂さんの力をお借りして、ようやく子どもに「これも書いたんだよ」って渡せる本ができた。間に合ってよかったなあと、心からホッとしております(笑)。