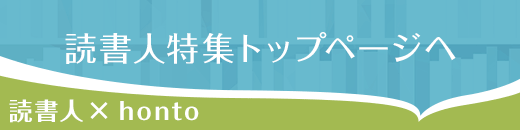2013年にフランスで発売され、翌年英語版の出版直後にアメリカで大ベストセラーとなったトマ・ピケティの『21世紀の資本』。この邦訳がみすず書房から上梓された。日本でも既に好調な売れ行きで、700頁を超える学術書としては異例のヒットをつづけている。また解説本や入門書なども邦訳刊行と同時に出版された。日本でも2014年夏から、雑誌などで特集が組まれ「ピケティ・ショック」とも評された。『21世紀の資本』は果たしていかに読まれるべきなのか。訳者のひとりである山形浩生氏と、早くから同書に注目した慶應義塾大学総合政策学部教授・堀茂樹氏、『本当の経済の話をしよう』の著書を持つ栗原裕一郎氏(若田部昌澄氏との共著)、3人に話をしてもらった。
トマ・ピケティ『21世紀の資本』
堀: 私は経済については門外漢なんですが、『21世紀の資本』はフランス語の原典で読みました。一般人にもわかるように書かれていて、非常に勉強になりました。
栗原: 教科書的な感じもありますよね。特にⅠ部は。
山形: GDPの定義についてなど、かなり丁寧に書かれています。その辺りの知識をある程度持っている人は、第Ⅰ部を飛ばしてⅡ部Ⅲ部から読んだ方が入りやすいかもしれませんね。格差の話や少し下世話な話題もありますから、そちらを読んで、用語の定義がわからなくなったらⅠ部に戻る。
堀: 経済学の素養に欠ける私には、第Ⅰ部は勉強になりましたよ。この本を読んで第一に感じたのは、テクニカルではなく啓蒙的だということでした。2013年の冬、来日したエマニュエル・トッドに薦められたんです。
それで今年の春先、読んでみて大変感心しました。が、まずは、山形さんがこれだけの大著をこの短期間で訳されたことに頭が下がります。本当にすごい貢献だと思います。理論的には、私にも理解できるぐらいだから、学問的にそれほど難しいことを言っているわけではないと思うんですね。ただ、とにかく膨大なデータを集めて事実を示した。そこにこの本の意義があるのであり、経済学というよりは、言ってみれば歴史家の仕事なんじゃないかと思いました。ここまでデータを持って来られると、事実に屈服せざるを得ない。因果関係まで説明できなくとも相関関係で説明していく。そういうタイプの仕事だと思いますね。
山形: そうですね。確かに、経済学的な理論上のモデルではこうなっているはずだということに対して、ピケティはそれとはまったく違う事実を次々と出してくる。そこがこの本の醍醐味でもありますね。

栗原: 内容的には、すごいシンプルですよね。資本収益率r(資産から得られる収入=利息・配当金・家賃など)は経済成長率g(給与所得から得られる賃金)を上回ってしまうものであり、格差は必然的に広がっていくものである。この「r>g」について200年の歴史にわたってデータ分析して、格差はどうなっていくかという話をしている。
山形: ただそうは言いつつも、アメリカでは資本収益率がそれほど上がっていない。r>gの傾向が明確に出ていないのにもかかわらず、格差が広がっているという話もしていますね。例外とするにはアメリカは大き過ぎるし、そこはピケティの理論の弱いところかもしれません。
栗原: r>gについて、ヨーロッパと日本では、歴史的に大体同じようなグラフを描くんだけれども、アメリカだけはちょっと違う。資本収益率が低いわけですよね。それなのに格差は広がっている。
山形: 本の中では、アメリカの格差の原因は企業の重役報酬が極端に高くなったこととされている。

堀: アメリカに関しては、この本を読んで極めて驚いたことがあるんです。独立の時の人口が300万人しかなかった。現在までに百倍にも増えている。当時日本もフランスも3000万人ぐらいですよね。なおかつフロンティアだから面積も物凄く増えている。あれほど極端に面積が増えた国は、歴史上にない。だからアメリカ合衆国を、それまであったヨーロッパのネーションと比較するのは難しいと思いますね。特に19世紀、20世紀までは同じ条件下になく、アメリカに特殊の原因があると考えるしかないと思いました。
山形: 働き盛りの若い移民がどんどん来たことによって栄え、人口がずっと増えつづけた。それが経済成長を支えた。
堀: しかしアメリカも今後は、イギリスやフランスや日本と似たようなタイプになっていくでしょうね。
栗原: ピケティも本の中で、アメリカが英・仏と同じような推移を辿っていくだろうと言っていますよね。資本が蓄積されると、どこも同じようなr>gの比率になっていく。

山形: そうですね。僕は普段開発援助の仕事をしていて、世界各国の情勢を見る機会があるんですけれども、各国内での格差はどこも上昇している。でも世界的に見ると、中国・インドや発展途上国の躍進で、貧困層はかなり減っている。結果として全世界の人口で見れば、格差は縮まっているというのが今の基本的な見方です。ピケティもその認識を共有しています。でも将来的に各国の経済成長が進んでくれば、どこでも国内の格差は大きくなる。それはどの国でも再現されるという話をしている。だから最近の国際的な格差の縮小の話はあまり考えないという理屈で議論を進めているところはありますね。
栗原: r>gという状況が前提であるなら、経済成長率gを上げないことには、ますます格差が広がっていってしまう。そこでまずはgを上げる方法を考えないといけない。
山形: あるいは資本に課税し、そこから分捕って再分配するということですね。
栗原: 資本を分捕って再分配するか、経済成長の促進をするか。これがピケティの最終的な解になってくるわけですよね。
山形: はい。ピケティの議論では、経済成長は今後当てにならないから、再分配の方式を主に考えるという理屈です。
栗原: たとえば今の日本の状況に当てはめて考えてみるとどうなるんでしょう。
レビューアープロフィール

山形浩生
東京大学大学院修士課程およびMIT不動産センター修士課程修了。大手調査会社に勤務し、途上国援助業務のかたわら、翻訳および各種の文章執筆を行う。著書に「貧乏人の経済学」など。一九六四年生。

堀茂樹
慶応義塾大学総合政策学部教授、アンスティチュ・フランセ東京講師、翻訳家。慶應義塾大学大学院修士課程修了。訳書に「文盲 アゴタ・クリストフ自伝」「悪童日記」など。一九五二年生。

栗原裕一郎
評論家。東京大学除籍。著書に「<盗作>の文学史」、『本当の経済の話をしよう』(若田部昌澄との共著)、『石原慎太郎を読んでみた』(豊崎由美との共著) など。一九六五年生。
週刊読書人おすすめ記事(外部サイト)

週刊読書人
http://www.dokushojin.co.jp/
最新号はこちらから購入できます!
http://www.d-newsdirect.com/list/23.html
週刊読書人とは…
「読書人」は、いわゆる知識人階級だけでなく、市井の読書層まで含めた「日常的に読書をたしなむ人々」の意味をもつ中国語に由来します。文学・芸術、学術・思想から一般書、サブカルチャーまで幅広く、文化界の最新トピックスを、第一線の研究者や著名作家による定評ある署名入り書評と、巻頭のロングインタビューや対談、座談会などで詳細に紹介します。署名入り書評掲載点数は日本一で、創刊1958年の伝統ある新聞です。