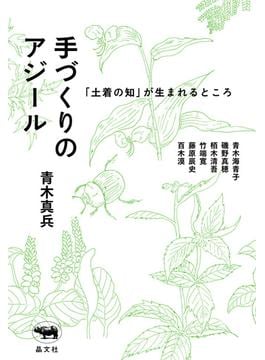- みんなの評価
 1件
1件
手づくりのアジール
著者 青木真兵
青木君たち、やっていることは「けっこう極端」なんだけれど、言葉の手ざわりがとてもやさしい。
だから話をずっと聴いていられる。──内田樹
注目の在野研究者・移住者・図書館主宰者による土着人類学宣言! あたらしい人文知はここからはじまる。
市場原理主義や、社会に浸透する高度なテクノロジーによる管理化に飲み込まれず、地に足がついたまっとうな生き方をするためには、社会のなかでの「アジール(避難所)」を自分たちの手で確保することが必要ではないか。
・スピードが最優先される「スマート化」にどう抗うか?
・これからの「はたらく」のかたちとは?
・研究と生活をどう一致させるか?……
奈良の東吉野村で自宅兼・人文系私設図書館「ルチャ・リブロ」を主宰する著者が、志を同じくする若手研究者たちとの対話を通じて、「土着の知性」の可能性を考える考察の記録。あたらしい人文知はここからはじまる。
ぼくらの直感は合っていました。合っていたからと言って世界が劇的には変わるわけではないのだけれど、でももうちょっと、この「土着の知」とも言うべき人間の生き物としての部分を認めないと、ぼくたちは生き残ることができないのではないか。社会を維持することだってできないのではないか。本書は『彼岸の図書館』で言語化でき始めたこの直感を、同年代の研究者と共有し、意見交換した記録です。(「はじめに」より)
【目次】
「闘う」ために逃げるのだ──二つの原理を取り戻す
対話1 逃げ延びるという選択 栢木清吾×青木真兵×青木海青子
対話2 これからの「働く」を考える 百木漠×青木真兵
「最強」とはなにか──山村で自宅を開くこと
対話3 「スマート」と闘う 藤原辰史×青木真兵
対話4 土着の楽観主義 竹端寛×青木真兵
手づくりのアジール──「自分のために」生きていく
対話5 生活と研究 磯野真穂×青木真兵
対話6 ぼくらのVita Activa??マルクス・アーレント・網野善彦 百木漠×青木真兵
山村デモクラシーII
手づくりのアジール
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
手づくりのアジール 「土着の知」が生まれるところ
2021/12/02 16:20
今の社会にモヤモヤしている人におすすめ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:dsukesan - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本で問われている現代資本主義社会への違和感や、そうした巨大なシステムに対してどの様なスタンスで生きることが、より楽しく生きられるのかという思索は非常に心地よく、分かりやすかった。
自然と人との共存というのを、ずっと私自身のテーマにしていたが、その中で社会のシステムをサステナブルに変えていくことと、そのシステムのオルタナティブにして社会の外側に立つことの意義というのを、この本を読んで改めて具体化することができ、また、著者の言う様に両者を行ったり来たりしたいと思った。
持続可能な調達やCSR経営は、資本主義社会を持続可能なシステムに変えていく取り組みで必要だし、他方で、東日本大震災の被災地を訪れて感じた資本主義経済のシステムのもろさとオルタナティブとして地方分散・自給自足の的生活が必要と感じた直感も大事だし、そうした両方のいずれかではなく、両者の間を行ったり来たりすることこそ、自分がしたいことなのだと、この本を読んで理解できた。システムは大切だけれども、システムから弾かれる存在は必ずあって、その弾かれたものが生きるオルタナティブな場が必要であり、そのオルタナティブな場が、システムを相対化していきやすい社会をもたらす。だから、一つの正解・合理性だけのシステムだけではなくて、オルタナティブが必要になるのだ。
こちらの本は、内田樹氏の「ローカリズム宣言」、平川克己氏の「21世紀の楕円幻想論」で知った、社会の在り方、都市と田舎などの二つの原理の焦点を持ち、共存させるという考え方を、実践しさらに両者を行き来することの価値・意義を教えてくれる本であった。自分のやりたいことは、正にこの二つの世界を行ったり来たりすることだということに気づかされて、勇気を頂くことができた。自分も、漸う、やりたいことの哲学的意義を整理し、また具体的な行動方針を明らかにすることができてきた、この頃の中で、本書は自分の考えを整理して動き出す準備を整えるのに役立った。
間を生きるということは、7~3バランスで行動の選択肢を広げてくこと、白黒思考からの脱却ともリンクしていて、認知行動療法的と通じるところがあって面白い。
この本を読んで、気になったのは次の言葉たち。
・ハンナ・アーレントの定義
「労働」自分の生活維持のため
「仕事」世界をつくるため
「活動」他者とコミュニケーションをするため
→自分は、「労働」で自給自足、「仕事」で森林認証、「活動」で地域活性化とブックカフェをやろうと思った。
・社会のあらゆる領域を資本主義理論に置き換えていくと、全体主義的になる
・人は「離床」によって、地縁・血縁というしがらみから自由になったが、個別性、身体性をおろそかにすることになった。そのため、個別性、身体性に根差した土着が必要。
・社会制度や公共秩序に縛られることで、それにそぐわないものが、病気や欠陥として疎外される。そして、ユングのいう「個別化」が進まない。皆が皆、スーパーカーではないのに、皆が高速道路をぶっ飛ばせるスーパーカーの様な働き方を求められている。そうではなく、自分なりに走れる道を自分で探す方が良い。働き方の多様性を考えることが大切。そして、一つの基準(生産性がある)ことだけが大切という価値観を内面化すると、働けない人を殺してしまうことにもつながる。
・自由の本質は、二つの原理を行ったり来たりできること。この自由を手に入れるためには、対立する二つの原理を全く別物として捉えるのではなく、連続性においてみることが必要となります。