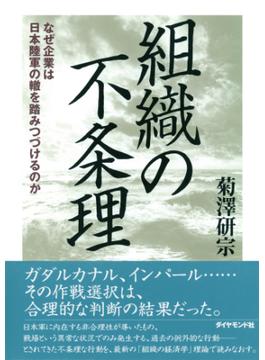- みんなの評価
 4件
4件
組織の不条理―――なぜ企業は日本陸軍の轍を踏みつづけるのか
著者 菊澤研宗
ガダルカナル、インパール……作戦選択には合理性があったが……。最新経済学理論に基づく解釈で不条理な組織のあり方を照射。なぜ企業は日本陸軍の轍を踏み続けるのか。
組織の不条理
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
組織の不条理 なぜ企業は日本陸軍の轍を踏みつづけるのか
2001/03/09 11:22
若手研究者の野心的挑戦
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:塩津計 - この投稿者のレビュー一覧を見る
防衛大学の若手研究者である著者が、敢えてきら星のごとき防衛大の先輩研究者の論理に挑戦状をたたきつけた野心策。不朽の名著「失敗の本質」が提示した日本の組織にある構造的欠陥の指摘を正面から否定。人間が完全無欠な存在には必ずミスを犯すし、あそこが悪かったここが悪かったとあと講釈で欠点をあげつらっても進歩には繋がらないと主張。やや荒削りな部分もあるが傾聴にあたいする指摘も多い。「失敗の本質」ダイヤモンド社との併読を薦める。
組織の不条理 なぜ企業は日本陸軍の轍を踏みつづけるのか
2004/09/11 15:53
華やかさは無くても、地に足の着いた良書
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:六等星 - この投稿者のレビュー一覧を見る
人間は限定合理的であり、その限定合理的な人間の集団であるいかなる組織も、限定合理的である。そして条件さえそろえば、組織は合理的に非効率な手段を選び、やがて破綻していく。題材は大東亜戦争で敗退した日本軍であるが、今日のどんな組織にも当てはまる、鋭い指摘である。
本書では、人間と組織の限定合理性を認め、常に批判を受け入れる「開かれた組織」を構築することを、その解決策として主張している。セオリーとしての組織論は理解できても、実際の組織が不条理に陥らない方法を見出すことのできる組織経営者は少数派であろう。多くの経営者が、このメカニズムを研究し、具現化することを切に望む。華やかさは無いが、地に足の着いた良書である。
組織の不条理 なぜ企業は日本陸軍の轍を踏みつづけるのか
2003/07/04 23:56
なぜ失敗したのか、その答えはここに
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:北祭 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、戸部良一らによる『失敗の本質』では不明確に終わっていた、大東亜戦争における日本軍の不条理なる失敗の「根本原因」を論理的に解析してみせた名著である。
ガダルカナル戦における肉弾白兵突撃による日本軍の全滅、インパール戦における日本軍の餓死…なぜなのか。
これまでの正統派研究者は、日本軍の非合理性を指摘し、戦場における異常な行動であったとしてきた。著者は、ここで凛然と異を唱える。 <しかし、このような不条理な行動に導く原因は、実は人間の非合理性にあるのではなく、人間の合理性にあるというのが本書を貫く基本的な考え方である。p.2>
人間が様々な意思決定を行うにあたり、いくら合理的であろうとしても、何よりも人間の情報収集・処理・伝達能力は限定されているが故に「限定合理的」でしかありえない。著者は、この理論を適応することで、日本軍の失敗の原因を鮮やかに解明してみせるのである。
例えば、日本陸軍はガダルカナル戦に至るまでに白兵銃剣主義に適合するように組織的に多くの特殊な投資をしていた。白兵突撃を念頭に軽戦車・手動連発小銃の開発に投資し、多大な教育コストをかけて兵士を訓練していた。ここでもし、白兵戦術を変更すれば、これまでの特殊な投資がすべて埋没コストとなり、利害関係者の説得にも多大な時間と取引コストを生み出してしまう。さらに、<そして何よりも、この伝統的白兵銃剣主義を放棄し作戦を変更すれば、この戦術のもとにこれまで戦死した数多くの勇敢な日本兵士の死自体が回収できない埋没コストとなることを意味した。p.99>と著者はいう。埋没コストなどと表現するにはあまりにも重い。
これらの巨大なコストのために、ガダルカナル戦における日本陸軍は、たとえ白兵突撃戦術が非効率な戦術であったとしても、依然としてその戦術をスタンダードとして採用し続けるほうが「合理的」な状況にあった。そして日本陸軍はわずかな勝利の可能性を追及するに至る。されど、人間は限定合理的でしかありえない。敵の情報は得られず、現場にいる兵士の本意が大本営には届かず、結果として、非効率かつ非人道的な作戦となってしまう。
人間が、自らの不完全性に配慮せず、完全に合理的な作戦を取ろうとすればするほどに不条理な結果を招くこととなる。ガダルカナル島やインパールは、人間の合理性が生み出す最悪の戦場と化したのである。
著者は、日本がなぜ負けるべき戦争に訴えたのか、その原因についても臆することなく「限定合理性」を用いた持論を述べる。大東亜戦争の原因は本書による理論のみで説明されるものではないだろう。しかし、その答えを追い求める者ならば、本書の中に確かな手ごたえを感じるに違いない。