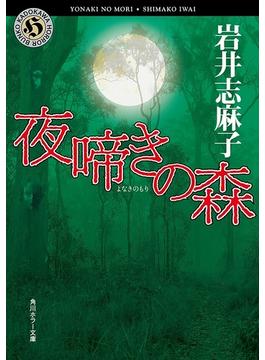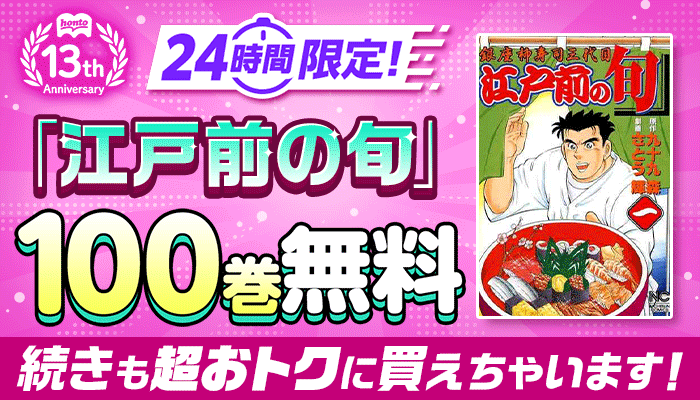- みんなの評価
 2件
2件
夜啼きの森
著者 岩井志麻子
暗黒の森の中で銃声とともにこだまするうめき声。「来た。鬼が来たんじゃ」。昭和十三年、岡山県北部で起こった伝説の「三十三人殺傷事件」。おとなしく、利発でええ子だったはずの辰男は、なぜ、前代未聞の凶行へと至ったのか。狂気か? 憤怒か? 怨恨か? 古い村の因習と閉ざされた家族の歪な様相、人間の業と性の深淵を掘り下げながら、満月の晩に異形の「鬼」となって疾駈する主人公を濃密な文体で描き出した戦慄の長編小説。話題の女流作家が切り拓いた圧倒的迫力の新境地!
夜啼きの森
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
夜啼きの森
2004/05/31 16:47
滅び行く村に、この世界の縮図がある
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:岑城聡美 - この投稿者のレビュー一覧を見る
岡山北部の寒村、「お森様」として恐れられる暗黒の森、濃い血脈の果てに作られた貧しい村落。いかにも岩井志麻子的な要素が贅沢すぎるほどに盛り込まれているこの作品は、期待に違わず、やはり鉛を飲み込んだような重い読後感を抱かせてくれた。
新月、二日月、三日月。巡ってゆく四季もさることながら、この物語においては狂気の象徴とも言える月が章ごとの区切りを形作っている。呪われたような禍々しさを持って描かれる月(それは同じように呪われた森を暗く浮かび上がらせるための巧妙な舞台装置でもあるのだが)の下に棲む村人たちの姿は、まるで章から章へバトンを渡すように、巧みに描写されていく。
例えば「お森様」においては、傍目にさしたる苦労も無いように描かれる分限者の妻モト。彼女は次章の「サネモリ様」においてクローズアップされ、忌まわしい生い立ちと現在の不幸を読者の前に暴かれて、女たる生き物の本性をさらけ出す。同様に「サネモリ様」においては全ての女の羨望の的であるかのように描かれたみち子が、「さむはら様」においてはやはり辛酸をなめ続けてきた半生と、女としての悦びを欲しいままにするかに見えて、実はそこにもやるせない人生からの逃避があったのだという事実を露わになるのだ。著者の容赦ない筆には、半端な同情や哀れみなど消し飛んでしまう迫力がある。まさにこの村において(あるいはこの世界において)苦しみから逃れる場所などないのだと言わんばかりの書き様なのである。
一方で、主人公たる辰男の姿は、直接的に描かれることは少ない。周囲の人間からの村八分の扱い、そして冷ややかな視線を通した客観的な描写が、かえってこの疎ましい存在の不気味さをかき立てる辺り、非常に巧みな描きようである。「堤婆様」「荒神様」において辰男はいよいよ抜き差しならない状態へ追い込まれていくが、ここでも前述のバトンタッチ方式の構成が生きていて、単なる貧乏人として物語のすみに登場するだけだった馬場家の治夫、そして村中から軽蔑の対象となっている虔吉の存在がにわかにクローズアップされてくる。この二人を通して、辰男の狂気、追いつめられた思いが二重写しに描かれるのだが、こうした手法によって辰男の憎悪の念の迫力はいや増し、読者も危うく辰男の狂気に引きずり込まれそうになる。世を拗ね、生きるためのまっとうな努力もしない辰男に感情移入の余地などあるはずもないのに、である。
村中の人々(ことに弱者達)のあらゆる辛酸を描き尽くした後に来るカタルシスは、悲惨と言うよりも、むしろ清々しくさえ感じられる。特に死に至るまでの数日の、ようやく自我の尊厳らしきものに目覚めた虔吉の心理描写は圧巻である。
著者特有の道具立てによる雰囲気作りも十分だが、この作品の真価はむしろラストの惨劇の描写よりも、そこに至るまでの物語の中で、人々の絶望を余すところなく描き出したところにあるのではなかろうか。不謹慎な物言いかもしれないが、この呪われた村とそこに棲む人々は、滅びるべくして滅びたのだと思われてならない。
夜啼きの森
2005/08/31 21:02
この岡山の一寒村を舞台にしたジゴロの話が、あの事件に結び付くなんて。わたしは衝撃でした。さほどに、あの事件は根が深いものなのでしょう
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
《大正三年の岡山の小さな村。異常な数の雀が発生した村。その死骸の山に祝福されて生まれてきた子供たち。彼らの愛憎が行き着くところは》ホラー?
岩井志麻子のいい読者ではないので恐縮ですが、彼女の小説を、ホラーと言うことにためらいを覚えます。大正、昭和にかけて流行った怪奇小説という言い方とも違います。どちらかと言うと江戸時代からの流れを汲む因縁談、これが一番ふさわしい気がするのですが、どうでしょう。
それにしても、横溝正史といい、岩井といい、岡山県にとって、戦前の「あの事件」が如何にこの地方を震撼させたのか、つくづく考えさせられてしまいます。
舞台は、大正三年、岡山の小さな寒村です。異常な数の雀が発生し、夥しい死骸が田畑を覆います。その死骸の山に祝福されて生まれてきた子供たち。その森に生まれたことは決して口にしてはならない「きょうてい」森。岡山の暗い森の近くにある23戸ばかりの小さな村で一番賢いといわれながら貧しさゆえに進学もできず、次第に女に狂い始める辰夫。女たちは彼の魅力の前になす術もありません。
村で一番の資産家 泰三に嫁いだモトも、昔、辰夫から「きれいだね」と言われた一言が忘れられないのです。そして体が弱く、兵隊に採られることのなかった辰夫は、兵役に就けなかったことを怒るかのように女に狂い続けます。村はずれに住む占い師の娘 みち、村に流行る「眠り病」、夜這いの風習などが、岡山に起きた有名な事件へと雪崩れ込んで行きます。
人の世の縁(えにし)を描くという点では、ある意味きわめてオーソドックスな小説です。上田秋成や鶴屋南北を思い出すといってもいいかもしれません。しかし、まさかこの話が、あの伝説的な事件になっていくとは予想もしませんでした。今流行の恐怖譚に憧れて手にした人は戸惑うでしょう。
ここでは貧困や死といった、今の若い人が目をそむけているものが克明に描かれています。しかし、ここには私たちの祖父が生きていた時代、ついこの間まで両親が育ち、あるいは今でも場所によっては、これが現実であるかもしれない世界があるのです。縁(えにし)とは恐いものです。