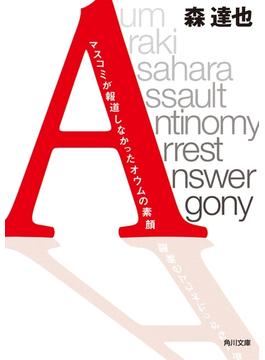- みんなの評価
 6件
6件
「A」 マスコミが報道しなかったオウムの素顔
著者 著者:森 達也
――オウムの中から見ると、外の世界はどう映るのだろう?1995年。熱狂的なオウム報道に感じる欠落感の由来を求めて、森達也はオウム真理教のドキュメンタリーを撮り始める。オウムと世間という2つの乖離した社会の狭間であがく広報担当の荒木浩。彼をピンホールとして照射した世界は、かつて見たことのない、生々しい敵意と偏見を剥き出しにしていく――!メディアが流す現実感のない2次情報、正義感の麻痺、蔓延する世論(ルサンチマン)を鋭く批判した問題作!ベルリン映画祭を始め、各国映画祭で絶賛された「A」の全てを描く。
「A」 マスコミが報道しなかったオウムの素顔
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
A マスコミが報道しなかったオウムの素顔
2005/04/10 23:40
見事な補強
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まさぴゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
時系列的にはほぼ同じ素材を扱っていますが、ドキュメンタリーとは、まったく異なる印象を受けました。というのは映像作品の『A』はオウムの側という視点から描く映像として、オウムにシンパシーを感じさせせるもので、実際に僕も圧倒的な社会権力である世間と報道に恐怖を感じる弱者側にシンパシーを強く感じました。だからこの本とドキュメンタリー作家森達也の凄みは、ドキュメンタリーである『A』という映像作品を見比べなければ分からない。映像作品には、日本社会が異端者や弱者に向ける強烈な排除の力を告発する視点が描かれており、素直にあの作品を見れば、絶対にオウム真理教に感情移入してしまいます。
けれど、この森監督の文章を読むと「組織従属的なメンタリティ」は、「社会のこちら側」にせよ「あちら側」にせよ、同じ位相であり、どちらがわも「わけのわからなさ」にはかわりがないと言っているように感じました。この「どちら側にも組しない立場」をつらぬく森監督のドキュメンタリー作家としての資質は、物凄く見事だと思いました。普通ああいう映像作品を、異端者の立場からドキュメンタリーに構成した監督が、実は「どちらの視点も信じていないんだ」というスタンスに立つのはありえない。しかし、実際にはこの立場しかありえないですよね、こういうギリギリのラインを扱う作品では。スタンスが素晴らしかった。
個人的に興味深かったのは、信者が情愛を切断しようとしているところ。宗教にはつきものですが、たとえばキリスト教の隣人愛の概念なんかは、家族や民族を切り離して考える可能性を作り出すもので、僕はその概念を「殺し合いを続ける民族や氏族のセクト争い」から脱出させるものというイメージで理解していました。情愛や「目には目を」の復讐法に縛られるからこそ、物凄い殺し合いが起こるのですからね。しかし考えてみれば情愛から切り離された人間ほど、極端な虐殺行為をも平気で行えるのですよね。うーん、この部分はいろいろ考えさせられました。
あと、大江健三郎の作品が奇妙なほどリアル感を感じた。というのは、大江さんの作品は、宗教共同体に自ら選んで入る人や、共同体の内部の世界を描いているからで、今までは「物語」として読んでいたが、日本のいま、この瞬間に同世代のやつらで、同じようなこと現実に生きている人々がいるんだ、というのを突きつけられた気がして、少し背筋が寒くなった。想像力さえあれば、自分の友人や「まかり間違えば自分が」その「立場」であっても不思議はないのです。とにかく、日常でリーマンしている自分を、いろいろ考えさせられる作品ですした。
A マスコミが報道しなかったオウムの素顔
2003/10/31 01:15
わたしたちは本当に事実を見ているといえるのだろうか。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ポカ - この投稿者のレビュー一覧を見る
わたしたちは、自分の頭で考えているのだろうか。
物事の事実を見ているといえるのだろうか。
垂れ流しの情報のなかで、わたしたちは、物事の事実を見ようとする努力さえ忘れてしまっているのではないのだろうか。
事実を見極めるのには、自分が努力をしなくてはいけないことをどこかの時点で忘れてしまったのではないのか。
わたしたちの目の前に流されるテレビや新聞や雑誌の情報は、その事柄をどこかで切り取ったものでしかないのに、それが情報の全てだと思い込んでしまってはいないだろうか。
そんな自分の危険性を目の当たりにしたような気がする。
それは、すなわち、わたしが暮らす社会の危険性でもあるのだ。
日本中を震撼させたオウム事件で、わたしたちは、「オウム真理教」という集団をひとくくりにして、そのなかの「個」を見ようともしなかった。
集団といっても、結局は「個」の集まりなのに、大半は、ひとくくりのままで騒ぎ立てて、この事件の本質を深く掘り下げようということがなかった。
なぜ、こういうことが起きてしまったのか、そこへたどり着こうとしなかった。ただ騒ぎ立てるだけではなにも解決しないのに。
わたしもその一人だ。
日々の報道の中で、「なんて恐ろしい集団だろう」という感想。ただそれだけだった。
わたしは、オウム事件後の、あきらかに行き過ぎた報道にも、人権を全く無視した言われ方にも、なんとも思わなかった。
「なんて恐ろしい集団」それだけの思考から抜け出せなかった。
完全に麻痺していた。
それを思って、はっとした。恐ろしかった。
ショックだった。
オウムの「内」と「外」。その温度差。
外から眺めて騒いでいるだけでは、内でなにが起きているのか(もしくは起きていない)なんてわかるわけがない。
報道は、外に居る者たちの貧弱な想像力でしか行われていなかった。
マスコミの過激な取材攻勢、報道は、今になって思えば、薄っぺらにしかみえない。
どう見ても、真実を映し出そうとしているとは思えないのに、わたしたちは、これらの報道を事実の全てと思い込んで良いとか悪いとか無責任に云っていたことにはたと気づく。
わたしたち社会が望んでしまいがちなのは、完全なる悪者と、完全なる正義。
そして、その社会が望むものをマスコミは作り上げようとする、そんな構図があることに、全く疑いもしなかった。
そのシナリオに邪魔なものは切り捨てる。
しかし、わたしたちが真実を知ろうとするときには、全ての「事実」を見なくてはならない。
すべての事実を見てしまうと、とても複雑なものになり、簡単に答えをだすことはできなくなる。
それでも全てを見なくてはならない。その上で、考えなくてはならない。
今更ながら、わたしは、「理不尽」を感じている。
オウムがおこした地下鉄サリン事件や弁護士一家殺人事件などの「理不尽」と同じくらい、わたしたちが住むこの世の中の「理不尽」を感じている。
物事の決着を簡単につけてしまうことの危うさを、世の中が気づいていないということこそが恐ろしいことなのだ。
理不尽を理不尽と思わなくなってしまうこと、想像力が麻痺すること、その恐ろしさを改めて知る。
この本は、自分の感覚をもう一度立て直すきっかけになったような気がしている。
わたしたちは、もっと注意深く生きなくてはならない。
A マスコミが報道しなかったオウムの素顔
2002/09/20 21:55
オウムを取り巻く日本社会の駄目さが見える
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:uwasano - この投稿者のレビュー一覧を見る
オウム真理教・広報担当の荒木浩氏を主人公にしたドキュメンタリー映画「A」の製作過程を、監督の森達也氏が語った本である。
一連のオウム事件に関与したとされる教団幹部達が逮捕された後、荒木氏が広報担当として、テレビに出てきた。彼を見て、ドキュメンタリー素材として、直感・確信した(p17)という著者は、何度も手紙を出しコンタクトを図る。荒木氏と接触し、その依頼は受諾され、撮影を開始する。著者が撮りたかった「オウムの中から外を見る」(p50)と、日本社会はどのように見えるのか?
警官達の仕掛けによる公務執行妨害(「転び公妨」という)により信者が不当逮捕される(p120)。通りがかりの人は「全部死刑にしちまえばいいんだよなあ」「ポアされて本望だろ」(p121)と笑い合う。「穏やかで常識のある方」と荒木の言う人物が、週刊誌の中吊り広告では「殺人マシン」と書かれている(p169)。テレビ番組は、オウムに対してある種のイメージを刷り込ませるように作られる(p195)。この時期の日本は、ヨーロッパ中世の魔女狩り状態にも似た状況が形作られていった。
【自らの空白に、「グル」ではなく「組織」の大いなる意思を充填させて、自分の言葉で思考することを放棄して、他者への情感と営為への想像力をとりあえず停止させただけ】(p196)、と著者の語る日本社会。オウム側も、それを糾弾する日本社会側も、実は同じ病の中にある。まるで鏡のような関係なのだ。一人一人が自分の頭で考えないように操作されているような社会。国家が仕組んでいるわけでなく、メディアが一方向に進んでいく。テレビのドキュメンタリー番組製作にいた著者は、その仕組みを見抜き、警鐘を鳴らし続ける。
ドキュメンタリー映画「A」がドイツで上映され、観客の質問に答える著者の言葉もいい。「ほとんどの日本人に共通するメンタリティ」として、【共同体に帰属することで、思考や他者に対しての想像力を停止してしまう。その危険さを僕は描いたつもりです】(p249)。先の大戦で、日本とドイツは全体主義どおしで同盟国だった。そんな国の国民に、「ドイツ人にはそんなメンタリティはないと本当に言いきれるのでしょうか?」と問いかける著者。圧巻である。
著者はあとがきで、オウム事件以後の日本がどんどん悪くなっていると指摘する。「世界はもっと豊かだし、人はもっと優しい」(p253)と言う言葉を持ち続け、「こうなれば持久戦だ」と語る。イスラムの自爆テロや北朝鮮の拉致事件問題がクローズアップされているが、この本の著者のような姿勢が大切なのではないか? 私は今後も著者の活躍から目が離せない。
あとがきの後の、宮台真司(社会学者)の文庫解説「私たちが自滅しないための戦略」もいい。