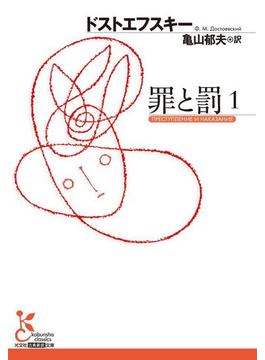- みんなの評価
 7件
7件
罪と罰
貧困・孤独・狂気の渦巻く大都会のかたすみに、「理想的な」殺人をたくらむ青年が住んでいた。酔いどれ役人との出会い、母からの重い手紙、馬が殺される悪夢。ディテールが、運命となって彼に押し寄せる!歩いて七百三十歩のアパートに住む金貸しの老女を、主人公ラスコーリニコフはなぜ殺さねばならないのか。日本をはじめ世界の文学に決定的な影響を与えたドストエフスキーの代表作のひとつ、ついに新訳刊行。
罪と罰 3
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
罪と罰 1
2009/06/17 13:38
2冊目以降は、訳語へのこだわりからできるだけ遠ざかり、自然に小説そのものに没入したい
13人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:本を読むひと - この投稿者のレビュー一覧を見る
この『罪と罰』の新訳はいい、というのが私の実感である。ドストエフスキーの小説は会話が多いが、この会話の言葉が生き生きとしていて、今までにない新鮮さを感じた。
主人公の友人ラズミーヒンがラスコーリニコフの下宿に来て、彼を看病する場面を、まず手持ちの新潮社版全集(工藤精一郎訳)から引用し、続いて本書の同じ部分を引用する。
《「これもみなパーシェンカが、ここのおかみさんがね、あてがってくれるんだよ。まったくじつに親切にもてなしてくれるぜ。むろん、ぼくはねだりはしないよ。なにことわりもしないがね。そら、ナスターシヤが茶を持って来た。ほんとにすばしっこい女だよ! ナスチェンカ、ビール飲むかい?」》
《これも、みんなきみんとこのおかみの、パーシェンカのおごりでね、どうやらこのおれを、心から尊敬してくれてるらしくってさ。別にこっちからおねだりしてるわけじゃなし、かといって、断りもしちゃいないけどね。おう、ナスターシヤがお茶をもってきた。ほんとうにフットワークのいい女だぜ! ナスターシヤ、ビール、飲むかい?」》
この部分に関していえば、それほど前者の訳に古めかしさはない。それでも「なにことわりもしないがね」の「なに」などは、今では使いにくい。
この訳文のなかで、下宿の気のよさそうな「女中」ナスターシヤに対して、ラズミーヒンは愛称もまじえて喋っているのを、工藤訳では生かしているが、亀井訳はそうしていない。訳者は本書全体にわたって人名の訳を大胆に統一している。こうした単純化は、読みすすめるとき、無駄な瑣末な判断をしなくてすむ分、小説の自然な流れに入り込めて、いい処理だと私は思う。また、おそろしく長い母親の手紙のなかに、工藤訳では「ピョートル・ペトローヴィチ」が十回以上登場するが、亀井訳では、これを「ルージンさん」とし、全体の長ったらしさを、いくらかでも縮めようとしている。
ナスターシヤを「フットワークのいい」と形容するようなカタカナ言葉がうるさくない程度に登場するのも、この何となく暗い小説に効果的なアクセントがつけられていて、悪くない。
ロシア語をまったく解さず、『罪と罰』の原書の実物を拝んだことのないものが僭越だと思うが、私はマルメラードフが娼婦になった娘ソーニャについて語る部分の訳語について、新訳が面白いと思えた。娘からわずかのお金を酒代として結果的に奪ってしまった彼は、そのお金が娘にとって必要なものだったと見ず知らずのラスコーリニコフに話す。「だっていまのあの娘には身なりをきれいにすることが大切ですからな」(工藤訳)。
ここは亀井訳では、「だって、あの子はいま清潔を守らなくちゃならない身ですよ」となるが、たんに「身なりをきれいにする」ではなく「清潔を守る」(ルージンと結婚しようとしている妹に対して、同じ言葉が主人公の頭に浮かぶ)は、そこに、ある種のセクシュアリティを読ませないだろうか。
つまり工藤訳では、たんにいい服を着て化粧をして、という以上の意味を見出しにくいが、亀井訳では、ドストエフスキー作品では決してあからさまに描かれることのない女性の性的な肉体が暗示されているように思うからで、それは原文にも暗示されているものでは、と推測する。もっとも集英社文学全集の小泉猛訳も亀井訳と同じ「清潔」だった。
ラスコーリニコフが殺人決行の前日、市場で偶然聞く、金貸しの妹が翌日のその時間に外にいると彼が判断する「時」の訳が、工藤訳の「七時ですよ」に対して、亀井訳では正確に「六時すぎですよ」となっている。これは本文庫解説で丁寧にフォローされているが、まさに必要な注釈である。これに関しては小泉訳も「七時」だった。
十年前にドストエフスキー全集を買い、最初期の作品を少し読んだまま段ボールに入れたままにしてあったのが、今回有効活用できた。二つを比較して、訳自体の差とは別に文字の大きさが、年をとったせいもあるが、ひどく気になった。光文社文庫版は適切な大きさであり、その意味でも好感がもてる。この文字の大きさなしには、新鮮な訳も生きはしなかったろう。
この小説を読むのは三度目だが、二度目からでも30年以上が経つ。二度目のときは数日で読んだが、今度はじっくりと読むつもりだ。そして、この小説が、今の私に何をもたらすのかを、できるだけ冷静に見極めたいと思う。
罪と罰 1
2009/08/16 18:14
『罪と罰』の世界を身近に感じラスコーリニコフの犯罪を自己流解釈で楽しもう。
10人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:よっちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
まもなく衆議院選挙だ。日本が羅針盤を失い漂流しはじめてから何年になるか。その間に積もり積もった焦燥感が解消されるどころか、さらにふくれあがるであろうことをだれもが認識している政治的プロセスである。
昭和19年に生まれて40年のサラリーマン人生を金融危機の激動のなかで終えたものの実感なのだが、グローバリゼーション・グローバルスタンダード・新自由主義、その資本運動の法則を絶対的正義だとしたあれこそ、日本人にとっては新たな神の降臨だったのだ。新しい神がその神の国を作り上げる過程は経済活動だけではなく、政治や社会生活、精神活動、価値観の変革を強制するものであり、一方で犠牲者はつきもの、屍の山が築かれることになる。大量殺人も正義とされることがある。本来、救世主こそこの大いなる罪の十字架を背負うべきところ、日本にはそういう偉大な存在が出現しなかったということだろう。自民党、民主党いやどの政党のマニフェストも市場原理主義からの訣別を謳い、バラマキ財政を正義として、今度はあれのアンチテーゼにあたる神の国を作ろうとしているのか。ああ、それではあの時降臨したものは悪魔だったのか。
宗教が世界秩序を作り、人間の歴史に深く関与し、しかも現実に根を下ろしていることは「知っている」だけで、神とか悪魔、極楽や地獄、あるいは死後の世界などとは、まったく無縁で、神仏の救済などは実感することのない私にとって降臨やら救世主うんぬんは言葉の遊びをやっているに過ぎない。しかし、亀山郁夫の著書『「罪と罰」ノート』を片手に『罪と罰』をじっくり読んだら、その後遺症だろう、普段考えもしなかった、こんな突拍子もない発想方法にとりつかれるはめになったのだ。視野が広がったというのはこういうことを指すのではないだろうか。
亀山郁夫には読者を一度、現代日本という座標軸に立たせたうえで、ドストエフスキーのメッセージを受け取ってもらおうとする意図があって、その姿勢が翻訳に投影されているものだから、読者が『罪と罰』の世界を身近に感じ、自分なりに解釈を楽しむには都合のいい訳本になっている。『「罪と罰」ノート』を併読すればなおさらのことである。
1860年代前半にアレクサンドル2世のもとで行われた身分制度の解体や資本主義原理の導入など西洋合理主義の枠組み作りは伝統的なロシア人の思想とは相容れず、偏重する富の蓄積がまた新たな貧困層を生み出すなど社会的不安と混乱をもたらした。このような世相を背景に、困窮のうちに中退した元学生のラスコーリニコフはこの新しい世界を拒否し隔絶していった。かなり重症の鬱病であった彼はこの世界への憎悪をつのらせるだけで抜け道を見出せない。また神を否定する彼には宗教に救いを求める観念はない。だからといって自ら別な世界を築き上げようとする志もない。そしてシラミのように存在しているだけの自分を嫌悪している。他人に対して傲慢でありながら弱いものへはひとかたならぬやさしさをもつ分裂した人格。
この彼が金貸しの老婆を殺害し、金品を強奪することを思いつく。思いつきは思いつきにとどまらず、紆余曲折の精神的葛藤のすえようやく決意にいたる。そして用意周到のはずだったのだが、結局はまるでずさんで不完全な犯行に追い込まれる。これが今回、第一部を先入観抜きにして、読んだ私の印象だった。そして疑問。閉塞した精神状態は共感できるのだが、なぜこれが一足飛びに殺人へと短絡するのだろうか?
親殺し、子殺し。ドメスティックバイオレンス。変質者による幼児への性犯罪。「だれでもいいから殺したかった」と供述する現代の無差別殺人者たち。「なぜ人を殺してはいけないんですか」とうそぶく少年たち。抑圧が短絡的に暴力へ移行するキレタ症候群。そして今でも根深くある若者たちのカルト願望。
これら最近の理解しがたい狂気の周囲にはラスコーリニコフの犯罪、その罪と罰と贖罪の様相に近接したところがありそうな気がする。昨年読んだ平野啓一郎『決壊』が描いた犯罪がそうであった。今回よいタイミングで『罪と罰』を読んだと思う。これから読む高村薫『太陽を曳く馬』、さらに村上春樹『1Q84』がこれでいっそう楽しめそうな気配がしている。
罪と罰 2
2009/08/26 15:08
「義を見てせざるは 勇なきなり」と一肌脱いで感謝されるとうれしくなる。ところが思いがけないところから余計なことをしてくれたとお小言を頂戴する。内心複雑な思いで弁解にあい努めるハメに追い込まれた。よくあることだが、これってナポレオン主義と関係あり!?
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:よっちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
ラスコーリニコフの犯罪論を読んだポリフィーリーがラスコーリニコフの殺人哲学について挑発的に言及する。
「この世にはどんな無法行為だろうと、犯罪だろうと、それを行うことができる人間が存在するという………いや、できるなんてもんじゃなく、完全な権利をもつ人間が存在する、そういう人間には法律も適用されないという(のがあなたの考えのようだ)」
高校生の時に初めて『罪と罰』を手にとって、読む前からこれは完璧な殺人理論を持った犯罪者の話であると聞いていたものだから、ラスコーリニコフは体制破壊のパワーをもつカッコイイ殺人者というイメージばかりが先行してあった。この反動は大きく、読んでみれば優柔不断、なんともだらしない男なんだと、期待はずれのせいで実はまともに読み続けることができなかった。その後もラスコーリニコフの殺人の思想・動機についてはこのいわゆるナポレオン主義であるとの先入観には抜きがたいものがあった。
「犯罪理論」は冒頭からではなく第三部で初めて明らかにされる。読者としては、なぜ彼は殺したのかと疑問を持ちながら読んでいくと、きわめて衝撃的にこれが現れる。魅力的なミステリー仕立てのため、なるほどこれかと胸に刻み込まされることになるのだ。
ただ今回は本当にそうなのかと突っ込んでみた。
彼の「犯罪理論」はすべての人を「凡人」か「非凡人」に分け、「非凡人」はあらゆる犯罪をおかし、勝手に法を踏み越える権利をもつとするもの………ポルフィーリーはこうも指摘するのだ。
ポルフィーリーの過激かつ一面的な指摘に歴史的検証を加えれば次のような論証が成立する。
法の制定者や人類の指導者が新しい世界秩序をつくる作為はそれまでの社会が神聖であると認めてきた枠組みをぶっこわすことであるから、旧秩序からみればまさに犯罪行為である。しかし新しい社会体制ではその犯罪行為そのものが「正義」の実現行為であるとされる。また大きな正義を実現するプロセスでは捨石は必然的に発生するものだ。(ポリフィーリーはあえて的をはずしてこの負の面だけを言及したものである)たとえば新秩序の形成者によって日本に原爆を落としたのは「正義」の実現であったされる。いわゆるナポレオン主義だ。ただし、これは歴史事象をある断面に切り取ってみせたひとつの事実認識である。
変革者の作為は変革に成功して初めてその権利が社会的に認知されるであって、失敗すれば思い上がりの確信犯としてしっぺ返しを受けるものでもある。
ドストエフスキーにはナポレオン主義という表現はない。後に研究家がつけたものである。それによればナポレオン三世の著述にある、歴史を変えるような偉大な英雄・指導者は神が地上に遣わせた天才であり、彼は諸国民と対峙して神の命に従った事業を短期間で完成させるとする考えに由来する。
ドストエフスキーの描く人間は真・善・美の完成体ではない。もっとなまなましい偽・悪・醜が混じりあった存在のはずだ。そう思えば、きれいごとで飾られたナポレオン三世のこの思想は実にいかがわしいものだと気がつく。選良たちがよかれと成し遂げる事業の反作用は累々たる屍の山を築くことに他ならない。天才たちといえども生身の人間であるからこれら犠牲者から発せられる怨嗟の重圧には決して平然としてはいられないのだ。そしてナポレオン主義は大いなる錯誤であるのだが必要とされる自己欺瞞なのだ。ナポレオン主義の実体は自分たちのこの醜悪な行為を隠蔽し、無言の譴責から自己を弁護するために用意された究極の砦なのだ。彼らは強い思い込みにより錯覚を錯覚として気づくことのない、そして破綻のない自己欺瞞を完成させている。
ところで、倫理的、宗教的、政治的、この世のあらゆる秩序を拒否していたラスコーリニコフはそれに替わる世界を自ら作り上げようとする意思はなかった。彼は理想とする世界がどういう世界なのか、イメージすら持ち合わせていない。貧乏人を苦しめる金貸しの老女を殺すことでひきかえに何千もの命を救う?あるいは強奪した金を将来の正義の実現の元手とする?それはラスコーリニコフの意図した犯罪ではない。
ラスコーリニコフはポリフィーリーがなした挑発的指摘を否定はしなかったが次のような論旨を展開している。非凡人には法を踏み越える権利があるといっても公的な権利ではない。「彼らは(非凡人は)自分の思想のためにもし死体や流血といった事態を踏み越える必要があれば、ぼくの考えでは、彼らは心の中で良心に従って、流血を踏み越える許可を自分に与えることができるんです。」
これがラスコーリニコフ犯罪論の本音であろう。なんと謙虚な犯罪論であることか。ナポレオン三世の言う天才たちは国民に対してもっともっと傲慢だった。私はラスコーリニコフの犯罪そのものは終始ナポレオン主義と呼べるシロモノではないと思う。
にもかかわらず<思想のために><公的な権利のことではなく><自分の良心に許可を与える権利>などとした自己撞着的犯罪論は彼にとってなくてはならないものであった。ナポレオン主義は天才たちが社会的に通用させねばならない自己弁護のための論理だったのに対して、これは彼だけにしか通用しない屁理屈である。しかし彼だけには通用させねばならないと彼の内心が用意した「自己弁護のための究極の砦」だったところでナポレオン主義の実体に相通ずるものがあるのだ。
では彼の犯罪はなんであったのだろうか?