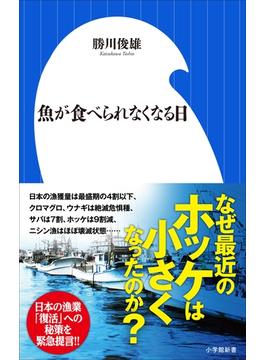- みんなの評価
 2件
2件
魚が食べられなくなる日(小学館新書)
著者 勝川俊雄
なぜホッケは高くて小さくなったのか?
居酒屋で出てくるホッケ、最近はは小さいと思いませんか。小さいどころか、ホッケを置いていない店も増えています。ホッケの漁獲量は、なんと最盛期の9割減。大きな魚を獲り尽くして、いまは成長しきっていない小さいホッケまで獲っている状態なのです。ホッケだけではありません。サバは7割減、クロマグロやウナギはすでに絶滅危惧種です。輸入魚も、世界的和食ブームの影響で、価格が上がっています。このままでは本当に、魚はめったに食べられなくなってしまいます。
日本は世界第6位の広大な排他的経済水域をもつ漁業大国だったはずなのに、なぜこうなってしまったのでしょうか。中国漁船の乱獲? クジラが食べ尽くした? 地球温暖化の影響? いいえ、そうではありません。日本の漁業が抱えている大問題を気鋭の水産学者が解き明かし、日本人がこれからも美味しい魚を食べ続けるにはどうしたらいいかをわかりやすく解説します。
魚が食べられなくなる日(小学館新書)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
魚が食べられなくなる日
2018/06/15 18:36
問題を先送りにする日本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:melon - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本の漁業は将来の水産資源について考えることをせず、今あるものを獲ってしまえという発想である。ノルウェーではサバについて個別漁獲枠方式による漁獲制限という規制によって資源管理を徹底し、サバの資源量を維持し続けているそうだ。一方の日本は、楽観的な資源量予測に基づく意味のない漁獲制限によって乱獲を助長し、水産資源は減る一方だ。ついに太平洋のクロマグロなど絶滅危惧種となってしまったようだ。
これは何も漁業に限らないと思う。最も顕著にこのような現象が起こっているのが財政だ。日本国債を発行して今がよければという状況を続け、今や先進国では経験したことのないほど財政が悪化している。それでもまだすぐにデフォルトになる状況ではないことをいいことに、問題を先送りにして、国債を発行し続けている。
水産資源も財産も破綻するような末期の状況に陥らなければ抜本的な対策をすることは日本ではないだろう(ドイツはこういったことにならないのが素晴らしい)。ポイント・オブ・ノーリターンがどこにあるのかはわからないが(もう既に引き返せないところまできているのかもしれない)、解決できるところでは放置して、もうどうしょうもなくなって、実際に危機が起こってから騒ぎ始めるのだ。そのときにはもう遅い。
2020/04/21 21:18
日本の漁業の問題に関する本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:絶望詩人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本には、日本の漁業の問題に関することが書かれてある。
この本を読めば、日本の漁業の厳しい状況が明らかとなろう。