melonさんのレビュー一覧
投稿者:melon

薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100
2017/12/07 22:48
類似薬の比較
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
一般的な『今日の治療薬』や『治療薬マニュアル』、『治療薬ハンドブック』では、それぞれの薬についての説明は載っていますが、類似薬の比較はそこまで検討されていないため、どっちの方が合っているかというのを考えるのには適さないといえます。しかし現在では似た作用を持つ医薬品が数多く出ているため、類似薬での比較というテーマは実に重要なものではないかと思うのです。
本書はそういった観点で非常に有用でしょう。たとえば第2世代抗ヒスタミン薬はたくさんありますが、「ザイザル」と「アレグラ」ではどう違うのか、最近出た「デザレックス」と「ビラノア」はどうなのかといったテーマや、抗アレルギー薬でも「ザイザル(第2世代抗ヒスタミン薬)」と「シングレア(抗ロイコトリエン薬)」の違い、花粉症などで用いられるステロイド点鼻薬「アラミスト」・「ナゾネックス」・「エリザス」の違いなど、身近な薬品でも違いを知らない人が多いのではないかと思います。去痰薬では「ムコダイン」と「ムコソルバン」はなぜ併用できるのか、それもこの両者の違いを理解すれば納得できるはずです。
生活習慣病の分野では、スタチン系の薬剤が豊富にありますが、「クレストール」と「リピトール」と「リバロ」の比較(それぞれ作用の強度、使用実績、相互作用に強みがある)をしていたり、フィブラート系の薬剤でも副作用の少ない「パルモディア」と「リピディル」という比較であったりをしています。その他改良した薬(PPIにおいては「オメプラール」から個人差を少なくした「ネキシウム」、「タケプロン」から個人差とピロリ除菌成功率を良くした「タケキャブ」が挙げられます。同様に個人差を小さくした改良では「プラビックス」を改良した抗血小板薬「エフィエント」が紹介されています。抗血小板薬では「プラビックス」も「パナルジン」から副作用を減らす改良がなされた薬です。光学異性体での改良としては非ベンゾジアゼピン系睡眠薬「アモバン」の改良薬「ルネスタ」や第2世代抗ヒスタミン薬「ジルテック」の改良薬「ザイザル」が紹介されています。)について、改良前と改良後を比較しているなど、薬の進化をみることもできます。
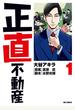
正直不動産 1 (ビッグコミックス)
2018/10/08 00:44
実に面白い業界物
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
不動産業界は情報の非対称性が顕著であり、一般消費者は損をしやすい商品である。そしてそれをマザマザと思い知らされる。
設定としては、祟りにより嘘をつけなくなった主人公の不動産営業マンが、顧客に真実(営業マンとしては致命的な)を伝えてしまうというもので、そのような形式で不動産の実態を読者に教えてくれるものだ。しかも難しい本と違い、娯楽としての面白さが成立している。
1巻の最初の話で、敷金・礼金を取るために、破格の家賃で客を釣り、嫌がらせをして追い出すという悪質な大家を取り扱っている。なるほど、そんな事例があるのか。敷金はまだ担保的な意味合いがあるので、必要なものであるが、礼金は悪習だろう。礼金という慣習がこのような問題を生じさせているのではないだろうか。

いちご同盟
2015/08/15 21:57
『四月は君の嘘』のオマージュ元
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
四月は君の嘘の元ネタということで読んでみました。
かなり読みやすく、すいすい進んでいきました。
「あたしと、心中しない?」
この台詞は君嘘でも登場したものであるが、それぞれの台詞に対する私の感じ方はかなり異なったものであった。
いちご同盟について、主人公が将来について、人生について悩みながら前々から自殺した少年のことなど考えていて、そのことを直美に話している前提での台詞であったことから、少女の心中について主人公はかなり度肝を抜かれたのだろうとひやひやした。
自殺についてふと考え、議論していた主人公が、出会った異性の重病人との心中や病死といった本物の死を間近に感じることは自殺とは縁遠い人が直面するよりも耐え難いことであろう。
(なお、君嘘では主人公が自殺について言及した場面は確かなかったと記憶している。死した母の呪縛を乗り越えた後のかをりの病気という出来事の中であり、主人公がもともと死というものと向き合った経験があることは同様であり、度肝を抜かれたのは確かであろう。しかし君嘘の主人公は強制的に死に直面させられたわけで自ら積極的に死を想起する自殺という事柄を思い浮かべて生活していたわけではなかったことから、私の目線において主人公の台詞の感じ方に違いを覚えた。ちなみにこの場面は演出が優れていて、おそらく多くの視聴者は心臓をわしづかみにされる感覚を覚えたのではないか。ともかく君嘘の作者がこの台詞、いちご同盟という作品をリスペクトしていたことは間違いないだろう。)

凍
2019/09/12 21:34
絶望的な状況が目の前に浮かぶ臨場感
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
世界的に著名な登山家である山野井夫妻がギャチュンカンで雪崩の巣と化した北壁からの脱出行という極限のサバイバルをしたときのドキュメントである。文章が読者を本の世界に引き込んでくる。知らないうちに、そこに書いてある絶望的な情景が目の前に見えるかのごとく感じながら読んでいた。私にとってここまで小説に夢中になることは珍しいことであった。
山野井の登山に対する考え方などを登山前の部分で知り、そしてギャチュンカンへと挑んでいく過程を描いていく。そして緊迫の下山、雪崩による危機は地獄である。しかしそれでも生還を果たすべく、最善の判断を続けていく。読んでいてドキドキする話であった。

青い鳥
2019/05/20 08:04
感動的な短編
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
吃音により特に「カ行」と「タ行」が上手に話せない村内先生が、各地の学校で非常勤講師となり、問題を抱えた生徒を救っていく話。副題の「My teacher cannot speak well. So when he speaks, he says something important.」という題がしっくりくる。
・ハンカチ
昔学校であったいじめによりルールができたとある公立中学校。そこのルールに違反したと指摘されてから、学校でしゃべることができなくなった少女が主人公。村内先生もうまくしゃべることができないことから、この少女に寄り添うことができたのだろう。
・ひむりーる独唱
教師を刺してしまって保護観察になった少年。しかし田舎の島根でもカエルを殺していたことにより祖母は面倒を見ることを拒否したため、もとの学校に戻ることとなった。カエルの詩を紹介して彼を更生する。
・おまもり
主人公の少女は自転車で事故に遭った部活仲間を見舞った。それは自身の父が事故で加害者になったことがあったため、事故にトラウマがあったからだ。しかし加害者を犯人と呼ぶ彼女にどこか違和感を覚える。毎年父が被害者家族を訪問するのに、今年は付いていきたいと懇願する。そこで奇跡は起きたのだった。
・青い鳥
コンビニ店長の息子は笑いながらパシリにされていたが、実はそれを苦に感じていた。自殺未遂により学校はおかしくなった。村内先生は彼を忘れさせないために彼の机を戻し、大事なことを教えるのであった。
・静かな楽隊
私立中受験に失敗したあやちゃんが公立中学で帝国を築く。幼馴染の中山さんは彼女を恐れるようになった。この話は村内先生があやちゃんを救うことができていない話で少し異色に思う。
・拝啓ねずみ大王さま
有名私立中にいたが、父の自殺で電車通学できなくなり公立に転校した少年が主人公。仲間になじめずにいた。この話の救いは、級友が良い人たちであったことだ。
・進路は北へ
中学校は公立でこそ問題が起こるものであるが、私立でもこういったことはあるのだろうか。小学校からの内部進学者と中学からの進学者との対立で外部性が1人退学してしまった。このような閉鎖的な空間でありながら、それをなかったことにしようとする学校に違和感を覚える少女。右利きのために教室が西向きであることを例に彼女を導いていく。
・カッコウの卵
かつて両親に捨てられ、施設に入れられた'てっちゃん'が、再婚した父に引き取られたものの、虐待を受けていた。そこに村内先生が現れ、大切なことを教えた。施設の少女と出会って結婚までした主人公が村内先生を発見して、再び大切なことを教わる。この話が最後に置かれているのが良い。現役の中学生ではなく、教え子の話というところにジーンとくるものがある。
全体的に感動的な話であり、なかでも『おまもり』はストーリーもそうだが、書き方が優れているのか、非常に感動するだろう。そして構成として、最後に教え子の話を持ってきて、本が終わることに読後感もスッキリしたものがある。
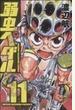
弱虫ペダル 11 (少年チャンピオン・コミックス)
2019/01/26 23:16
チーム力
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
厳しい登りはクライマーがチームの先頭で他メンバーを風から守り、上へ引き上げる必要がある。小野田にその役割が与えられ、巻島は山岳賞を獲りにいく作戦であった。巻島は、1年前のインターハイではチームを引き上げる必要があり、勝負できなかったのだが、今年は思う存分登りを戦えると楽しみにしていた。ところが小野田が落車事故に巻き込まれ最下位まで後退してしまう。ここで巻島は、チームを上に引き上げる役として勝負にいくわけにはいかなくなってしまったのだった。
箱根学園の東堂は、これまで巻島とは五分であり、この3年のインターハイで決着を付けたいと考えていた。巻島もその思いは非常に強い。しかし、小野田を欠いた総北ではそれが実現し得ないことであった。何より辛かったのは巻島だろう。一方の東堂の思いも非常に強く感じさせられた。2人の出会いやこれまでの対戦などの経緯が描かれ、東堂にとって巻島は絶対的なライバルなのだ。それは巻島も同じだ。両者とも戦いたい。しかしそれが実現できないというこの状況。ただ1位になるのでなく、巻島と戦っての1位がほしい東堂に強く感銘を覚えた。
そしてそれだけのストーリーがありながら、それでもチームを置き去りにせず、チーム内での役割を果たす巻島。ここも本巻の見所である。

日本一読みやすい会社六法 関連政省令付き条文集
2018/08/05 22:33
こういう六法があるといい
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
六法は縦書きで漢数字によって書かれている。これは条文を引用している場面では読みにくさを特に感じることとなる。会社法は条文の引用も多く、横書きでアラビア数字で記載されていることはありがたい。さらに括弧書きについて文字の大きさを小さくするとともに網掛けにしてあるという工夫が良い。
金融商品取引法などはこの傾向がもっと強い。使う人は少ないかもしれないが、こちらも同様の書き方をした六法があればと思う。さらに会社法関係だけでなく、六法全体として、このようなコンセプトのものがあればと思う。横書きでアラビア数字の方が圧倒的に読みやすいのは全員思っているのではないか。
![週刊 東洋経済 2017年 10/14号 [雑誌]](https://img.honto.jp/item/1/f8f7ef/75/110/28712282_1.jpg)
週刊 東洋経済 2017年 10/14号 [雑誌]
2017/12/08 22:16
地価崩壊が来る
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
地方においては、所有者不明土地が増加しているのが問題となっている。相続が発生しても価値の低い土地について登記をせずにおいていて、そういった状態で長年置いていることにより、相続が大量に発生し、相続人が80人以上出るなどしているようだ。宮城県南三陸町では、復興するのに相続人がたくさんいて、用地買収が進まなかったり、相続人の所在を突き止められず相続財産管理人を選任してもらって対処するなどしたようだ。また熊本でも同様の問題が生じたようだ。神奈川県横須賀市など首都圏でもそういった土地はあるようで、危険な建物を自治体が解体する必要に迫られているようだ。さらに建替えにあたって所有者が不明であることが問題となるマンションも出てきているようで、解体費用も戸建てとは比べ物にならないくらい高く、これも問題となるだろう。相続時に登記をすることがメリットになる制度を作ることと、不要な土地を放棄できる仕組みを作る必要があるだろう。特に地方の不便な土地は価値がむしろマイナスである場所もあるだろう。そういった土地をうまく使える団体などに寄付できる、国有地化するなど何らかの対策が必要ではないか。
立地適正化計画によって、街のコンパクト化をしていくことが必要になってくるだろう。埼玉県毛呂山町では職員が1人で質の高い計画を作成したようで、こういったことに自治体は真剣に取り組む必要がある。しかし補助金のため形式上計画を作り、その実中身のないような自治体も多いようだ。コンパクトシティを実現させなければ、行政の負担は増え、やがて衰退していくだろう。政治家の利権などが絡み難しい面があるようだが、そんなことで適当な計画を作り、骨抜きの立地適正化計画をしていては、その自治体が沈むだけだ。効率の良い行政を実現し、利便性の高い街を目指すべきである。
東京でも既に青梅市などは人口が減少しているようで、利便性の低い土地は見向きもされなくなってくる。マンション選びでも、駅徒歩7分というのが重要な条件だろう。駅から遠い土地は価値がどんどん低下する。地方でも県都や県内最大都市などを除きこれからますます厳しい状況になることが予想される。土地の格差は広がるばかりだ。
最後に都心近郊で地価が上がる街と下がる街を特集している。1位は埼玉県蕨市であり、蕨駅は快速は停車しないものの、赤羽駅まで3駅であり、東京駅まで直通で約32分とそれなりに便利なところである。これは納得できる結果であろう。神奈川県でも武蔵小杉を擁する川崎市中原区などがランクインしていてこの点は妥当である。意外なのは千葉県では千葉市中央区、柏市、千葉市稲毛区などそれなりに利便性のあるところだけでなく、千葉市緑区、成田市、八千代市、印西市など不便なところも上位にランクインしているところである。埼玉県でも冒頭の蕨市のほか、和光市や戸田市、朝霞市などの利便性の高いところもランクインしているが、吉川市という都心に直結していないところがランクインしている。これは本当に信用できるのか心配になるところだが大丈夫なのだろうか。
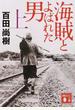
海賊とよばれた男 上
2017/07/11 22:29
実に愛国心にあふれた経営者
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
出光佐三をモデルにした、伝記のような小説である。実際に主人公は国岡鐡造、国岡鐡造が創業した会社は国岡商店と名前は変えてあるものの、その他の会社や時の首相、軍部の人達は実名で登場している。また『永遠の0』で主人公として描かれていた宮部も少し登場し、ニヤッとできる。
第1章は戦後、敗戦によって全てを失った国岡商店が、GHQの占領政策の中、国のために立ち直っていく様子が描かれている。この期に及んでなお、戦前の石油業界の人達は国益よりも自身の利権を貪ることのみを考えていること、GHQや石油メジャーが日本をどうするかについて揺れている様子が見て取れる。国岡鐡造の店員を大事にする姿勢が胸にしみるとともに、どんな状態でも馘首せず会社を立て直していく姿には感動を覚える。
第2章は出生から敗戦まで、会社を立ち上げる苦労や、戦前・戦中の苦難が描かれている。国岡鐡造の原点が、日田重太郎の会社を軌道に乗せるまでの支援にあったことが読み取れる。日田は鐡造が日本にとって大切な、大きな事を成し遂げてくれる人物であると見抜き、自身の財産を無償で提供して、精神的にも鐡造を支えた。鐡造は初期の石油が重要な存在になる前の石油を商品として扱うのに大変な時代から、一時はつぶれるのではないかというほど危うい状態になりながらも商売を維持し続け、さらに満州鉄道で外油との性能争いに打ち勝ち、石油業界においてなくてはならない存在にのし上がった。さらに国内の石油業界の利権とも争い、真に国益を考えて行動していた。また若者達を必死で育て、家族のように接した鐡造の素晴らしさが描かれている。
国岡鐡造はこれほどの人物がいたのかと思えるほど優れた人であると思う。しかし1つ残念に思うのは、やはり息子が第1であったことだ。女の子は事業を託す存在ではないという考えに囚われ、また真に優れた人物を後継者として考えるのではなく、世襲制を敷こうとした点は、やはり彼も神ならぬ人であるというべきか。現在出光興産は創業者と経営者がいがみ合って問題が生じているが、本当に創業者がいつまでも影響力を保持し続け、企業を牛耳るのが望ましいのかは大変疑問である。

私学制服手帖 エレガント篇
2017/04/12 20:11
制服という切り口でのエッセイ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
実在の学校制服をイラストたっぷりで紹介する本書。制服という文化が素晴らしいものであると教えてくれます。
伝統的な雙葉のセーラー服、新世代の共栄学園のセーラー服、聖心女子の特徴的なブレザー、頌栄女子学院の本格的なブレザーなど、印象的な制服がたくさん登場します。
制服という枠組みの中で、各校個性を出しているところがよくわかります。

法律入門判例まんが本 7
2016/11/16 21:20
わかりやすくイメージしやすい
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
判例の事案が漫画になっているので、あの判例だなとイメージがつかめます。
文字だけで読んでもピンとこないものですが、この本を読めば、ここに載っている判例については記憶できると思います。
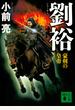
劉裕 豪剣の皇帝
2024/02/17 13:33
マイナーな時代は次に何が起こるかわからないのがワクワクする
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
項羽と劉邦であったり三国志であったりは非常に有名であり、どのような出来事があるのかほとんど把握している状態である人も多いだろう。一方で東晋末というマイナーな時代は何が起こるのか全く知らなかったため、物語の先が読めないため、面白いと感じられる。
次にどうなるのかということが気になって、夢中で本書を読んできた。書き方も題材も素晴らしいものである。
本書はどこまで本当の龍裕を描いているのかはわかりかねるが、軍事一辺倒という主人公像は途中までは一貫していた。そういった物語だと思っていたが、司馬休之を政治的に排除するときは冷酷な君主の一面が出ているように感じ、通常の物語よりも劉裕やその一味の悪さを感じるように思えた。
基本的には政治的な内乱に明け暮れているように思える。それが東晋という王朝・時代なのだろう。東晋を滅ぼし劉宋を建国した劉裕も、前漢の劉邦のように、かつての同士を次々と粛清していくところは、中国の歴史も同じことの繰り返しなのだと強く感じるところであった。狡兎死して良狗煮らるという故事が中国という国の特徴なのだと感じさせられた。
![鉄道ジャーナル 2022年 06月号 [雑誌]](https://img.honto.jp/item/1/f8f7ef/75/110/31605574_1.jpg)
鉄道ジャーナル 2022年 06月号 [雑誌]
2024/02/17 13:32
輸送密度の非情
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
JR西日本の赤字路線としては芸備線や木次線がよく取り上げられるが、実は山陰本線の方がより問題ある路線であろう。というのも、芸備線や木次線と異なり、廃線は容易ではないと考えられるからだ。現在では貨物路線としての用を終えているが、山陽本線が災害などでダウンしたときには代替路線となる可能性もある。そう考えると廃線は難しい。さらに距離も長く赤字額は芸備線や木次線よりはるかに多い。
安易な高速道路の整備が問題の一因とも思える。四国では高速道路の整備により、鉄道利用が減少して、全線赤字という悲惨な状況であるが、そのような状況を考慮するともはや鉄道は不要として、全線廃線でも良いのではとさえ思える。一方で山陰本線は廃線とはいかないわけで、高速道路の建設などやめればいいのに、2025年に島根、2026年に鳥取で山陰道が全線開通する予定とのこと。
本誌では山陰本線の乗車レポートがあり面白い。金曜に島根県、土曜に山口県で乗車したそうだ。
出雲市12:11発の列車には20名くらい乗車している。西出雲で3名、江南で9名下車。太田市では次に出雲市に停車する快速とすれ違い(現在は廃止)、15名乗車していったそうだ。浜田行には10名程乗車。仁万では7名下車9名乗車と盛況。温泉津で9名下車。途中の江津で降りるが、ここで高校生が多く入れ替わったそうだ。
江津15:11発の快速で浜田を目指す。途中都野津と波子に停車する。江津で10名程高校生が入れ替わったようだ。浜田駅近くの国立浜田病院は広い駐車場があり、鉄道利用が便利なはずであるのに、病院利用者に比して駅の乗降客数は少ない。
浜田17:15発の433Dはこの日最大の乗客数で浜田を出発した。過半は高校生とのこと。西浜田と周布で6名ずつ下車。5名の乗客と共に益田に到着した。
早朝6:30に益田を出て、江崎で3名の高校生が乗車し、乗客1人の状況が解消された。その後須佐で8名乗車したようだ。その後奈古で4名乗車。
島根・山口の両県は平成の大合併に積極的であったため、行政の合理化が進んでいるようだ。そのため、駅のほとんどは市に存在しているとのこと。また、人口減少による公立高校の整理に迫られ、地理的条件の良かった山口県は再編が進んでいる。県立奈古高校は廃校となり、分校として存続しているようだ(分校としての存在と元の高校として存在することに差はないような気がする無意味なことと思えるのだが。)。
東萩、萩、玉江と駅があるが、発展しているとは言い難い。玉江駅近くには萩高校と萩商工高校があり、高校生の利用があるとのこと。
長門市駅は、市役所が駅裏の国道191号側に移転し、その周囲にロードサイド店舗が展開されたが、駅前は寂しい状況とのこと。人口減少のペースを超える利用者減となっている。
長門市11:51発の列車は7人の乗客。小串で降車する乗客は7名であったようだ。小串駅近くに済生会豊浦病院があるが、ここも広い駐車場を備える病院であるが、駅利用者は少ないとのこと。
14:17小串発の列車で下関を目指す。川棚温泉では12名乗車してきた。吉見で
7名乗車。安岡までくると住宅地となる。安岡は太田市・江津・浜田・益田・東萩・長門市といった山陰本線西部代表6駅より乗降客数が多く、西出雲以西最多とのことである。
以上のことを考えると、山陰本線がいかに悲惨な状況かがよくわかる。本線でありながら、実態は地方ローカル線である。こういった鉄道が高校生ばかりの利用であり、彼らは免許取得後に車利用者になるか都市に出ていくかのどちらかで、鉄道需要がいかに少ないかということがわかる。こういった路線はどうするのが良いのか難しい問題に迫られている。
![日経 PC 21 (ピーシーニジュウイチ) 2023年 08月号 [雑誌]](https://img.honto.jp/item/1/f8f7ef/75/110/32537764_1.jpg)
日経 PC 21 (ピーシーニジュウイチ) 2023年 08月号 [雑誌]
2023/12/12 07:56
OneDriveの大迷惑を一掃
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
買ったときから勝手に自動バックアップという設定では困る。OneDriveを使うか否かは利用者にゆだねられるべきで最初から使うように設定しておいて、5GBしかストレージなく、不足だ不足だと警告を出す仕様はあまりに酷いものだ。
同期されているドキュメント・写真・デスクトップについて、まずは自動同期を切る必要があるだろう。
他のクラウドサービスとしてはAmzonPhotosなど便利なものも多い。そういったものを使っても良いだろう。Googleは15GB無料であるし、iPhoneユーザーならiCloudも良いだろう。
![週刊 東洋経済 2022年 4/9号 [雑誌]](https://img.honto.jp/item/1/f8f7ef/75/110/31584278_1.jpg)
週刊 東洋経済 2022年 4/9号 [雑誌]
2023/04/16 19:36
東証沈没
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「東証沈没」という特集タイトルそのままの状況である。東証1部といった区分は名ばかりになっていて、魅力のない企業まで最上位区分に入っている状況を是正するために、区分を変えることとなった。しかし最上位区分となるプライムの基準は形骸化し、これまでの1部と何ら変わらない状況となった。意味のない骨抜きの改革が実施され、東証プライムは何の価値もない状態となったのだ。国内だけで考えれば、別に東証の改革が骨抜きで、魅力のない市場が継続したとしても良いのかもしれない。しかし海外と比較をしたときに日本の金融市場の地位低下を更に進行させることとなる今回の事態は東証にとって本当にそれでよいのかと自問すらしないのだろうか。
経過措置という抜け穴には機関投資家も呆れている。期限もなく、そのまま本来はプライム市場に適さないゾンビプライムがいつまでも居座り続けるのだろう。
プライムに魅力ない企業が多数いたって構わないのではないかと考える人もいるかもしれない。確かにプライム市場が玉が少なく石ばかりの玉石混交だとしても、個別銘柄に自由に投資する立場であればそれで問題はあまりない。しかし機関投資家はベンチマークを基に投資するが、これはTOPIXが石ばかりのプライム全体に投資することになっているので、プライムに魅力ない企業が溢れかえっているのは良くない事態なのだ。真に改革すべきは、実は適正なベンチマーク指標の創設にも思える。日経平均は確かに企業が厳選されているようだが、しかしながら時価総額ではなく株価を基にしているので値嵩株の影響を受けすぎるため、TOPIXの方がマシであるというのもこれまた問題だ。
日本の株式市場で最もおかしいのは親子上場だろう。ガバナンスの歪みを放置し続けている。日本郵政はゆうちょ銀行に88.9%出資している。しかし両社ともプライム上場とのこと。これは変である。日本郵政の他にもイオン、ソフトバンク、GMOなど親子上場を続けている企業は多数ある。イオンモールも親会社のイオンを慮って集客力の乏しいイオンリテールのGMSをテナントとして多く入れるなど、利益相反は起きている。テナント賃料などしっかりした説明が必要だろう。
履きだめのスタンダードという衝撃的なタイトルの記事はまさに事実である。赤字企業がずらりと並び、酷い有様だ。合成繊維の染色加工メーカー倉庫精練は営業利益ベースで2012年3月期から10期連続赤字。ぷらっとホームは2000年7月の上場後、初年度以外最終赤字が20期連続。このような企業が上場に適しているのかはさておき、プライムの基準が甘すぎて、プライムに属せないということは本当に酷い状況なのだと逆説的に感じてしまうのは私だけだろうか。
個人投資家もこの状況を嘆いている。プライム上場維持基準は流通株式時価総額100億円以上だがぷりんときばんECのピーバンドットコムは行こう基準日の2021年6月末時点で約21億円。営業利益は近年2億円で推移していて高成長銘柄でもない。しかし時価総額を5~6年後に106億円にするという到底むりそうな計画書を提出しているが、それでも上場維持基準の経過措置を許している東証。
東証のビジネスモデルが上場企業数が多いほどもうかる構造にこれらの原因がある(p60)。NYは世界一であり、競争相手とならないにしてもロンドンや上海と比較してどんどん地位低下するのだが、国内では競争相手がいないからこうやっていい加減なことができるわけだ。
日本の株式市場を東証が担うのはやめた方が良いのではないか。いっそのこと外資に運営してもらった方が日本の金融市場が適正化されて良いのではないかとすら思える。


