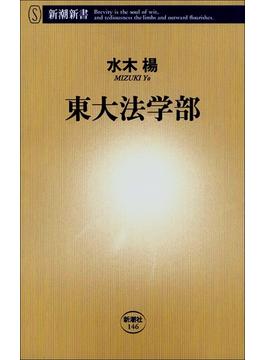- みんなの評価
 2件
2件
東大法学部
著者 水木楊 (著)
明治政府の国策として、創立以来、官僚機構はもちろん政財界にも幹部候補生を供給してきた東大法学部。維新から高度経済成長期へと続くその栄光の歴史、そして霞ヶ関の落日以降に訪れた変化とは――。ニッポン最高とされるエリート養成機関は何を教え何を教えてこなかったのか。あなたの隣のトーダイ君を正しく理解するためにぜひ読んでおきたい1冊。
東大法学部
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
東大法学部
2005/12/29 16:33
東大法学部を撃とうというからにはそれなりのリサーチは欠かせないが、残念ながら杜撰にして大ざっぱな本である。
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:越知 - この投稿者のレビュー一覧を見る
長らく近代日本のエリート養成学校として機能してきた東京大学法学部について書かれた本である。しかし出来映えは残念ながら芳しからずである。
理由は、焦点が絞り切れておらず、書き方も大ざっぱ、調査もいい加減、と言うに尽きる。根本的には著者の問題把握能力の低さが原因かと思うが、本を書く上でのコンセプトでまず失敗している。
つまり、あまりに網羅的なのである。コンパクトで紙数も限られた新書という制約がある中、明治時代に創立されてから近年に至るまでの東大法学部の歴史をたどり、なおかつ現役東大生の性格をさぐるべくインタビューし、東大不要論までぶとうというのだから、いきおい、筆の運びはスカスカになってしまう。網羅的であろうとして、逆に中身が薄くなっているのだ。
加えて、新聞記者としての活動歴が長いせいか、著者の書き方は悪い意味でジャーナリスティックである。つまり、特定の人物のエピソードが入り込んでしまっており、データにものを言わせるという記述法になっていない。いや、エピソードだけでまとめるならまだしも面白いのだが、大ざっぱな歴史記述の中にぽつりぽつりと半端な長さのエピソードが混じるので、歴史としてもエピソード集成としても半端としか言いようがないのである。
そして最後に至ってこの本の不出来ぶりは歴然としてくる。記述の杜撰さがその極に達するからだ。「国立大学はすでに役割を終えているのだから、すべて民営化しなければならない」という文句が突然出てくる(133ページ)。しかし、本書で或る程度(きわめて不十分ながら)具体的に内実が明らかにされたのは東大法学部だけなのである。それでどうして「国立大学はすべて民営化」という飛躍的な物言いになるのだろうか。なるほど、著者は別の箇所で、東大法学部生の親の平均年収は1200万円で国民の平均を越えていると書いている(6ページ)。しかし東大は特別なのであって、国立大学全体で見ると、親の平均年収は私大生の親の平均年収を下回っているのだ(私がBK1で書評した『日本の高学費をどうするか』を参照)。高等教育に国費を投入する理由がなくなっていないことは明らかだろう。
要するに、著者は東大法学部を論じて国立大学全体のこととと短絡するほどにいい加減なのである。例えば、慶応大学を論じて私大全体のこととしたら、誰もが変に思うだろう。その程度の考えさえ、著者の頭には浮かばなかったのであろうか?
なお、欧米では一流といわれる大学はほとんど私立と書かれているが(24ページ)、ヨーロッパでは一流大学はほとんど国公立である。アメリカでもカリフォルニア大学など、州立の名門校はそれなりに存在する。どうやら著者は「民間活力」という日本で流行しているスローガンを信じ込むあまり、まともなリサーチもしないで本書をでっちあげてしまったらしい。困ったことである。
東大法学部
2006/01/09 21:26
調査不足にくわえてシニシズム多用
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:masa - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は東大法学部出身者でも官僚でもないが、これはかなり問題のある本だと思った。
①(61ページ)
1990年代前半に法学部内の講座再編があり、いわゆる社会主義思想系統の講義ないし教授陣がなくなった(去ってしまった)のか意味不明。ちなみに東大経済学部は1990年代前半に学部講義の経済学原論がなくなった。
②(73ページ)
『秘書課長に泣きつかれた』自治省の秘書課長は、省内人事とOB対応が主な担当。仮に大臣の味方をするとするならば、自治大臣の秘書官(自治省内のキャリアか、大臣が連れてきた私設秘書)ではないか。また事務官に先輩の役人が丁寧な言葉で言うはずもない。
③(75ページ)
先鞭をつけたのがボート部の先輩である、の部分だが、ここで述べられている「ボート部」は、旧制一高端艇部とすべきであり、東大ボート部ではありえない。取材が不足している。ちなみに、竹内道雄氏、長岡実氏は、東大漕艇部には入部した記録はないはずである。
④(94ページ)
中には、毎夜ノーパンシャブシャブに打ち興じる者もいた、についてだが、毎晩楼蘭に行っていたと取材できたのだろうか。知っている限りでは最高でも週1、2回だと記憶している。
⑤(99ページ)
安延氏のことを書かれているが、彼はS53東大経済学部卒。なんでも東大法学部のような論調だ。
⑥(105ページ)
銀行のMOF担のエリート行員のくだり。MOF担当には東大経済、京大、一橋もMOF担当で少なかならず存在しており、すべて東大法学部という表現はおかしい。また、MOF担当が日参する銀行局、証券局(軟派)のキャリア担当者は東大法学部と経済学部・他大学出身者がほぼ半々の配置であったはず。したがって、「東大法学部卒の鉄壁のネットワーク」という表現は誤りだ。
⑦(107ページ)
時価発行増資の自社株のくだり。時価発行増資の株式を証券会社経由で購入した銀行員はいたかもしれないが、なぜ時価発行増資で自社株を証券会社を通じて購入するのが問題なのか?。不法であるのか、不当であるのか、意見をもらいたいものだ。
⑧(176ページ)
節のテーマで、「戦略的価値を持つ私立大学」と書いてあるが、そう考えられているのかと思う。ふさわしくない大学生、教職員を多数かかえつつ苦闘しているのが大多数の私立大学の現状であり、東大以上に深刻な問題ではないだろうか。今や、私立大学の半数はかつての専門学校あるいは高校レベルの教育を行っているのが実態だ。この節は「玉石混交で深刻な問題をかかえつつも、将来の戦略的価値に期待しなければならない一部の私立大学」と書きべきでないか。
私も、これまでのミラミッド型システムを八ヶ岳に変えなければならないと思う。しかし、筆者は、その変化のための『生贄』に東大法学部を据えている。たとえば、あとがきで筆者は現代のシニシズム流行を批判したいと書いてあるが、本書に流れているものは、世間的に極めて有名である東大法学部に「三角帽をかぶせて街を歩かせ、世間の方々に東大法学部へ石を投げさせて、なおかつ三角帽をかぶせた人間(=筆者)を英雄にするようにもっていく」という毒(シニシズム)が隠されている。あるいは、そうした方が著書の販売戦略上よいと無意識に筆が動いたのではないか。そのように感じてしまった。
大学への評価は、世間が一致して思うようなものではない。どこの大学に行った人も、良かれ悪しかれ人それなりの思い出を持って通っている(通った)。国が予算を減らす増やすは小さな問題ではないが、一大学の学部を真正面から批判するだけの能力も責務も筆者にはないと思う。それを出版した出版社も同じだけの責任を問われるべきである。