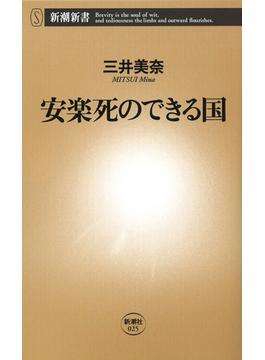- みんなの評価
 3件
3件
安楽死のできる国(新潮新書)
著者 三井美奈
大麻・売春・同性結婚と同じく、安楽死が認められる国オランダ。わずか30年で実現された世界唯一の合法安楽死は、回復の見込みのない患者にとって、いまや当然かつ正当な権利となった。しかし、末期患者の尊厳を守り、苦痛から解放するその選択肢は、一方で人々に「間引き」「姥捨て」「自殺」という、古くて新しい生死の線引きについて問いかける――。「最期の自由」をめぐる、最先端の現実とは。
安楽死のできる国(新潮新書)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
安楽死のできる国
2003/09/12 08:22
輸出不可能なオランダの安楽死
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちひ - この投稿者のレビュー一覧を見る
安楽死とは、大まかに言えば、助かる見込みのない者がさまざまな(肉体的・精神的・スピリチュアル的な)苦痛にさいなまれているとき、いわゆる「延命治療」や「濃厚治療」を停止して死ぬにまかせたり、その苦痛を緩和するための薬品を処方して結果的に死を早めたり、むしろ積極的に毒を処方して死を早めたりすることである。いわゆる「尊厳死」が本人以外の選択による場合が多いのに対し、安楽死は本人の意志以外では決定されることがない点が決定的に異なっている。
現在の日本では、安楽死は非合法である。だがオランダでは2000年11月に厳密な手続きにのっとった安楽死が合法とされ、今では「年間死者数の2〜3%に当たる2千〜3千人が安楽死している。」(5頁)
本書は、「なぜオランダでは安楽死が合法となったのか?」という問題を中心に据え、オランダにおける安楽死合法化のあゆみや、安楽死法の具体的内容、そしてオランダがいま新たに抱えている問題や悩みについて(たとえば、自殺と安楽死との境界線はあるのか否か、など)、現地での取材をもとに詳細に報告している。
また、日本など他の国や地域ではなぜ安楽死が非合法なのか、もし安楽死を合法的におこなおうとする場合にはどのような問題をクリアしなければならないのか、などの問題についても考察をおこなっている。
安楽死の制度化には「(1)だれもが公平に高度な治療が受けられる医療・福祉制度、(2)腐敗がなく信頼度の高い医療、(3)個人主義の徹底、(4)教育の普及」(60頁。安楽死容認派の医師ヘルベルト・コーヘン氏)という四つの条件がそろっていなければならない、よってオランダの安楽死は輸出できない、との意見を紹介している。具体的な考察や事例については実際に読んでもらいたい。
われわれが安楽死をどのように考え、安楽死とどのように向き合っていくべきなのかを考える際の、間違いなく必読書である。
安楽死のできる国
2004/04/26 20:37
生と死を考えること
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:パティロ - この投稿者のレビュー一覧を見る
生命倫理を専門とする方から、新潮新書『安楽死のできる国』を薦められた。とても良い本だからといろんな人に薦めているとのことだったが、同時に、この本のテーマである安楽死のできる国オランダの隣国、ベルギーに暮らす私が、近くにいる者としてどう感じるか、そのことにも関心があってのことだった。
本書の第10章には、ベルギーの事例も報告されている。このロランさんの事例が毎日メディアをにぎわせていた頃、たまたま私は、彼のいる施設から徒歩10分ほどのところにある農家の片隅で暮らしていた。でも、法律が定められた今、身近に安楽死をテーマとする話題は、ほとんどなくなってしまった。
この本を読むと、安楽死に関する基本的知識が得ることができる。さらに感心するのは、ネーデルランドと呼ばれるヨーロッパのこの地域について、歴史的背景とそこに住む人々の気質が、とてもよく把握されているということだ。また、オランダ人の生き方・考え方に深い尊敬を表明しつつも、それを絶対視しない書き方に、深い共感をおぼえる。
第9章の最後に、
「人は一人で神に向き合わなければならない。家族や友人から離れて、たった一人で死までの道のりを歩いて行かなければならない。こんな孤独な死生観が、安楽死容認の社会の根底に流れている。」
と述べられている。
死とは何か、意味のある人生とは何か、命とはなにか…、死も人生も命も、「ほら、これだよ」と、取り出して見ることができないものである以上、安楽死も、行き着くところは哲学のテーマなのだ。
安楽死、こういうテーマについて話し合うためには、まず私たちひとりひとりが、生と死を自分自身の問題として自分の手に取り戻さなければいけないと、そう考えさせられる一冊だと思う。
安楽死のできる国
2005/12/11 12:30
死の権利を与えられた国での生き方
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:花代 - この投稿者のレビュー一覧を見る
耐え難い苦痛を受けながら何年も死を待つ。
それが私に与えられた生き方ならと、甘んじて受けることを選択するか。
それとも、安らかに逝くことを選ぶか。
合法的に安楽死が認められる国、オランダ。
著者は読売新聞の麗しい才女で、同国での丹念な取材を元に、
安楽死法成立の歩み、それを支える社会、生と死の境界線の課題、
日本での安楽死法成立の可能性について、緻密に網羅的に語られている。
どこまでを安楽死してよい苦痛と認めるか。
この曖昧で宗教的な境界線を法制度化したオランダは画期的だ。
同国には「安楽死パスポート」がある。
自らの安楽死の意思表示のためのパスポート。
身体の耐え難い痛み、寝たきりで飲食や排泄が自分ではできない場合、
完全な痴呆に陥った場合など、自分にとって耐え難い苦痛とは何かを、
予め具体化しておく。
まるでピザのトッピングを選ぶように・・・。
日本の倫理観と大きく異なるのは、家族ではなく自分自身の意思だけが決定要素というところだ。
いかに家族が反対しても、それが本人の意思なら安楽死を行う。
しかし、この安楽死をめぐる境界線は議論が耐えない。
「もう充分生きた」と言う高齢者が求める「よき死」。
重度の障害を持って生まれた新生児の親。
これらを認めたときには、新たに「姥捨て」「間引き」との境界線が曖昧になる。
「あんなに年をとってまだ生きてるなんて」と言われる社会。
私がヨボヨボのおばあさんになるまで生きる運命だとして、
半世紀後には日本でも安楽死法が制度化しているかもしれない。
その時に、私は安楽死を選ばない勇気を持ちえるだろうか。
寝たきりの日々、家族に迷惑をかける日々、親しい人が喪われる日々。
それも私に与えられた生であれば、その生き方を探す人間でありたい。