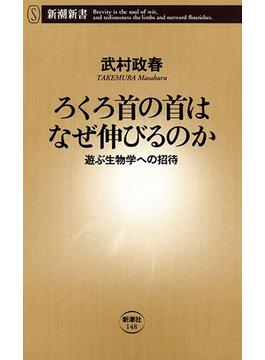- みんなの評価
 3件
3件
ろくろ首の首はなぜ伸びるのか―遊ぶ生物学への招待―(新潮新書)
著者 武村政春 (著)
ドラキュラはなぜ日光で灰になってしまうのか。モスラはどうやって呼吸しているのか。人と魚が合体して人魚になる過程、カマイタチの鎌の成分、カオナシが食べた生物の声になるメカニズムとは――。古今東西の「架空生物」の謎を最新生物学で解き明かす。読み進むうちに頭が柔らかくなること間違いなし。仮想と現実、冗談と本気、奇想と学問が大胆に結合した「遊ぶ生物学」がここに誕生!
ろくろ首の首はなぜ伸びるのか―遊ぶ生物学への招待―(新潮新書)
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ろくろ首の首はなぜ伸びるのか 遊ぶ生物学への招待
2010/06/05 08:04
知的遊戯
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:想井兼人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
古今東西、妖怪の類は数知れず。百鬼夜行だけでも100の魑魅魍魎が跋扈する。ただ、彼らは架空という前提をみんなが理解しているからこそ、生き生きとした存在になるのではないだろうか。ホラー映画に登場する彼らの躍動的な姿に生物学的考察など不必要だ。しかし、本書は架空生物に対して、生物学的見地から取り組んでしまった。それも含み笑いを誘うような生真面目さで。
本書の基本スタンスは「予測不可能な機能の創造と、予測可能な構造の応用」(135頁)である。例えばタイトルにあるろくろ首。首が伸びるろくろ首の場合、首が伸びるシステムが予測不可能な機能で、これを筋肉細胞の可能性から“実在性”を示して見せた。筋肉細胞の研究成果が、予測可能な構造の応用ということになる。この基本スタンスは全16話を通して守られる。そして、予測可能な構造を示すため、まずそれぞれの架空生物に関わるであろう生物の身体の解説からはじまる。
さて、全16話は5つの章にまとめられている。解剖学、免疫学・発生生物学、生化学・分子生物学、細胞生物学、生態学という柱を立て、それに則して架空生物の分析が試みられている。
『平家物語』のぬえや『ギリシア神話』のキマイラの場合、異なる生物の集合体である点を注視している。『平家物語』で源頼政が退治したぬえは、頭が猿で手足は虎、胴体が狸で尾は蛇という姿態の怪物である。鳴き声が鵺(ぬえ)-現在のトラツグミ-に似ているということが、その名の由来という。この怪物の生体的問題点として、筆者は免疫システムをあげている。つまり、異なる生物の部位同士が攻撃し合うのではないかという観点から議論を出発した。そして、考察である。考察では免疫寛容の説明から入る。免疫寛容とは「異物に対して寛容になる現象、すなわち異物が体内に侵入しても免疫反応が起こらない現象」(58頁)とのこと。ぬえの免疫システムを統括しているのは、狸の胴体部分の「キメラ線」という特殊臓器、ということにして筆者は考察を進める。4種の生物部位は、胎児段階に免疫反応を起こす、とする。その前提で免疫寛容を考慮してまとめていく。ぬえの話は、当然免疫学の章に収められているが、その他の生物についても章のタイトルに則した視点からの分析を試みている。
本書あとがきには「知的な遊戯とアカデミズムの取り合わせが絶妙」という評価を得たと記述されているが、同感である。昨今、新書に取り組む出版社が非常に増えた。いまやタレントやスポーツ選手までもが著者として新書を刊行するようになった。ただ、裾野が広がった分、知的満足度が低い本も多い気がするのは私だけだろうか。そんな昨今の状況下、本書は“知的な遊戯”を心から楽しめる貴重な作品と言える。新書の内容に対する許容範囲が広がった結果として、本書が誕生したのかもしれない。新書の裾野が広がったことは、あながち悪いことばかりではないらしい。頭の体操として一読をおすすめしたい。
ろくろ首の首はなぜ伸びるのか―遊ぶ生物学への招待―(新潮新書)
2021/01/21 22:18
着眼点に惹かれて
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読書灯 - この投稿者のレビュー一覧を見る
吸血鬼ものの小説が書きたくて、資料になるかと期待して購入。目当ての吸血鬼のところは、ちょっと期待はずれだった。吸血鬼が灰になっても再生できるかどうか科学的に検証してみようという内容だったが、結局「ムリでしょ」みたいな結論になってしまっていた。せっかくこういうタイトルの本なのだから、そこは無理矢理にでもこじつけて欲しかった。
そのほかの部分は、まあ読み物としては面白いんじゃないかな。