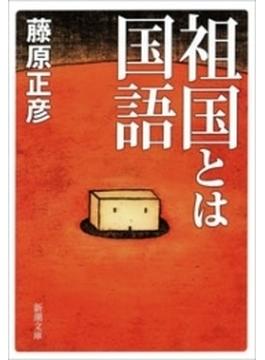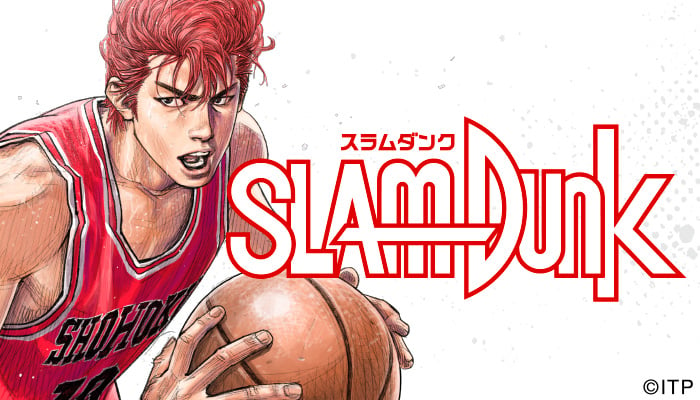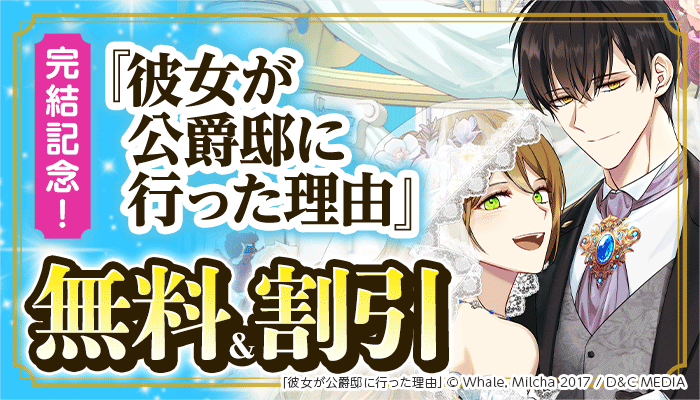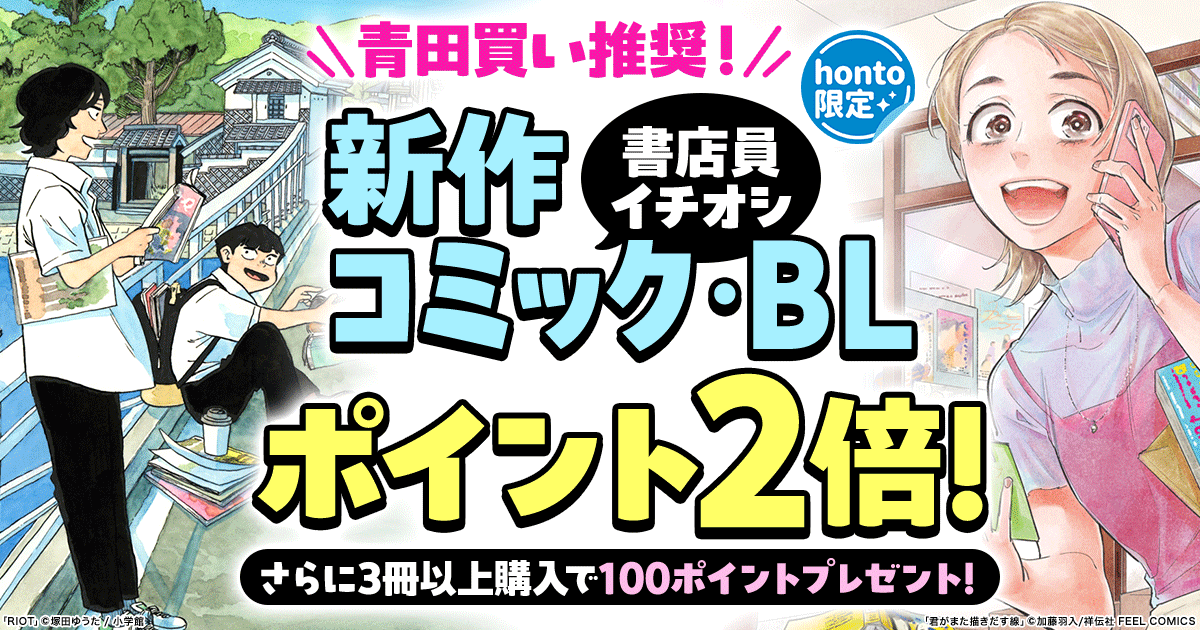- みんなの評価
 3件
3件
祖国とは国語(新潮文庫)
著者 藤原正彦
国家の根幹は、国語教育にかかっている。国語は、論理を育み、情緒を培い、すべての知的活動・教養の支えとなる読書する力を生む。国際派の数学者だからこそ見えてくる国語の重要性。全身全霊で提出する血涙の国家論的教育論「国語教育絶対論」他、ユーモラスな藤原家の知的な風景を軽快に描く「いじわるにも程がある」、出生地満州への老母との感動的な旅を描く「満州再訪記」を収録。
祖国とは国語(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
祖国とは国語
2006/03/22 16:30
国家の浮沈は国語に
17人中、17人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ろこのすけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
いろいろな事件が起き、社会が、人間がおかしくなっている昨今。
詩人の荒川洋治氏は「いま好んで読まれるものを見ると、情報だけの本だったり、時流にあわせたりするだけの本だったり、簡単な言葉だけで作られたものだったりする。簡単なものに吸い寄せられ、簡単な人間が出来上がり、そのため人は怖い思いをする。今もっとも読まれないのは文学書だ」と「詩とことば」の中で言っている。
この憂いの元を藤原正彦は「教育を立て直す以外に、この国を立て直すことは無理だ」と説くことから本書は始まる。
「国家の浮沈は小学校の国語にかかっている」という「国語教育絶対論」。
日本には、万葉集、徒然草、奥の細道、朔太郎、中也にいたる世界に冠たる文学遺産が山のようにある。
しかし、小中学校の教科書に導入できない。なぜか?「漢字制限」があり、常用漢字以外は教科書にだせない。したがって、鷗外や漱石は一掃されてしまったというわけである。古い名作は教科書に登場しにくくなった。
漢字の力が低いと読書に困難をきたし、本から遠のいてしまう。つまり活字離れとなる。
著者は「教科書も新聞もルビをとりいれることで本来の漢字文化を取り戻すべきだ」と説く。
さらに「子どもへの迎合が国語教科書を平易で軽い作品ばかりにしている。日本語の美しい表現や、リズム、深い情感、自然への繊細な感受性などに触れる機会を子どもから奪っている。小学生のうちに古典に触れさせ、イギリス人がシェイクスピアを誦するがごとく、日本人も古典を誦さねばならない。誦すべき文学なき国家は惨めである」とあり、先にあげた荒川氏に呼応するようだ。
国語は「論理」を育て、情緒を培い、知的活動を高め、教養の支えとなる読書する力を生む。
『ユダヤ民族は二千年以上も流浪しながら、ヘブライ語を失わなかったから、二十世紀になって再び建国できた。つまり祖国とは血でなく、国土でもない。「祖国とは国語である」。
「祖国とは国語である」のは、国語の中に祖国を祖国たらしめる文化、伝統、情緒などの大部分が包含されているからである。血でも国土でもないとしたら、これ以外に祖国の最終的アイデンテイテイーとなるものがない。』
『祖国の文化、伝統、情緒などは文学にもっともよく表れている。国語を大事にする、ということを教育の中軸にすえなければならない』
まさに言いえて妙である。熱を帯びた論「国語教育絶対論」は国際派の数学者である著者が二十年以上も説いてきたことがらである。
斎藤孝氏は解説で「ああ、この人に、文部大臣になってもらいたい」と書いている。まさに名言!
このほか、本書には「満州再訪記」が収められている。著者の母藤原てい著『流れる星は生きている』の地を今は老いてしまった母と家族とで再訪する記である。
幼子であった著者と兄、乳児をつれて壮絶な引き揚げ体験をした地に、今はその記憶も定かでなくなった老いた藤原ていさんが立つ。
熱いものがこみあげる感動の旅行記であると同時に、日本の歴史が凝縮された「満州」を丁寧に遡った記述は昭和をたどる旅ともなっていて白眉。
著者の文才を最初に認めたのはあの山本夏彦氏。
まさに達意の文とユーモアのセンスは夏彦氏をして「自分の目に狂いはなかった」と言わしめた。
文章の一つ一つから熱意がほとばしり、読者を思考させ、共感を与え、笑わせ、そして泣かせるこの本。
多くの人に是非読んでもらいたい。
祖国とは国語
2006/08/09 18:13
真の国際人とは、文化を越えて尊敬を得ることができる人物であり、流暢な英会話ができることではない。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
基本的には正論である。英語第二公用語論は暴論である。私もこの記事を新聞で読んだ時に最初に頭に浮かんだのは、ドーデの『最後の授業』だった。国民全員に英語の運用能力が必要とは思われない。母国語教育が最優先されるべきところを、それを軽視したうえ英語教育だけ重視しようというのはおかしい。算数にしても12までと13以降で扱いの違う英語よりも、日本語のほうが10進法には適している。政治家や官僚たちも自分が英語ができないコンプレックスからこのような施策を考え出したのかもしれないが、英語ができないのは、自分の努力不足であり教育システムのせいではないと気づくべきである。また、他教科と同様、英語もまた分からない生徒には分からないのだから、優秀な専門家を育成することが大切で、全員に使いものにならない中途半端な英語力をつけさせるのは壮大な無駄である。
数学や理科の教科書は内容削減のため、分かる生徒には、全体像が見えにくいため分かりにくくなり、分からない生徒には自分には分からないと気づきにくい教科書になってしまった。さらに問題なのは、中学校の理科で数値的な扱いをなくしてしまったため、高校の理科で突然数値を扱うことになるのだが、教科間の連携が考えられていないため、数学で学習する前に、理科で指数や対数が必要になったりしているし、少数の桁の多い計算の能力も極端に落ちていて本質の理解へいたらないのが現状である。(その弊害を逃れるために中高一貫の有名私立への流れが加速した。)
「ノーベル賞ダブル受賞」からあとの新聞用エッセイは素晴らしいものもあるが、どうでもよいようなものも入っている。「この世は数学だらけ」や「いじわるにも程がある」などは珠玉の小品と言ってよい。「雪でなければ白くない?」も、最後の3行がなければ素晴らしい。彼の女性ネタはユーモアのつもりだろうが、残念ながらいつもユーモアになっていない。
さて、最後の「満州再訪記」だが、解説で齋藤孝は『感慨深い文章だ』と褒めているが、私にはよさが分からなかった。彼の史観は概ね是認できるものなのだが、紀行文あるいは自分の原点を探る旅行記としては中途半端だと感じた。この件に関しては、3歳だった彼に『流れる星は生きている』(藤原てい)以上のものを期待することは無理だし、ボケの始まったていの姿の描写は彼女の作品の価値を汚しかねないと思った。
祖国とは国語
2008/03/02 19:09
早期英語教育への反対と「祖国とは国語」(シオラン)という点では,私は藤原派です。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BCKT - この投稿者のレビュー一覧を見る
国語教育絶対論 (英語第二公用語論に/犯罪的な教科書/まずは我慢力を/産学協同の果ては/ノーベル賞ダブル受賞/情報機関の創設を/アメリカ帰りが多すぎる/大局観と教養/戦略なき国家の悲劇/パトリオティズム)
いじわるにも程がある(お茶の謎/ギーギー音/ダイハッケン/科学は無情/ネギよ来い/右目の落涙/ガス漏れ感知器/数学は宝石箱/雪でなければ白くない/エベレストの積雪/この世は数学だらけ/力士の汗かき/求む 踊り子/卑怯を憎む/一石三鳥ならず/血が騒ぐとき/ウォーキング/ライアンの娘/中原中也詩集/いじわるにもほどがある)
満州再訪記
著者は、満州国生まれ(1943-)。作家の新田次郎・藤原ていの次男。東大数学科卒業(66年)。同大学院修士課程修了と同時に東京都立大学理学部助手(68年)。博士号(東大,73年)取得と同時にコロラド大学助教授。76年からお茶の水女子大学理学部数学科勤務。専攻は不定方程式論。『若き数学者のアメリカ』(77年,日本エッセイストクラブ賞),日本数学会『岩波数学辞典 第3版』(85年),『国家の品格』(05年)。以上,Wikipediaより。
Wikipediaの著作一覧を眺めると, 80年代までに3冊しかなかった著作が,90年代に4冊,00年代には8冊と,エッセイスト賞に有頂天にはならなかったことがわかる。下種の勘ぐりだが,数学者の着想力は40歳までと言われるが,彼もちょうどその頃から“雑文”(および対談集,関係者失礼)を書き始めている。
本書はその雑文の寄集め,失礼,エッセイ集。彼の雑念,いや思想は『国家の品格』と『若き数学者のアメリカ』に尽きている。経済学部卒業生として言わせてもらうと,もちっと統計やら論理やらで主張の裏付けが欲しい。これじゃあ感想文だよ。『心は孤独な数学者』(97年)を加えれば,専門分の以外の基本的著作姿勢は判明する。特筆すべきは,初出が文芸春秋や産経新聞など右翼系メディアから左翼の極北=朝日新聞までにまたがっているということ。
扱き下ろしているようだけれど,エッセイ自体は面白い。新ネタがないというだけ。早期英語教育への反対と「祖国とは国語」(シオラン)という点では,私は藤原派です。(885字)

実施中のおすすめキャンペーン