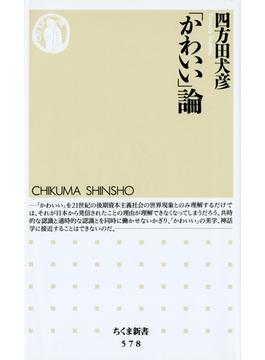- みんなの評価
 3件
3件
「かわいい」論
著者 四方田犬彦 (著)
世界に冠たる「かわいい」大国ニッポン。キティちゃん、ポケモン、セーラームーンなどなど、日本製のキャラクター商品が世界中を席巻している。では、なぜ、日本の「かわいい」は、これほどまでに眩しげな光を放つのか? 「かわいい」を21世紀の美学として位置づけ、その構造を通時的かつ共時的に分析する。
「かわいい」論
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
「かわいい」論
2006/02/24 12:58
「かわいい」とは何か。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちひ - この投稿者のレビュー一覧を見る
たとえば、西洋では「子ども」に対して「大人になりきっていない小さな存在」という否定的評価が下されるにすぎなかった。しかし日本ではそのような評価と並行しつつ・それに加えて、『枕草子』中の「うつくしきもの」から現在にいたるまで、千年以上にわたり「かわいい!」という積極的で肯定的な評価がなされている。ここには我々が「かわいい」を論じる上での大きなヒントが隠されている。
日本語の「かわいい」に厳密に相当する外国語は存在しない。英語では「cute」や「pretty」がそれに相当するとされるが、英語圏で「cute」や「pretty」と評されて喜ぶ「大人」の女性はごく稀であり、日本では20歳前後の微妙な時期をほぼ唯一の例外としつつ、多くの女性が「かわいい」と評されたがる傾向があるように思える。
『Cawaii!』『CUTiE』『JJ』『ゆうゆう』などの女性雑誌が最近あいついで「かわいい」をめぐる特集を組んだことなどに触れながら、文化・歴史・政治・世代・ジェンダーなどなど、さまざまなカテゴリを網羅して「かわいい」が分類整理され、分析され、語られていく。当然のことながら一部は「萌え」論にも発展する。ヘテロとゲイ、おたくとやおいとでは「かわいい」観におのずと質的差異があることをふまえ、「ジェンダーにおける「かわいい」の問題は、まずこうした比較検討の分析から開始されなければならない。」(一七〇頁)との指摘もおこなっている。
「きもかわ」や「腐女子」という、わたしは初めて聞く言葉も多数出てきた。それらの意味を知っていささか衝撃を受けたが「ルフィ受け」「ゾロ受け」という言葉はその正確な意味を知るにつけ衝撃を通り越して拒否反応が出た。
森岡正博が『感じない男』(ちくま新書)で現代の日本全体を覆う「総ロリコン化現象」のようなものを指摘して久しい。「かわいい」を論じつつ「ロリコン」の「ロ」も出さない態度に、逆に共通する問題意識、あるいは時代を読み解く上で重要な示唆があるように感じられる。
「かわいい」論
2008/03/13 10:46
これは「かわいい」論ではない
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:けんいち - この投稿者のレビュー一覧を見る
四方田犬彦氏の「筆力」については、いまさらいうこともないように思うが、本書での、キャッチーなトピックを、深い洞察を経ながら、しかも伝わるように書くという、「新書」の基本といえばそうだが、困難といえばこの上ない困難をしなやかに達成した鮮やかな「筆力」は、まず特筆に値する。
その上で、内容にめをむけてみれば、端的にこれは「かわいい」論などにおさまるものでは決してない。もちろん、「かわいい」自体が本書を一貫したモチーフではあるのだが、正確にいうならばそれはテーマではない。理論的考察から、現状のレビュー、さらにはアンケート、といった複数の方法を組み合わせて展開されていく本書が議論しているのは、一言でいえば「文化政治学」に他ならない。「かわいい」という記号から(世界)都市が論じられもすれば、バルト経由の神話分析、スチュワート経由の憧憬(ノスタルジア)分析、そしてバルト/ボードリヤール経由での雑誌分析、といった具合に、一般読者の目線と興味を保持しながらも、「かわいい」という記号で表象される現実の諸相を転位しながら読み解き、その深層で進行していく「政治学」を摘出していく、その鮮やかな思考/筆の軌跡。
その意味で、本書を読みこなし、理解することは、実は難しいし、軽薄なTVコメンテーターの戯れ言とは水準はもちろん「志」が違う。それでも、私たちが「かわいい」という記号の瀰漫するこの社会に生きている以上、本書は読むべきものであると思うし、あたう限り理解する努力もするべきだと思う。本書はそうしたアプローチに、真摯に応えてくれるはずなのだから。
「かわいい」論
2006/02/23 16:47
人はなぜ「かわいい」に魅かれるのか。
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ソネアキラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
老若男女(違うか)、みな、なんで「かわいい」というのか。いっとう最初は女子が自分の美意識や価値観にかなったものを「かわいい」と呼んだ。大塚英志の本によると、連合赤軍の永田洋子も上述の同義で「かわいい」という言葉を使ったけれど、周囲の革命に燃える(萌えるじゃなくって)イデオロギッシュな野郎たちには理解してもらえなかったとか。この本は『枕草子』からはじまりポケモン、パフィ・アミユミまで古今東西の「かわいい」を検証する、かわいい・カルスタ、である。
「美しい」は、それこそ古典的美学の三点セットであるところの真・善・美に鎮座ましましており、おそれ多い。しかし、「かわいい」は、もっとカジュアルでポップで「美と醜」の間にあるものとか。アンガールズが象徴とされる「キモカワ(イイ)」が、まさしく、それ。クーミンの「エロカワ(イイ)」ってのもあって、かわいいはどんどん進化・変化・分化している。作者は「キャンプ」と懐かしいワードを出してきて、その延長上に「かわいい」があるという。
作者によると「かわいい」に「もっとも深い憎悪を示したのは、上野千鶴子で、「「かわいい」とは「女が生存戦略のために、ずっと採用してきた媚態である」と一刀両断。まあまあ、お平らに。「ぶりっ子」なら当該するが、「かわいい」はメタモルフォーゼしながら、拡散されるばかりだ。「かわいい」と隣接しているのが「ノスタルジア」だと作者。確かに。
本作によると、村松友視は、幸田文をかわいい女にあげている。杉村春子も舞台の上、周辺では厳しかったが、ふだんの何気ないところではかわいいところがあったという。いまなら外資系企業のバリバリのキャリアウーマン独身部長が、ケータイの待ち受け画面をウーパールーパーにしてるとか、フェミニズムの論客女史が繁華街のゲーセンのクレーンゲームでリラックマ、ゲットに凝っているとか、通常とは違った一面を覗かせる、その落差、意外性が「かわいい」につながると。
エピローグに写真で掲載されている「アウシュビッツの洗濯所の仔猫と天使のような少年の壁画」には、まいった。大量殺戮センターになぜ「かわいい」が必要なのか。味気ない収容所生活に、束の間のほっとひと息が狙いなら、この上もなくブラックだ。作者はそれを「「かわいい」における道徳的倒錯」と呼んでいる。かわいいとグロテスクは、表裏一体にあるとも。たとえば拘束衣のイメージが悪いんでキティちゃんプリント柄にしましたとか。なんだかリアリティをそこそこ覚えてしまうから、おそろしい。作者は、映画「グレムリン」を引き合いに出している。グレムリンってバブル景気でいい気になっていた日本人を蔑んだキャラじゃなかったっけ?
「かわいい」宇宙はかくもとらえどころのない、深く、濃ゆ〜いブラックホールのようなものなのだ。人の数だけ「かわいい」がある。でも、「かわいい」にもほどがある。