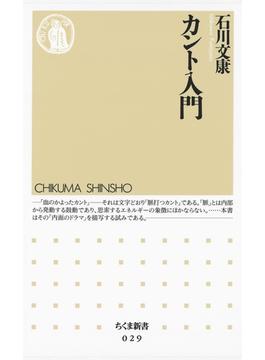- みんなの評価
 2件
2件
カント入門
著者 石川文康 (著)
真理の最高決定機関であるはずの理性が人間を欺く二枚舌をもつとしたら、一大事ではないだろうか。この理性の欺瞞性というショッキングな事実の発見こそが、カント哲学の出発点であった。彼の生涯を貫いた「内面のドラマ」に光をあて、哲学史上不朽の遺産である『純粋理性批判』を中心に、その哲学の核心を明快に読み解く。
カント入門
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
カント入門
2001/08/12 01:21
哲学の正統
7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:アルケー - この投稿者のレビュー一覧を見る
ちくま新書の「哲学入門シリーズ」のひとつ。このシリーズは哲学者の経歴や背景といったものよりも哲学者の思想そのもののに焦点をあてて解説するところに特徴がある。いわゆる内在的研究といわれるもの。
これまで人気のある著者によって多くの人気のある哲学者の解説がなされてきたが、面白いことにそれまで知られていなかった学者による解説に読みごたえのものがあるように思われる。最近では『アリストテレス入門』がそれだ(不案内なフランス思想はのぞく)。
最近カント復興がやってきているのであろうか。黒崎政男“カント『純粋理性批判』入門”(講談社)や文芸評論家柄谷行人『倫理21』(平凡社)などが目につく(文芸評論家は時代の潮流に敏感だから当然といえば当然。中沢新一『フィロソフィア・ヤポニカ』(集英社)は日本思想の隆盛にいち早く反応したもの。文芸評論家やそれに近い人が哲学を紹介するのは日本のお家芸)。また、カント著作集の翻訳もだされるなどしている。もっともこの翻訳はあまり意味があるとは思えない。著作集が翻訳されているのは日本だけかもしれない。しかし一方では、宇都宮芳明『カントと神』(岩波)というすばらしい研究書も出ている。
プラトンの後にはアリストテレス、ヘーゲルの後にはカントと分析的な思想へと向かっているのはそれなり理由があるのだろうか。それよりも弁証法に人々は飽食したのかもしれない。マルクス主義にはじまって、構造主義、ヴィトゲンシュタイン、システム論と実体概念よりも関係概念を志向する思想を中心に回転してきた現代の思想に食傷ぎみなのかもしれない。もしそうだとしたらそれはよい傾向だといえる。実体概念と関係概念は切り離すことができないからだ。
著者のカントは具体的な例を取り上げて論じるので分かりやすい。システム論などは例が挙がっておらず、挙がっていても読者にほとんどイメージ(表象)しがたいもので、著者独自の解釈による概念の羅列につきあわなければならないので、解読不能なものが多い。そういった類のものと比べると、難しいと敬遠されてきたカントが何と読みやすいものになっていることか。しかもカントの思想にはその前後の思想がすべて含まれている。現在ではそんなことも忘れられている。これから哲学とじっくりとつきあっていきたい人に大切な一冊となることをねがう。
カント入門
2016/02/11 11:20
平易なカント入門書
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:カント - この投稿者のレビュー一覧を見る
カントが、第一アンチノミーを解決するために、時間と空間は我々の感性の形式であるという第三の視点を持ち出したところに感銘を受けた。
カントの「認識論」と「倫理学」、さらには「宗教観」、「美学」について包括的に論じられている。
カント入門
2017/08/28 13:14
「仮象批判」「自律」といった一貫した概念
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ポージー - この投稿者のレビュー一覧を見る
あとがきで著者はカントの入門書を新書で書くのは難しかったと言っているが、読む方としてはなんとなくわかったつもりにはなれた。それはカントが哲学・道徳論・宗教論・美学など多岐にわたるテーマを一貫した概念で論じていて、本書がそれを平易にすくいとっているからだろう。