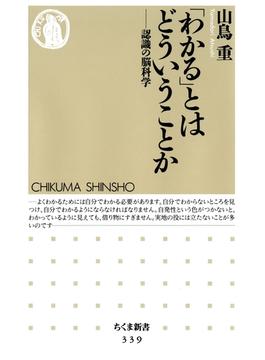- みんなの評価
 2件
2件
「わかる」とはどういうことか ――認識の脳科学
著者 山鳥重 (著)
人は、どんなときに「あ、わかった」「わけがわからない」「腑に落ちた!」などと感じるのだろうか。また「わかった」途端に快感が生じたりする。そのとき、脳ではなにが起こっているのか?脳の高次機能障害の臨床医である著者が、自身の経験(心像・知識・記憶)を総動員して、ヒトの認識のメカニズムを解き明かす。
「わかる」とはどういうことか ――認識の脳科学
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
「わかる」とはどういうことか 認識の脳科学
2016/07/28 10:50
「わかる」ということは脳でどのようなことが起こっているのかを考察した良書です。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
私たちは、毎日のように物事を考え、考察し、その解決に向けた行動を起こしています。その際、「わかった!」と感じることが何度もあるのですが、その時、私たちの脳では一体どのような反応が起こっているのでしょうか。本書は、脳の機能障害の臨床医である筆者がわかりやすく書き起こした学習と脳との関係についての入門書と言えるでしょう。多くの方々に広く読んでいただきたい良書です。
「わかる」とはどういうことか 認識の脳科学
2008/07/18 15:14
「わかる」という心の動きについて、認知科学の側面から論じた本です。
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:緑龍館 - この投稿者のレビュー一覧を見る
脳の機能障害の専門家であり、臨床医でもある著者が、「わかる」という心の動きについて、認知科学の側面から論じた本。高校生くらいが対象でしょうか。とても平易に書かれていますが、あつかっている内容はかなり面白いです。
「分かる」とは感情の動きであって、この原因となる心の動きが「考える」ということ。しかもこの心の動きにとって重要なのは、客観的事実ではなく「心像」(主観的現象)である、という著者の論には大きく共感できます。また、この「分かる」「考える」といった現象は、進化論的観点から見ると、(「分かった」とは、行為に移せる、という点で)知覚-運動過程の中間に挿入されたチェック機構であるとも考えることができる。この心理表象は一見知覚に近い現象に見えるけれども、実は知覚 - 運動変換を省略したものだから、運動要因が含まれている。つまり、いつでも運動に繋がる仕組みになっている。だから、心理表象とは身体的運動が省略された運動と考えられ、運動の進化した状態とみることができる、という論は、興味深いものがあります。
抜き書き
● 意味とは、とりもなおさず、わからないものをわかるようにする働きです。・・・・・ 心は多様な心像から、意味というより高い秩序(別の水準の心像)を形成するために絶えず活動しているのです。ですから、意味が分からないと、分かりたいと思うのは心の根本的な傾向です。生きるということ自体が情報収集なのです。それが意識化された水準にまで高められたのが心理現象です。意識は情報収集のための装置です。情報収集とは、結局のところ秩序を生み出すための働きです。
● ある高名な日本画家が絵の極意は対象をひたすら見ることだ、と述べていました。・・・・・ ひたすら見ることで対象がだんだん「見えてくる」というのです。よく見えれば、よく描ける、と言っています。これを少し言い換えますと、しっかりした心像が形成できれば(表象できれば)、それはそのまま運動に変換出来るということです。人間の心はそういう仕掛けになっているのです。・・・・・ 表現は心にあるイメージをなぞることです。イメージが無ければなぞりようがありません。
● 知能とは、常に変化し続ける状況に合わせ、その時にもっとも適切な行動を選び取る能力だといえます。
この著者の本は、ぼくの読んだ限りでははずれがありません。本屋さんで目に留まったら買ってくることにしています。
→緑龍館 Book of Days