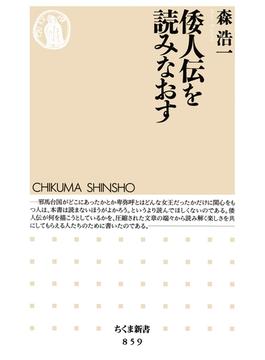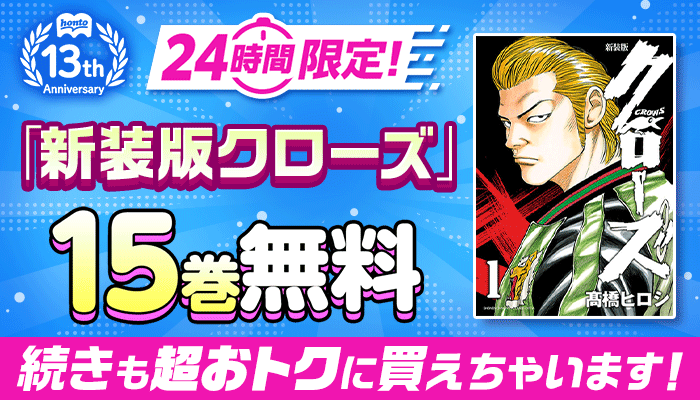- みんなの評価
 2件
2件
倭人伝を読みなおす
著者 森浩一
古代史の一級資料「倭人伝」。邪馬台国や卑弥呼への興味から言及されることの多い文章だが、それだけの関心で読むのは、あまりにもったいない。正確な読みと想像力で見えてくるのは、対馬、奴国、狗奴国、投馬国…などの活気ある国々。開けた都市、文字の使用、機敏な外交。さらには、魏や帯方郡などの思惑と情勢。在りし日の倭の姿を生き生きとよみがえらせて、読者を古代のロマンと学問の楽しみに誘う。
倭人伝を読みなおす
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
倭人伝を読みなおす
2012/12/12 20:24
倭人伝の入門書
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キック - この投稿者のレビュー一覧を見る
刺激あふれる好著でした。
邪馬台国論争で、特に「近畿説」は無理やり都合良く解釈している(例えば、魏の人が南を東と聞き間違えたという暴論)イメージが強く、今まで「倭人伝」自体に興味が持てませんでした。
しかし本書は、はしがきにあるとおり、「邪馬台国がどこにあったのかとか卑弥呼とはどんな女王だったかだけに関心をもつ人には読んでほしくない。倭人伝が何を描こうとしているのかを、読み解く楽しさを共有してもらえる人のために書いた」とのことです。惹かれるものを感じ、一気に読みました。
確かに本書は、詭弁を弄することなく、倭人伝の内容を38回にわたり、その文脈に沿って素直に読み解いています。1回が4ページ程度に簡潔にまとめられているので大変読みやすく、また毎回初めて知る話ばかりで、新鮮な感動がありました。例えば、東夷伝の中で倭人伝が最も字数を費やしている(第2回)とか、弥生時代は農村ばかりではなく小都市もあった(第4回)とか、対馬や壱岐は中継貿易を盛んに行っていた(12回)とか、卑弥呼は自殺の疑いがある(第28回)とか・・・。
とにかく、倭人伝の楽しさを十分満喫することができました。特に、古代史初心者にはお薦めの本です。
倭人伝を読みなおす
2019/10/23 10:16
漢字原文での紹介と81歳の著者の60年にわたる倭人伝にある土地を訪れた研究成果を織り交ぜ臨場感ある展開です
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:多摩のおじさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
233年生まれの陳寿により書かれた「三国志」のひとつである「魏志」の東夷伝の最後で分量も最多の3世紀の日本を描く倭人伝「魏志倭人伝」に
関して、冒頭の「邪馬台国はどこにあったかどうかとか卑弥呼とはどんな女王だったかだけに関心をもつ人は・・・本書を読んで欲しくない。倭人伝が何を
描こうとしているかを、圧縮された文章の端々から読み解く楽しさを共にしてもらえる人たちのために書いたのである」のとおり、帯方郡から邪馬台国、
卑弥呼の死と台与、帯方郡からの張政について、漢字原文での紹介と81歳の著者の60年にわたる倭人伝にある土地を訪れた研究成果を織り交
ぜながらの展開には実に臨場感があり、読み手の好奇心を一層掻き立てるものとなっています。
特に、8世紀のヤマト政権時にも吉備真備が怡土(いと)城を築き、倭人伝に王がいたとし、倭人伝の中で最多の字数を占める伊都国として、糸島
市の弥生時代中期の三雲南小路王墓、同後期前半の井原鑓溝王墓、同後期末の平原王墓での弥生時代の銅鏡の110面程もの出土や、同
国が6~7行目と28~30行目の二か所の記述に対し、前段は魏が公孫氏滅ぼした後の帯方郡が得た知見、後段は公孫氏勢力下の帯方郡が
倭や韓を支配していた時期の情報によるとし、一大率と政治と外交の中心地、それに続く最初の旁国の斯馬国を糸島半島の古代の志麻郡の比定
には首肯させられました。(p.93-113)
よく問われる不弥国に続く対馬国、邪馬台国が鹿児島県より南方の海中となる点については、卑弥呼の死後に泰始4(266)年の台与が晋への
遣使の際に新しい情報がもたらされたとし、その起点を帯方郡とし、また戸数の記述がそれまでの「有○○余戸」から「可○○余戸」と推量の「可」に
なっていることもそれを裏付けているとの指摘(p.136-138,p.155-156)や、非業の死を意味する漢字原文の48行目の「以死」に着目し、「張政
等・・・難升米為檄告喩之卑弥呼以死」で、張政等が難升米に檄をつくり告喩し、その結果卑弥呼は死んだ」との指摘には、目から鱗でした。
(p.158-161)
一方で以下疑問も浮かびました。
・考古学界での北部九州勢力の東遷説と張政と関係を裏付けるられるか(p.157)
・漢字原文の最終1行前の「送政等還」を張政を送り返すとの解釈(p.156)だが、「張政」の明記はない
・卑弥呼の死後に女王となった台与に「政等以檄告喩台与」を張政等が台与に檄をつくり告喩(p.168)だが、「張政」の明記はない
・対馬国、邪馬台国の記述は台与が晋への遣使でもたらした新しい情報(p.167)に対し、張政によって魏にもたらされた情報(p.168)
なお、理解するうえでは、漢字原文に対するまとまった訳文と帯方郡から邪馬台国までの道程図や年表、索引、また不弥国以降では遺跡を含む
地図が欲しかったですね・・・