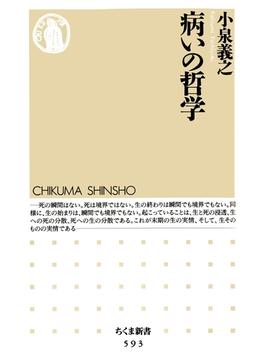- みんなの評価
 1件
1件
病いの哲学
著者 著:小泉義之
末期の状態にある人は死ぬほかないーー。死の哲学はそう考える。これに抗し、死へ向かう病人の生を肯定し擁護すること。本書はプラトン、パスカル、デリダ、フーコーといった、肉体的な生存の次元を肯定し擁護する哲学の系譜を取り出し、死の哲学から病いの哲学への転換を企てる、比類なき書である。
病いの哲学
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
病いの哲学
2006/05/07 18:04
死に過剰な意味を与えようとする「死の哲学」の批判のために
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:king - この投稿者のレビュー一覧を見る
「病いの哲学」といわれてもぴんとこないと思う。なので、著者が「病いの哲学」に対置している「死の哲学」の方から見てみる。
「死に淫する哲学は、末期の病人のことを、死ぬこと以外になす術のない、死ぬしかない人間と決め付けている、治療不可能と宣告しさえすれば、善をなす他者の手によって死を与えること以外に、何も為すべきことも考えるべきこともないと決め付けている。だからこそ、死ぬことに意味を賦与したがる」
著者は「死の哲学」とは「死に淫する哲学」であり、死に過剰な意味づけを与えようとする哲学であるとする。それを批判する著者がとっているスタンスはきわめて明確だ。それはあらゆる場面での生の肯定、立岩真也風にいえば「生の無条件の肯定」ということになる。
「死の哲学」が死に過剰な意味づけをあたえるとき、そこで毀損されるのは生だということが肝要だろう。「死の哲学」は、生を高次元の生と低次元の生とに分割し、低次元の生を、尊厳ある死よりも下に置こうとする。病人の悲惨な生より、選択された安らかな死を称揚する。それが「死の哲学」であり、つまりこれは「尊厳死の哲学」でもある。
「犠牲の構造は、死へ向かうこと、死なないで生きていることを無意味と決め付け、あっさりと、ある種の人間を死へと廃棄してしまう。その残酷な過程はさまざまな幻想や言動によって飾り立てられている。例えば、「死ぬ権利」「死ぬ自由」をとってみる。死ぬ権利に対比されているのは生きる権利ではなく、権利を喪失したと見なされる生、すなわち、ただの生、低次元の生、生き延びるに値しない生である。だから、死ぬ権利の行使を主張することは、必ずや、そんな生を死へと廃棄することを含意する。他方、死ぬ自由に対比されるのは、生きる自由なのではなく、自由を喪失した生を生かされる不自由である。だから、死ぬ自由を主張することは、不自由な生を死へと廃棄することを含意する」
しかしこれはおかしい。立岩氏だったか著者だったか忘れたけれども、ある人はこう言っていた。低次元の生、悲惨な生があったとき、それと対置されるべきなのは尊厳ある死ではなく、高次元の生であるはずだ、と。この言明は絶対的に正しいと私は思う。「死の哲学」は死に淫するあまり、生を死よりも劣等なものとする。そこでは生きることがむやみに低位におかれ、死を選択することを迫られる。
著者がこの本で論じているのは、そのような「死の哲学」の系譜をソクラテス、ハイデガー、レヴィナスらのなかに批判的に見いだす作業と、生を肯定する「病いの哲学」の系譜をパスカル、マルセル、ナンシー、パーソンズ、フーコーから取り出す作業だ。
基本的には本書は各哲学者らのテクストを読み込む作業にあてられていて、割合にむずかしい議論が続く。その部分をきちんと紹介する能力はないが、いくつかかなり興味深い論点が提示されている。そしてその根本には尊厳死批判、生の肯定があり、死に近づきつつある「病人の生」を生として肯定する試みはとても重要な意味を持っている。
本書は立岩真也の「ALS 不動の身体と息する機械」と基礎的な姿勢を同じくしているし、なんとなく文体も似ている気がする。こちらが哲学の側面からアプローチしているとすれば、立岩氏は個別具体的な病気、患者から、尊厳死に追い込まれる生を批判していこうとしているといえる。どちらも重要な仕事だと思う。
「壁の中」から