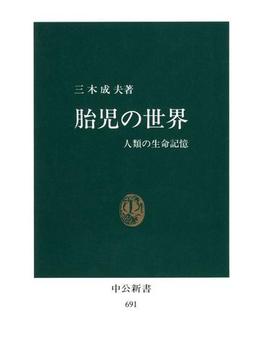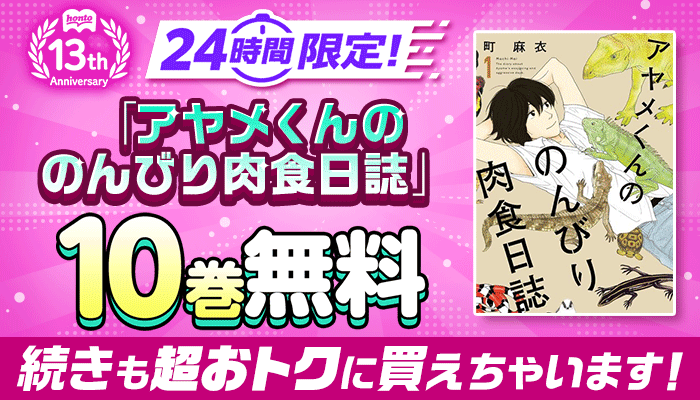- みんなの評価
 2件
2件
胎児の世界 人類の生命記憶
著者 著:三木成夫
赤ん坊が、突然、何かに怯えて泣き出したり、何かを思い出したようににっこり笑ったりする。母の胎内で見残した夢の名残りを見ているのだという。私たちは、かつて胎児であった「十{と}月{つき}十{とお}日{か}」のあいだ羊水にどっぷり漬かり、子宮壁に響く母の血潮のざわめき、心臓の鼓動のなかで、劇的な変身をとげたが、この変身劇は、太古の海に誕生した生命の進化の悠久の流れを再演する。それは劫初いらいの生命記憶の再現といえるものであろう。
胎児の世界 人類の生命記憶
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
胎児の世界 人類の生命記憶
2011/01/16 09:38
詩人の夢
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の本はこれで三冊目だ。感想は二点である。
一点目。人間が受精してから出産に至るまでの期間に「生物の進化の歴史」を辿って来ているという指摘には再度感銘を受けた。僕らの祖先が海の魚だったということだけではなく、受精から出産に至るまでの胎児の間に僕ら自身が魚である瞬間があったという話だ。つまり僕自身が生物の進化を自ら経験してきているということである。
確かにこれを書きながらお尻を触ってみても、そこには尾てい骨がある。尻尾が有った時代を自らの体に残しているわけだ。あと数万年したら、こんな骨も無くなっているのかもしれないが。
二点目。本書は科学や医学の本ではない。哲学の本とも読めるが、厳密な意味でロジックがあるわけでもない。おそらく「詩集」であると考えることが一番正しいのだと思う。
著者は医学的な知見を素材として「詩」を書き綴っている。「詩人」はどのように物事を感じ、どのように表現するか、全て自由だ。本書にはそんな自由さが満ち溢れている。
胎児の世界 人類の生命記憶
2005/01/10 00:49
稀代の奇書
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
魚を通じて自己の探求を行ったアートユニット明和電機の作品の中でも「サバオ」は特に有名だ。13週目の胎児の顔を模ったサバオ(鯖男)は、「胎児が魚の顔をしている時期がある」ことをそのモチーフにしている。
これを生物学の用語で言うと「個体発生は系統発生を繰り返す」(ヘッケル)となる。生物は、その発生の過程において、生命の誕生から現在までの進化の過程を辿る。原始の海で生まれた原始生命は魚へと進化した。そして、魚は上陸して爬虫類を経て哺乳類へと進化する。この過程が、固体の生命発生の過程でなぞられるのである。
著者はこの発生について研究をしていた学者で、本書は著者の研究の成果を著したものである。タイトルどおり、ヒトの発生過程である胎児の世界についての本であるが、これはまた、生命の本質を探求する試みでもある。
異様な本だ。こんな奇本もそうそうあるまい。脳味噌よりも内臓に来る、そんな本である。
れっきとした科学者の書いた本書が有するこの異様さは、著者の熱に浮かされたような語り口と、胎児の世界を通じて生命や宇宙の本質にまで迫ろうとする、時にナンセンスなまでの壮大な試みの故だろうと思う。
例えば、著者は、胎児の顔を確認したいという科学的探究心を抱きながらも、そのために必要な胎児の首を落とすという行為を前に倫理的な葛藤を抱えることになる。逡巡した末に胎児の首を落とすのだが、その時の熱に浮かされた状態をそのままに伝える以下の記述には、荘厳なまでの凄みがある。
『そんなある朝、深い木立におおわれた窓辺で、ふと手をのばして、三ニ日の標本瓶を静かに光にかざしたのである。嵐のような蝉しぐれが耳を打つ。半透明の珠玉のからだが液体のなかで小さく揺れる。蓋をとって、きれいに洗ったシャーレのフォルマリン溶液のなかに、そっと中身を移す。切断はいともたやすくおこなわれた。
グラッと傾き、やがて液のなかをゆらゆらと落ちていく、そのゴマ粒の頭部…。わたくしは、その一瞬、顔面が僅かにこちらに向いたのを見逃すはずはなかった。フカだ! 思わず息をのむ。やっぱりフカだ…。
(中略)
…おれたちの祖先を見よ! このとおり鰓をもった魚だったのだ…と、胎児は、みずからのからだを張って、そのまぎれもない事実を、人々に訴えようとしているかのようだ。読者はどうかこの迫真の無言劇を目をそらさないでご覧になって欲しい。』
本書の後半は、宇宙や生命の本質に迫ろうと言う野心的な試みにさかれている。そこでは、生命体が宇宙から切り離された一個の生きた惑星ではないかとの仮説が示される。全ての生命は宇宙と臍の緒でつながっていたからこそ、生の波は、宇宙リズムと交流することになる。「生きた惑星」であり、「星の胎児」である生命体という仮説。
このような仮説は、科学的常識から言えば、ナンセンスなものかもしれない。しかし、このナンセンスなまでの壮大な仮説を提示され、読者は否応なく異様な興奮に包まれていくのである。
最後に著者はこう締め括っている。
『いま、こうして筆を擱きながら、わたくしはあらためて、ここまでやらねばならぬ人間の“業”を思う。体腔のどこにも“生の舞台”を持たぬ、それは悲しき性に許された唯一の代償行為なのではないのか…。』
科学の道を生きながらも業を思う。その真摯な姿勢に触れられることにこそ、稀代の奇書である本書の価値があるのだろう。